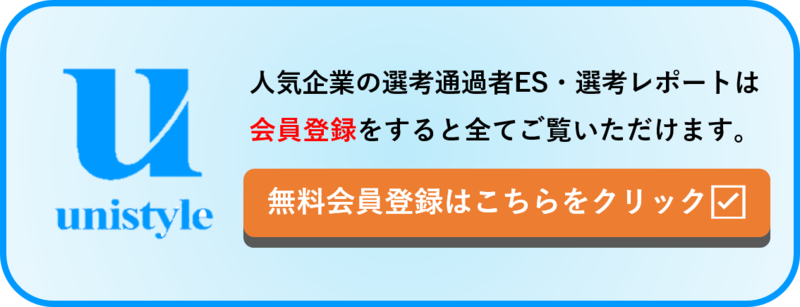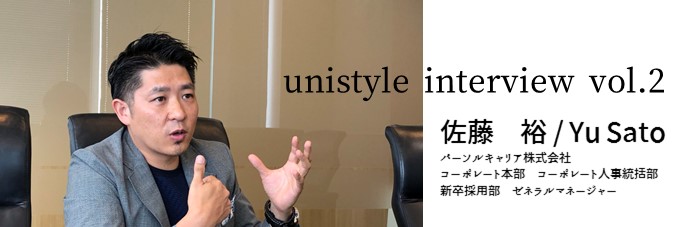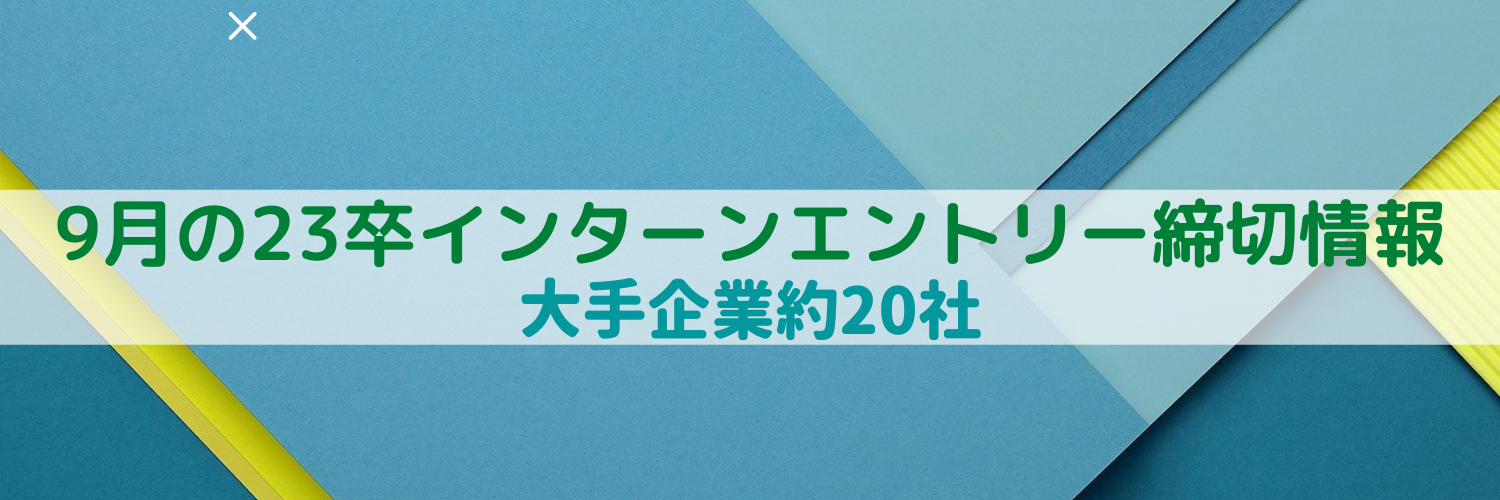就活初心者に読んで欲しい!志望企業内定のための12ステップ
335,711 views
最終更新日:2024年10月23日
.png?1580449670)
就活のスタートに際して「これだけは読んで欲しい!」というunistyleの記事をピックアップしてまとめています。
自己分析や面接など、各項目ごとに関連記事を掲載しているだけでなく、一般的な就活スケジュールに沿って記事を紹介しています。
すでに就活のスタートを切っている就活生の方も、改めて読んでいただければと思います。
また、すべての記事に目を通すのではなく、関心のある部分だけを拾い読みしても十分役立つと思いますので、自身の得たい情報に応じて読み進めていただければと思います。
※記事以外に、内定者のエントリーシート(ES)や選考レポートが読みたいという方は、こちらからご覧いただけます。
-
- 本記事のコンテンツ
- 【就活ステップ(1)】最初の心構えを知る
- 【就活ステップ(2)】就活スケジュールを理解する
- 【就活ステップ(3)】自己分析をする
- 【就活ステップ(4)】業界研究・企業研究をする
- 【就活ステップ(5)】就活マナーを理解する
- 【就活ステップ(6)】OB・OG訪問とリクルーター面談に臨む
- 【就活ステップ(7)】エントリーシート(ES)を書く
- 【就活ステップ(8)】Webテスト・筆記試験・適性検査を受験する
- 【就活ステップ(9)】グループディスカッション(GD)に臨む
- 【就活ステップ(10)】面接に臨む
- 【就活ステップ(11)】内定から入社までを考える
- 【就活ステップ(12)】働き方・キャリアを考える
- 最後に
【就活ステップ(1)】最初の心構えを知る
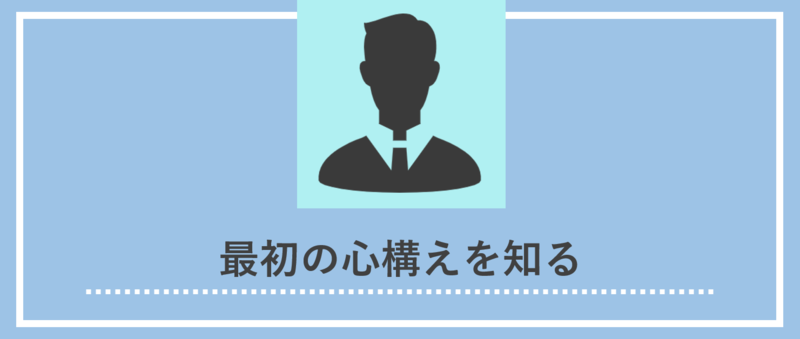
本記事を読んでいる方でも、就活中の方、これから就活を始める方、既に就活を終えた方など様々だと思います。
その中で「就活に対してポジティブな捉え方をしている就活生」はどの程度いるでしょうか。おそらく多くの方は、就活に対してネガティブな印象を抱いているのではないでしょうか。
しかし、その多くの方にとっても、就活は避けて通ることは出来ません。ここでは、就活を楽しいものにするために知っておくべき心構えについて述べたいと思います。
【就活を始める前に読んで欲しい】就職活動とは何か?なぜ働くのか?
就職活動における目標設定のススメ│社会人で後悔しないための考え方
内定を得るまでのプロセスとは
「スクリーニング基準」と「採用基準」の違い
結局、企業が見ているのは(1)仕事がきちんとできるか(2)仲間とうまくやれるかの2点です。
「お辞儀の角度、ノックの回数、スーツの色柄」などの枝葉末節だけに右往左往せず、「本当に自分に合った仕事は何なのか」を多くの人々の思いに触れながら考えてみてください。
【就活ステップ(2)】就活スケジュールを理解する
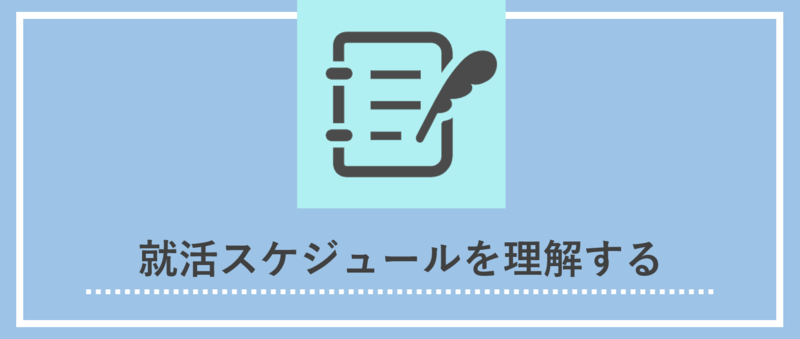
就活を始める時期は個々人で違えど、内定から逆算してスケジュールを設計することは重要となります。
自己分析・業界研究・面接対策など、就活ではやるべきことが無限にあります。そのため、あらかじめ大方のスケジュールを設計しなければ、「本選考までに対策が間に合わなかった!」という自体に陥る恐れがあります。
ここでは、自身の就活スケジュールの設計に役立つ情報を紹介したいと思います。
就職活動における目標設定のススメ│社会人で後悔しないための考え方
内定を得るまでのプロセスとは
就職活動チェックリスト|戦略的な就活プランで内定を勝ち取るまで
【26卒向け】日系大手志望者の就活スケジュール完全版!内定を得るために必要な9ステップとは
就活を始めた時期・志望業界によってスケジュールは異なりますが、重要なことは「目的(=志望企業)から逆算して、自分なりの就活スケジュールを設計すること」です。
上記の参考記事なども確認しながら、自分なりの就活スケジュールを設計しましょう。
【就活ステップ(3)】自己分析をする
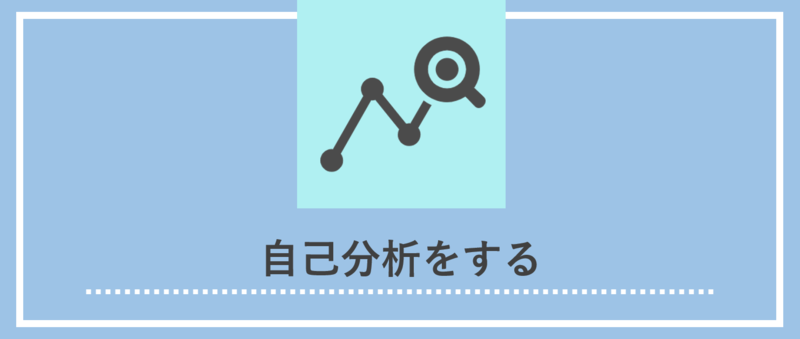
就職活動において自己分析は重要とされていますが、「なぜ行うのか」の目的意識もなく、過去の経験を書き出して年表にするだとか、ストレングスファインダーで強みを分析して終わりなどといった「手段」に囚われるのは本質的ではないと思っています。
就活における自己分析のゴールは「志望企業から内定を得ること」です。
最終的に内定を得るために、自己PRや志望動機などのアウトプットに結びつく形での自己分析を推奨します。
【自己分析とは?】これで攻略間違いなし!自己分析の目的と進め方
簡単にできる自己分析のやり方8選!-やり方別のメリット・デメリットをunistyleが独自調査-
カテゴリ別!自己分析を効率的に進めるための質問リスト
内定レベルの自己分析ができる!効果的な自己分析シートの書き方とは
本当に必要な本14選!自己分析にオススメの本をタイプ別に紹介
【おすすめテスト8選】自己分析に繋がる適職診断や性格診断ができるテストを紹介!
【厳選】自己分析が簡単にできるオススメツール8選!
【就活ステップ(4)】業界研究・企業研究をする
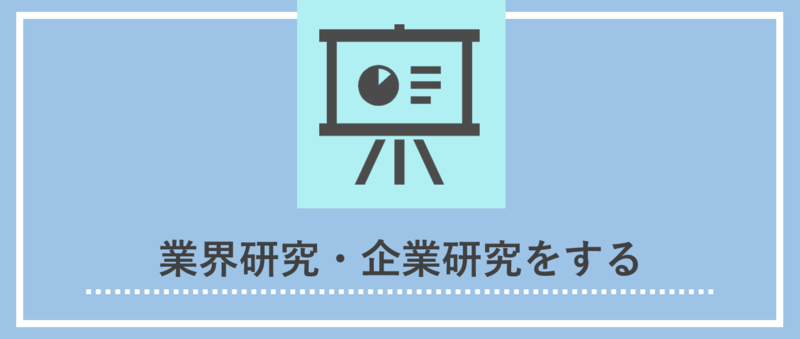
業界研究・企業研究についても自己分析と同様、「適切な目的意識」のもとで行なうことで初めて有効な情報を集められると考えています。
- 業界研究の目的は、その業界のビジネスモデルと働き方を知り、求められる素養を理解すること
- 企業研究の目的は、「業界の中でもなぜ当社?」という質問に答えられるようにすること
【最新版】業界研究のやり方やポイントをわかりやすく徹底解説
【ノート例有】業界研究ノートとは?作り方や必須項目をわかりやすく解説
【厳選10選】効果的な業界研究を行うために活用すべきオススメのサイト
【就活】業界研究に役立つオススメの本を5冊紹介
【保存版】41業界を徹底解説!unistyle業界研究記事まとめ
就活における企業研究の目的とは?やり方や項目を簡単に解説
企業研究はいつから始める?タイミングと時間を就活スケジュールに沿って解説
企業研究のやり方を徹底解説-新卒就活を効率的に進めるためのコツとは?-
企業研究ノート・企業研究シートの作り方を解説【ダウンロードできるテンプレ付】
企業研究に役に立つ!オススメのサイト・本・SNSを紹介
また、業界研究・企業研究を進める手段の一つに「合説(合同企業説明会)などの就活イベントに参加する」というものがあります。
「合説なんて意味がない」という話も度々聞くと思いますが、重要なのは参加する側のスタンスです。企業人事・社員とのコネクション作り、興味の幅を広げるといった機会にすることができれば、合説の機会を有意義なものにできるはずです。
【就活ステップ(5)】就活マナーを理解する
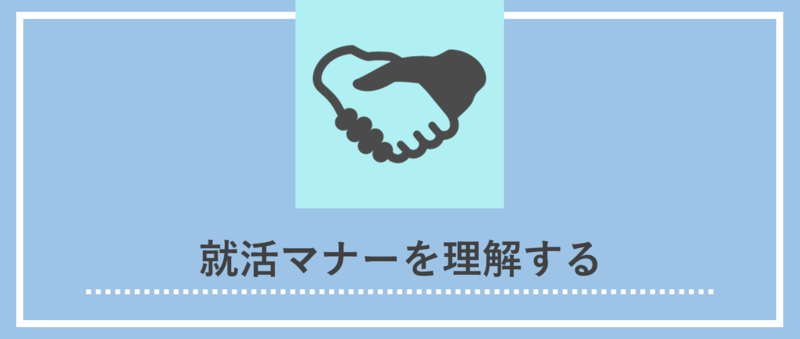
OB・OG訪問や面接に臨む前に、適切な就活マナーを理解しておくことは重要となります。
というのも、就活マナーの良し悪しは「印象面」に大きく影響し、その印象面は選考における評価を左右するためです。
適切な就活マナーを理解していないというだけで、悪印象をもたれたりマイナス評価を受けてしまっては非常にもったいないですので、以下の記事も参考にしながら適切な就活マナーを理解していただければと思います。
【就活の面接マナー対策完全版】服装・持ち物・入退室・メール・電話など
【就活】集団面接における入室・退室のマナーや流れを解説
【リクルーター面談の正しいマナーとは】基本マナーからメール・電話まで
エントリーシート(ES)郵送時の封筒の選び方・書き方-図解を用いて解説-
また、辞退に関するマナーは以下の記事を参考にしていただければと思います。
【就活ステップ(6)】OB・OG訪問とリクルーター面談に臨む
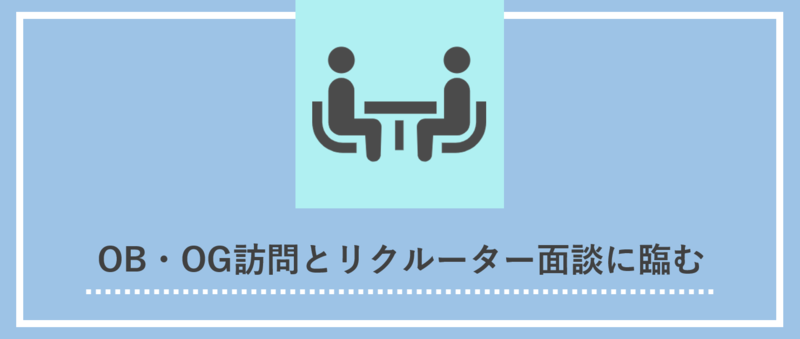
実際の現場社員から仕事について直接聞けるOB・OG訪問は積極的に活用するべきだと考えていますが、一方で漫然と「何となくやった方がよさそうだから」というスタンスでOB・OG訪問に臨むことは、就活生とOB・OG双方にとって無駄な時間になります。
また、忙しい中時間を割いてくれるOBやOGに対しても失礼でしょう。
OB・OG訪問に臨む際の適切な目的意識と、コミュニケーションのエッセンスを下記の記事にまとめています。
【参考記事】
OB訪問やり方大全!OB訪問の目的から時期・質問内容まで徹底解説
【ワンランク上のOB訪問】仮説に基づいた質問作成術39選
OB訪問の流れ・メリット・2回目に繋げてもらうための方法を解説!
【OB訪問アプリ8選】就活で勝者になるために使うべきおすすめアプリ
OB・OG訪問に比べ、より選考に影響があると言われているものがリクルーター面談になります。
リクルーター面談も、実際の現場社員へ直接質問したり現場社員からの質問に回答するというものにはなりますが、こちらは選考フローの一貫として盛り込まれている場合も多くあります。
特に金融業界・インフラ業界の企業に多いのですが、リクルーター面談が「実質の一次面接の役割」をしている場合もあるため、何の対策もせずに臨むのは避けるべきでしょう。
以下の記事も参考にしながら、リクルーター面談に向けた準備をしていただければと思います。
【就活】リクルーターとは?|メリット・意味・役割を徹底解説
リクルーター面談の対策は何をするべき?質問・逆質問例と対策方法を紹介
【リクルーター面談における逆質問とは】具体例とNG例を徹底解説
【リクルーター面談の正しいマナーとは】基本マナーからメール・電話まで
【例文付】リクルーターへのメールの書き方と正しいマナー|日程調整・お礼
【リクルーター面談の正しい電話マナーとは】日程調整・緊急の連絡
【リクルーター制度実施企業一覧39社】選考との関連性と条件を掲載
【就活ステップ(7)】エントリーシート(ES)を書く
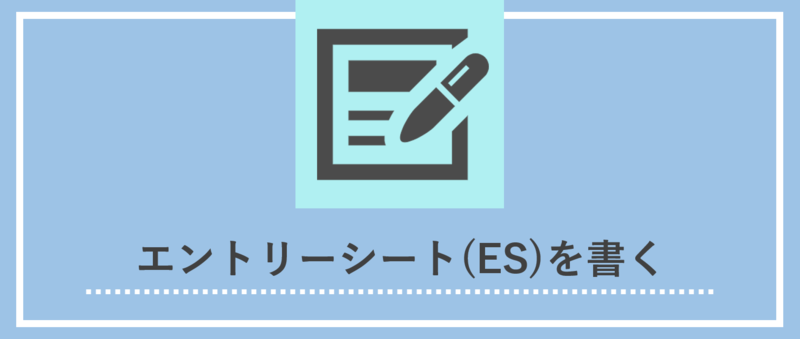
エントリーシート(ES)を書く際は、以下の5ステップに沿って書くのが望ましいとされています。
(1)企業が求める人材をビジネスモデルおよび働き方から知る
⇩
(2)トップ企業内定者のエントリーシートを複数読む
⇩
(3)内定者のエントリーシートに共通項がないか考える
⇩
(4)学生時代頑張ったこと、自己PRのフレームワークに基づき自分の経験を整理する
⇩
(5)自分が書いたものを第三者に評価してもらう
※記事以外に、内定者のエントリーシート(ES)や選考レポートが読みたいという方は、こちらからご覧いただけます。
ただ、上記の5ステップをおろそかにしている就活生は意外なほどに多いと感じます。
以下の記事も参考にしていただきながら、エントリーシート(ES)を書く際のコツを掴んでいただければと思います。
エントリーシート(ES)の書き方対策記事まとめ|自己PR・志望動機・ガクチカ
【エントリーシート(ES)の書き方入門】評価されるESの作成方法の基本
【設問別例文付】エントリーシートの書き方 頻出質問への回答方法を解説
また、エントリーシート(ES)の定番設問と言われているものに"学生時代頑張ったこと(通称ガクチカ)と自己PR"の2つがあります。
この2つの定番設問に特化した記事を確認したい方は以下の関連記事をご覧ください。
【ES例文8選】ガクチカとは?自己PRとの違いからポイントまで徹底解説-unistyle独自取材付き-
【ガクチカが本当にない人向け】意外な経験でガクチカを書く方法|例文5選
ガクチカの書き方とは-6ステップで書けるESテンプレを基に解説-
【ガクチカ例文】エピソード別にESの書き方を解説
新卒就活の自己PRとは-種類別例文19選と共にNG自己PR例も紹介-
自己PRすることがない!強みの見つけ方から回答例まで解説
文字数別で自己PRの書き方と例文を解説‐100字/200字/400字/500字/600字/800字‐
【例文31選】自己PR例文を経験・強み・職種別に紹介。面接で高評価を得るための伝え方とは?
学生時代頑張ったこと(ガクチカ)や自己PRと違って汎用性はないですが、"志望動機"もエントリーシート(ES)の定番設問になります。
正直なところ、志望動機はざっくりでも構わなく、「企業理念を理解し、共感しなければ…」などと固く考える必要はありません。
志望動機を構成する要素の一つである「企業・人生で成し遂げたいこと」を抽象化すると、大体が下記のいずれかに分類されるのではないでしょうか。
- 個人としての成果が明確な環境で、周囲と切磋琢磨できる仕事がしたい
- 個人の考えや行動が価値となる仕事、ヒトで勝負できる仕事がしたい
- スキルや価値観の異なるメンバーと協力して、共通の目標を求める仕事がしたい
- 新しい仕組みや事業を生み出す仕事がしたい
- 顧客と信頼関係を構築してニーズを引き出し、ニーズや課題を解決するための提案ができる仕事がしたい
このようなテンプレートを用いても、それらと結びつく具体的な経験を通して「あなたらしさ」を伝えることは可能です。
逆に、企業について一生懸命調べたことを並べただけの志望動機の方が、「あなたらしさ」の欠けた誰にでも書けてしまうエントリーシート(ES)なのではないでしょうか。
【新卒】就活の志望動機とは?書く時の注意点やテンプレも紹介-例文5選付-
【新卒】3ステップで完成!通過率を上げる志望動機の書き方|ES例文付
【例文12選】インターンシップの志望動機の書き方を業界・字数別(200字/300字/400字/500字)で解説
エントリーシート(ES)の設問は、上記で取り上げた「学生時代頑張ったこと(ガクチカ)・自己PR・志望動機」以外のものもあります。
その他設問の対策に関する記事は、以下からご確認ください。
長所と短所(強みと弱み)のES例文44選-エントリーシートの書き方付-
企業選びの軸(就活の軸)の定め方とES(エントリーシート)例文を紹介 -大手企業内定者の回答例13選-
【大手企業ES12選】「気になるニュース」を回答する際のポイントは3つ!
例文8選|挫折経験の魅力的な書き方とは?ない時の対処法や面接での答え方
【就活ステップ(8)】Webテスト・筆記試験・適性検査を受験する
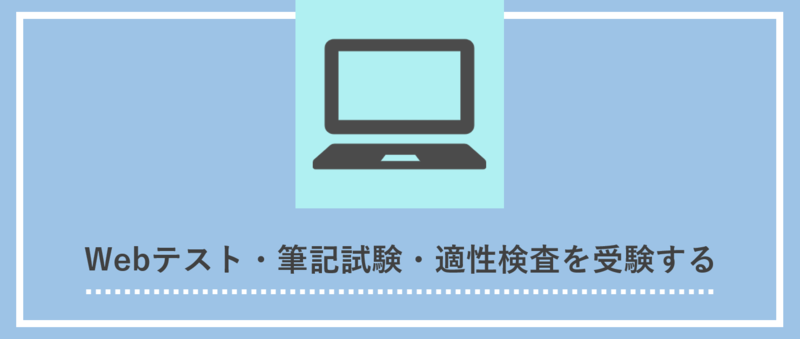
Webテストや筆記試験はエントリーシート(ES)と同様、一次選考などの初期の選考フローで課されることが多いものです。
テストの種類も多く、且つ一朝一夕で対策できるものでもないため、苦手と感じている就活生も多いのではないでしょうか。
ただエントリーシート(ES)や面接と異なり、選考突破の基準となる点数を取れたか否かで合否が判断されるため、見方を変えれば「最も対策のしやすい選考フロー」とも言えます。
ほとんどの企業の選考で避けては通ることができないものになるため、早め早めの対策・準備を心がけていただければと思います。
Webテストとは?受験形式や問題数、時間などを解説
【就活生必見!】17種類の適性検査まとめ、Webテストの種類と対策を知る
【Webテスト対策】基礎知識やオススメの本・アプリ・分野別対策などを解説
Webテストの答えを使うのはNG-解答集や替え玉受験など不正行為のリスクも解説-
【26卒向け】無料で試せるWebテスト(適性検査)サイト4選-SPI・玉手箱の対策をしよう-
また、Webテストには「SPI・玉手箱・TG-WEB」など、様々な種類のテスト形式があります。
各テスト形式の詳細な対策を調べたい方は、以下の関連記事からそれぞれ確認していただければと思います。
【SPI対策まとめ】これで完璧!初心者~上級者別SPIテストセンター対策を解説
【玉手箱の完全対策】言語・計数・英語の例題や最新出題企業を掲載
【TG-WEB対策】問題例・従来型(旧型)と新型の特徴などを解説
【就活ステップ(9)】グループディスカッション(GD)に臨む
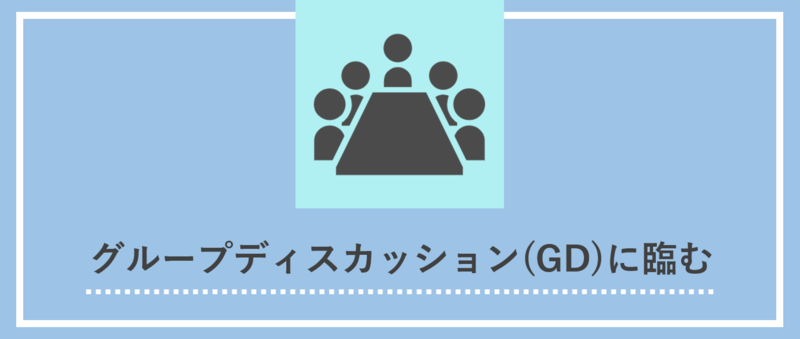
グループディスカッション(GD)については、「やれタイムキーパーだ、やれ書記だ」といった役割系のくだらない情報が世の中に溢れています。
ただ、あるべき目的意識は「グループでよりよい結論を導くこと」に集約されると考えています。
各々が議論に対する自分なりの貢献を考えた結果が役割として表れるのはよいのですが、自分が評価されようとして役割に固執し、議論をぎこちなくするのは論外です。
まずは自分一人でも論理立てて結論まで導けるようになった上で、チームで取り組む上での所作がある程度できていれば、落ちることはほぼないと考えてもらっていいでしょう。
グループディスカッションとは?対策、テーマ、進め方、練習方法などのコツを伝授
グループディスカッション(GD)の対策とは?通過率を上げるコツを紹介
【グループディスカッション(GD)の頻出テーマ89例】業界別に過去の出題テーマも公開
グループディスカッション(GD)の進め方とは?6つのコツとテーマごとの進め方をわかりやすく解説
グループディスカッションの役割とは?司会・書記・タイムキーパーの対策方法を徹底解説
【グループディスカッション練習11選】一人でも複数人でも出来る完全対策
【就活ステップ(10)】面接に臨む
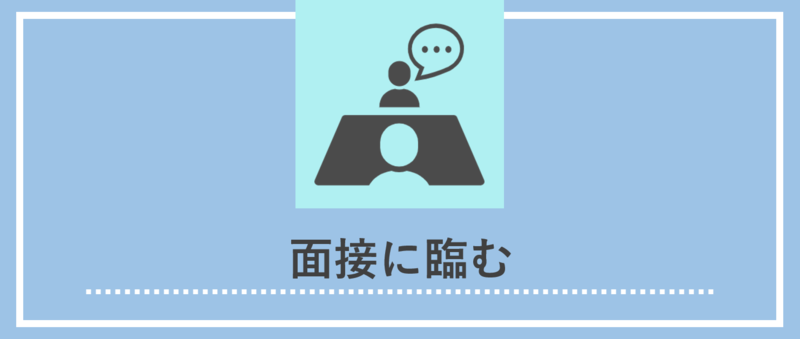
面接で聞かれる質問は、型がある程度決まっています。多少表現を変えたものが出てくることもありますが、下記に掲載した記事の内容を押さえておけばそこまで困ることはないでしょう。
また、エントリーシート(ES)を執筆する段階から、その先の面接を想定しておくことも重要となります。
【面接とは】意味や面談との違いから対策・頻出質問・マナーまでを解説|就活
【就活面接の頻出質問集と回答例まとめ】回答ポイントも紹介
【逆質問例21選】就活の面接ですべき逆質問とは-NG例付-
【就活の面接マナー対策完全版】服装・持ち物・入退室・メール・電話など
【就活の面接対策】頻出質問例から練習・準備方法までを解説
【就活】面接練習は何をするべき?練習方法9選と対策すべき質問を解説
【就活】面接の準備は何をするべき?準備不足で後悔しない当日を迎えるための準備とは
【就活ステップ(11)】内定から入社までを考える
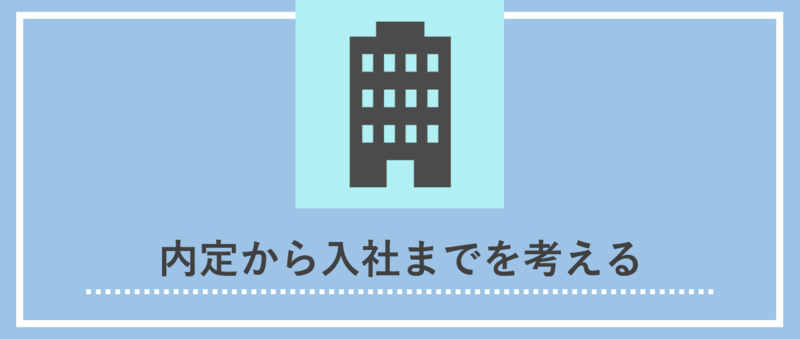
ここまで紹介してきた内容は「志望企業の内定を獲得するためのステップ」でしたが、大学4年生の6月頃を過ぎると"内定を獲得したいくつかの企業の中から、実際に入社する企業を決める"という段階を迎えます。
現代の就活市場では多くの就活生が複数社からの内定を獲得し、10社以上の内定を獲得する人も珍しくありません。
とは言え、最終的に入社できるのは1社だけですので、以下の記事も参考にしながら「納得のいく企業選び」をしていただければと思います。
【就活ステップ(12)】働き方・キャリアを考える
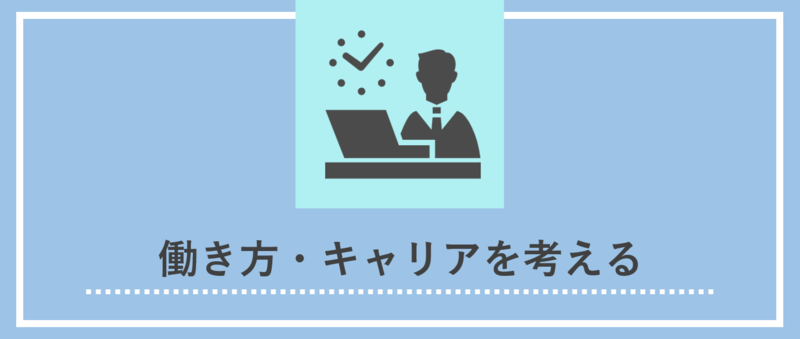
「入社後の働き方・将来のキャリア」と聞くと、かなり遠い先のことと感じる就活生もいるかと思いますが、就活中からこのような観点を意識しておくことは重要です。
もちろん、就職活動のゴールは「志望企業からの内定を獲得し、納得して就活を終えること」です。しかし、人生という長いスパンで考えると、志望企業からの内定を獲得することは"スタート地点"に過ぎません。
人生の大部分を占めると言われている「仕事」をより充実したものにするため、就活生の段階から働き方・キャリアを考えておいてみるのも良いと思います。
【就職活動の意味】安定を得るために必要なこととは?
最後に

意外と多くの就活生が今回紹介した記事の内容を意識せず、なんとなくの就職活動をしているものと思います。
また、記事を読んだ上で実際に行動するのはおそらく1〜2割程度の人だけだとも思っています。多くの就活生が中々動けないからこそ、記事を読んで実践するだけで大きく差をつけられるはずです。
今後も皆さんにとって有益なコンテンツを追加していきますので、適宜チェックしてみてください。
人事と求職者を繋げる採用知識サイト|採用百科事典