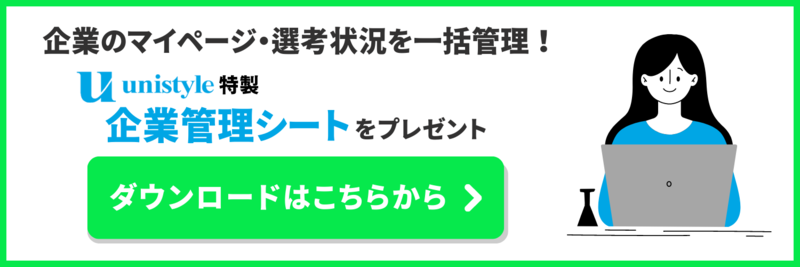合同企業説明会を無駄な時間にしないための3つの方法
54,097 views
最終更新日:2023年10月31日

例年、合同企業説明会に参加しただけで就職活動を頑張った気になってしまう人が一定数いるように感じています。
合同企業説明会で説明ブースに座ってはいけない3つの理由でも書いた通り、ただ受動的に参加して話を聞いているだけではHPに掲載されている程度の情報を得ることしかできません。
3月1日から企業の採用広報活動が解禁されるため、それに合わせて合同企業説明会が数多く開催されます。
そこで今回、合同企業説明会への参加を最大限効果的にするための3つの方法について書いていきます。
参加する目的意識を明確にする

合同企業説明会は無駄だという意見も実際あります。皆さんの中にも、サークルの先輩などから「あんなの行くだけ無駄だよ」などと言われた人もいるのではないでしょうか。
しかしそれは何のために参加するのか明確にせず、「皆が行くから行く」とか「就活気分を味わうために」などといった、いわば夏にお祭りに行くような風物詩的な気持ちで参加しているからだと言えます。
合同企業説明会も、事前に参加する目的を明確にしていけば無駄にはなりません。
ここでの目的とは、下記の3つになると思います。
- ①志望度の高い企業の人事に気に入られる
- ②志望度の高い企業の社員・内定者と知り合ってOB訪問など就活のアドバイスをもらう
- ③自主的には調べなさそうな企業の説明を聞いてみて自分の興味の幅を広げる
①志望度の高い企業の人事に気に入られる
もし合同企業説明会に志望度の高い企業が参加しているのであれば、人事に気に入られるつもりで行きましょう。
具体的には、よく説明の最後に設けられる質疑応答の時間に鋭い質問ができると評価されやすいと思います。
下記は面接における逆質問についてのコラムですが、説明会の質疑応答についても同様のことが言えるので参考にしてください。
一概には言えませんが、自身の価値観や経験に基づいた意図が明確な質問であれば評価されやすいように思います。
逆に評価されない質問は次のようなものが挙げられます。
- 「残業時間はどのくらいですか?」「福利厚生はどうですか?」といったような自分の不安を解消させたいだけの質問
- 「御社の社風はどのようなものですか?」といった答えにくく、そもそもそれを聞いてどうしたいのかという質問
- 「御社の強みは何ですか?」といった、会社のHPや四季報を読めばわかるような質問
合同企業説明会で説明ブースに座ってはいけない3つの理由でも書いているように、一度ブースに座ってしまうと抜け出しづらく時間を食ってしまうというデメリットがありますが、質疑応答で指されやすくするためにあえて前列に座るという手段を採用するのもアリですし、立ち見の学生に混じって質疑応答のタイミングを見計らってブースに寄るのも一つかと思います。
それぞれメリット・デメリットがあるため、どういった方法を用いるのかはご自身の判断で決めていただければ幸いです。
②志望度の高い企業の社員・内定者と知り合ってOB訪問など就活のアドバイスをもらう
せっかく現場で働く社員と触れ合えるのであれば、その場限りの付き合いで終わってしまうのは非常にもったいないことです。また、説明会に参加している社員はいわゆる「デキる人」であることも多いため、可能であればコネクションを作っておきたいところ。
社員とのコネクションを作るには、企業講演の隙間時間などで名刺をもらい後日、しっかりとしたお礼のメールとOB訪問のお願いをするのが有効的です。また、大手企業になると内定者をアルバイトとしてお手伝いに呼んでいる場合もあるため内定者と仲良くなることもできるかと思います。
実際、内定前から企業の社員や内定者と仲良くなって「引き上げてもらう」経験をしている学生も少なくありません。多くの社員に目をかけてもらい内定に近づくというのも立派な戦略だと言えるでしょう。
③自主的には調べなそうな企業の説明を聞いてみて自分の興味の幅を広げる
冒頭でも書きましたが、企業ブースでの説明は、そのほとんどが企業HPに掲載されている内容をきれいにスライドにまとめただけのものです。そのため自分から積極的に調べるような志望度の高い企業のブースに、情報収集のためだけに座るのであればあまり意味はありません。
逆に言えば、自分からは企業HPを見ようと思わないような業界・企業のブースには参加する意味があると言えます。わかりやすくスライドなどでプレゼンしてくれるので、もしかしたら一気に志望度が上がることもあるかもしれません。
就職活動を始めたばかりの視野の狭い状態で、特定の業界に固執するのは大きな機会損失です。志望業界は持ちつつも、偏見なしに幅広い業界を見ていくことは就活のリスクヘッジの上でもビジネスを知る上でも有効であると言えます。
最後に

合同企業説明会に限らず、周囲に流されて何となく行動すると無駄な時間を過ごしがちになります。自分がそこで何をするのか、目的を明確にした上で行動すればより少ない労力で大きな成果が得られるのではないでしょうか。
告知
なお、21卒対象で2月から合同説明会「レクミーLIVE」が全国で開催されます。以下のページからお申込みできるので、是非活用してみてください。
三菱商事、三井物産、住友商事、伊藤忠商事、サントリー、三菱地所、野村総合研究所、アマゾンジャパン、トヨタ自動車、ベイン・アンド・カンパニー、ユニリーバ、P&Gジャパン、楽天など