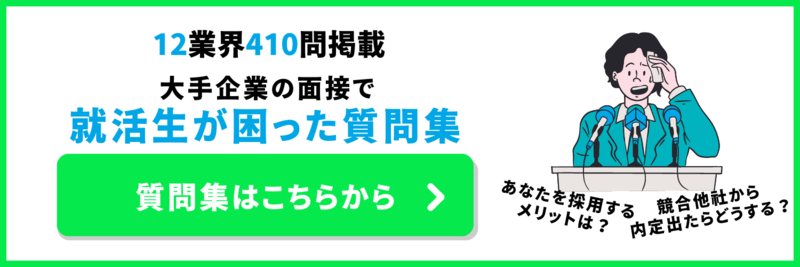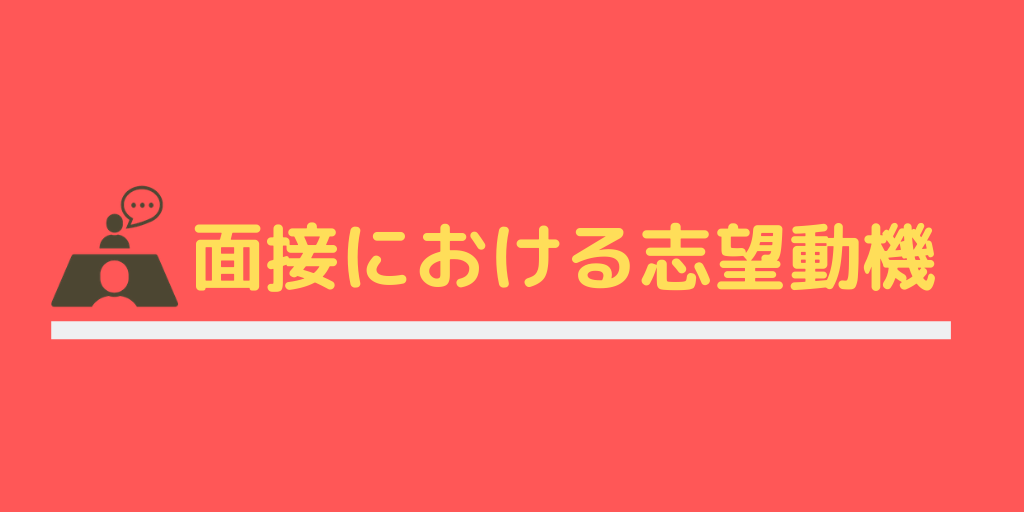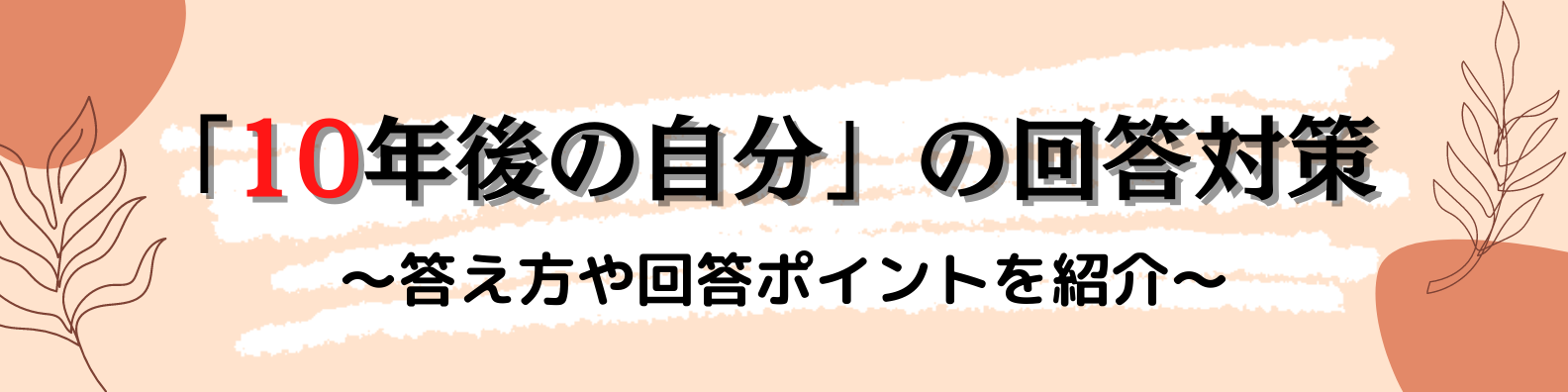【就活】模擬面接とは?本選考・インターンシップ選考で重要な面接対策のやり方
24,695 views
最終更新日:2022年02月02日
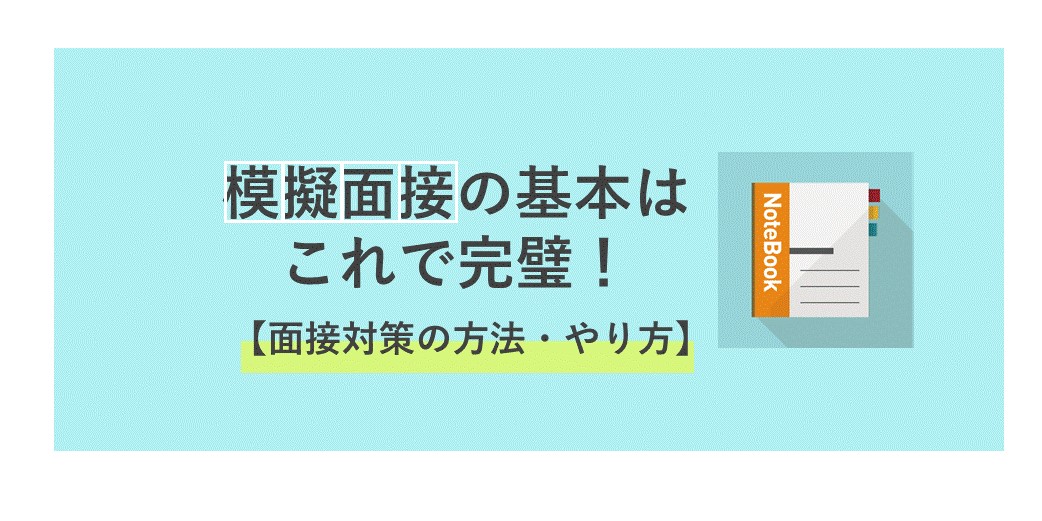
面接とは(面接を課す意味・評価基準・面談との違い)
面接の頻出質問一覧と回答例(志望動機・自己PR・ガクチカなど)
面接の逆質問一覧(考える際のポイント・具体例)
面接で必要なマナー(入退室・身だしなみ・メール・電話)
面接の対策(一次面接・二次面接・最終面接・集団面接・WEB面接・ケース面接・圧迫面接)
面接の練習(練習方法・ポイント)
面接の準備(選考通過に向けた準備・当日に向けた準備)
面接質問集(大手企業の面接で実際に聞かれた質問を厳選して掲載)
就職活動において最大の難関である、面接試験。志望企業からの内定を勝ち取るためには対策が必須となりますが、数ある対策方法の中でも基本となるのが「模擬面接」です。
本記事では、「模擬面接とは具体的にどんなメリットがあるのか。」「どのような方法で受けられるのか。」「何に留意して臨めばよいか。」などの疑問を持っている方に向け、模擬面接の概要について説明していきます。
模擬面接とは
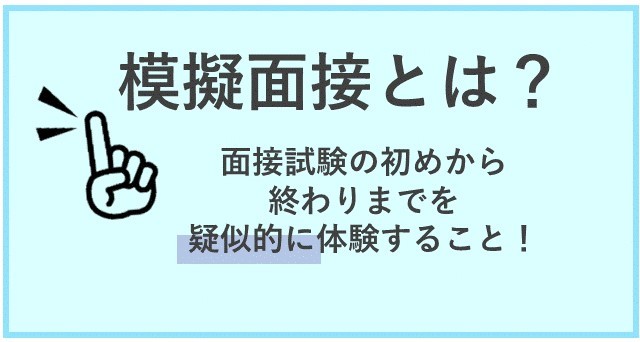
模擬面接とは、実際の面接状況を再現して、入室から質疑応答、退室までの一連の流れを疑似的に体験することです。就職活動における最大の難関である面接試験の基礎的な練習となり、内定を勝ち取る上で重要となります。
模擬面接を受ける目的・メリット
模擬面接を行う目的は大きく分けて以下の3点が挙げられます。
・面接に慣れ、本番で思うように話せるようにするため
初めての面接が本番当日となれば、緊張でうまく話すことが出来ないかもしれません。本番の前に練習をしておくことで、当日の流れを予行練習することが出来、自信を持って面接に臨むことが出来ます。
・複数人の面接官との面接や圧迫面接など、様々な設定で練習ができるため
面接には個人面接・グループ面接、圧迫面接など様々な種類があり、自身の志望する企業がどの種類の面接を行っているのかに合わせて、対策をする必要があります。
面接の種類によって面接官が重視して評価したいポイントが異なるため、この対策が出来れば就職活動を有利に進めることが出来ます。
・自身の弱点を知るため
一例ですが、ビデオカメラなどで模擬面接の風景を記録に残すことで、より客観的に自分を見つめ直すことが出来ます。弱点を知るには第三者の声が必要であり、これを通じて普段は自身が気づかない表情や声の調子について改善ができるのです。
無料でも模擬面接が受けることができるのか?
実は大学のキャリアセンターやハローワーク(ジョブカフェ)、就活エージェントなどでは、就活のプロ・就活の専門家の模擬面接が無料で受けられます。家族や友人と模擬面接をするのもよいですが、就活支援機関を利用して緊張感のある模擬面接をしてみてはいかがでしょうか。
また、Skype等を用いてオンラインで模擬面接を受けることが出来るWebサイトもあります。
模擬面接はどんな人におすすめなのか?
ほとんど全ての就活生が模擬面接を受けるべきでと考えられますが、特に「自己分析や業界分析が終わり、志望する企業が大方固まった就活生」や「言葉遣いや入退室時のマナーに不安を抱えている就活生」は受けてみることをお勧めします。
【自己分析とは?】これで攻略間違いなし!自己分析の目的と進め方
→自己分析の方法・目的について解説している記事です。
【26卒向け】日系大手志望者の就活スケジュール完全版!内定を得るために必要な9ステップとは
→就活のスケジュールについて解説しています。自己分析や模擬面接をどのようなタイミングで行うのが適切なのかが分かります。
模擬面接の方法3選
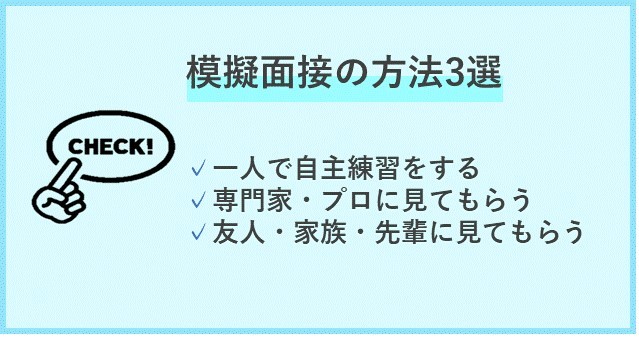
続いては模擬面接の方法・やり方として以下の3つを取り上げ、それぞれの特徴やメリット、効果的な実施方法などを解説していきます。
- 一人で模擬面接を行う
- 専門家やプロに模擬面接をしてもらう
- 友人・家族・先輩に模擬面接をしてもらう
一人で模擬面接を行う
自宅で一人で行う場合は、自分が面接官からどのように見えているかをより客観的に確認するために、ビデオカメラやスマートフォンなどで撮影をすることが効果的です。
いきなり模擬面接を行うことに抵抗がある場合、その事前準備としても有効です。自身のスケジュールによって柔軟に練習日程が組めますが、フィードバックがもらえないというデメリットもあります。
専門家やプロに模擬面接をしてもらう
この場合の面接官は外部のプロ講師が務めることが多く、たくさんの就活生に面接をしてきた経験値の高い方から、フィードバックを受けることが出来ます。また、個人面接だけでなくグループ面接やグループディスカッション等、数多くの面接を練習できる場合も多いです。
友人・家族・先輩に模擬面接をしてもらう
友人や家族、先輩に面接官役をしてもらい、練習をします。模擬面接で感じた素直な感想・フィードバックを聞くことができます。
特に練習したい質問に対して入念に準備して模擬面接を行うと効果的です。
模擬面接・面接対策が受けられる場所
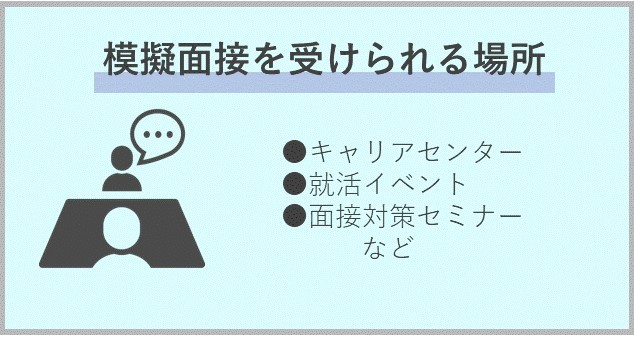
続いては模擬面接・面接対策が受けられる場所として4つを取り上げ、それぞれの概要・特徴について解説します。
大学のキャリアセンター(就職課)
学校で、個人またはグループを選択して面接対策ができます。無料で受講できるので積極的に活用しましょう。学校のwebサイトやキャリアセンターの受付から事前予約が可能です。
ハローワーク(ジョブカフェ)
20代の若年層向けの就活支援サービスでは就活の無料講座を行っています。ハローワークに併設しているジョブカフェにて、無料で受講できます。
模擬面接のような就職活動に関する講座は平日に行われることが多く、講師は外部のマナー講師やキャリアコンサルタントらが行う、といった特徴があります。
就活イベント
多くの企業が集まる合同説明会での面談体験ブースで、模擬面接が体験できます。中には面接官役を企業の人事担当者が行うこともあり、貴重なフィードバックがもらえることも少なくありません。
多くの就活生がイベントへの参加を希望し、面接体験も満席となりやすいため、事前予約の有無や整理券の配布などを確認しておく必要があります。
面接対策セミナー
就活支援塾やキャリア支援会社が行う面接対策セミナーを活用することもできます。有料でマンツーマンレッスンを行っており、お金がかかってしまうものの一部ありますが、他人の目を気にせず練習でき、その場で疑問点を質問しやすいといったメリットもあります。
面接対策として練習しておきたい模擬面接
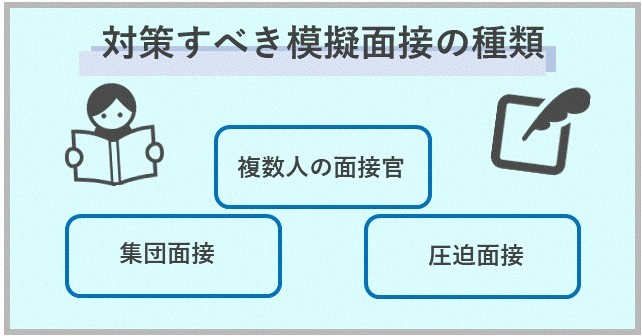
面接対策として練習しておきたい模擬面接の内容・種類について、面接の概要、面接のポイントなどを解説します。
複数人の面接官がいる模擬面接
実際の面接では、面接官が複数人いることもあります。思いがけない質問をされることが多くなり、うまく受け答えできるかがカギとなってきます。
またこの練習をすることで「大人数に対するプレッシャー」に慣れることができます。そのため模擬面接でもなるべく複数の面接官とやり取りをすることが効果的です。
圧迫面接を想定した模擬面接
圧迫面接とは、わざとプレッシャーがかかる質問をしたり、無視するような態度をとったりして、応募者のストレス耐性や対応力をチェックする面接のことです。これを行う企業は、ストレス耐性に強く、対応力の高い人材を求めているといえるでしょう。
大きな声で攻め立てたり、無視をしたりパターンは様々ですが、本番でうまく対処するために念入りに事前の対策を行う必要があります。
個人面接・集団面接(グループ面接)両方の模擬面接
個人面接を行うか集団面接を行うかは企業によって異なりますが、いずれの場合も対策しておくことに越したことはないでしょう。
個人面接では「自己紹介」や「学生時代に頑張ったこと」「挫折経験」をはじめとするあらゆる質問を想定し、対策しておくことが望ましいでしょう。志望者が複数人いる集団面接では、「限られた短い時間のなかでいかに自己PRができるか」が求められています。
自分が面接官役となる模擬面接
「もし自分が面接官になったら」と考えることで、面接官の視点に立つことができます。更に面接官の視点に立つために、採用や面接に関する本を読んで勉強することもおすすめです。
模擬面接を受ける際の準備・ポイント・注意点
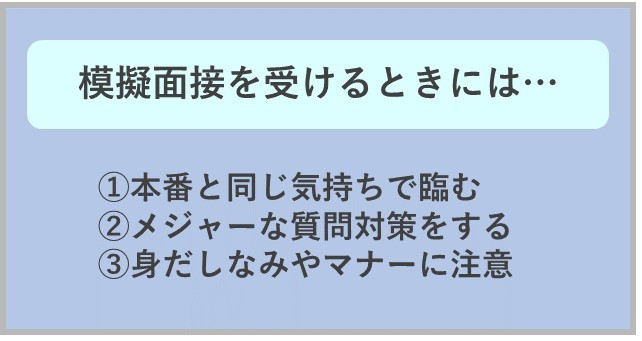
模擬面接を受ける際の準備・ポイント・注意点として、7つを取り上げてそれぞれについて解説します。
本番と同様に模擬面接に臨むことが大切
模擬面接はいくら「模擬」だとはいえ、本番の面接と同じ気持ちで臨むべきでしょう。しっかりと準備を行った分だけ、フィードバックから本番に生かせるものが明確になるためです。
対策しておくべき質問内容
「志望動機」「自身の長所と短所」「学生時代に頑張ったこと」などは非常にメジャーな質問であり、どの企業でも質問されるといっても過言ではありません。
【新卒】3ステップで完成!通過率を上げる志望動機の書き方|ES例文付
→選考に受かりやすい志望動機の書き方を紹介しています。
長所と短所(強みと弱み)のES例文44選-エントリーシートの書き方付-
→自身の長所と短所をどのようにESに書くのか、解説しています。
ガクチカの書き方とは-6ステップで書けるESテンプレを基に解説-
→「学生時代に力を入れたこと」をどのようにESに表現するか、また評価基準はなんであるか説明している記事です。
服装・身だしなみのポイント
服装・身だしなみの基本と併せて、男性・女性ごとの服装・身だしなみのポイント・注意点をいくつか解説していきます。
普段慣れないスーツを着ると緊張し、面接に集中できないことがあります。本番で最大限に自分の魅力を発揮するために、模擬面接の段階から清潔感のあるスーツスタイルを心掛けるべきでしょう。
→黒髪、髭をきちんと剃る、眉毛を整える
女性
→黒髪、長い髪は地味なヘアゴムでまとめる、控えめで清潔感のあるナチュラルメイクを心掛ける。
上記に挙げたように男女ともに華美でない服装・身だしなみに留意しましょう。
入室時・退室時のマナー
面接における入室時・退室時のマナーについて、ポイント・注意点をいくつか解説します。
(1)ドアを三回ノックする
ドアを3回軽くノックします。「どうぞ」という声が聞こえてから「失礼します」と言ってドアを開けます。
(2)入室しドアを閉める
部屋に入ったら、ドアのほうを向いてドアを閉めます。後ろ手で閉めることのないよう注意しましょう。
(3)面接官を向いてお辞儀
面接官に向かって30度の角度でお辞儀をします。お辞儀の前に「よろしくお願いいたします」と述べてもよいでしょう。
(4)椅子の横に立つ
椅子の前まで歩き、「着席してください」の指示を待ってから着席します。
(5)着席する
「どうぞ」と言われたら「失礼いたします」と言い、着席前に15度のお辞儀をしてから座ります。座っているときは、椅子に深く腰掛けない、背筋を伸ばし顎を少し引くという点にも留意しましょう。
(1)椅子から立ち上がりお礼
面接が終わったら起立をし、「本日はお忙しい中、お時間をいただきありがとうございます」と言い、45度の深めのお辞儀をします。
(2)ドアの前でお辞儀
「失礼いたします」と言い、30~45度の角度で丁寧にお辞儀をしてからドアを開けて退室します。
声の大きさ・スピード・言葉遣い
面接における声の大きさ・スピード・言葉遣いについて、ポイント・注意点をいくつか解説します。
ぼそぼそと話すと暗い印象を面接官に与えてしまいます。普段よりも声のトーンを高く、話す速度は少しゆっくり目を心掛け、相手に伝わりやすく話すようにしましょう。
また、正しい敬語を用いて社会人としての常識を守ることも重要です。
表情・姿勢
面接における表情や姿勢について、ポイント・注意点をいくつか解説します。自然な笑顔を心掛け、落ち着いて面接に臨みましょう。
立っている場合
→頭のてっぺんが糸でつるされているようなイメージで立ち、顎を少し引きます。
座っている場合
→椅子に浅く腰掛け、背もたれにもたれないように心がけます。本番で美しい姿勢を保てるよう、普段から心掛けることが重要です。
面接後にフィードバックをもらい、改善するまでが模擬面接
友人や家族、専門家からのフィードバックを受け、それを改善した上で本番の面接に臨みましょう。余裕があれば改善した後、もう一度模擬面接を受けることをお勧めします。
まとめ
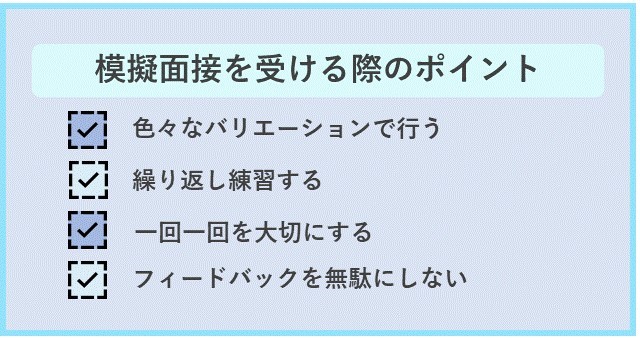
面接対策として非常に有効な模擬面接。なるべく多くのバリエーションを持たせて、繰り返し練習することが重要です。
そのために、「多くの練習の機会を複数の人行うこと」、「一回一回を大切に、フィードバックを無駄にしないこと」がポイントでしょう。
悔いのない就活をするため、綿密な練習を重ねましょう。
面接とは(面接を課す意味・評価基準・面談との違い)
面接の頻出質問一覧と回答例(志望動機・自己PR・ガクチカなど)
面接の逆質問一覧(考える際のポイント・具体例)
面接で必要なマナー(入退室・身だしなみ・メール・電話)
面接の対策(一次面接・二次面接・最終面接・集団面接・WEB面接・ケース面接・圧迫面接)
面接の練習(練習方法・ポイント)
面接の準備(選考通過に向けた準備・当日に向けた準備)
面接質問集(大手企業の面接で実際に聞かれた質問を厳選して掲載)