「就活は団体戦」という言葉をとあるシチュエーションで解説してみた
9,321 views
最終更新日:2023年11月01日

"就活は団体戦"
就活生の皆さんはこの言葉を聞いたことがあるでしょうか。
事実、「就活は団体戦」という考えは間違ってはいないと考えられます。
と言っても「団体戦って具体的にどういうこと?」、「別に個人戦でもうまくいく人はいるでしょ」と思う方もいると思います。
unistyleとしては、「就活は団体戦」という言葉を"就活は、周りの方と協力して進めることで自分だけでは知りえない情報・新たな発見を得ることができ、効率的な行動に繋がる"と定義づけることができると考えています。
そこで本記事では「就活は団体戦」という言葉をより分かりやすく解説するために、とあるシチュエーションに基づいて紹介していきます。
また、併せて「就活は団体戦という言葉の注意点」も紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。
就活は団体戦をとあるシチュエーションに例えてみると

※下記に記載している物語はフィクションであり、unistyleが独自に作成したものになります。文中に出てくる登場人物・企業名なども全て仮名ですので、参考程度にご覧ください。
ちなみに、この物語の主人公である「ユニ男」のプロフィールは以下の通りです。
- 都内の有名私立大学に通っている文系学生
- 総合商社への内定を目指している
また、物語の登場人物である「よっぴ・あんちゃん・なっちゃん」のプロフィールは以下の通りです。
- よっぴ
エントリーシート(以下、ESと明記)が得意
インターンからの特別選考ルートで大手広告代理店B社に内定 - あんちゃん
GDが得意
早期選考でメガベンチャーC社に内定 - なっちゃん
面接が得意
学校推薦で大手メーカーD社に内定
各登場人物のプロフィールを紹介したところで、いよいよ物語に入っていきましょう。
この物語は、「ユニ男が就活を意識し始めた大学3年生の夏」から始まります。
大学3年生の夏
周りの友達が少しずつ就活のことを意識し始めた大学3年生の夏、ユニ男も周りの友達と一緒にインターンに参加し始めました。
この時期はまだ志望業界・企業などは特になく、且つ選考対策もほとんどしていなかったため、"先着・抽選制の1dayインターン"だけに申し込みをしました。
その結果、見事全てのインターンに合格・参加することができました。
そしてどのインターンでも比較的楽しく活動することができ、「就活ってこんなものか。世間一般では有名な大学に通っているし、このままいけば順調に内定を貰えそうだな。(ユニ男の心の声)」とこの頃は思っていました。
大学3年生の冬
充実した夏休みが終わり、その後秋学期が始まり、いよいよ冬がやって来ました。
そしてこの辺りの時期から、多くの企業で「冬季インターンの申し込み」が開始します。
「夏季インターンがうまくいった」と感じていたユニ男は、夏季インターン参加後は全く就活対策を行っていませんでした。
また、この頃から「高い給与が欲しい・海外で働きたい」という軸を持ち始めたユニ男は、志望業界を"総合商社・専門商社"に絞ることに決めました。
そしてユニ男は、志望している企業の冬季インターンに片っ端から申し込みました。
⇩
ただその結果はというと…"申し込んだ企業、全落ち…。"
それもそのはず、申し込んだ冬季インターンでは全ての企業で何かしらの選考フローがあり、これまで全く選考対策をしてこなったユニ男にとっては"歯が立たなかった"のです。
そうこうしているうちに冬が終わり、3/1の「就活解禁日」が訪れました。
冬季インターンに全落ちし、すっかり自信をなくしてしまったユニ男は、その後もほとんど選考対策をせずに過ごしてきました。
しかし3月の某日、ふとしたきっかけで友達の「よっぴ・あんちゃん・なっちゃん」と4人で集まる機会がありました。
そしてこの日が、ユニ男の就活における"ターニングポイント"となったのです。
3月某日のとあるカフェにて
ユニ男
「3人ともすごいよな~。3月のこの時期に志望企業から内定を貰って就活が終了してるんだもんな~。オレなんか冬季インターンの選考に全滅しちゃって、全然経験が積めてないんだよ。今からの本選考が不安でしょうがないよ…。」
よっぴ
「ユニ男それやばくない?インターンに全落ちしたやつが何も対策しなければ、本選考で内定を取るのはかなり難しいよ!」
あんちゃん
「確かにそれはかなりやばいね。ちなみにユニ男はどの選考フェーズで落ちることが多かったの?」
ユニ男
「そうだな~、企業によってバラバラだな。一次選考で落ちるとこもあれば、最終選考で落ちるところもあったわ。だからこそ自分の何が悪いのか良くわからないんだよ…。」
なっちゃん
「なるほどね。じゃあせっかく今日はES・GD・面接のスペシャリストが集まっているし、ユニ男の就活対策をすることにしましょ!」
ユニ男
「マジで!?それはマジ助かる!どうしても総合商社に行きたいんだ!オレに協力してくれ!」
ES編
よっぴ
「じゃあまずはESのスペシャリストであるオレがユニ男のESを見てやるよ。普段使っているガクチカとかってあるか?」
ユニ男
「普段使っているのはこれかな~。指定文字数400文字のガクチカだな。」
ユニ男
「よっぴ、このESはどうだ?」
よっぴ
「正直に言ってもいいか…?ユニ男、このESじゃ中々通過しないと思うわ…。」
ユニ男
「…!!??(がーーーん…。)」
よっぴ
「どの箇所に問題があるかを説明してやるから、まずはガクチカの書き方とは-6ステップで書けるESテンプレを基に解説-を読んでみろ。」
ユニ男
「この記事にガクチカのフレームワークが書かれているが、オレのガクチカには書かれていない内容がたくさん書かれているな…。」
よっぴ
「そうだ、その箇所だ!ユニ男のESでいうと、"行動に至るまでの背景が書かれていない・結果(実績)の具体性が薄い"という問題があるっていうわけだ。」
ユニ男
「なるほどな。だからオレのESは内容が抽象的だって良く言われるのか。」
よっぴ
「そういうことだ!だから先ほどのフレームワークに沿ってESを添削すると以下のような文章になる!」
あんちゃん・なっちゃん
「すごい…エピソードは同じでも内容のわかりやすさが段違いだね…。」
ユニ男
「よっぴ、マジでありがとう!これを元にさらにESをブラッシュアップしていくよ!」
よっぴ
「おう!ちなみに"志望動機・自己PRのフレームワーク"に関する記事も以下に抜粋しておくから、ぜひ参考にしてくれ!」
GD編
あんちゃん
「じゃあ続いてはGDのスペシャリストである私がGDの選考突破の秘訣を教えてあげるね。ところでユニ男、GDにはテーマはいくつかに分類することができることは知っている?」
ユニ男
「え…いや…知らないわ…。」
あんちゃん
「まぁそうだと思ったわ。GDのテーマは主に以下の5つに分類されているよ。」
- ①課題解決型:与えられた課題に対する解決策を考える
- ②売上アップ型:企業の売り上げを増加させる方法を考える
- ③新規事業立案型:企業が取り組むべき新規事業を提案する
- ④抽象テーマ型:抽象的なテーマに対する解決策を考える
- ⑤意思決定型:与えられた選択肢の中から当事者が取るべき選択を決定する
ユニ男
「なるほど~。各テーマの型によって手順も変わるっていうことか。」
あんちゃん
「そういうこと。各テーマの進め方に関する記事は以下に記載しておくから、家に帰ってからゆっくり確認してね。」
なっちゃん
「ちなみにユニ男、あなたってGDでいつもどの役割を担っているかとかってある?」
ユニ男
「そうだな、基本的にはファシリテーター(司会者)を担当することが多いかな。」
なっちゃん
「なるほどね。ちなみにそれは何か理由がある?」
ユニ男
「えっ?だって統率力を発揮してグループを引っ張った方が良いんじゃないのか?あと、ファシリテーターをすれば受かるとも聞いたことがあるし…。」
あんちゃん
「はぁ~、やっぱり勘違いしていたわね。ユニ男、GDの評価基準は何もリーダーシップだけではないわよ。GDの評価基準は主に以下の4つに分類されると言われているわ。」
- 議論に臨む基本姿勢
- 議論のテーマや流れへの理解力
- 自身の意見の主張力
- 議論を統率するリーダーシップ
あんちゃん
「確かに、リーダーシップは一つの評価基準ではあるわ。しかし、それだけでは高い評価を得ることはできない。あらゆる評価基準を総合して評価されるというわけなのね。評価基準の詳細は以下に記載しておくから、帰りの電車の中とかで確認しておいてね。」
ユニ男
「なるほど、そういうことだったのか。ちなみに一点質問なんだけど、ファシリテーターをすれば受かるというのは本当なのか?」
あんちゃん
「そうね、別にファシリテーターをしたから受かる確率が高くなるということはまずないわね。大切なことは"どんな役割を担うにしろ、グループでの議論を良い方向(結論)に導こうとする姿勢。そして議論を進めることに貢献する"ということよ。」
ユニ男
「なるほどな…。別にファシリテーターに固執する必要はなかったのか…。」
あんちゃん
「そういうこと。ただ、自分がファシリテーターが得意なのであれば担当すれば良いと思う。重要なことは、自身の役割に固執しすぎず、より良い結論を導き出そうと努力することってわけよ。」
ユニ男
「あんちゃん、ありがとう!これからGDに臨む際は教えてくれたポイントを意識して取り組むよ!」
面接編
なっちゃん
「じゃあ最後に面接のスペシャリストである私が面接の極意を教えてあげるね。じゃあ早速質問だけど、ユニ男は面接に臨む前に何か準備していることはある?」
ユニ男
「そうだな…。面接は提出したESを元に質問されるって聞くし、ESの内容を見直すくらいかな。」
なっちゃん
「なるほどね、確かにESを元に質問されるってのは正しいわ。ただ、ESの内容を見直しただけでは選考突破することは難しいと思うよ。
ユニ男
「えっ?そうなのか?」
なっちゃん
「ESを元に質問されるってことは、別にESの内容を改めて質問されるという意味ではないわ。正しくは"ESの内容を元に、さらに深堀りされる"ということなよ。」
ユニ男
「なるほど、だからオレは突っ込んだ質問に答えることができず、あいまいな回答しかできずに落ちてしまったというわけか…。ちなみに具体的にはどのような質問がされるんだ?」
なっちゃん
「いい質問ね。以下に記載したのが志望動機に関する具体例になるわ。」
- 志望動機を教えて下さい。
- 将来の夢、成し遂げたいこと、キャリアビジョンについて教えて下さい。
- 5年後・10年後のビジョンについて教えて下さい。
- 企業選びの軸について教えて下さい。
- 他にはどのような業界を受けていますか。
- 他業界ではなくこの業界を志望する理由について教えて下さい。
- 具体的に取り組みたい仕事について教えて下さい。
- 業界内でも当社の理由について教えて下さい。
- 当社の改善点について意見を下さい。
- あなたにとって就職するとはどういうことですか?
- 希望の配属先・部署にいけない場合はどうしますか?
- 当社に落ちた場合、どうしますか?
- 他社の選考状況について教えて下さい。
- 内定を出した場合、すぐに就職活動を辞めますか?
ユニ男
「かなり細かく深堀りされるんだな。確かにこれまでの面接で聞かれたことのある質問がいくつもあるわ…。」
なっちゃん
「そう、つまりこのくらい深堀りされてもすぐに答えることができるくらいの準備は必要というわけよ。ちなみに具体例の詳細は以下に記事を記載しておくから、授業とアルバイトの空き時間にでも確認しておいてね。」
なっちゃん
「ちなみにユニ男にもう一点質問だけど、面接では一次・二次・最終とそれぞれ見られているポイントが異なることは知っている?」
ユニ男
「えっ?そうなのか?面接官が変わるのは知っているけど、見られているポイントまで変わるのは知らなかった。具体的にどう変わるんだ?」
なっちゃん
「やはりそうだったわね。下記に記載したものはあくまでも一例にはなるけど、基本的には以下のように言われているわ。」
【一次面接】
◆担当社員
→若手社員
◆見られているポイント
→一般的なビジネスマナー・対人スキル・事業や会社についての基本的な理解
◆詳細
→一次面接では、最低限のマナーや会社への理解、対人スキルを見極められています。自己紹介、学生時代頑張ったことや自分の強みなど、面接で必ず聞かれる項目についてはよどみなく話すことができる準備をしておきましょう。
【二次面接】
◆担当社員
→中堅社員(現場責任者)
◆見られているポイント
→自己理解の深さ・業務内容とのマッチング
◆詳細
→一次面接以上に思考の深さを見極められているため、抽象度の高い質問も増えてきます。具体的なエピソードから、「なぜその行動をとったのか」「どんな価値観に基づいていたのか」というように自分自身の核に迫った深掘りをしておくとよいでしょう。
【最終面接】
◆担当社員
→役員・社長
◆見られているポイント
→入社意欲・将来のビジョン
◆詳細
→最終面接まで進むと、能力や適性などは一定の評価を得ていることがわかります。そのため、最終面接では「会社の方向性と応募者の描く未来が合致しているかどうか」「内定を出した時に入社するのか」といった志望度が見極められています。
ユニ男
「なるほど、だから質問内容とかもフェーズによって変わるというわけか。」
なっちゃん
「そういうこと。ちなみに以下に面接に関するまとめ記事を記載しておくから、面接に臨む前に必ず確認しておいてね!」
ユニ男
「3人ともありがとう!本当に助かった!今日の学びを活かして志望企業からの内定を貰えるようにこれから頑張るわ!」
よっちゃん・あんちゃん・なっちゃん
「ファイト!」
6月某日
ユニ男
「お~い!みんなのおかげで総合商社A社からの内定をもらえたよ!」
よっちゃん・あんちゃん・なっちゃん
「マジ!?おめでとう!」
ユニ男
「よっぴから添削してもらったESは、本選考では見事全通過だったよ。やはり他人から添削してもらうのは大事なんだな。」
よっぴ
「そういうことだ。ユニ男のESを評価する面接官は第三者であるし、誰かに添削してもらうことで第三者からの見られ方を確認することは重要ってわけだ。」
ユニ男
「確かにな。あんちゃんとなっちゃんにアドバイスを貰ったGDと面接に関しても、事前に入念な対策ができたおかげで本番は緊張せずに臨むことができたよ!」
あんちゃんとなっちゃん
「ユアウェルカム!」
ユニ男
「あの時3人に相談に乗ってもらって本当に良かったよ。やっぱり就活は団体戦だね!」
「就活は団体戦」とは

今回はとあるシチュエーションを例に出して紹介しましたが、「就活は団体戦」という言葉の意味を少しでも理解することができたでしょうか。
改めてまとめさせていただくと、「就活は団体戦」という言葉は、"就活は、周りの方と協力して進めることで自分だけでは知りえない情報・新たな発見を得ることができ、効率的な行動に繋がる"と定義づけることができると考えています。
そのため、勘違いしていただきたくないのは、「就活は団体戦」という言葉は別に"とにかく周りの友達や知り合いの社会人を頼りながら就活を進めなさい"という意味ではないということです。
そのため、「就活は団体戦」という意味を文字通りに受け取り、「とにかく周りの人の言う通りにだけ行動しよう」という考えは良くありません。
また、注意点として以下の2点が挙げられます。
- 友達・先輩・知り合いの社会人からの意見・アドバイスを鵜呑みにしすぎない。
- 得た情報を自分なりに取捨選択し、本当に必要な部分だけを活かす。
もちろん、「友達・先輩・知り合いの社会人からの意見・アドバイス」は参考になるものも非常に多くあります。
ただ、先輩がこの方法でうまくいったからといって自分に当てはまるわけではありませんし、そもそも境遇・スキルが異なるのであれば別の方法が必要になります。
意見・アドバイスを貰うことは重要ではありますが、その情報を自分なりに"取捨選択"し、本当に必要な部分だけを活かすことを意識していただければと思います。
また、得た情報に関しても"全ての情報を100%正しいと思わない"ということも重要です。
どの情報が正しく、どの情報が正しくないのかを見極めるのは難しいのですが、そういった情報はあくまでも参考程度にとどめ、判断資料の一つとして活用するのが望ましいかと思います。
最後に"ES・GD・面接の対策に役立つunistyleの記事"を掲載しておきますので、こちらも併せてご覧ください。
エントリーシート(ES)の書き方対策記事まとめ|自己PR・志望動機・ガクチカ
【300・400・500字】魅力的な自己PRの書き方|解決力・思考力など
【例文35選】新卒就活で高評価を得る自己PRの書き方・伝え方を徹底解説
グループディスカッションの評価基準とは
グループディスカッションの対策|個人での対策方法と面接への活かし方
【グループディスカッション練習11選】一人でも複数人でも出来る完全対策
【志望動機対策】面接がうまくいかない?4つの回答ポイントとESとの違いを紹介
面接における10の心構え
面接質問例|志望動機やガクチカなどの質問って面接でどう聞かれる?






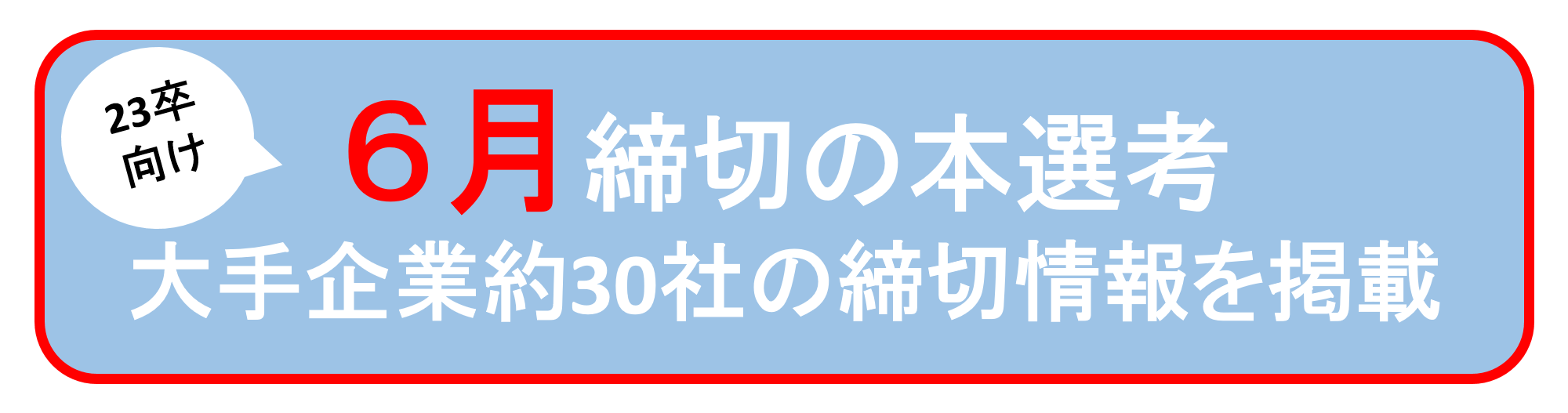


.png?1616998615)
