【最終面接の対策とは?】頻出質問・逆質問例・落ちる就活生の特徴を解説
136,229 views
最終更新日:2024年10月04日
.png?1581470880)
志望企業の内定に向け、最後の壁となるのが「面接」です。大手企業では複数回の面接を課されることが一般的であり、その面接を突破しなければ内定を獲得することはできません。
ただその一方で、「一次面接・二次面接・最終面接」の違いを理解している就活生はどれほどいるでしょうか?
「面接なんて一次も最終も同じでしょ」などと考えている就活生もいるかもしれませんが、"選考に落ちる就活生の特徴・頻出質問・するべき逆質問"は異なります。
そこで本記事では、内定獲得の最後の関門である「最終面接」に特化し、最終面接の特徴・対策(頻出質問・逆質問)などを紹介していきます。
最終面接の頻出質問と回答ポイント

続いては、「最終面接の頻出質問と回答ポイント」を紹介していきます。
一次面接や二次面接では「エントリーシート(ES)の回答の深堀り」がメインとなりますが、最終面接では聞かれる質問が少し異なります。
上記の「最終面接で落ちる就活生の特徴」の項でも解説しましたが、最終面接は「志望度の高さ」が評価におけるウェイトの大部分を占めるため、より志望度に関連する質問が多くなります。
それらを踏まえて最終面接の頻出質問を見ていくと、以下のようなものが挙げられます。
- 志望動機に関する質問
- 他社の選考状況に関する質問
- 学生時代頑張ったこと(ガクチカ)に関する質問
- 自己PRに関する質問
頻出質問として4種類の質問を取り上げていますが、本記事で再三お伝えしている通り、最終面接では「志望度の高さ」が主な評価項目になります。
もちろん4種類全ての質問の対策を進めるに越したことはありませんが、特に"志望動機に関する質問・他社の選考状況に関する質問"の対策は進めるべきでしょう。
それでは、質問ごとに具体的に見ていきます。
志望動機に関する質問
このコンテンツは会員(無料)の方のみご覧になれます。
また、会員(無料)の方は81062枚のエントリーシートを全て閲覧可能になります。
(無料会員登録はこちら)
他社の選考状況に関する質問
このコンテンツは会員(無料)の方のみご覧になれます。
また、会員(無料)の方は81062枚のエントリーシートを全て閲覧可能になります。
(無料会員登録はこちら)
学生時代頑張ったこと(ガクチカ)に関する質問
このコンテンツは会員(無料)の方のみご覧になれます。
また、会員(無料)の方は81062枚のエントリーシートを全て閲覧可能になります。
(無料会員登録はこちら)
自己PRに関する質問
このコンテンツは会員(無料)の方のみご覧になれます。
また、会員(無料)の方は81062枚のエントリーシートを全て閲覧可能になります。
(無料会員登録はこちら)
最終面接でするべき逆質問
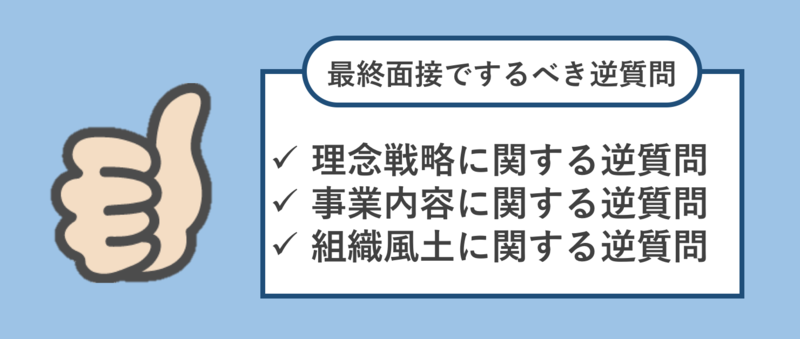
先ほど頻出質問を紹介しましたが、最終面接では逆質問の時間を設けられる可能性もあります。
大前提、逆質問を考える際には「(1)自身の企業選びの軸に沿って質問をする(2)説明会やHP上では知り得ない情報に関する質問をする」の2点は必須項目ですので、こちらは必ず認識していただければと思います。
最終面接でするべき逆質問の特徴とは
『最終面接の特徴』の際にも述べましたが、最終面接では基本的に「人事部門の部長や各事業部の責任者、役員」が担当する場合が多いです。
そのため、"人事部門の部長や各事業部の責任者、役員への質問として適した内容"を聞く必要があります。一次面接や二次面接のように、現場社員でしか知り得ないような質問をしても意味がありませんので、正しい質問を正しい人に聞くように心がけましょう。
最終面接でするべき逆質問の具体例とは
『【逆質問例21選】就活の面接ですべき逆質問とは-NG例付-』の記事を参考にすると、最終面接でするべき逆質問は以下の3点に大別されます。
- 理念戦略に関する逆質問
- 事業内容に関する逆質問
- 組織風土に関する逆質問
【理念戦略に関する逆質問】
このコンテンツは会員(無料)の方のみご覧になれます。
また、会員(無料)の方は81062枚のエントリーシートを全て閲覧可能になります。
(無料会員登録はこちら)
【事業内容に関する逆質問】
このコンテンツは会員(無料)の方のみご覧になれます。
また、会員(無料)の方は81062枚のエントリーシートを全て閲覧可能になります。
(無料会員登録はこちら)
【組織風土に関する逆質問】
このコンテンツは会員(無料)の方のみご覧になれます。
また、会員(無料)の方は81062枚のエントリーシートを全て閲覧可能になります。
(無料会員登録はこちら)
面接の目的
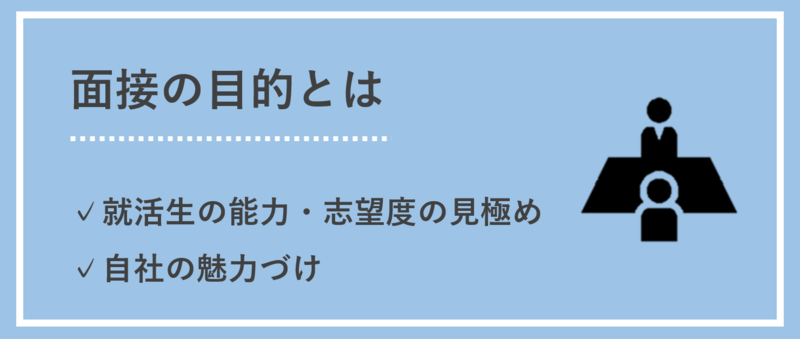
面接はほとんどの企業の選考フローで用いられていますが、なぜ企業はそもそも面接を課すのでしょうか。
まず大前提、ESや面接といった複数回に渡る選考フローの中で、企業側は"その就活生が企業の利益に貢献できる人物であるかどうか"を判断しています。
それを判断するに際し、企業側はどのような目的を持って面接を行っているのでしょうか。
もちろん業界・企業によって多少の違いはありますが、基本的には以下の2点に大別されると言われています。
- 就活生の能力・志望度の見極め
- 自社の魅力づけ
就活生の能力・志望度の見極めに関しては、文字通り「企業で活躍できる能力があるかどうか・自社への志望度が高いかどうか」になります。
ただ、就活生の能力・志望度を見極めることに関しては、「ES・webテスト・グルディス(GD)」など他の選考フローでも同様です。
では、なぜ企業側が面接という選考フローを課すかというと、ES・webテスト・グルディス(GD)は"面接の前段階で就活生を絞り込むため(=スクリーニング基準)"、面接は"採用する就活生を決めるため(採用基準)"とそれぞれ基準が異なるためです。
分かりやすく言い換えるのであれば、前者は「選考から落とす人を決めるための選考」、後者は「選考を通過させる人を決めるための選考」となります。
これに関しては、面接はES・webテスト・グルディス(GD)の次の選考フェーズ、つまり選考フローの最終段階として用いられることが多いという特徴も起因しているのですが、一般的には上記のような違いがあるとされています。
自社の魅力づけに関しては、簡単に言うと「就活生との対話を通じ、自社への志望度を向上してもらうこと」となります。
「非常に優秀だ!ぜひ採用したい!」と思った就活生に対し、逆質問の時間などを用いて魅力づけをし、"自社への志望度を向上させること"も面接の大きな目的となります。
ただ単に選考の合否を判断するだけでなく、就活生との直接的な対話を通じて自社の魅力づけをすることも面接の大きな目的となります。
厚生労働省のHPに掲載されている『公正な採用選考の基本』によると、応募者の適性や能力とは関係のない事項で採否を決定しないようにするため、家族や生活環境などの応募者本人の適性・能力に関係のない事項や、思想・宗教などの本来自由であるべき事項に関しては面接で把握しないようにすることが求められています。
このような事項は面接で質問されることも十分考えられますが、面接で質問するべきではない事項があるという前提を認識しておきましょう。
【参考】厚生労働省:公正な採用選考の基本
面接の評価基準
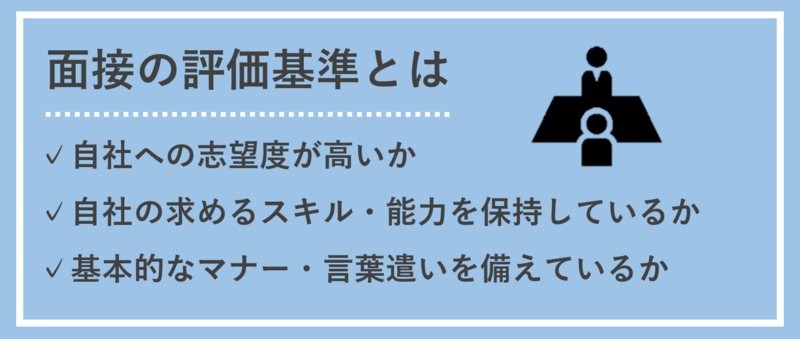
企業側が面接を課す意味・目的は理解していただけたと思いますが、その評価基準はどのようなものがあるのでしょうか。
一般的に企業側は"その就活生が企業の利益に貢献できる人物であるかどうか"で選考の合否を判断しています。
企業が求めている人材を知るには
「利益に貢献できる」ということを2つの要素に分解すると、「貢献できる能力があること」と「その能力を100%引き出すやる気(モチベーション)があること」になります。
上記の2つの要素を基に面接の評価基準を考察してみると、以下の3点が面接の評価基準と言えます。
- 自社への志望度が高いか
- 自社の求めるスキル・能力を所持しているか
- 基本的なマナー・言葉遣いを備えているか
自社への志望度が高いか
志望度に関しては、上記で述べた2つの要素の「その能力を100%引き出すやる気(モチベーション)があること」に該当します。
ESにも「志望動機」の項目はありますが、面接ではより詳細な志望動機を問われます。
「なぜその企業を志望しているのか?」という単純な志望動機だけでなく、「●●業界の中でなぜその企業なのか?その企業でどんなことに取り組みたいのか?その企業の志望順位はどの程度なのか?」といった詳細な部分まで面接では問われます。
売り手市場と言われる現代において、一人で複数社の内定を獲得することはもはや当たり前であり、人によっては10社以上の内定を獲得することも珍しくありません。(もちろん、人気企業であれば倍率が低下しているということはなく、むしろ高まっているというデータもあります)
そのような現状において、企業側も内定辞退を低減することに努めており、"より志望度の高い=内定辞退をする可能性の低い就活生を採用する"という傾向が高まっています。
もちろん、「自社の採用基準を満たしている」という前提の上での話にはなりますが、就活生の方は「面接を受けている企業の志望度が高いことをしっかりとアピールする必要がある」と言えるでしょう。
自社の求めるスキル・能力を所持しているか
スキル・能力に関しては、上記で述べた2つの要素の「貢献できる能力があること」に該当します。
総合商社での英語力・証券会社での営業力など、業界・企業によって求められる能力は異なりますが、社会人としての基礎的な能力に関しては全業界・全企業で求められるものになります。
企業側は面接という場で、その社会人としての基礎的な能力を所持しているかを見極めようと考えています。
今回は"経済産業省が定義している社会人基礎力"という資料をもとに、紹介します。(各業界・各社でどのような能力が求められるかは、本記事では割愛させていただきます。)
前に踏み出す力
●主体性
●働きかけ力
●実行力
チームで働く力
●発信力
●傾聴力
●柔軟性
●状況把握力
●規律性
●ストレスコントロール力
考え抜く力
●課題発見力
●計画力
●想像力
【出典】経済産業省:社会人基礎力
社会人基礎力は上記の12の能力要素にセグメントされます。
ただ、12の能力要素の中には面接の場では知り得ない能力もありますし、全業界・全企業共通で全ての能力が求められるという訳でもないため、あくまでも参考程度に確認していただければと思います。
基本的なマナー・言葉遣いを備えているか
マナー・言葉遣いに関しては、上記で述べた2つの要素の「貢献できる能力があること」に該当します。
志望度・能力だけでなく、マナーや言葉遣いといった印象面も面接では見られています。
というのも、面接の場における基本的なマナー・言葉遣いは「社会人としてできて当たり前のもの」であり、就活生の時点で最低限身につけておかなければいけないものであるためです。
面接の場で適切な言葉遣いをできていない人が営業の商談の場で適切な言葉遣いができるとは限りませんし、社会人は社内外問わず様々な人と仕事に取り組む必要があるため、失礼な振る舞いをしないように基本的なマナーを身に着けておくことは必須となります。
読者の皆さんはメラビアンの法則というものをご存知でしょうか。
このメラビアンの法則では、"話し手が聞き手に与える影響は「言語情報・聴覚情報・視覚情報」の3つから構成され、それぞれの情報の影響力は「7%・38%・55%」である"とされています。
面接におけるマナー・言葉遣いというものは「視覚情報」に該当されますので、こういった印象面にも気を配らなければいけないことは理解できるでしょう。
質問への回答方法を準備することももちろん重要ですが、こういった印象面を疎かにしてしまっては本末転倒ですので、「マナー・言葉遣い」にも細心の注意を払うように心掛けましょう。
最終面接の特徴
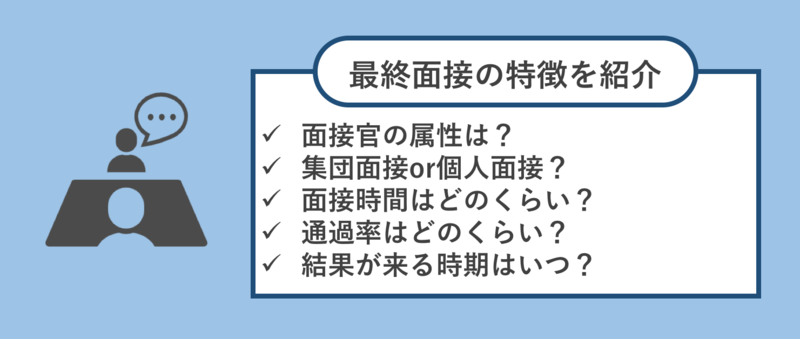
ここまで紹介してきた「企業側が面接を課す目的・面接の評価基準」に関しては、一次~最終面接の面接段階問わず、大きな違いはありません。
ただ、一次面接と二次以降の面接(二次面接~最終面接)では「面接における意味合い」が異なります。
端的に言うと、"一次面接は選考を落とす人を決めるための面接・二次以降の面接は選考を通過させる人を決めるための面接"ということです。
一次面接
●選考を落とす人を決めるための面接
→「採用したい!」と面接官が特段思わなくとも、「特に落とす理由がないな・とりあず選考を通過させて内定の判断は次の面接官に委ねるか」と思わせれば、選考通過の可能性は高いと考えられます。
二次以降の面接(二次面接~最終面接)
●選考を通過させる人を決めるための面接
→「特に落とす理由がないな」と面接官に思わせるだけでは選考を通過する可能性は低く、「ぜひ採用したい!スペックなどの採用条件は十分満たしているから、あとは経営陣の判断に任せよう」と思わせることが選考通過の鍵となります。
また、上記の「面接の目的」の項で『面接は採用する就活生を決めるため(採用基準)・選考を通過させる人を決めるための選考』と述べましたが、一次面接は例外の場合が多いです。
例外の理由としては、本記事の冒頭で述べた「本記事は大手企業の一次面接を前提としている」というものに起因しています。
大手企業では、いくら一次面接前に「エントリーシート(ES)・webテスト」で絞り込んでいるとしても、そもそもの応募者数が桁違いに多いため限界があります。それゆえに、一次面接までを「落とす人を決めるための選考」として課しているという訳です。
それではここからは、タイトルにもあるように「最終面接」に特化した内容を紹介します。まずは、最終面接の特徴を以下の5点から説明していきます。
- 面接官の属性
- 集団面接or個人面接
- 面接時間
- 通過率
- 結果(が来る時期)
面接官の属性
最終面接に関しては、"人事部門の部長や各事業部の責任者、役員"などの比較的役職の高い社員が担当することが多いです。
大手企業ではあまり見かけませんが、「取締役・社長」といった企業のトップが担当することもあります。
いずれにしろ、諸々の決済権を持つ社員が担当するため、「この就活生とぜひ一緒に働きたい!この就活生ならうちで活躍してくれるだろう!」と思わせることが重要となります。
集団面接or個人面接
最終面接は「面接官1~3人:就活生1人」の"個人面接"となります。
企業によっては「最終面接だけが個人面接(最終面接以前は全て集団面接)」という場合も珍しくありませんので、これまでの面接とは少し異なる雰囲気となる場合が多いでしょう。
面接時間
最終面接は「15~45分」程度で行われることが多いです。
一次面接に関する記事で「一次面接の面接時間は30~60分程度」、二次面接に関する記事で「二次面接の面接時間は20~50分程度」と紹介したのですが、最終面接に限っては企業・個々人によって面接時間が大きく異なります。
具体例を挙げるのであれば、「入社・内定承諾の意思確認だけしたい」場合はすぐに面接が終わり、「入社の意思確認だけでなく、最終面接でもスペック・志望動機を確認したい」場合は面接時間も長くなるということです。(あくまでも一例となります)
ただ、「すぐに面接が終了したから合格(内定)だ!/面接時間が長かったから不合格(落選)だ…。」という訳ではありませんので、あくまでも一つの目安程度に留めておいていただければと思います。
通過率
もちろん企業によって異なりますが、おおよそ"50%程度"と言われています。
「最終面接まで来れば内定も同然でしょ。最終面接って入社・内定承諾の意思確認じゃないの?」と考えている就活生もいるかもしれませんが、そういった企業は一部だけであり、多くの大手企業は最終面接でも半数程度の就活生を落とします。
それに加え、「最終面接までの全ての選考を突破してきた就活生の中の50%」であるため、むしろ一次・二次面接よりも選考突破難易度が高いとも読み取ることができます。
unistyleには、各社の内定者や選考通過者が寄稿したES・レポートが多数掲載されています。自身の志望企業の選考内容・選考倍率を確認したい方は、以下からレポートを確認していただければと思います。
結果(が来る時期)
おおよそ"1,2日以内"と言われています。
面接する人数が減るため、一次・二次面接よりも早めに結果が来ることが多いです。
基本的に「合格(内定)の就活生には先に連絡し、不合格(落選)の就活生には後から連絡する」場合が多いため、内定(内定)の場合は「1週間以内に連絡します」と伝えられた場合でも"面接日当日や翌日"に連絡が来ることがほとんどでしょう。
ただ、面接日から2日以上過ぎたからといって選考に落ちたとは限りませんので、採用担当側から伝えられた期間内は待つのが望ましいでしょう。
最終面接で落ちる就活生の特徴
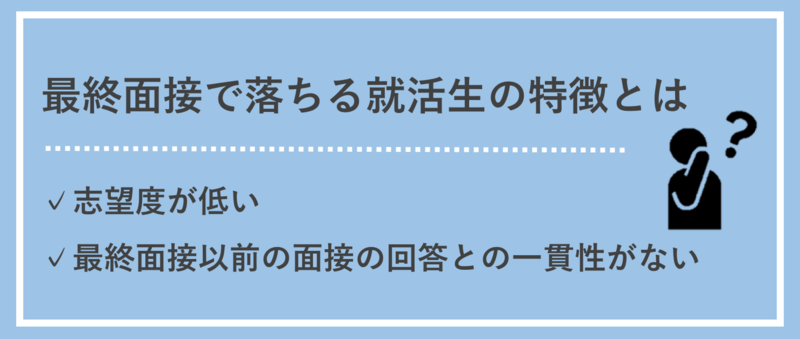
続いては「最終面接で落ちる就活生の特徴」を紹介します。
先ほどもお伝えした通り、最終面接は「選考を通過させる人(内定を出す人)を決めるための面接」という意味合いが強いです。
ちなみに、「一次面接で落ちる就活生の特徴」・「二次面接で落ちる就活生の特徴」は以下の通りです。
一次面接で落ちる就活生の特徴
(1)基礎的なコミュニケーション力が欠けている
(2)服装や姿勢など、印象面が悪い
(3)基本的なマナーを守れていない
二次面接で落ちる就活生の特徴
(1)ESの内容・一次面接の回答との一貫性がない
(2)志望度が低い
(3)入社後に活躍できる素養・能力を示すことができていない
(4)社風とマッチしていない
そして、一般的に「最終面接で落ちる就活生の特徴」として挙げられるものは以下の2点です。 上記に記載した「一次・二次面接で落ちる就活生の特徴」との違いと照らし合わせながら、ご確認ください。
- 志望度が低い
- 最終面接以前の面接(一次面接・二次面接etc)の回答との一貫性がない
志望度が低い
結論、最終面接の評価(合否)は「志望度の高さ」が大半を占めます。
一次面接は「スクリーニング(絞り込み)」の意味合いが強く、二次~最終以前の面接は「就活生の能力評価」の意味合いが強いためです。つまり、最終面接まで到達した就活生は"志望度以外の指標は内定レベル"と言うことができます。
最終面接において志望度の高さは重要であり、志望度の高さを評価するために面接官は「志望動機」を質問します。『【新卒】就活の面接で聞かれる志望動機にどう答える?人事に刺さる伝え方とは』の記事を参考にすると、面接官が志望動機を聞く意図は以下の2点になります。
(1)志望度の高さを知りたい
(2)社風やビジョンとマッチするかを知りたい
「(2)社風やビジョンとマッチするかを知りたい」に関しては、最終面接以前の面接で既に評価されているため(最終面接まで到達したということはマッチ度は問題ないと読み取ることができる)、最終面接ではそこまで問われません。
つまり、最終面接では「志望度の高さ」が重要視されているということです。
そして、「志望度の高さ」は「働く際のモチベーションの高さ」と言い換えることができます。この働く際のモチベーションの高さを要素分解すると、"働く際のモチベーション=入社したい理由×入社後に活躍できる理由"となります。
まだ少し抽象的だと思いますので、この「(1)入社したい理由(2)入社後に活躍できる理由」をさらに要素分解すると、以下のような式に当てはめることができるでしょう。
- 入社したい理由=過去の経験×価値観×将来実現したいキャリアビジョン
- 入社後に活躍できる理由=過去の経験×価値観
つまり、「(1)入社したい理由(2)入社後に活躍できる理由」を構成する"過去の経験・価値観・将来実現したいキャリアビジョン"の3点を質問することで、面接官は就活生の志望度の高さを判断するという訳です。
後述でも紹介しますが、この3点を知るために、面接官は具体的に以下のような質問をします。
●志望動機を教えて下さい。
●将来の夢、成し遂げたいこと、キャリアビジョンについて教えて下さい。
●企業選びの軸について教えて下さい。
●他社の選考状況について教えて下さい。
つまり、就活生自身のスペックがいくら内定レベルに達していようと、入社したい理由・入社後に活躍できる理由を明確に述べることができなかったり、上記に取り上げた質問の具体例に回答できなければ、内定(合格)には繋がらないと言えるでしょう。
最終面接以前の面接(一次面接・二次面接etc)の回答との一貫性がない
最終面接は、それ以前の面接(一次面接・二次面接etc)との一貫性を持った上で臨む必要があります。
稀に「最終面接は内定に向けた最後の関門だから、よりアピールする必要がある。ここまで話していなかった長所・エピソードを話そう!」などと考える就活生がいますが、これはおそらく逆効果です。
ある程度一貫性のある長所・エピソードであれば問題ありませんが、全く異なる内容を話してしまうと「この就活生は話していることに一貫性がないな。」と面接官が感じてしまう可能性があります。(もちろん、これまでの面接と異なる長所・エピソードを求められた場合は例外です。)
最終面接と言えど、面接官はこれまでの面接を踏まえた上で質問を投げかけてきます。最終面接以前の選考との一貫性は必ず意識するべきです。
一次面接や二次面接と同様の質問が聞かれる場合も往々にしてあるとは思いますが、一言一句同じではないにしても一貫性を持った回答は心がけ、その後に聞かれるであろう「追加の質問・深堀り」にも落ち着いて対処しましょう。
まとめ
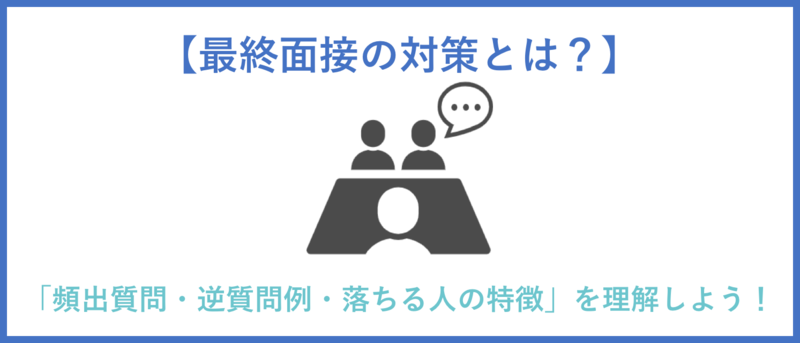
本記事では、"最終面接の特徴・対策(頻出質問・逆質問)"を紹介してきました。
ひとえに面接と言っても、一次面接・二次面接・最終面接ではそれぞれ違いがあります。そのため、「最終面接は最終面接なりの対策」が必要になります。
最終面接は内定獲得に向けた最後の関門であり、どの選考よりも緊張感のある雰囲気となるでしょう。
多くの就活生が緊張感を持って臨むことかと思いますが、それは全員に共通することであり、この最終面接を突破しなければ志望企業の内定獲得はできません。
本記事を参考にし、最終面接の合格、そして志望企業の内定に向けて準備・対策を進めていただければと思います。


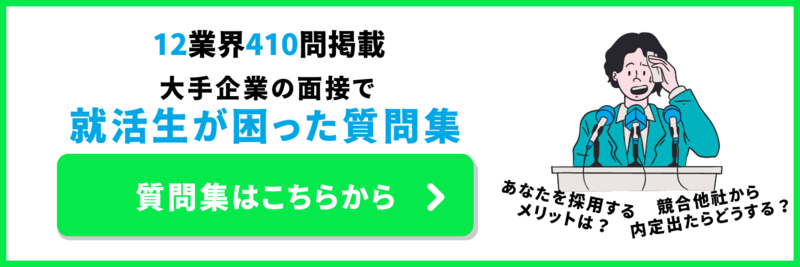
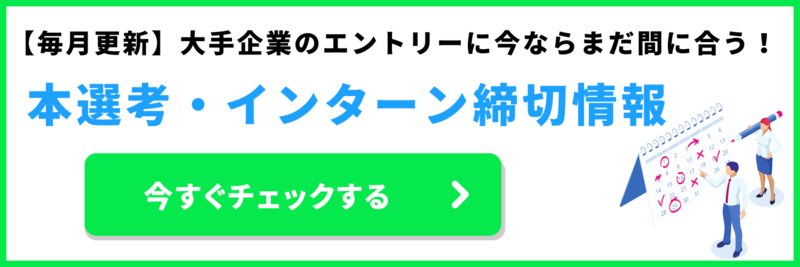


.jpg?1678248490)

.png?1581936006)

