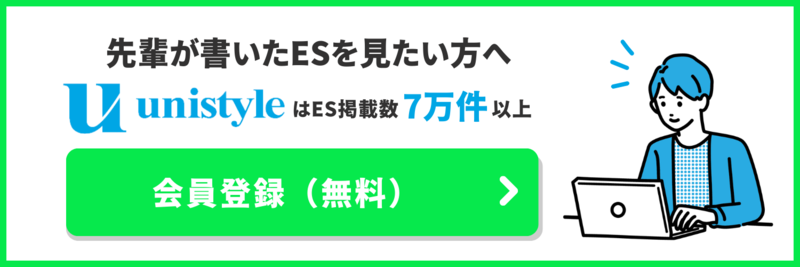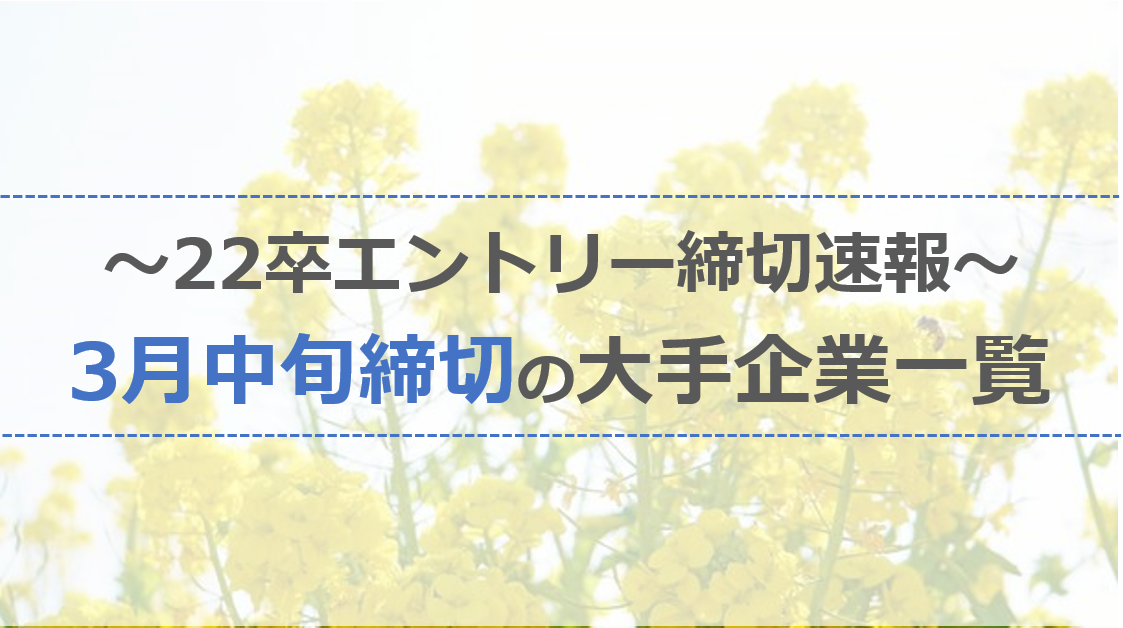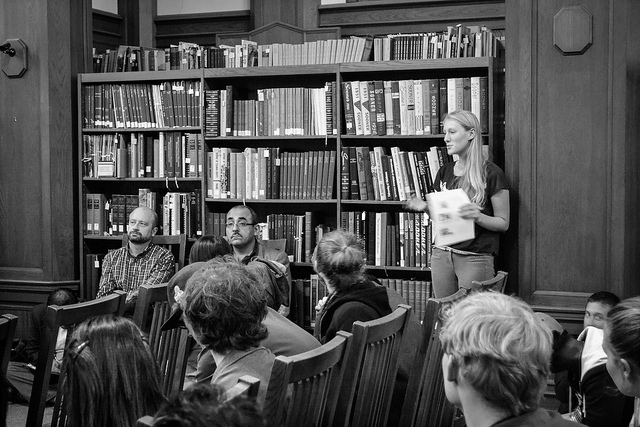unistyleを徹底的に使い込む事で就活無双した学生が3/1までに読むべき記事をまとめました
23,167 views
最終更新日:2023年12月18日
.png?1581477465)
こんにちは、20卒の慶應生です。
突然ですが皆さんはunistyleを徹底的に使いこなすことができているでしょうか。unistyleには6万を超すESや豊富なテクニック・コラム記事が掲載されています。
unistyleのヘビーユーザーである筆者は、unistyleにある全テクニック・コラム記事を読み込み実践することで納得のいく就職活動を送ることができました。
後輩の皆さんにもぜひunistyleにある全コンテンツを余す事なく利用することで就職活動に役立てて欲しいと思います。
とはいえ、自己分析・ES・業界研究etcと就活が本格化する3月に向けての準備が忙しい中で、今から数あるunistyleの記事を全て読み込むのは至難の業です。
そこで、本記事ではunistyleの全コンテンツを読み込む事で就活を戦いきった筆者が3/1までに読むべき記事を厳選しコメント付きでまとめました。
就活生のみなさん、ぜひunistyleを徹底的に活用して内定を獲得しましょう。
- 本記事の構成
- どの企業を受けるか迷っているときに読んでおきたい記事
- ESを書く前に読んでおきたい記事
- グループディスカッションを受ける前に読んでおきたい記事
- 面接を受ける前に読んでおきたい記事
- 内定を獲得した後に読んでおきたい記事
- その他読んでおきたい記事
- さいごに
どの企業を受けるか迷っているときに読んでおきたい記事
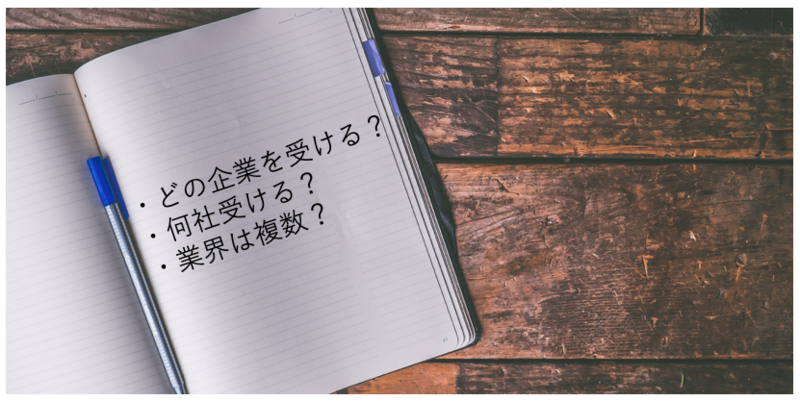
- 【就活生必見】内定者に学ぶ3/1のエントリー戦略:目安読了時間15分
- 先輩内定者の3月の就活スケジュールを大公開します!:目安読了時間5分
- 世界の全ての仕事が年収360万円だったとしたらどの仕事に就きたいですか?:目安読了時間7分
- 自己分析はどこまでやるべき?|自己分析のやり方とゴールについて:目安読了時間10分
【就活生必見】内定者に学ぶ3/1のエントリー戦略
本記事では3/1から始まる本エントリーに如何にして戦略的にエントリーするかについてまとめています。
- どのようにしてエントリー企業を選ぶべきなのか
- クリック戦争には参加するべきなのか
- そもそも何社受けるべきなのか
- 4月や5月にもエントリーするべきなのか
次のいずれかの疑問を持っている方はぜひ一読してみましょう。
本記事はこちらから→【就活生必見】内定者に学ぶ3/1のエントリー戦略
先輩内定者の3月の就活スケジュールを大公開します!
3/1以降は説明会にESの提出に面接も始まるとは聞くけど、、、なかなか3/1以降の実態を掴めていない方も多いのではないでしょうか。
本記事では、19卒の先輩の3月のスケージュール帳を大公開しています。本記事を通して3月1日以降の過ごし方のイメージを掴んでください。
- 3月1日以降のイメージが掴めない
- 先輩のリアルなスケジュールが知りたい
本記事はこちらから→先輩内定者の3月の就活スケジュールを大公開します!
世界の全ての仕事が年収360万円だったとしたらどの仕事に就きたいですか?
説得力のある志望動機を語るためにも企業選びの軸は大切になります。
ですが、この企業選びの軸を給料・知名度・福利厚生などの待遇面で選んでしまっている学生がいるようです。これでは志望動機も”入社したい理由”になってしまいます。
学生側は志望動機を文字通り、その企業に「入社したい理由」だと考えている人が多いと思います。(中略)一方で企業が知りたいのは、自分たちの企業のいいところをどれだけ知っているかということよりも、志望者が入社してからやる仕事を理解しているかどうかと、その仕事に適正があるかどうかです。
引用:志望動機を「入社したい理由」だと考えるから噛み合わない面接になる
全ての年収・知名度・待遇が同じという条件下であるならばどのような選択をするのでしょうか。その選択をした理由にこそ、本当の企業選択の軸があるはずです。
- 企業ブランドや待遇で企業を選択してしまっている
- やりたい仕事がわからない
- 納得のいく企業選びの軸を見つけたい
本記事はこちらから→世界の全ての仕事が年収360万円だったとしたらどの仕事に就きたいですか?
自己分析はどこまでやるべき?|自己分析のやり方とゴールについて
自分の強みや弱み、企業選びの軸を見つける・理解するためにも自己分析は重要です。
一方で、自己分析が重要であると考えるあまり、自己分析の本来の目的を見落としてしまってただ闇雲に自己分析を行ってしまっている学生もいます。
本選考が始まる前段階である今が深く自己分析をする最後の機会だと思われます。もう一度、なんの為の自己分析なのかその目的を思い出しましょう。
- 自己分析のゴールが見えない
- 自己分析ってどこまでやればいいの?
本記事はこちらから→自己分析はどこまでやるべき?|自己分析のやり方とゴールについて
ESを書く前に読んでおきたい記事
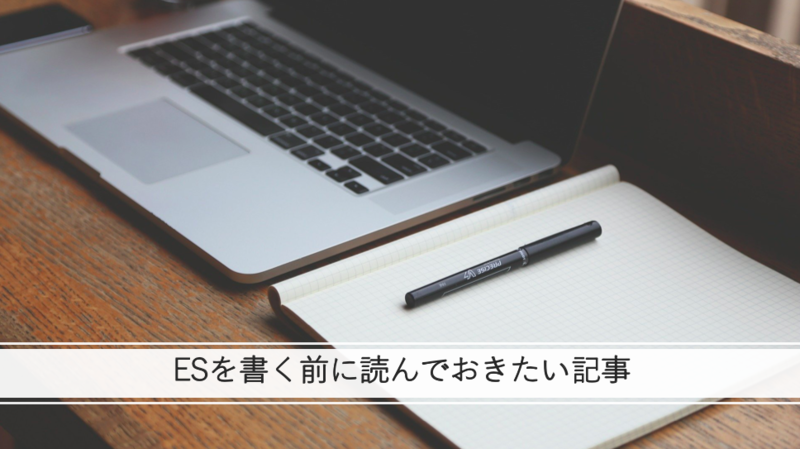
- 【例文6選】エントリーシート(ES)の志望動機の書き方!独自調査を基に人気業界ごとに解説:目安読了時間10分
- ガクチカの書き方とは-6ステップで書けるESテンプレを基に解説-:目安読了時間10分
- 【ガクチカの悪い例】賢者は失敗から学ぶ、評価されないガクチカとは:目安読了時間7分
【例文6選】エントリーシート(ES)の志望動機の書き方!独自調査を基に人気業界ごとに解説
本選考ESで必ずと言ってもいいほど聞かれるのが”なぜこの企業を選んだのか(志望動機)”でしょう。
unistyleでは志望動機の書き方を6つのプロセスで書くことを推奨しています。
このプロセスさえ押さえてしまえば質の高いESを短時間で作成することが可能になり、効率的にエントリーできるようになります。
unistyleの必読テクニック記事です。
- 志望動機の書き方は?
- ESは絶対に通りたい
- 完成度の高い志望動機を作るための6つのプロセスとは?
本記事はこちらから→【例文6選】エントリーシート(ES)の志望動機の書き方!独自調査を基に人気業界ごとに解説
ガクチカの書き方とは-6ステップで書けるESテンプレを基に解説-
志望動機と同様に必ず聞かれるのがガクチカでしょう。
志望動機と同様にガクチカも6つのプロセスに別けて書くことを推奨しています。
本記事はESでのガクチカの書き方だけではなく、面接でのガクチカ対策にも繋がる内容になっています。志望動機の記事と併せてunistyleの必読テクニックです。
- ガクチカの書き方は?
- 面接官も唸るガクチカを書くための6つのプロセスとは?
- ガクチカの評価基準ってなに?
- ガクチカは複数準備しておいた方がいいの?
本記事はこちらから→ガクチカの書き方とは-6ステップで書けるESテンプレを基に解説-
【ガクチカの悪い例】賢者は失敗から学ぶ、評価されないガクチカとは
ガクチカには自信があるけどなぜだかいつも通過しない、、、面接でも自分のガクチカがあまり評価されていないような気がする、、、
自分では完成されたと思っているガクチカも本選考前にもう一度確認した方がいいかもしれません。
本記事では評価されないNGガクチカを例を交えながら解説しています。ガクチカが完成していると思っている学生ほど必読です。
- 書けているはずのガクチカが評価されない
- 自分のガクチカに穴がないか確認したい
- インターンの面接でガクチカが評価されなかった
本記事はこちらから→【ガクチカの悪い例】賢者は失敗から学ぶ、評価されないガクチカとは
グループディスカッションを受ける前に読んでおきたい記事

- グループディスカッション(GD)完全対策!企業の意図・役割・議論の進め方まで:目安読了時間15分
- グループディスカッションの対策|個人での対策方法と面接への活かし方:目安読了時間10分
グループディスカッション(GD)完全対策!企業の意図・役割・議論の進め方まで
GDでの評価基準を正しく把握することはできているでしょうか。何が評価のポイントをきちんと押さえないままGDに臨んでも高い評価を得ることはできません。
本記事を通してGDの目的・役割から対策までを一括して学べる内容になっています。
GDの直前に是非とも読み直したい記事です。
- GDは何で評価されているか知っていますか?
- GDの3つのパターンは?
- GDの進め方は?
- GDでは役割が大事だと思っていませんか?
本記事はこちらから→グループディスカッション(GD)完全対策!企業の意図・役割・議論の進め方まで
グループディスカッションの対策|個人での対策方法と面接への活かし方
GDでもっとも重要なのは一人で結論まで導くことのできる力です。
ではどのように一人で結論まで導くことのできる力をつけることができるのでしょうか。また、GD対策を一人ですることは可能でしょうか。
本記事では一人でもできるGD対策を3つのプロセスに分けて解説しています。
- 一人でGD対策って具体的に何をすればいいの?
- GDを突破するために鍛えるべきたった一つの力って?
本記事はこちらから→グループディスカッションの対策|個人での対策方法と面接への活かし方
面接を受ける前に読んでおきたい記事

- 【就活の面接で忘れてはいけない!】面接で必ず聞かれる質問33問と回答例:目安読了時間7分
- 【面接が上手い人の特徴】問われているのは瞬発力ではなく思考力?:目安読了時間7分
- あなたの志望動機が共感されないのは自分の経験に根ざしていないから?:目安読了時間5分
- 【例文35選】新卒就活で高評価を得る自己PRの書き方・伝え方を徹底解説:目安読了時間20分
【就活の面接で忘れてはいけない!】面接で必ず聞かれる質問33問と回答例
企業や面接官ごとに聞かれる質問は変わってきます。ですが、どの企業でも共通して聞かれるであろう質問をまとめたのが本記事になります。
本記事に掲載してある質問を事前に答えられるように準備することで面接の通過率が上がるはずです。
- 本選考の面接で共通して聞かれる質問って?
- 一次面接、二次面接、最終面接ってそれぞれどのようなことが聞かれるの?
本記事はこちらから→【就活の面接で忘れてはいけない!】面接で必ず聞かれる質問33問と回答例
【面接が上手い人の特徴】問われているのは瞬発力ではなく思考力?
なぜ企業はそもそも面接試験を実施するのでしょうか。受験の様にペーパーテストだけで優劣をつけたりしないのはなぜでしょうか。
本記事では企業が面接試験を実施する理由を本質的に解説しています。
本記事を読むことで、「あなたを動物に例えると?」「あなたを色に例えると?」などの想定していない質問がなぜされるのか、その本質が見えてくるはずです。
- 面接試験ってなぜ実施されているの?
- 面接で問われているのは”普段から”考える力だって知ってましたか?
- 定型文を用意した面接対策を実施していませんか?
本記事はこちらから→【面接が上手い人の特徴】問われているのは瞬発力ではなく思考力?
あなたの志望動機が共感されないのは自分の経験に根ざしていないから?
ES・面接問わず、選考過程で必ず一度は聞かれるのが”志望動機”です。
自己分析や業界研究を重ねて作った志望動機がなかなか評価されなかったという経験が一度はあるのではないでしょうか。
なぜ渾身の志望動機が評価されないのか、それは自身の経験に基づいているものではないからかもしれません。
面接を受ける直前に読み返したい内容になっています。
- 渾身の志望動機が評価されなかった
- 経験に基づいた志望動機を話せていますか?
本記事はこちらから→あなたの志望動機が共感されないのは自分の経験に根ざしていないから?
【例文35選】新卒就活で高評価を得る自己PRの書き方・伝え方を徹底解説
企業に伝えるべき5つの強みを知っていますか?面接官に「今から自己PR」をしてくださいと聞かれた時に論理的に順序立てて説明できているでしょうか?
unistyleでは自己PRで伝えるべき強みを5つ、そして伝える際のフレームワークとして5つのフレームを考えています。
本記事を読み込むことでESから面接の自己PRまで一括して対策をすることができます。
- 企業に伝えるべき5つの強みとは?
- 自己PRを効果的に伝える5つのフレームとは?
- 自己PRに自信がない…
本記事はこちらから→【例文35選】新卒就活で高評価を得る自己PRの書き方・伝え方を徹底解説
内定を獲得した後に読んでおきたい記事

- キャリアにおける「鶏口牛後」〜あえて難易度が低い企業を選ぶという選択〜:目安読了時間20分
- 【就活を始める前に読んで欲しい】就職活動とは何か?なぜ働くのか?:目安読了時間7分
- 内定承諾先に悩む複数内定者に捧げる「意思決定マトリックス表」:目安読了時間15分
就活生のキャリア採用ページの活用法|キャリア選択に客観的な指標を加えるために
就職活動をしているとどうしても”就社活動”になってしまっていませんか。希望する会社に入って5年後10年後自分が社外からどのような評価を得ているかを想像したことがあるでしょうか。
本記事では入社後5年10年で自身がどれほどの市場価値を持った人材になっているかについて測る指標としてキャリア採用ページを用いています。
自己完結しがちなキャリアプランに客観的指標を加えてみましょう。
- 就職活動ではなく就社活動になっていないか
- 5年後10年後の自分の市場価値を考えたことがあるか
本記事はこちらから→就活生のキャリア採用ページの活用法|キャリア選択に客観的な指標を加えるために
キャリアにおける「鶏口牛後」〜あえて難易度が低い企業を選ぶという選択〜
就職活動では所謂入社難易度の難しい企業に入社した学生が勝ち組と見られる風潮がまだあります。
入社難易度の高い企業に入社することで周りからは羨望の眼差しを向けてもらえるかもしれません。ですが、長期的な目線で見たとき、入社難易度だけで選択するのは本当に幸せだと言うことができるのでしょうか。
本記事では”鶏口牛後”をキーワードにキャリア選択の一つの考え方を提示しています。内定を獲得した後にこそ読んでいただきたい内容となっています。
- 難関企業への内定が人生の勝ち組?
- キャリアにおける鶏口牛後とは?
- あなたの会社選びは人のモノサシで選んでいませんか?
本記事はこちらから→キャリアにおける「鶏口牛後」〜あえて難易度が低い企業を選ぶという選択〜
【就活を始める前に読んで欲しい】就職活動とは何か?なぜ働くのか?
内定を獲得してホッとしたのも束の間、改めて考え直して欲しいことがあります。それはなぜ”就職活動”を始めたのかということです。
内定を獲得することは中間点であってゴールではありません。ですが、就職活動を行なっているとどうしても内定獲得がゴールになってしまいがちです。
内定を獲得した今だからこそ、なぜ就職活動を始めたのか、自分は何が成し遂げたいのかを振り返ってみるべきでしょう。
- 内定を獲得したらもう一度就職活動を始めた頃を思い出してみよう
- なんで今の会社を受けようと考えたのか振り返ってみよう
本記事はこちらから→【就活を始める前に読んで欲しい】就職活動とは何か?なぜ働くのか?
内定承諾先に悩む複数内定者に捧げる「意思決定マトリックス表」
納得した意思決定をする為にも複数内定を獲得することは大切です。ですが、複数内定を獲得した後にどのように企業を選ぶべきなのかは就職活動で一番難しい問題であると言っても過言ではないでしょう。
本記事では複数内定を獲得した後にどのように意思決定をするべきなのか、”マトリックス表”を用いる方法を紹介しています。
また、企業選択のNG例も紹介しているので複数内定で迷っている就活生に必見の内容となっています。
- 複数内定の中からどのように選択するのか
- 企業選択でのNGとは
本記事はこちらから→内定承諾先に悩む複数内定者に捧げる「意思決定マトリックス表」
その他読んでおきたい記事

- 就職活動における運と相性 ー「人事を尽くして天命を待つ」の意味ー:目安読了時間7分
- unistyleの記事をひたすら読み込んだ私が面接で無双した話:目安読了時間7分
- 就活生が話しがちな志望動機「グローバルに働きたい」その理由や実情を考える:目安読了時間10分
- 10年前は東電・シャープに入社した人は勝ち組だった:目安読了時間5分
就職活動における運と相性 ー「人事を尽くして天命を待つ」の意味ー
「就職活動って運ゲーだよねー」これ本当でしょうか。ESやwebテスト、面接などの評価はブラックボックス化しており、明確な合格点が見えないことがこのような発言の元になっているのかもしれません。
だからといって、単に就職活動を運と結びつけて語ってもいいのでしょうか。
本記事では、就職活動での運と相性について「人事を尽くして天命を待つ」をキーワードに掘り下げています。
- 就職活動を運と相性で片付けてしまってもいいのか
- 就職活動は運要素が強いのではないか
本記事はこちらから→就職活動における運と相性 ー「人事を尽くして天命を待つ」の意味ー
unistyleの記事をひたすら読み込んだ私が面接で無双した話
就活は情報戦という言葉を耳にします。企業説明会やネットで得た情報など就活生は大量の情報に触れることになります。
大量の情報と向き合う中で大事なのは必要な情報を取捨選択することでしょう。
本記事ではunistyleを徹底的に使用して就活を無双した弊社の元インターン生のunistyleの活用法を紹介しています。ぜひ本コラムと合わせて読んでいただけたらと思います。
- unistyleを100%活用するには
- 量よりも質は量をこなしてから?正しい情報との向き合い方とは?
- unistyleの記事を読むだけで終わっていませんか?
本記事はこちらから→unistyleの記事をひたすら読み込んだ私が面接で無双した話
就活生が話しがちな志望動機「グローバルに働きたい」その理由や実情を考える
総合商社や外資系企業、メーカー志望の学生の多くに共通しているのが”グローバルに働きたい”ではないでしょうか。
実は、この就活生が話しがちな志望動機である”グローバルに働きたい”は大きな穴があります。本選考で”グローバルに働きたい”とうっかり話してしまわない為にも本記事は必読です。
- 将来グローバルに働きたい
- 志望動機がグローバルに働きたい
- グローバルに働くを明確に落とし込んでいますか?
本記事はこちらから→就活生が話しがちな志望動機「グローバルに働きたい」その理由や実情を考える
10年前は東電・シャープに入社した人は勝ち組だった
企業ブランドや知名度だけで入社先を決めるのは良くないと聞きますがそれは何故なのでしょうか。
複数内定を獲得した後に1社をいざ選ぶとなると、どうしても知名度やブランドも捨てられません。もちろんブランドや知名度も大切ですが、大切なのは4月にはその会社に入社して働いているということです。
ブランドや待遇などで企業を選んでしまいそうな時にもう一度読み直したい記事です。
- 業界トップだけをエントリーしていませんか?
- ブランド就活をしていませんか?
本記事はこちらから→ 10年前は東電・シャープに入社した人は勝ち組だった
さいごに
数あるunistyleの記事の中から自身が就活生だったときに特に参考にした記事を厳選し、コメント付きでまとめさせていただきました。
何が正解かわからないなかで自分なりの答えを探さなくてはならない就職活動は、人生における最も難しくかつ重要なイベントです。答えのない就職活動だからこそ、就職活動を通して”それぞれが自分らしい生き方を支える自分独自の考え方”を確立してほしいという思いからunistyleは生まれました。
就活生のみなさん、unistyleを徹底的に使い込みましょう!皆さんの就職活動が実りあるものになるよう、陰ながら応援しています!