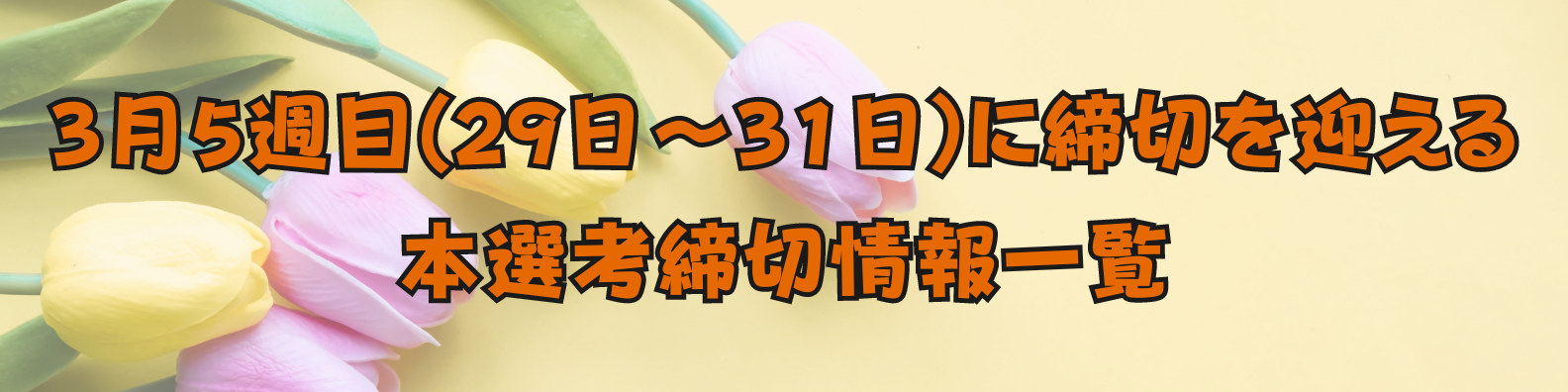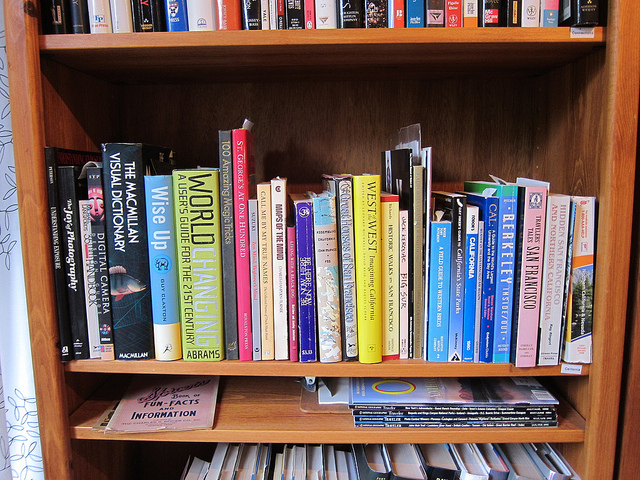文系学部廃止論?阪大学部長の言葉から考える内定獲得のための学業の"使い方"
21,016 views
最終更新日:2023年11月06日
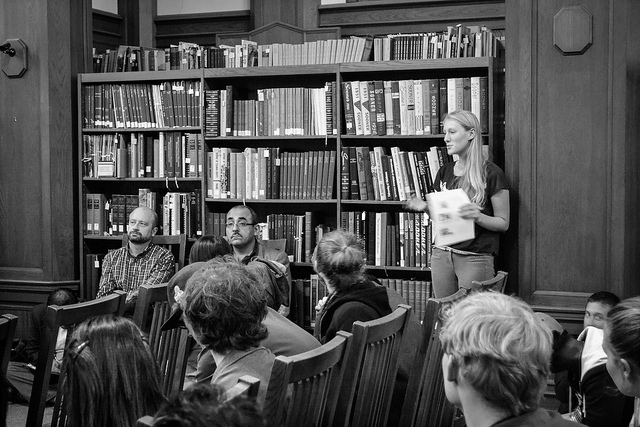
「やべー、授業出てないしテスト勉強も全然してねー。」
「〇〇の授業とってる人いますか?」
「これまでのノート写させてくれない?」
こんにちは、18卒就活生です。
恐らくほとんどの大学で前期の試験が修了し、夏休みに突入した時期かと思います。何より試験の方お疲れさまでした。
夏選考やインターン選考に臨んでいる18卒・19卒の方も、就職活動を一休みで長期休暇を謳歌している方が多い時期かもしれません。
さて、一年で最も大学の学業に向き合うことが多いとも言える試験期間を乗り越えた皆さん、この時期一度はこのような疑問が浮かんでくるのではないでしょうか。
「大学で学んでいる内容って何の役に立つの?」
年度当初もしくは入学当初は、いわゆる"意識高い"考えで大学でしっかり学ぼうとしようとしたものの、徐々に授業に行くのが面倒になり、「4月病」「5月病」といった言葉が生み出されているのだと思います。こうして意識の下がった学生がテスト前に発する言葉が冒頭で挙げたような"意識低い"言葉の数々であり、もはやこれが一般的な大学生のあり方と考えられている、という風潮すら感じられます。
この大学で学ぶ意味に関連して、先月以下のような記事がSNSで取り上げられました。
こちらは、先日話題に挙がった大阪大学文学部長の卒業セレモニーでの言葉がまとめられた記事です。
式自体は2017年3月に開催されたものですが、最近になってTwitterを始めとしたSNSで拡散されたこともあり、皆さんの中でも読んだことがあるという方は多いかもしれません。一時はTwitterのトレンドに上がるほど拡散された本件ですが、これだけの注目が集まったことは、この件について考えさせられた人が多かった証ではないかとう見方もできると思います。
この方が述べている「人文学への風当たりが一段と厳しさを増した時期」という言葉の意味について、事の発端の一つに2015年6月に文部科学省が発表した以下の通知があると考えています。
教員養成系学部・大学院、人文社会科学系学部・大学院については、18歳人口の減少や人材需要、教育研究水準の確保、国立大学としての役割等を踏まえた組織見直し計画を策定し、組織の廃止や社会的要請の高い分野への転換に積極的に取り組むよう努めることとする。
参考:国立大学法人等の組織及び業務全般の見直しについて
文部科学省としては、「国立大学における文系学部を廃止すべき」という意図を持って書いた言葉では無かったようですが、マスコミの伝達の仕方やそもそもこの文章の書き方が完全に適切とは言えなかったこともあり、「大学から文系学部が無くなるのではないか」という形で人々の間で情報が錯綜したことは就活生の皆さんにとっても関心のある話であったと思います。
この件が大きく話題に挙がった要因として、それだけ特に文系学部に通う学生の中に「大学で学んでいる内容は何の役に立つのか?」という思いが少なからずあるのだと考えています。学校教育法では「学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする」と定義づけられた"大学"において、学業にモチベーションを感じられないことは問題なのかもしれません。とは言っても、例えば応用化学専攻の学生が化学メーカーの開発職で自身の大学で学んだ内容をダイレクトに活かせるといったことはあるでしょうが、法学部に入ったから弁護士になる・商学部に入ったから会計士になるといった形で文系学生が直接専攻内容を役立てるという可能性はかなり低いというのが実情でしょう。
私自身も文系学生の一人なのですが、大学時代学業にモチベーションを感じられる機会はほとんど無く、「授業への出席=単位を獲得するための手段」「ゼミへの入会=学業について就活で話すことがなくなるのを避けるため(ネタ作り)」程度に一応留年は嫌だから真面目にこなしていたという感じの学生でした。
しかし、実際に就職活動をしていくと、「学業に関する質問」は程度こそあれほとんどの企業で一度は聞かれた点については個人的に印象に残りました。学業を重視する企業としては以下にあるようにキヤノンが特に有名でしょう。
キヤノンは、学生の本分である学業に力を入れて取り組んでいる人を評価したいと考えています。あなたが力を入れている学問領域は何ですか。具体的な取り組みとあわせて説明してください。
参考:【内定】エントリーシート
こちらとしても専攻内容を説明する程度なら一応準備はしておくのですが、「なぜそのゼミに入ったのか」「印象に残った科目について説明して」など想像していたよりもそのパターンは多く、正直そこまで真面目に取り組んでいなかった自分としては回答に困ったことも度々ありました。「なぜ企業は将来役にも立たない学業について尋ねるのか」「自身の学んだ内容をどう伝えるのが正解なのか」など、文系学生にとって学業に関する質問を難しく感じてしまうのは珍しいことではないでしょう。
以上を踏まえ、今回は就職活動の場において文理問わず避けては通れない「学業」というキーワードについて、unistyleの過去記事や筆者自身の就活体験を踏まえて考察していきたいと思います。こちらでいくつか挙げている例に関しては、ご自身の大学や専攻内容に照らし合わせながら思考を深めていただければと思います。それではまず就職活動において学業がどのような尋ねられ方をされているかについて考えていきましょう。
就職活動における学業の位置づけ
こちらは一般に、文理によって異なります。
先述の通り、理系職の場合は専攻内容がダイレクトに仕事内容に活かせることが多く、学業で功績を残した人=自社の利益に貢献できる人材という見方がなされるほど、ES・面接共に自身の専攻内容について深く尋ねられることになります。また、文系学生と比較して学生生活における学業のウエイトが高いことが一般のため、仮に直接専攻と関係がない企業を受ける場合でも、「なぜあえて専攻と関係がないウチを志望しているのか」という形で深掘りがなされることがあります。
一方、文系学生の場合は全く尋ねられないケースは少ないものの、ES・面接のメインのテーマとして挙がることはほとんどありません。以下の三菱電機の記事のような形式が一般的なウエイトの置かれ方と言えるでしょう。
こちらは事務系・技術系で問われる質が大きく異なるようです。技術職の場合は研究内容と三菱電機の事業の関連性といった内容をかなり突っ込まれることもあるようです。事務系の場合は問われる機会はあまりないですので、自身が大学で学んだことについてわかりやすく説明できるようにしておくといったの最低限の準備をしておけば十分だと思われます。
参考:三菱電機の面接過去問リスト23選
これについては、「文系の学問は直接仕事に活かされる機会が少ないから」という学術的な理由ももちろんありますが、他にもいくつか要因があると考えています。
一つ目は「学業」と「仕事」の性質の違いについてです。
以下の記事にもあるように、「学業」は主にインプットとしての性質が強い一方、ビジネスとは典型的なアウトプットの取り組みであることは理解しておく必要があるでしょう。そのため、仮に学業成績といったインプットの能力をアピールしたとしても、企業が求める人材の究極形である「企業の利益に貢献できる人材」であることを示すには至らず、的外れな自己PRで採用に繋がらないのが一つ目の要因だと考えられます。
二つ目はアピール項目の不適切性です。
学業成績については確かにコツコツと真面目に努力することができることを伝える手段としては機能しうるでしょうが、「就活生が伝えがちな自己PRで伝えてはいけない三つの強み」にもあるように、そもそも「努力ができる」という強みは学歴や取得資格という履歴書の段階で判断できるものであり、それをわざわざESや面接でアピールするのは的確とは言えないでしょう。
三つ目は集団性の欠如です。
仕事においては確かに個人としての行動も大事ではありますが、結局は大小こそあれ組織として動いていくことになることから、「集団の中でどのような貢献の仕方ができるか」を企業としては知りたいと考えています。一方、学業での取り組みを尋ねようとした場合、どうしても個人としての取り組みについてを述べるにとどまってしまうことが多い印象があります。実際、「ゼミ・学業・その他資格試験などへの取り組みに基づいた学生時代頑張ったこと」で有名企業内定者の回答を参照しても、多くの学生が個人としての努力に+αのチームへの貢献の仕方を述べており、単なる努力自慢の内容になることを避けていることからもこの理由が伺われるでしょう。
以上のような背景から、特に文系の新卒採用活動における学業の位置づけは「多くの企業で尋ねられるが、メインの話題として上がることはほとんどない」とまとめることができるでしょう。
それでもなぜ企業は学業について尋ねるのか?
ここまでは、「文系の新卒採用活動で学業がメインテーマとしてあがりにくい理由」について考えていきましたが、では一方でなぜ企業は多くの場合仕事で直接活かされない文系の学業を多少なりとも尋ねてくるのでしょうか。これにもいくつかの理由があると考えています。
一つ目は、経団連の指針についてです。
こちらは直接企業の意図からは外れるかもしれませんが、近年の経団連の新卒スケジュール変更理由の一つとして、(実際その役割を果たしているかは別として)学生の学業への影響が挙げられています。スケジュールに限らず、経団連は以下にあるように学業優先の姿勢を所属企業に対して求めています。成績表を事前に提出させそれに基づいた質問をしていくいわゆる「リシュ面」という形式もこの影響が少なからずあると考えられています。
選考活動は、広報活動と異なり、学生が自主的に参加不参加を決定することができるものではないため、今般の開始時期の変更に伴い、学事日程に一層配慮していくことが求められる。
具体的には、面接や試験の実施に際し、対象となる学生から申し出があるケースも想定されるため、事前連絡についても余裕をもって行うほか、当該学生の事情を十分勘案しながら、例えば授業やゼミ、実験、教育実習などの時間と重ならないような設定とすることや、土日・祝日、夕方以降の時間帯の活用なども含めた工夫を行うことが考えられる。
また、大学等の履修履歴(成績証明書等)について一層の活用を検討することが望ましい。
参考:「採用選考に関する指針」の手引き
二つ目は、地頭の良さを見るためです。
以下の記事にもあるように、学業への取り組みについて尋ねる質問は、自身の専攻内容をその分野に全くの無知である採用側に対してわかりやすく伝えることができるかを通して地頭の良さを見ているという意図があると考えられます。例えば日系人気企業であるキリンでは「卒論内容を小学生にもわかるように説明して」という形で尋ねられたことがあるようです。こちらが精通している専門事項について相手方に理解させる力というのは、日々のコミュニケーションが前提となるビジネスの場においても求められるスキルと言えるのではないでしょうか。
三つ目は、今いる環境での姿勢を知るためです。
確かに履歴書の「学歴」の項目でどれだけ勉強ができるかスクリーニングの判断材料にはなるでしょうが、学歴は高校までの学習の成果に過ぎません。大学受験から大卒の就職活動時期には3年程度のブランクがあることから、その間の学業での取り組みについて尋ねたいと思うのは自然な考えではないでしょうか。大学受検への「合格」を目標とし、入学後あまりに学業に疎かになってしまっているようでは、就職活動でも「内定」をゴールと考え肝心の入社後にモチベーション高く働いてくれないのではと採用側からしても疑わしく感じてしまうかもしれません。もちろん「就職活動とは何か」の記事にあるように、就職活動=職に就くための活動であるためこの姿勢自体は間違ってはいないのですが、採用側から見れば自分が属する環境で高いパフォーマンスを発揮できるかどうかは重要な見極めポイントと言えるでしょう。以下の記事にあるような「今の大学は第一志望の大学ですか?」という質問も、本意/不本意関わらず属することになったコミュニティーで成果を上げられているかを尋ねようという意図を考えると、この3つ目の要因と関連していると考えられるでしょう。
以上の要因から、企業が文系学生に対して学業について尋ねるのにも一定の意図があるということが読み取られると思います。すなわち、学業について「将来どうせ役にたたないから意味ない」という姿勢で完全に切り捨ててしまうと就職活動の場ではやや苦しいと言うことができるでしょう。
学業の就活での"活かし方”の考えを変えてみる
さて、ここまで見ていても就職活動での学業の活かし方はまだ理解されていないかと思います。これについては”活かす”という言葉についての解釈によるものだと考えています。一般には、「大学で学んだ内容が仕事上の実務で直接的に活用される」ことが「活かされる」が表す意味とみなされているように感じています。しかし先述の通り、この意味での活かされ方はほとんどの文系学生にとって実現されません。ここでは学んだことの活かし方の考えを変えてみましょう。
◎ツールとして活かす(例:プロダクトポートフォリオ)
元々はBCG が生み出した分析手法である一方で、今では経営学やマーケティングの基本用語として知られているプロダクトポートフォリオ。経営・商学系統の学生ならば一度は学んだことがあると思います。企業の製品分析や意思決定プロセスに関わるツールではありますが、これを就職活動に当てはめてみましょう。
「自分にはどんな仕事が向いているのか」の記事では複数業界に興味を持つうえでクライアント×商材の二軸でポートフォリオを組みましたが、他にもエントリーの段階で企業のレベル×志望度でポートフォリオを組むという使い方も考えられます。
「受けたいところから受ける」のはエントリー戦略の基本の一つではありますが、例えば「5大商社しか受けない」といった姿勢は無内定のリスクを高める賢明な判断とは言えず、ポートフォリオを活用してエントリーする企業を整理しておくことは有効な手段であると考えています。そもそも一般的なポートフォリオの使われ方である金融の分野においては、リスクの分散化・投資リスクの軽減という意味で用いられることからこの点と親和性が高いと言えるでしょう。
また、人事の側からしても採用基準を設けるうえでポートフォリオを活用している企業は一定数存在していると考えています。例えば「体育会の社風」と言われている企業であっても全員が全員体育会気質ということはほぼなく、ある程度多様性がある採用戦略を取っていることが特に日系企業の場合は一般です。金融業界が理系の人材を一定数採用していたり、リクルートの営業タイプ/企画タイプの方針はその典型と言えるかもしれません。
他にも、「弊社は今後市場・製品の2軸で既存/製品新規のそれぞれ計4領域のどこに注力すべきか」というテーマでGDが課されたことがあったのですが、このとき私は大学で学んだアンゾフの成長マトリックスを用いて議論を展開し高く評価されたことがありました。
このように、学業は実務上活かす機会はほとんどない一方で、使い方によっては就職活動を進めるうえで有効なツールになることは認識しておくべきでしょう。
◎説得力・再現性を高める形で活かす(例:”考え抜く”)
こちらについては以下の記事を一読していただければと思います。
この記事では「志望動機の説得力・自己PRの再現性を高めるうえでは経験・エピソードが必要だ」ということが複数述べられています。学業についても学生時代の経験である以上これの例外ではなく、説得力・再現性を高めるうえで活用すべきものであると考えています。例えば冒頭で示した阪大学部長は人文学が「直面した問題を『考え抜くきっかけ』となる」と述べていますが、これを「「考え抜くこと」で総合商社を勝ち取った普通の学生体験記 ー思考の抽出化で道を切り開くー」の学生が用いたらどうでしょうか?コーヒーチェーン店のアルバイト経験からだけでなく、人文学で学んだ内容が思考の抽象化に結びついたと述べることで、多くの他の学生が用いないアプローチから格段に説得力を高められていると言えるのではないでしょうか。
以上のように、学業を”活かす”とは何も実務上で直接的に活用されることだけを表すものではなく、ツールとしての活用・エピソードとしての活用という活かし方があるとまとめることができます。
学業と就職活動の繋がりについて考えを深める意義
これまでの内容で、学業が就職活動で多少なりとも活かされるものであるということは理解していただけたかと思います。
では、両者を結びつけて就職活動を進めていくことにはどのような利点があるのでしょうか。筆者は先述した学業を就職活動で活かすということだけでなく、逆にそれが普段の学業にも活かされるという双方向の働きかけができるのではと考えています。
理由1:単純に学業に関する設問に答えやすくなる
企業が学業に関する質問を尋ねる理由の一つとして、専攻内容をわかりやすく説明できるかを通して地頭の良さを見ているということを先ほど述べました。自分で考えて学業の就職活動での活用法を生み出すということは、それだけ自分の中で噛み砕いた解釈ができていることが前提となります。それができていれば、あとは実際に他の人に伝えるというアウトプットの対策をするだけで選考の場でのわかりやすい説明に繋げることができます。ただ単に専攻内容の説明用として文章を準備しておくよりも、それをうまく活用できている状態にある方がそれを「自分のもの」として身になっており、よりレベルの高い段階にあると言うことができます。このレベルを高めることで、準備した文章を述べるその先にある深掘りへの対応力も同時に高まるのではと考えています。
理由2:大学の勉強(ゼミなど)にも役立つ
こちらは逆に就職活動での活用が普段の学習に役立つという考え方です。
「わかりやすく説明する」というのは何もESや面接の場での手段ではなく、普段の学習を進めていくうえでも重要でしょう。例えば普段のゼミ(ゼミ内)やインゼミ(ゼミ外)での発表の際にも、学術的な内容を聞き手に理解できるような説明をしていくことは重要なスキルだと思います。また、「人に理解してもらうようにする」というのは自分の中でそれ以上の理解があることが前提であることから、その学問における自分の中での理解を深める良いきっかけになるとも言うことができるでしょう。
理由3:思考の一貫性をアピールできる
個人的には、これが一番の利点ではないかと考えています。
就職活動におけるエピソードとは何も大学時代の経験だけではなく、「自分の生い立ちを語ることで自己PRに説得力を持たせる方法」の記事にもあるように幼少期からの経験が全て該当します。多くの学生がエピソードとして用いるサークル・ゼミ・アルバイトといった経験の多くは大学時代に限定されたものである一方、学業は程度の差こそあれ小学校から大学まで学生生活と切っても切り離せない関係であったことから、幼少期からの一貫性を示すアプローチとして有効であると考えています。
例えば私は大学で専攻していた統計学を「集計したデータの意味を探る学問」だと簡潔に説明したうえで、「なぜこのような相関が生じるのか」「なぜこの変数が重要な意味を持つのか」といった「なぜ」の追究が学問上の特性として重要であるという解釈を述べていました。一方自分は幼少期から両親を困らせてしまうぐらい「なんでー?なんでー?」と目の前の事象の背景を追究する人間であり、その姿勢は大学生になった今でも一貫して持っていることを示していました。例えば小学校から大学まで続けているスポーツの練習においても、「走る」という単純な動作において、「この練習にどのような意味があるのか」「なぜこの時期にこの練習をするのが効果的と言えるのか」といった「なぜ」を追求しており、この姿勢が大学での専攻内容や今の自分の価値観に結びついていると一気通貫の形で示しました。そしてこの姿勢は御社でも〜〜という形で活かされると考えており...と、志望動機や自己PRを補完するうえで学業をうまく活用し高く評価されていたように感じています。また、経営・商系統の分野では(少なくとも私の大学では)マーケティングや経営学が花形とされる中で、地味で人気が低いとも言える統計学を選択したことが、そういった他者からの評価に流されることなく自分がやりたいと考えたことを追求できる根拠の一つとして挙げていました。この姿勢を、特にリーディングカンパニーでない志望度低めの企業の同業比較に繋げ、知名度や就職難易度といったミーハーな基準から企業を選んでいるのではないというアピールから内定の確保へ結びつけました。
このように、学業とは専攻内容を説明できるよう準備・暗記しておかなければというネガティブなものではなく、その使い方によっては説得力や再現性を高める良い手法になるとまとめることができるのではないでしょうか。また、学業と並行して先ほどの「ESで「書くことがない」と感じる就活生必見!日常生活から就活で使える”ネタ”を類推するアプローチ」の記事のように日常生活から補完していくアプローチも活用していくとより効果的と考えられるでしょう。
確かにこじつけかもしれないが、こじつけは大切だ
このような内容を書いていくと、「学業で述べたことなんてそれが実際に企業で役立つかはわからないし、そんなのただのこじつけだ」という意見が出てくるかもしれません。私自身正直この意見は正しく、自らが取ったアプローチをこじつけと言っても間違っていないと考えています。
しかし、就職活動における理由付けは学業に限ることなくほとんどこじつけに過ぎないということは認識しておくべきでしょう。例えばテニスサークルで周囲を巻き込んだ提案をしてリーダーシップを発揮したとしても、それが実際のビジネスの場で役に立つかどうかは採用側も学生本人ですらもわかりません。でもそれで評価を得ていくのが就職活動なのです。先ほどの「「考え抜くこと」で総合商社を勝ち取った普通の学生体験記 ー思考の抽出化で道を切り開くー」の学生が述べていた「一般的な体験から、考えや概念を抽出して、他に応用する」ことを意味する「思考の抽象化」も言ってしまえば「こじつけ力」であり、その水準の高さから総合商社から内定を得た良い例であると考えています。そしてこのこじつけ力は、それが評価される以上、就職活動に限らずビジネスの場でも応用が効くものでは、と推測できるのではないでしょうか。
最後に
大学受験までは、「勉学に励む=志望大学への合格のため」という形で努力がダイレクトに重要な成果に繋がったことでしょう。一方、大学生活では真面目に勉強するのはナンセンスであり、サークルや飲み会で遊び呆けていた方が就職活動でも有利になるというような風潮があるように感じています。
近代の著名な心理学者アドラーは以下のような言葉を残しました。
「何が与えられたかではない、それをどう使うかだ」
どんなことでも、「意味ない」として片付けてしまえばそれまでであり、アドラーのようにそれを「どう活かすか」という点について焦点をおき思考を深めていくことも大切なのではと考えています。
「学業」は学生の本分とも言われます。その「学業」について、本記事を通して皆さんの捉え方や就職活動における活かし方について思考を深めるきっかけとなれば幸いです。
photo by World Literature Today