【厳選】すべての就活生が読んでおくべき4冊の必読書
162,014 views
最終更新日:2024年10月23日

かつて伊藤忠商事で社長・会長を歴任した丹羽宇一郎氏も、著書『死ぬほど読書 (幻冬舎新書)』のなかで「本はいってみれば、人間力を磨くための栄養です。草木にとっての水のようなものといえます」と綴っています。
本記事では、就職活動を控えた方や、真っただ中の方に向けて、選りすぐりの必読書・4冊をご紹介します。また、記事の最後ではそれとは別に、就職活動の各フェーズで効果を発揮する5冊の選考対策本も紹介していますので、こちらも併せて参考にしてください。
【本記事のトピック】
■ 就活生が本を読むべき2つの理由
■ 必読書・4選
└内田和成 『仮説思考』
└杉野幹人『超・箇条書き』
└伊賀泰代『採用基準』
└橘玲『幸福の資本論』
■ 付録:【完全版】おすすめ選考対策本・5選
└【テスト対策】『これが本当のSPI3だ!』
└【GD・ケース対策】『東大生が書いた 問題を解く力を鍛えるケース問題ノート』
└【GD・ケース対策】『現役東大生が書いた 地頭を鍛えるフェルミ推定ノート』
└【自己分析】『さあ、才能(じぶん)に目覚めよう 新版 ストレングス・ファインダー2.0』
└【業界研究】『日経業界地図 2018年版』
■ 最後に:就活生よ、本を読もう!
就活生が本を読むべき2つの理由
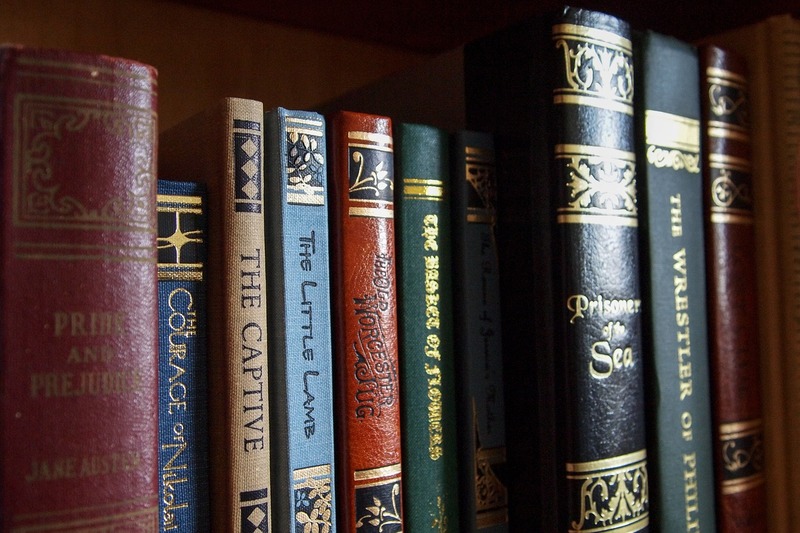
まずは導入として、「なぜ就活生は本を読むべきなのか」、この問いについて少しだけ検討してみましょう。
就活生の皆さんが(これまでにも増して)活字を読むべき理由は、2つあります。
① キャリアを考えるための土台になる
1つめに、あなたの幸福なキャリアを深く考えるための土台ができるためです。
就職活動とは、数ある選択肢のなかから、あなた自身の幸福を最大化するようなファーストキャリアを選び取るプロセスです。
さまざまな考え方や知識をインプットして見識を広め、改めてあなたの価値観を見つめなおすには、最適なタイミングのひとつであるといえるでしょう。
② 選考で評価されやすくなる
2つめに、思考法や伝え方の原則を学ぶことで選考で評価されやすくなるためです。
効率のよい思考法や相手が理解しやすい伝え方を心得ているだけで、就職活動の選考でのパフォーマンスは大きく改善されます。
とりわけ、ビジネスの現場で活躍している著者の書籍を読み、そこから彼らの思考法やコミュニケーションスキルを学び取ることは、企業の選考で課される面接やグループディスカッション(GD)に直接的に活きてくるはずです。
これらの理由から、読書は就職活動で納得のいく結果を手にするための最強のソリューションのひとつだと言えます。
必読書・4選
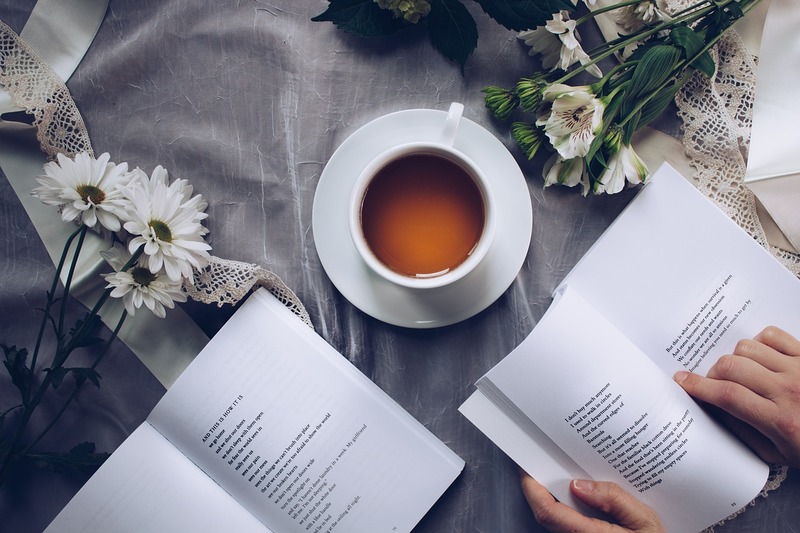
前置きが長くなりましたが、以下、unistyleから学生のみなさんに推奨したい4冊を紹介します。
必読書①:内田和成 『仮説思考』
トップファームのひとつ、ボストン・コンサルティング・グループ(BCG)でディレクターまで上りつめた内田和成氏が、短時間で高い成果を出すための思考法を分かりやすく解説した一冊です。
「仮説」とは、「まだ証明はしていないが、最も答えに近いと思われる答え」(本書より抜粋)のことであり、これを用いた思考法のことを「仮説思考」と呼んでいます。
これは、絶対的な解が存在しないビジネスの世界において、高い成果を出すためには欠かせない思考法のひとつだといえます。
これを会得し、実践することは、面接で高く評価されるような魅力的な経験・エピソードにつながるほか、GDやケース面接での議論にも活きてくるはずです。
また、中長期的なメリットとして、入社後に実際のビジネスの現場で活躍するための素地をつくることにもつながるでしょう。
必読書②:杉野幹人『超・箇条書き』
トップティアのコンサルティングファーム、A.T.カーニーでマネジャーを務める杉野幹人氏の著書。
「短く、魅力的に伝える」ための必須スキル「Bullet Points(箇条書き)」について、実践的なテクニックまでが詳細に解説されています。
皆さんがどんなに魅力的なアピールポイントを持っていたとしても、それを正しく企業側に伝えることができなければ、残念ながら何の意味もありません。
本書が指南する「超・箇条書き」というスキルは、ESの作成はもちろん、面接でのアピールやGD・ケース面接でのディスカッションなど、就職活動のあらゆるフェーズで劇的な効果を発揮するはずです。
必読書③:伊賀泰代『採用基準』
マッキンゼー・アンド・カンパニーの採用マネジャーを12年のあいだ務めた伊賀泰代氏が、社会から本当に必要とされる優秀な人材像を明らかにした一冊です。
「マッキンゼーが求める人材」は、実は「いまの日本社会が必要としている人材」とまったく同じであるとしたうえで、その条件(採用基準)となるたった1つの資質を解説しています(その資質が何であるかは、ぜひ実際に著書を手に取って確認してください)。
マッキンゼーのようなコンサルティングファームを志望する学生だけでなく、これからビジネスのフィールドで活躍したいと考えているすべての学生が読むべき内容になっています。
なお、本書については、unistyleにおいて以下の記事でも言及しています。
必読書④:橘玲『幸福の資本論』
作家・社会評論家である橘玲氏が、「これからの社会で”幸福に生きる”ためには、どのように人生を設計すべきか」という本質的な論点を検討した一冊です。
橘氏は、人間が手にすることのできる資本を「金融資産(資本)」「人的資本」「社会資本」の3つに分けて定義したうえで、すべての人間の「幸福」な人生パターンはこれら3つの組み合わせによって説明できるとしています。
ファーストキャリアとする企業を選び、社会人生活のエントランスをくぐる前に、ぜひ本書をヒントに「自分にとって”幸福な人生”とは何か」を考えてみてください。
付録:【完全版】おすすめ選考対策本5選
ここまで紹介してきた必読書とは別に、自己分析や業界研究、面接対策など、実際の選考に向けて具体的な対策を行うための5冊のおすすめ就活本も挙げておきます。
書店の就活コーナーには大量の書籍が並べられており、どれを買えばいいか分からなくなってしまう方も多いかと思いますが、ひとまずは以下の5冊を選べば間違いはありません。
【テスト対策】『これが本当のSPI3だ!』
SPIの主要3方式(テストセンター・ペーパーテスト・WEBテスティング)すべてに対応したテスト対策問題集。(もちろん、個人の得手・不得手にもよりますが)これ一冊をしっかりと解き込んでおけば、一般的な水準のテスト対策としては十分でしょう。
▼テスト対策については、以下の記事もご覧ください。
【GD・ケース対策】『東大生が書いた 問題を解く力を鍛えるケース問題ノート』
本来は外資コンサルなどの選考で課されるケース問題対策本ですが、グループディスカッション(GD)対策としても高い効果を発揮します(なぜなら、GDとケース問題の違いは「与えられた問題を複数人で解くか、ひとりで解くか」にすぎないため)。
また、以下の記事にもあるように、最近では総合商社を始めとした日系大手企業でもケース問題が課される機会が増えています。
シンプルなフレームワークの助けを借りながら例題に取り組めば、みるみる実力がつくはずです。
コンサル志望者はもちろん、グループディスカッションに苦手意識がある日系大手志望の方も今すぐ取り組みましょう。
▼GD対策については、以下の記事もご覧ください。
【GD・ケース対策】『現役東大生が書いた 地頭を鍛えるフェルミ推定ノート』
上記の『ケース問題ノート』と併用したいのが、こちらの『フェルミ推定ノート』です。
フェルミ推定とは、「日本全国にマンホールはいくつ存在するか」など、正確に求めるのが難しい数値を論理的に概算することをいいます。
ビジネスライクな数的思考力を鍛えられるほか、ケース問題やグループディスカッションのなかで売上推定を行うときなど、ケースワークに取り組むうえで大いに役立ちます。
本書は数学が苦手な文系学生でも親しみやすいよう、具体的な例題を交えながらシンプルに書かれており、効率よく学習を進めることができます。
すべての就活生におすすめしたいワークブックです。
【自己分析】『さあ、才能(じぶん)に目覚めよう 新版 ストレングス・ファインダー2.0』
あなた自身の強みを知るために一役買う、ベストセラー本です。
一冊ごとに固有のシリアルナンバーが付属しており、Web上でこれを入力して〈ストレングス・ファインダー2.0〉という診断テストを受けると、あなた自身が持つ「5つの資質」を知ることができます。
独力での自己分析に行き詰まってしまったとき、新しい視点から自分を顧みたいときなどに活用するとよいでしょう。
ただし、こうした書籍はあくまでツールに過ぎません。
「やって満足」で終わらないよう、戦略的に自己分析を進めましょう。
▼自己分析については、以下の記事を必ずご覧ください。
【業界研究】『日経業界地図 2018年版』
日経新聞社が毎年リリースしている業界地図も、さまざまな業界を広く・浅く俯瞰するのには役立ちます。
志望業界の見当がつかない方や産業構造を広く知りたい方などは、本書を入り口にして業界研究を始めるとよいでしょう。
(もちろん、より本格的な業界研究を行う際は、また別の手段を講じる必要があります。)
▼業界研究については、以下の記事を必ずご覧ください。
最後に:就活生よ、本を読もう!

本記事では、unistyleが学生の皆さんにおすすめしたい4冊の必読書、さらに付録として5冊の選考対策本をご紹介しました。
以下、ラインナップを再掲しておきます。
【4冊の必読書】
■ 内田和成 『仮説思考』
■ 杉野幹人『超・箇条書き』
■ 伊賀泰代『採用基準』
■ 橘玲『幸福の資本論』
【付録:5冊の選考対策本】
■『これが本当のSPI3だ!』
■『東大生が書いた 問題を解く力を鍛えるケース問題ノート』
■『現役東大生が書いた 地頭を鍛えるフェルミ推定ノート』
■『さあ、才能(じぶん)に目覚めよう 新版 ストレングス・ファインダー2.0』
■『日経業界地図 2018年版』
就職活動というタイミング、そして本記事で挙げた4冊の良著をきっかけにして、ぜひたくさんの本を読んでみてください。
読破した本たちはきっと、皆さんの人生の肥やしになるはずです。
下記には、その他各業界志望者におすすめの書籍を紹介した記事へのリンクもありますので、併せて参考にしてみてください。


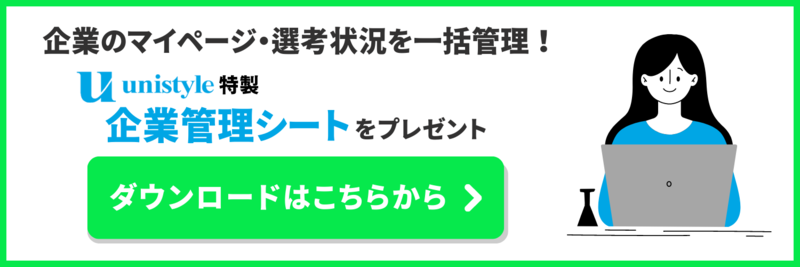












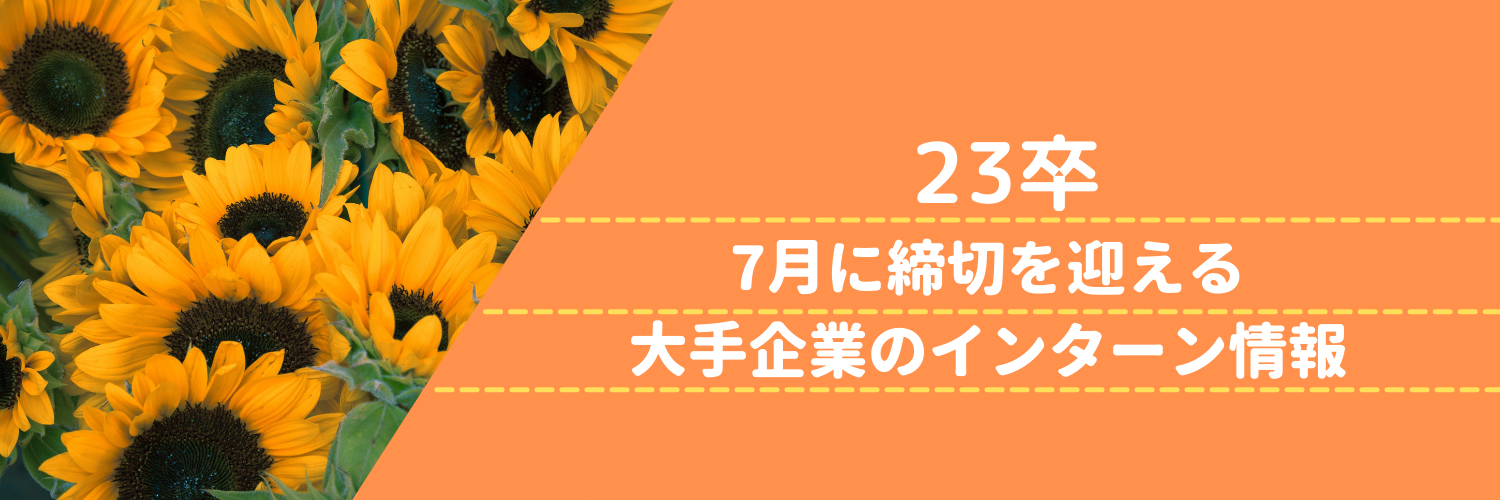
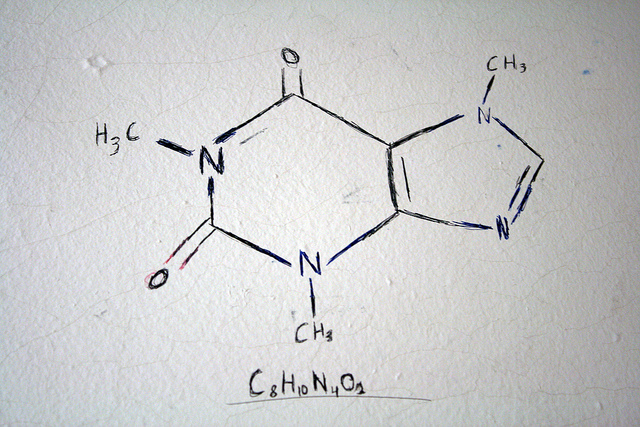
.jpeg?1436927238)

