お祈りメールに返信はした方が良い?例文や送った方がいい状況について紹介!
15,697 views
最終更新日:2023年09月25日
.png?1585118794)
アドバイザーから、なぜ不採用になってしまうのか弱点を教えてもらい、その弱点にフォーカスして対策することで、就職活動失敗の回避につながります。
少しでも興味があるという方は、下記の画像をクリックしてサービスを利用してみてください。
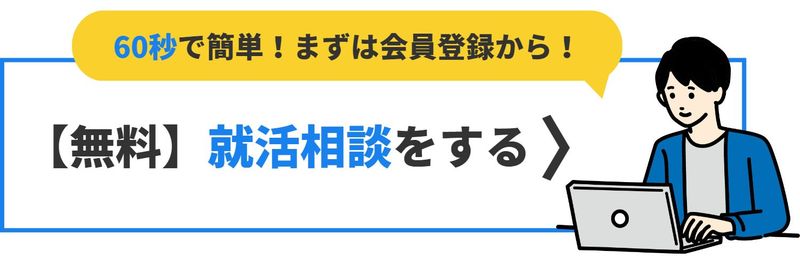
企業からのお祈りメール。就職活動を行っていると誰しもが聞いたことがあるでしょう。
お祈りメールとは不採用通知の俗称であり、末尾に「今後のご活躍をお祈り申し上げます。」と一文で締めくくられることからお祈りメールと呼称されるようになりました。
お祈りメールに関して、就活生によく生じる疑問があります。
それは「返信をしたほうがいいのかどうか」です。
結論、お祈りメールには返信したほうが良い場合と返信しなくても良い場合があります。
本記事ではその理由を場合別に詳しく紹介していきます。
基本的にお祈りメールに返信が必要ない理由
お祈りをされた時点で一方的にやり取りが終了されており、その企業と就活の場で関わりを持つことはありません。
わざわざもう1度やり取りを復活させなくても大丈夫です。
また、それ以外に基本的に返信が必要のない理由を就活生側の観点、企業側の観点からそれぞれ説明します。
就活生側の観点から
就活生は数多くの企業にESや履歴書を送っています。
全てにその都度返信していたら時間がもったいありません。返信をする時間を他の就活対策にあてることが得策です。
また、お祈りメールが送られてきて落ち込むこともあるでしょう。しかし、落ち込みすぎてはいけません。
たかだか数万ある会社の一部とマッチしなかっただけのことです。気持ちを切り替えて、内定を取るために施策を考えて行動することが大切です。
企業側の観点から
なぜ企業は電話や郵便ではなくお祈りメールを送るのか?
それは不採用者への対応になるべくリソースをかけないためです。
人事は自社にとって適切な人材を採用することを目標としており、採用に使えるリソース(人、資金、時間 等)は限られています。
より適切な人材を見極めるために、リソースを使って応募者を絞っていかなければいけません。不採用者に対してリソースをかけすぎることは不適切となります。
ではなぜお祈りメールがあまりリソースがかからないのか?
それはお祈りメールはシステムによって自動送信をすることができるからです。
大量採用を行う大手企業にとっては、不採用通知を送るにあたってコストと手間があまりかからないので効率的です。もちろん企業によっては自動送信をせずにお祈りメールを送る場合もあります。
返信をしたほうがいい4つの状況とは?
このコンテンツは会員(無料)の方のみご覧になれます。
また、会員(無料)の方は81698枚のエントリーシートを全て閲覧可能になります。
(無料会員登録はこちら)
なお、なぜ不採用になってしまうのか、自身の弱点を知りたいという就活生には就職エージェントneoの利用も検討してみましょう。
アドバイザーから面接対策や自己分析の方法に対して客観的にアドバイスがもらえるため、自身の弱点を克服し内定獲得に近づくことができます。
少しでも興味があるという方は、下記の画像をクリックしてサービスを利用してみてください。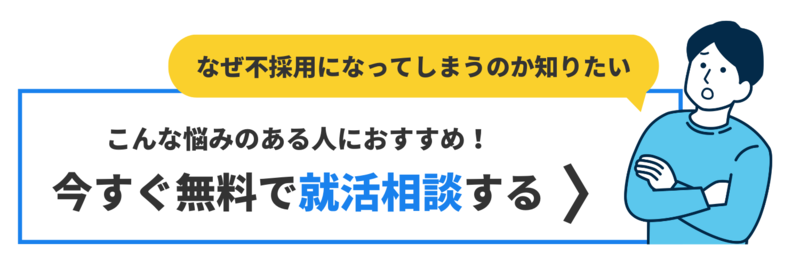
お祈りメールの返信文の6つのポイントと状況別の例

「返信はしたいけれど、何を書いたらいいのかわからない」と悩む就活生も多いと思います。
以下では返信文の6つのポイントと状況別の例文を解説しているので、ぜひ参考にしてください。
このコンテンツは会員(無料)の方のみご覧になれます。
また、会員(無料)の方は81698枚のエントリーシートを全て閲覧可能になります。
(無料会員登録はこちら)
まとめ
本記事ではお祈りメールの対処法について紹介しました。
お祈りメールの対処法に関して、以下の4つの要点を参考にしてください。
- 基本的に返信しないことはマナー違反にならない
- 理由があるときは返信をしても良い
- 返信する際には6つのポイントを意識する
- お祈りメールにあてる時間をほかの就活対策に割り当てる
お祈りメールで正しい対応をすることがゴールではありません。内定を獲得し輝かしいキャリアを築くことをゴールです。そのためには落ちてしまった理由を考えることが大切です。
「自己分析が足りなかったのか」「面接準備が足りなかったのか」「企業研究が足りなかったのか」
なぜ落ちたのかをしっかりと考えて次の選考までに対策できるようにしましょう。




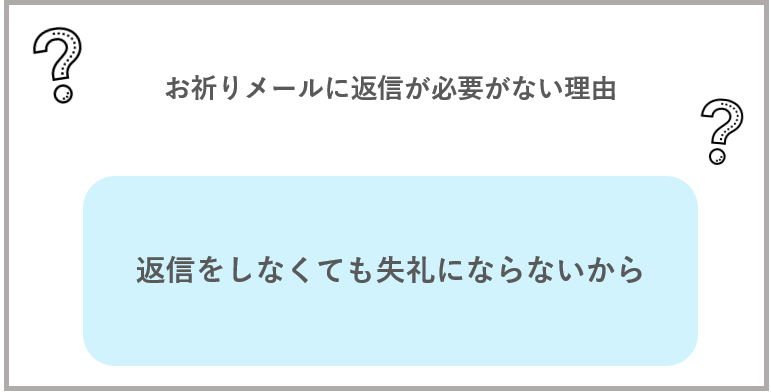
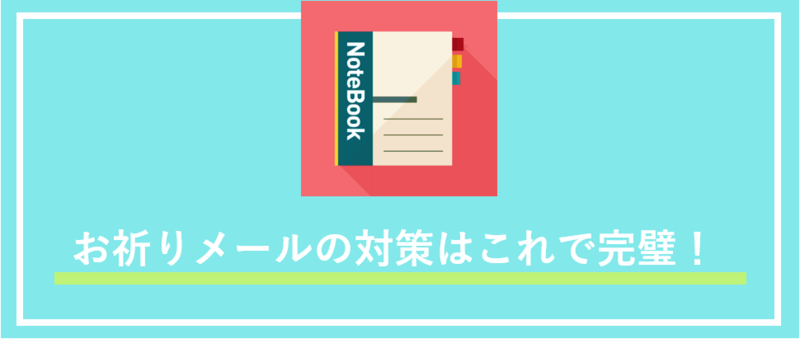


.png?1582596398)

アイキャッチ.png?1625472837)
.png?1586159709)
