内定者の逆質問は真似るべきなのか?【大手企業内定者逆質問例】
13,372 views
最終更新日:2023年10月30日
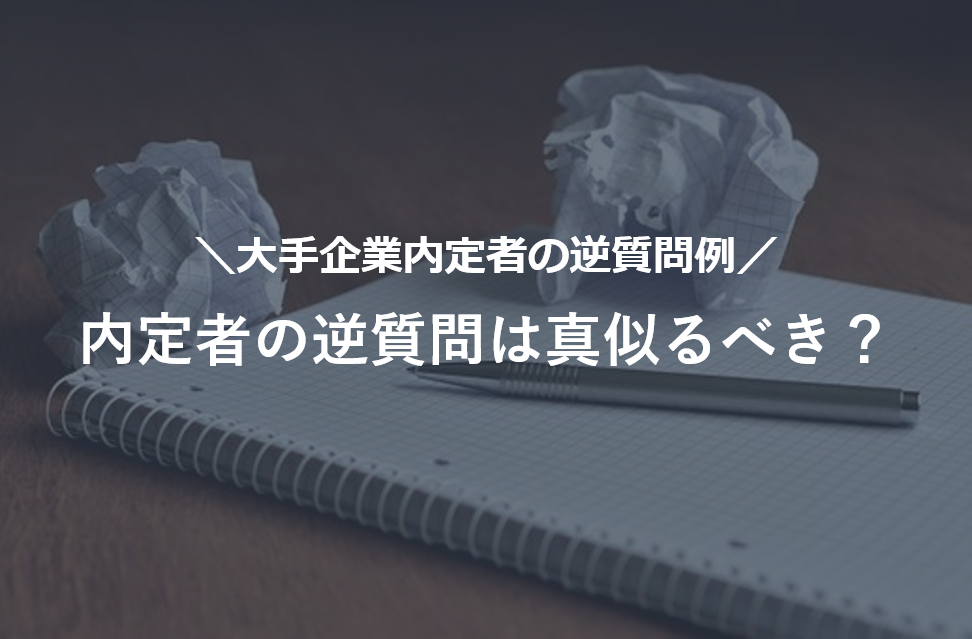
来たる本選考に向け、多くの就活生の方は面接対策に励むことかと思いますが、その際に多くの方から聞く悩みが"逆質問"です。
「逆質問ってどんな質問をすればいいの…?」
「評価される逆質問とは何か知りたい!」
本記事を読んでいる方、さらには周りの友達などでも上記のような悩みを抱いている方はいるのではないでしょうか。
では実際に逆質問を考える際、最も簡単で効率的な方法は何でしょうか?
それはおそらく「大手企業に内定した就活生の逆質問を真似すること」だと思います。
そこで本記事では、大手企業に内定した2人の就活生にヒアリングをし、実際の本選考でした逆質問をまとめてみました。2人の就活生のプロフィールは以下の通りです。
【実際の本選考で聞いた逆質問】就活生Aさん

21卒就活生のAさんは、内定を獲得した大手外資系コンサルティングファームの面接で以下のような逆質問をしたようです。
※企業名や就活生個人の特定に繋がる箇所は隠させていただいています。ご了承ください。
●今後の成長戦略についてお聞きします。◯◯という背景を考慮すると、御社は今後◯◯という戦略を打ち進めて行くという印象を持ちました。この認識は合っていますでしょうか?
●御社の◯◯領域への進出についてお聞きします。御社は◯◯社の買収など、◯◯領域にも注力されていることと思います。その背景を考慮すると、◯◯領域の進出には◯◯という目的があると考えたのですが、この認識は合っていますでしょうか?
●御社の強みとして◯◯を持っているという認識がありますが、その認識は合っていますでしょうか?
●私は将来的に◯◯(役職名)まで昇進したいと考えているのですが、そのように昇進する社員の方に共通する特徴・素養などはありますでしょうか?
上記で取り上げた逆質問を見てみると「質問の大枠→実際のデータや仮説を踏まえた上での具体的な質問」という構成になっていることが読み取れるかと思います。
また、上記の質問の多くは"クローズドクエスチョン"であることも分かるかと思います。
【クローズドクエスチョンとは】
yes/noで答えられるような、答える方法や回答範囲を限定した質問の仕方。対義語は「オープンクエスチョン」。
Aさんによると、オープンクエスチョンよりもクローズドクエスチョンの方が面接官の反応が良かったようです。仮説ではありますが、後者の方が瞬発的に回答でき話も広げやすいため、より面接官視点に立った質問と言えるのではないでしょうか。
また、4番目に取り上げた「昇進に関する逆質問」は特に面接官からの反応が良かったようです。実際にこの逆質問をした際、「現在では外コンに長年勤める想定で入社する人は珍しいし、入社・仕事への意欲を非常に感じるね」というようなフィードバックを貰ったそうです。
【実際の本選考で聞いた逆質問】就活生Bさん

20卒就活生のBさんは、内定を獲得した3大通信キャリアや大手自動車メーカーの面接で以下のような逆質問をしたようです。
※企業名や就活生個人の特定に繋がる箇所は隠させていただいています。ご了承ください。
●(仮説を述べた上で)御社で活躍している社員の方に共通点はありますでしょうか?
●(描きたいキャリアを述べた上で)自分自身の描きたいキャリアの前例となる人がいますでしょうか?もしくは叶えられるでしょうか?
●(自分自身が入社先を迷っていることを伝えた上で)◯◯さん(面接官)はなぜ御社への入社を決めたのでしょうか?
●(業界研究をしてある程度仮説を持った上で)御社が競合他社と比べて勝っていると感じる部分、負けていると感じる部分はどこでしょうか?
●入社までにやっておくべきことは何かありますでしょうか?
●◯◯さん(面接官)に新たに部下がつくとした場合、どのような人を求めるでしょうか?
→(上記の質問に付随し)〇〇さん(前の選考を担当してくれた面接官)は~と話していたのですが、どう思いますでしょうか?
上記の質問を見てみると、その多くが「仮説や前提を持った上での逆質問」であることが分かると思います。
仮説や前提を伝えることで、しっかりと練り上げられた逆質問であることをアピールすることができますし、納得感のある回答が返ってくる可能性も高いでしょう。
また、「会社で活躍している人の共通点・入社までにやっておくべきこと」など、入社意欲を示すような逆質問が複数あることも特徴です。
Aさんの逆質問が外コンに特化した内容だったのに対し、Bさんの逆質問は「どの業界にも応用可能な汎用性の高い逆質問」と言えるでしょう。
内定者の逆質問をそのまま真似しよう!と考えるのは浅はか…かも?

ここまで、大手企業内定者が実際の本選考で聞いた逆質問をいくつか紹介してきました。
逆質問は面接の終盤やリクルーター面談で課されることが多いのですが、この逆質問の良し悪しが面接・面談全体の評価にも大きく影響するため、非常に重要と言えます。
「どんな逆質問をすればいいか分からない…。」と悩んでいる就活生の方は、真似してみてはいかがでしょうか?
と言いたいところですが、文章を丸々真似してもおそらく高い評価を得ることは難しく、自分自身の意図した回答が返って来る可能性も低いでしょう。
これまで、「大手企業内定者が実際の本選考で聞いた逆質問集」などと銘打って紹介しておきながら、「何を今さら?」と思う方もいるかもしれませんが、あくまでも"内定者の逆質問をそのまま真似するのではなく、参考にした上で自分なりの逆質問に作り変えること"が重要です。
ではなぜ、丸々真似することを避けるべきなのでしょうか?
その理由を「面接官が逆質問の時間を設ける目的・就活生が逆質問をする目的」の観点から解説していきます。
逆質問をする際は「面接官と就活生双方の目的」を理解しよう

逆質問をする際は「面接官と就活生双方の目的」を理解することが非常に重要になります。
面接官が逆質問の時間を設ける目的
まずは、面接官が逆質問の時間を設ける目的から紹介します。
結論から言うと、面接官側の目的は"その就活生を採用すべきか否かを判断するため"という観点に集約されます。
さらに、上記の基準を要素分解すると、「スキル面(自社の採用基準を満たすスペックがあるか)・モチベーション面(自社に興味があり、志望度は高いのか)」の2つになります。
そしてこの2点を判断するにあたり、「それまでの面接における回答との一貫性があるのか?」という部分も重要になります。
あくまでも、面接官は「面接の中の一つの判断基準として逆質問の時間を設けている」ため、その観点を忘れないように心掛けるべきでしょう。
ちなみに、面接官からの「逆質問はありますか?」という問いに対し「特にありません。」と話す就活生も稀にいますが、この回答は論外です。
「御社の企業研究・企業理解は万全なため、面接の場でわざわざ質問することなどありません!」ということを暗に示したいのかもしれませんが、確実に逆効果でしょう。
面接官から「逆質問はありますか?」と振られた際は何かしらの質問はする、これは最低限必要な部分になります。
就活生が逆質問をする目的
続いては、就活生が逆質問をする目的を紹介します。
就活生が逆質問をする目的は、大きく以下の3つに大別することができます。
- 自身の志望度の高さをアピールするため
- 業界理解・企業理解をより深めるため
- 自身の企業選びの軸がその企業と合致しているかを確認するため
(1)自身の志望度をアピールするため
逆質問といえど、間接的に「志望度の高さをアピールする」ことは可能です。
「入社意欲を示す逆質問・いち社員として活躍したいという心意気を示す逆質問などを通じ、面接官から「この就活生はうちへの入社意思が強いな」と感じてもらえることができるかもしれません。
とは言え、志望度をアピールすることに関しては結果論でもあるため、「どうすれば高い評価をもらえるか?」にあまり固執しすぎないように注意しましょう。
(2)業界理解・企業理解をより深めるため
面接の逆質問は、「説明会やHP上では知り得ない情報」を得る貴重な機会となります。
逆質問は基本的に自分の聞きたいことを質問できるため、この機会を利用して「業界理解・企業理解」をより深めていきましょう。
また、業界理解・企業理解を深めることに加えて「自身の仮説を検証すること」もできます。
逆質問をする際に「私は~~と考えているのですが、この認識は合っていますでしょうか?」などと聞くことで、仮説の正誤を確認することができます。
これらの観点は「志望動機作成」にも直結しますので、逆質問を効果的に利用しましょう。
【最新版】業界研究のやり方やポイントをわかりやすく徹底解説
【保存版】41業界を徹底解説!unistyle業界研究記事まとめ
企業研究のやり方を徹底解説-新卒就活を効率的に進めるためのコツとは?-
→逆質問で業界理解・企業理解を深める前に、最低限の「業界研究・企業研究」に取り組んでおくことは必須となります。上記3記事を確認し、逆質問に臨む前に業界研究・企業研究を進めておきましょう。
(3)自身の企業選びの軸がその企業と合致しているかを確認するため
就活生が逆質問をする目的としては、この観点が「最重要」と言われています。
この観点を見落としてしまうと、「とりあえず質問をしたはいいけど、結局この情報を得たところでこれから何をすればいいんだろう…」と本来の目的を見失ってしまう可能性があるためです。
自身の企業選びの軸を持った上で、「自身の企業選びの軸と合致しているか」という観点を意識して逆質問の質問内容を考えましょう。
簡単にできる自己分析のやり方8選!-やり方別のメリット・デメリットをunistyleが独自調査-
カテゴリ別!自己分析を効率的に進めるための質問リスト
→大前提、「自己分析をしなければ企業選びの軸を定めることは難しい」と考えられます。企業選びの軸がまだ定まっていない方は、上記の2記事を参考にし、まずは自己分析から取り組んでいただければと思います。
つまり、「大手企業内定者の逆質問を丸々真似すること」がなぜダメかというと?

ここまで読み進めていただいてくれた方であれば、「大手企業内定者の逆質問を丸々真似することがダメな理由」を理解していただいたでしょう。
逆質問は、質問をすること自体に価値・意味があるという訳ではありません。逆質問をすることが目的化しないように注意しましょう。
ここまで紹介してきた「大手企業内定者の逆質問を丸々真似するべきではない理由」をおさらいさせていただくと、以下の2点にまとめられます。
(1)逆質問はこれまでの面接での回答との一貫性がないと評価されないため
(2)大手企業内定者と自分自身の企業選びの軸が異なっている場合があるため
(1)逆質問はこれまでの面接での回答との一貫性がないと評価されないため
こちらの理由に関しては少し分かりづらいかもしれないため、一つ具体例を挙げて説明させていただきます。
A社の面接に就活生のB君が臨みました。B君は志望動機で「営業でトップの成果を挙げたいです!」と話したのにも関わらず、逆質問の際に「御社の営業職にはノルマはあるでしょうか?」と質問した場合、面接官はどのように感じるでしょうか。
おそらく面接官は「トップの成果を挙げたいと話していたのに、ノルマを気にするなんて矛盾しているな。トップの成果を挙げたいというのは本心ではないのだろうな。」と思う可能性は少なからずあるでしょう。
これが「面接との一貫性」の説明になります。あくまでも「面接の中の一つの判断基準としての逆質問」であるため、その観点を忘れないように心掛けるべきでしょう。
(2)大手企業内定者と自分自身の企業選びの軸が異なっている場合があるため
上記でも紹介しましたが、「自身の企業選びの軸がその企業と合致しているかを確認すること」も、就活生が逆質問をする目的となります。
企業選びの軸が異なれば、聞くべき質問・逆質問から得たい情報も異なりますので、「自分はどんな情報を得たいのか?その情報を得るためにはどんな質問をするべきなのか?」という観点は見落とさないようにしましょう。
企業選びの軸(就活の軸)の定め方とES(エントリーシート)例文を紹介 -大手企業内定者の回答例13選-
【企業選びの軸一覧】内定者ES例文50選と軸の定め方を紹介
→企業選びの軸を定めることは非常に重要です。上記の2記事では「企業選びの軸を定める意味・各業界内定者の企業選びの軸」などが紹介されています。
まとめ:自分なりの逆質問を考えるには?
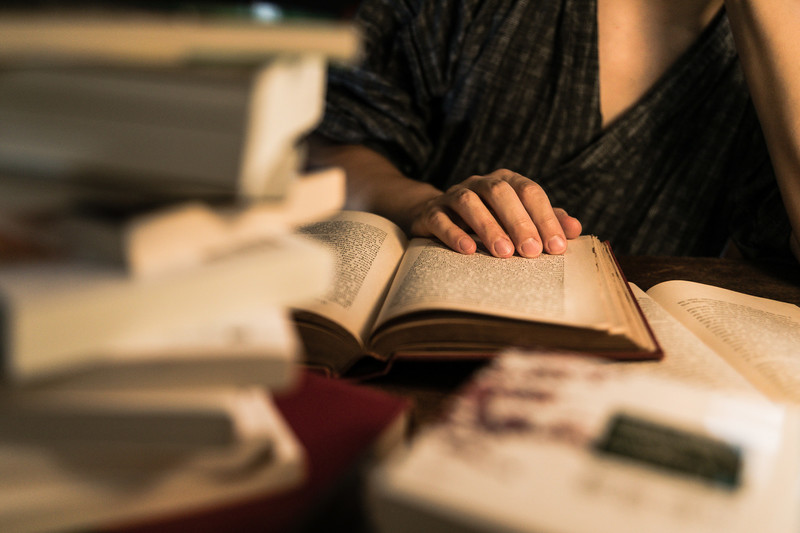
「大手企業内定者の逆質問を参考にするのは良いが、丸々真似するべきではない」ことは理解していただけたと思いますので、最後に「自分なりの逆質問を考えるには?」という観点から述べさせていただきます。
改めてにはなりますが、大手企業内定者の逆質問をそのまま真似してもあまり意味はありません。
大切なのは"逆質問をする目的を正しく理解し、その上で大手企業の内定者が実際の本選考でした逆質問などを参考にし、自分なりの逆質問を作成すること"だと考えられます。
unistyleには、逆質問をテーマにした記事がいくつか掲載されています。
本記事の内容と関連記事なども確認し、逆質問作成の参考にしていただければと思います。
逆質問の考え方・作り方を知りたい方はこちらの記事へ
逆質問の作り方・考え方を解説した上で、例文も掲載している記事になります。本記事の内容と関連している部分も多数ありますので、本記事と併せてご確認ください。
●面接官が逆質問をする意図
●面接官に好印象を与える逆質問の考え方
●面接官に好印象を与える逆質問の作り方
●最終面接の逆質問例
●最後に
逆質問のNG例を知りたい方はこちらの記事へ
【逆質問でのNG質問3パターン】説明会・面接で失敗しないためには?
評価されない逆質問の特徴を解説しています。自分自身で考えていた逆質問がNG例に該当していないか、確認してみてください。
●逆質問は非常に評価されてる、質問は差が出やすい
●自分のできなさから来る不安を解消するための質問は評価されない
●調べればわかる質問をわざわざ対面で聞くのは評価されない
●それ聞いてどうするの?と思われる質問は評価されない
●良い質問の最低条件は「質問の意図を伝えること」
●最後に
逆質問の具体的なイメージを掴みたい方はこちらの記事へ
面接での逆質問で選考官の心を掴む!面接官・企業別面接シーン3選
実例を元に「逆質問がどのように進むのか」を紹介した記事です。逆質問のリアルなイメージを掴みたい方にとって参考になる内容が記載されています。
●生命保険の1次面接
●シンクタンクの2次面接
●ITメガベンチャーの最終面接
●全体へのフィードバック










