営業タイプor企画タイプ!?リクルートの採用方針に見る企業が求める人材の変遷
22,433 views
最終更新日:2023年11月01日

「未来の起業家集団?!リクルート内定者が内定者懇親会に行って感じたこと」でも内定者に書いてもらいましたが、リクルートは分社化してからより明確に採用したい人材に変化があるように感じられます。古きよきリクルートの社員というと、どちらかというと猪突猛進の営業マンタイプの人が多く、リクルートの社員であればどんな商材も売れるといったタイプの人が多かったように思います。
一方で、最近では受験サプリ、Airレジなど様々な新規サービスをリリースし、またアメリカのindeed買収をはじめとする巨額買収を繰り返すなど、営業だけでなく新規事業やM&Aに積極的な印象を受けます。ビジネスモデル環境の変化からか、内定者や転職者の質も変化してきているという話を中で働く人や内定者から聞いていますので、今回はそれについて説明したいと思います。
競争力のあるサービスが生まれた段階では、営業マンタイプが欲しい
企業の成長サイクルとして、サービスが生まれてある程度認知されてからは浸透させるために営業マンタイプの人材が欲しくなります。例えば、リクナビがネットで生まれてからは市場のシェアを取るために優秀な営業マンがそれこそ全国に散らばりリクナビという商品を売りまくりました。ゼクシィも同様に1993年に創刊してからじわじわと部数をのばし、一気にのばす段階で営業マンタイプの人間を大量に採用したと言います。
近年では、受験サプリの営業に力を入れているらしく、各カンパニーの優秀な営業マンが受験サプリの営業として全国の各高校に売って歩いているようです。
このように競争力のあるサービスが生まれてその認知を促進する段階では、いわゆる古きよきリクルートの人のような営業マンタイプの人材を多く採用する傾向にあります。2000年代のリクルートはリクナビ、ゼクシィなどの商品の成長がまだまだ見込めたためにそういった営業マンタイプの人材を多めに採用していたようです。
サービスの競争力が低下したり成長が鈍化した段階では、企画タイプの人材が欲しい
リクナビで言えば既に市場の大部分を牛耳っており、ゼクシィについても国内についてはかなりのシェアを占めるようになり、必然的に成長が鈍化しています。そのため営業の方法としても同業他社からシェアを奪われないようにする守りの戦いがメインになり、優秀な営業マンが活躍できる土壌も減ってきます。
そのためサービスがある程度成長した段階では、優秀な営業マンタイプの人材よりも新たな新規サービスを生み出すことのできる企画系の人材を多数採用したくなります。
近年はリクルートも企画タイプの人材を採用している傾向が強く、特に販促系のリクルート各カンパニーは、自分でサービスを生み出し大きく育てたいといったタイプの人が多いように感じられます。上記の通り、既存のサービスの成長が鈍化しており、Airレジや受験サプリなど次の成長分野になるサービスを生み出したり、買収して提携するなどして生み出せる企画系の人材を欲していると考えられます。
ベンチャー企業も同様に、営業タイプが欲しい会社と企画タイプが欲しい会社が存在する
「ベンチャー企業に行けば、新しい事業にスピード感を持って取り組める」と短絡的に考えて受けてしまう人も多いのですが、ベンチャーも上記と同様に営業タイプが欲しいのか企画タイプが欲しい会社なのか明確に存在しています。多くの場合、「ベンチャー」というフェーズから抜け出し上場しているような企業の方が企画タイプを欲しているように思います。上記の通り、既存サービスの成長力が鈍化している時に新規サービスが生まれる傾向にあるため、既にイケてるサービスをリリースして市場のシェアを奪う段階では営業マンタイプが欲しいのです。だからこそDeNAのように既存のソーシャルゲーム市場がシュリンクして別事業に転換せざるを得ないような企業や、アメーバ事業の成長が鈍化し、スマホ分野に移行したサイバーエージェントのように、少し成長力にかげりが見えるものの、キャッシュは豊富にある企業の方が企画で新しいサービスを生み出すことにフォーカスします。
ベンチャーならではのスピード感で事業を生み出したいと考えてベンチャーを志望すると、上記のように営業マンタイプが欲しいだけの会社で企画を志望することになりミスマッチになることも考えられます。
企画タイプをそこまで欲してない銀行・証券、不動産営業
企画による商品の差別化が難しい業界においては常に営業マンタイプが求められることになります。特に銀行や証券などは差別化の難しい金融商品を扱っており、そうした企業においてはとにかく商品を売ることのできる営業マンタイプを多数必要としており、企画タイプの人材は多数の営業マンの中に少数いればOKと考えているように感じられます。同様のことが不動産営業についても言えるでしょう。不動産営業については多くの業者がレインズという不動産の管理サイトを利用しており、商品や企画力による差別化が難しくなっています。不動産ディベロッパーのように商品そのものを生み出すことができる企業であれば別ですが、その販売を行う会社となると常に営業タイプの人材を欲するようになります。
最後に
営業タイプ、企画タイプに優劣があるわけではなく、それぞれ向いている人と向いていない人がいると考えてください。営業タイプの人が企画タイプの仕事に入社してしまうとその力を発揮できないでしょうし、逆もまたしかりです。また自分としては企画タイプの仕事を望んだとしても、テストや面接を通して、企画タイプには向いていないと判断されるケースももちろんあります。冒頭で紹介したリクルート内定者は、「モチベーションの源泉が違う」と言われて志望度の高かった販促系のカンパニーに落ちてしまっていますが、そういった志向性も企業としてはよく見ているということでしょう。
自分自身の志向性がどちら向きなのか最後までわからない部分もあると思いますので営業タイプの人材が欲しい企業も企画タイプの人材が欲しい企業も両方とも受けながら結果で判断してみるというのも一つだと思います。企画タイプの企業に入りたいから、営業タイプの企業に入りたいからと嘘の志向性を話すことは見破られることがそもそも多いですし、見破られずに入社したとしても向いてない仕事を続けるのはなかなか辛いものです。ぜひ正直に自分自身の経験や考えを話して評価してもらってほしいと思います。
photo by Martin Thomas



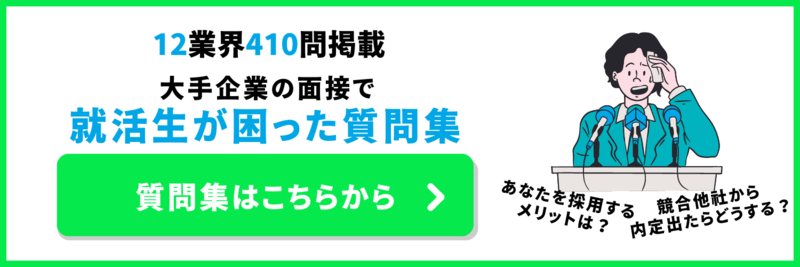



.png?1556260027)


