「転職」で総合商社を比較する ―投資側への転職なら三菱商事を選べ―
30,290 views
最終更新日:2023年10月26日

新卒就活中の皆さんは、どれだけ【入社後の転職】を視野に入れているでしょうか?日本的な終身雇用原則が崩れつつあるなか、同一企業に40年勤め上げることを過度に信奉せず、将来的な転職までを見越して新卒入社先を検討するべきでしょう。
unistyleでも「勝ち組企業に内定したと思ってる学生は「ブラック・スワン」を読んでおこう」・「10年前は東電・シャープに入社した人は勝ち組だった」を始めとした記事で、入社時のブランドや給与水準が永劫保証されているわけではないとお伝えしています。
また、入社してから転職活動のための業界研究ができる時間は限られていることから、就職活動の段階でベンチャー起業も含めて幅広く様々な業界を受けることが重要であると考えています。
今回は、いわゆる日本的大企業の代表格とも言える「総合商社」をピックアップしました。
実際の転職者データをもとに、【総合商社に新卒入社した方の転職キャリア】について考察していきたいと思います。
転職キャリアのリサーチ

unistyleでは「人気企業に新卒入社したあとに転職して辿り着くエリートキャリア」を考えるため、
◆プライベート・エクイティ・ファンド(PE)
◆ベンチャー・キャピタル(VC)
◆戦略コンサル
◆ベンチャー企業の創業者および役員(未上場も含む)
以上4つの集団の現職者に対象を限定し、これに該当するビジネスエリート計1231名のキャリアをリサーチすることで「一流転職市場のリアル」に迫りました。
(なお、全ての情報は有価証券報告書ないし企業HPから収集したものです)
総合商社の転職事情

今回は【総合商社からの転職ルート】、特に【ファンドへの転職】にフォーカスします。
新卒就活市場において非常に人気の高い総合商社ですが、その後の転職までを視野に入れて検討している学生は決して多くないと思います。
・実際に総合商社から転職した方が、その後にどんなキャリアを歩んでいるか
・各総合商社を比較したとき、その転職キャリアの傾向に違いはあるか
本記事から以上2点を把握し、キャリア選択の好材料としていただきたく思います。
a. 総合商社から転職する人数は多くない
最初の論点は、「そもそも総合商社からの転職者はどの程度いるか」という点です。
以下、4つの集団それぞれにおける総合商社7社(三菱商事、三井物産、伊藤忠商事、住友商事、丸紅、双日、豊田通商)出身者の人数を合計しました。
◆各集団の7大商社出身者(人)
| PE (N=169) |
VC (N=182) |
戦略コンサル (N=138) |
ベンチャー役員 (N=742) |
合計 (N=1231) |
| 16(1) | 12(3) | 7(1) | 32(4) | 67(9) |
※()内は総合商社出身者のうち、各商社に中途入社した人数
【総合商社からのエリート転職者は、決して多くはない】と評価していいでしょう。
以下の表の通り、母集団1231名のなかでリクルート出身者が63名、マッキンゼー出身者が50名ということを鑑みれば、総合商社7社合計で67名というのは大きい数字ではありません。
◆母集団(N=1231)のうち、出身者が多い上位5社(人)
| 1 | リクルート | 63 |
| 2 | McKinsey & Co. | 50 |
| 3 | Accenture | 49 |
| 4 | BCG | 34 |
| 5 | Goldman Sachs | 33 |
実際のところ、総合商社は給与水準も高いうえ、年功序列・終身雇用の日本企業体質が多分に根付いており、極めて離職率の低い層の企業と言えます。したがって、各総合商社の社員は「そもそも転職市場に出て来にくい」層であり、また「転職市場価値が必ずしも高くない」層だ、というのが実態でしょう。
b. 総合商社から転職する3類型(投資/経営/起業)
しかし、それでも転職に踏み切る総合商社社員が一定数いるのも事実です。総合商社を出る方の転職ルートは、主に3つに分類できると考えられます。
◆総合商社を飛び出す転職の3類型
| 「投資」 | 「経営」 | 「起業」 | |
| 志向 | 事業・企業に 投資する側に回りたい |
企業経営の上流に 深く携わりたい |
自ら新規事業を 立ち上げたい |
| 例 | ・投資ファンド ・投資銀行 |
・コンサルファーム ・ベンチャー役員 |
・スタートアップ創業 |
【投資】
総合商社でプレイヤーとして事業に関わるよりも、そこに投資する側に移りたいと考える層です。
商社社内の投資機能では満足できない、あるいはそこへの配属が叶わないケースや、より大きな額の給与を望むケース、その後のキャリアアップの為の助走として利用するケース等が考えられます。
例:投資ファンド(PE、VCなど)、投資銀行(ゴールドマン・サックスなど)
【経営】
若いうちから企業経営の上流部分に携わりたいと考える層です。
コンサルタントとして幅広い業界の企業経営に関与する、実際に社内の役員メンバーとして経営に参画する、といった実現方法に辿り着きます。
特に前者は、その後のキャリア形成のための修行期間として捉える方も多いようです。
例:コンサル(マッキンゼー、BCGなど)、各種ベンチャーの役員ポスト
【起業】
興したい事業の実現のため、独立・起業という手段を選択する層です。
自分の「やりたい事業」のイメージをクリアに持ち、かつそれが総合商社で実現できない、あるいは若いうちに実現したいケースに選択されます(三菱商事の「Soup Stock Tokyo」、伊藤忠商事の「カブドットコム証券」のような、「総合商社に残ったまま社内起業」という選択肢も無いわけではありませんが、運良くこれを主導できるのは未だレアケースと言わざるを得ません)。
例:スタートアップの創業メンバー(CEO、COOなど)
以下では、この3つの類型のうち【投資】、特に投資ファンドへの転職にフォーカスし、各商社間の転職実績比較から「総合商社から投資サイドに転職する際のリアル」を明らかにします。
ファンドへの転職:際立つ三菱商事の強さ

a. 投資ファンドへの転職実績を比較する
unistyleが調査した、国内PE・VCファンドの現職メンバーにおける各商社の内訳です。
◆PE・VCファンドにおける五大商社出身者の内訳(人)
| 三菱商事 | 三井物産 | 伊藤忠商事 | 住友商事 | 丸紅 | 合計 | |
| PE | 11(1) | 2(0) | 1(0) | 0(0) | 2(0) | 16(1) |
| VC | 6(1) | 3(2) | 2(0) | 1(0) | 0(0) | 12(3) |
| 計 | 17(2) | 5(2) | 3(0) | 1(0) | 2(0) | 28(4) |
※()内は出身者のうち各商社に中途入社した人数
三菱商事が圧倒的に多く、大きく水をあけられて三井物産、伊藤忠商事と続く格好となっています。住友商事、丸紅はそれぞれ少なく、投資ファンドへの転職という観点においては商社間で明白な差が見えてきます。
※なお、各社グループ内ファンド(三菱商事:丸の内キャピタル、伊藤忠商事:伊藤忠テクノロジーベンチャーズなど)は調査対象から除外しています。
b. 示唆:「ファンドへの転職」なら、三菱商事を選ぶ
この比較から導かれるのは、【総合商社で働きながら投資側への転職を見据えるなら、三菱商事が最良の選択だ】という示唆です。
2015年度の決算では連結最終損益において設立以来初の最終赤字を計上し、伊藤忠商事に業界首位の座を明け渡した三菱商事。
しかし、上記の「投資ファンドメンバー輩出数」においては、同社の揺るがない「人材力」「ブランド力」が透けて見える結果となりました。
三菱商事の「17名(うち2名は中途採用で三菱商事入社)」という輩出人数は、他業界の企業を含めたなかでも相当多い数値です(以下表を参照)。上位2社へは中途採用で入社するケースが多いため、こと「新卒入社したケース」に限定してみると、三菱商事の「15名」という数値は全業界の中でも最多となります。
将来的な投資ファンド入りを検討しているならば、三菱商事は全企業群のなかでも最良の選択のひとつであると言えるでしょう。
◆投資ファンド(PE+VC)メンバー輩出人数・上位5社(人)
| 1 | McKinsey & Co. | 24(12) |
| 2 | Goldman Sachs | 18(6) |
| 3 | 三菱商事 | 17(2) |
| 3 | 日本興業銀行(現:みずほFG) | 17(3) |
| 5 | BCG | 16(6) |
※()内は出身者のうち、各社に中途入社した人数
ファンドへの転職事例:外コン・外銀の経由も有効

次に、総合商社出身者が実際にどんな転職ルートを辿って投資ファンドに到達しているのか、実例を通じて考察しましょう。
a. 総合商社からファンドへの転職事例を見る
【例1】水谷 謙作 氏(現・インテグラル/元・三菱商事)
慶應義塾大学/理工学部卒
慶應義塾大学大学院/理工学研究科修了
一橋大学大学院/国際企業戦略研究科(金融戦略MBA)修了
1998年 三菱商事入社/機械グループ・プラントプロジェクト本部
2003年 同社/金融事業本部・M&Aユニット
2005年 モルガン・スタンレー証券/投資銀行本部・M&Aアドバイザリー部
2006年 GCA入社/M&Aアドバイザリー/メザニン出向
2007年 インテグラル入社/パートナー(現職)
三菱商事から投資銀行、M&Aアドバイザリーファームへと転職してM&A経験を積み、現在はPEファンド・インテグラル社パートナーとして活躍されています。
当初は三菱商事・機械グループにおいてプラントの海外輸出や事業投資に従事されており、その後に「投資」特に「M&A」という切り口でキャリアを展開されたようです。
【例2】侍留 啓介 氏(現・CLSAサンライズ・キャピタル/元・三菱商事)
早稲田大学/商学部卒
シカゴ大学大学院/MBA
2004年 三菱商事入社/金融事業本部
2012年 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
2015年 CLSAサンライズ・キャピタル入社/ヴァイス・プレジデント(現職)
三菱商事からマッキンゼー・アンド・カンパニーに転職し、その後にポスト・コンサルとしてPEファンドのキャリアを選択された例です。また、シカゴ大にてMBAを取得されていることも、その後のキャリア形成に重要な影響を与えていると推測できます。
【例3】久保田 雅也 氏(現・WiL社パートナー/元・伊藤忠商事)
慶應義塾大学/経済学部卒
1997年 伊藤忠商事入社
1998年 リーマン・ブラザーズ証券/投資銀行本部
2008年 バークレイズ証券/投資銀行本部
2011年 SMBC日興証券/投資銀行本部
2014年 WiL共同創業/パートナー(現職)
参考:WiL Team
伊藤忠商事を僅か1年で退職し、16年間一貫して投資銀行のフィールドを歩んだのち、VCファンド・WiLの立ち上げに踏み切られた方です。なお、同社WiLの共同創業者のお一人である西条晋一氏(元サイバーエージェント、現コイニー取締役など)も伊藤忠商事のご出身です。
b. 示唆:「ファンドへの転職」なら、外コン・外銀の経由も有効だ
総合商社からファンドへの転職を考えるとき、上に例として挙げさせていただいた方々のように【総合商社から外資系投資銀行や戦略コンサルを経由し、そののちにファンドに転身する】というルートを辿る方が相当数いるようです(以下、表参照)。
◆総合商社に新卒入社後、投資ファンドに辿り着くまでに経由した企業(人)
| 投資銀行 | 戦略コンサル | ファンドへ直接 | その他 | |
| PE:14名 | 3 | 5 | 6 | 0 |
| VC:9名 | 1 | 0 | 3 | 5 |
とりわけPEファンドにおいては半数以上が外資投資銀行・コンサルを経由しているため、【将来的にはファンドで投資業務に従事したいが、そのための助走期間として投資銀行・コンサルに転職する】という転職アプローチも有効である、という仮説が立ちます。
最後に

いかがでしたでしょうか。本記事では、
◎総合商社からの転職3類型(投資/経営/起業)
総合商社からの転職者は大きく分けて3パターン、
①投資、②経営、③起業の3つがあります。
◎「ファンドへの転職」なら、三菱商事を選ぶ
なかでも「投資」の転職としてPE・VCファンドを目指すケースでは、総合商社のなかでは三菱商事が圧倒的な実績を挙げていると言えます。
◎「ファンドへの転職」なら、外コン・外銀の経由も有効だ
そして、投資ファンドを目指す上では、まず総合商社から外資系投資銀行、戦略コンサルに転職し、そこを経由するかたちでファンドに移るというアプローチも有効なようです。
以上の3点がポイントになるとまとめることができます。
「本当に自分が入社すべきは総合商社なのか」「総合商社のなかでもどこを選ぶのか」という問いを考えるとき、上記のような転職市場における実態というポイントも重要な切り口の1つになるでしょう。皆さんのキャリアを考えるうえで、本記事を参考にしていただければ幸いです。







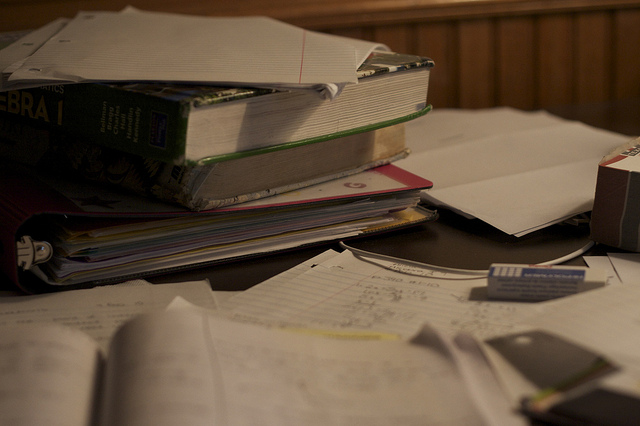
.png?1718763849)

