グループディスカッション(GD)の対策とは?通過率を上げるコツを紹介
45,716 views
最終更新日:2024年10月25日

1.【まず始めにこれを読もう!】GDとは?基礎知識を解説
2.GDの対策方法・コツ
3.GD頻出テーマと業界別の過去に出題されたテーマ
4.GDのテーマごとの進め方
5.GDの役割別(司会・書記・タイムキーパー)の対策方法
6.一人でも複数人でも出来るGD練習方法(11選)
本記事ではグループディスカッション(GD)の具体的な対策(選考前に行っておくべき対策・選考中に意識すべき対策方法)について紹介します。
本記事で紹介しているステップ順に対策を行えば、対策に関しては完璧な状態でグループディスカッション(GD)に臨めるようになるでしょう。
グループディスカッション(GD)が苦手だと感じている就活生や、初めてグループディスカッション(GD)の選考に参加するという就活生はぜひ参考にしてみてください。
-
- 本記事の構成
- グループディスカッション(GD)選考前の対策方法
グループディスカッション(GD)対策①評価基準を理解しておく
グループディスカッション(GD)対策②頻出のお題を押さえておく
グループディスカッション(GD)対策③テーマごとの進め方を理解する
グループディスカッション(GD)対策④事前準備として業界研究・企業研究を行う
グループディスカッション(GD)対策⑤本を読む
グループディスカッション(GD)対策⑥イベントに参加する - グループディスカッション(GD)選考中の対策方法
グループディスカッション(GD)対策⑦グループの人と始める前に話しておく
グループディスカッション(GD)対策⑧発言回数が少ない人に発言機会を与える
グループディスカッション(GD)対策⑨自分一人が長く話しすぎないように注意する - 最後に
グループディスカッション(GD)選考前の対策方法
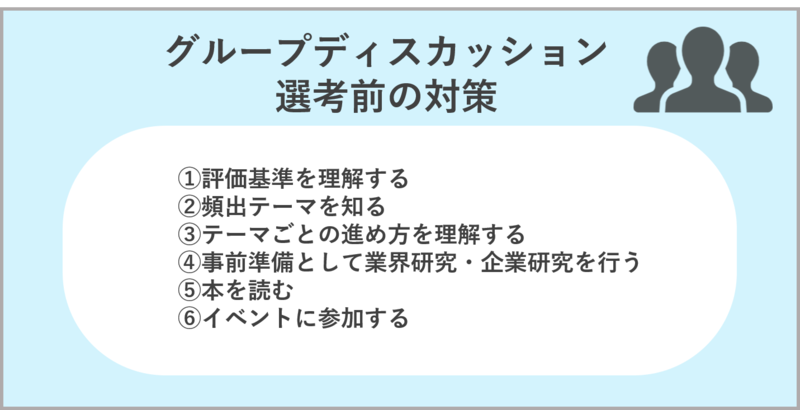
グループディスカッション(GD)の選考は事前の対策が重要となります。志望している企業のグループディスカッション(GD)の選考で落ちることがないようしっかりと対策をするようにしましょう。
本記事では、グループディスカッション(GD)の選考前対策を以下の6つのステップに分解し、それぞれ解説していきます。
1.評価基準を理解する
2.頻出のテーマを知る
3.テーマごとの進め方を理解する
4.事前準備として業界研究・企業研究を行う
5.本を読む
6.イベントに参加する
各ステップごとに「対策の詳細・対策を行うことで得れる知識やスキル・関連記事」を掲載していますので、それぞれ確認していただければと思います。
グループディスカッション(GD)対策①評価基準を理解する
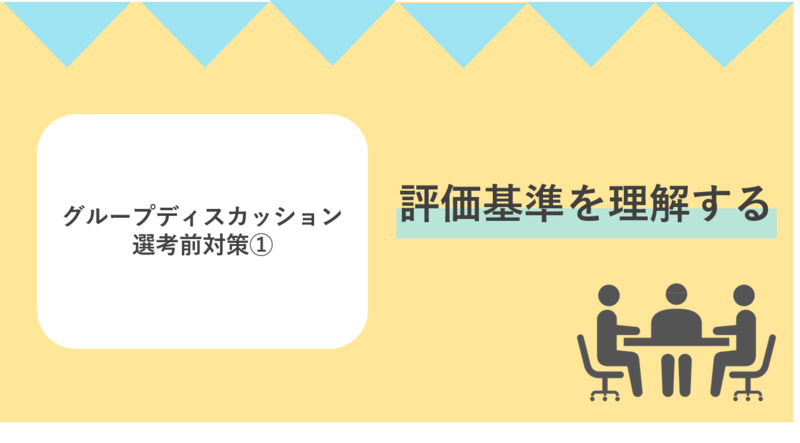
このコンテンツは会員(無料)の方のみご覧になれます。
また、会員(無料)の方は81698枚のエントリーシートを全て閲覧可能になります。
(無料会員登録はこちら)
グループディスカッション(GD)対策②頻出のテーマを知る
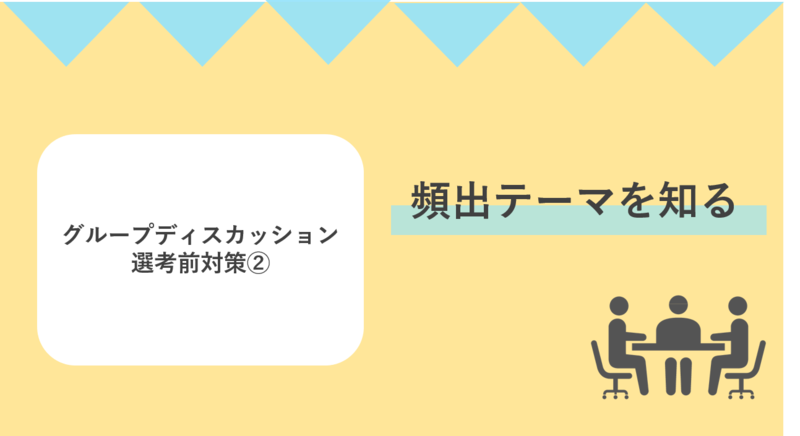
グループディスカッション(GD)で出題されるテーマは企業や業界によって異なり、同様に出題されるテーマによって議論の進め方も変わってきます。
そのためグループディスカッション(GD)本番で「どう進めればいいの?」とならないよう、事前に各テーマごとの進め方を知っておくことが重要となります。
以下の記事で過去に実際に出題されたテーマを89例紹介しています。また、業界ごとの頻出テーマも記載しているので自分の志望している業界ではどのようなテーマが出題されているのかチェックしてみてください。
このコンテンツは会員(無料)の方のみご覧になれます。
また、会員(無料)の方は81698枚のエントリーシートを全て閲覧可能になります。
(無料会員登録はこちら)
グループディスカッション(GD)対策③テーマごとの進め方を理解する
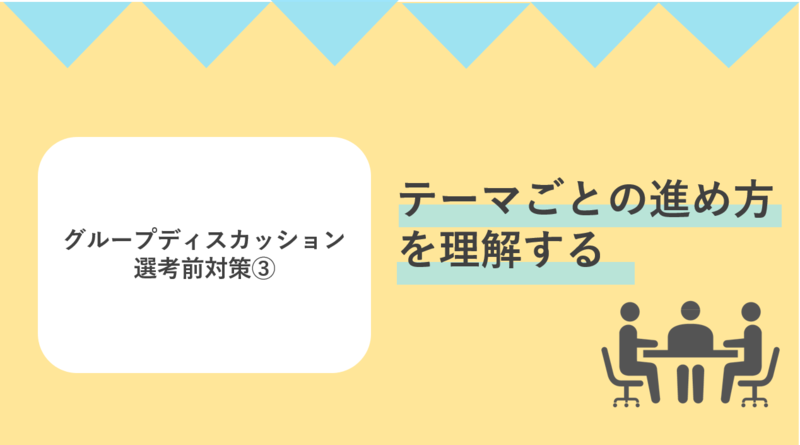
グループディスカッション(GD)はテーマによって基本的な進め方が異なります。
例えば「理系女子を増やすには?」というテーマが出題されたのであれば、以下のような手順で進めるのが基本となるでしょう。
このコンテンツは会員(無料)の方のみご覧になれます。
また、会員(無料)の方は81698枚のエントリーシートを全て閲覧可能になります。
(無料会員登録はこちら)
グループディスカッション(GD)対策④事前準備として業界研究・企業研究を行う
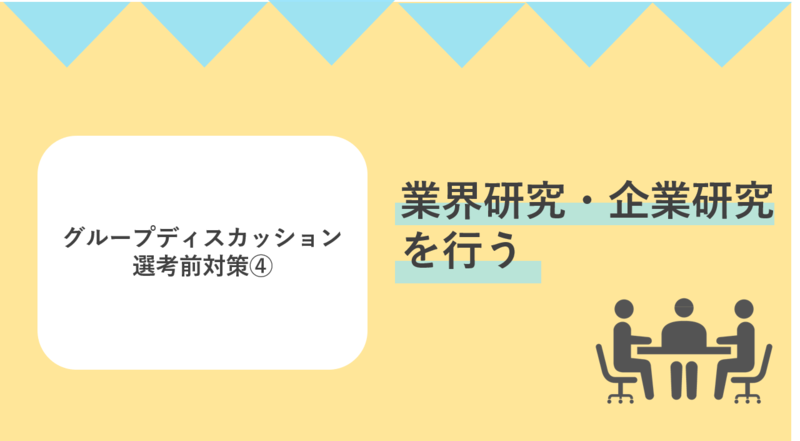
グループディスカッション(GD)のテーマは業界によって一定の傾向があると言えるため、業界研究や企業研究をしておくと間接的にグループディスカッション(GD)の対策にもなります。
具体的には、日系大手企業で出題されるグループディスカッション(GD)のテーマは自社の強みを活かした新規事業の立案求められることが多くなっています。
例えば三井物産では下記のようなテーマが過去に出題されました。
このコンテンツは会員(無料)の方のみご覧になれます。
また、会員(無料)の方は81698枚のエントリーシートを全て閲覧可能になります。
(無料会員登録はこちら)
グループディスカッション(GD)対策⑤本を読む
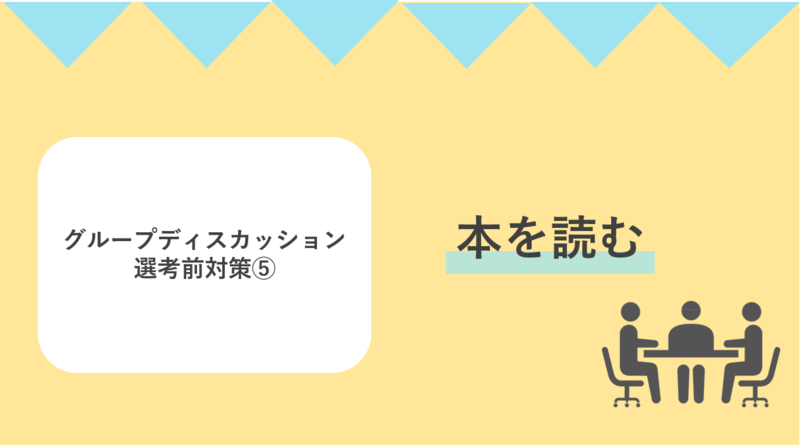
本を読むことで1人でグループディスカッション(GD)の対策をすることができます。
そこで、以下では「グループディスカッション(GD)の基本を身につけたい人」に読んでほしい本を紹介します。
本記事ではグループディスカッション(GD)対策に役立つ本を3つ取り上げ、「どんな就活生にオススメの本なのか・本を読むことでどんな知識を身につけることができるのか」という観点から紹介していきます。
グループディスカッション(GD)の基本が身につく本
このコンテンツは会員(無料)の方のみご覧になれます。
また、会員(無料)の方は81698枚のエントリーシートを全て閲覧可能になります。
(無料会員登録はこちら)
また、外資系企業やコンサルティングファームではケース面接のようなテーマを課される場合がありますので、そちらに関しても少し触れておきます。
ケース面接対策の本
このコンテンツは会員(無料)の方のみご覧になれます。
また、会員(無料)の方は81698枚のエントリーシートを全て閲覧可能になります。
(無料会員登録はこちら)
グループディスカッション(GD)対策⑥イベントに参加する
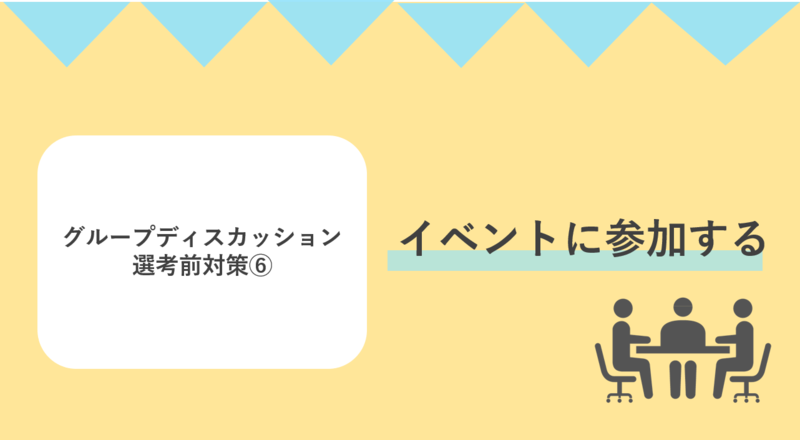
このコンテンツは会員(無料)の方のみご覧になれます。
また、会員(無料)の方は81698枚のエントリーシートを全て閲覧可能になります。
(無料会員登録はこちら)
https://unistyleinc.com/topics/26055
https://unistyleinc.com/topics/26715
グループディスカッション(GD)選考中の対策方法
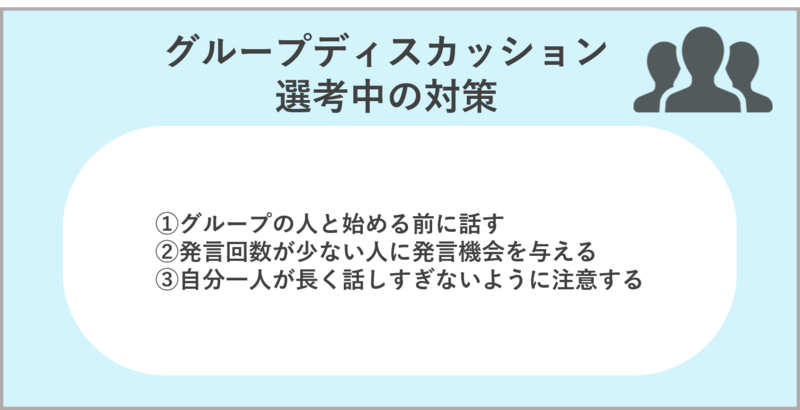
グループディスカッション(GD)では選考前の対策だけではなく、選考中の対策も行う必要があります。
グループディスカッション(GD)の選考中では、『グループディスカッション(GD)の進め方とは?6つのコツとテーマごとの進め方をわかりやすく解説』で紹介している進め方を意識して議論を進めるのはもちろんのこと、以下の3つのコツを意識すべきだと言われています。
1.グループの人と始まる前に話す
2.発言回数が少ない人に発言機会を与える
3.自分一人が長く話しすぎないように注意する
とは言え、上記の紹介だけでは「具体的にどうすればいいの?」という疑問が浮かんでしまう方も多いかと思いますので、下記でそれぞれの具体例についても紹介していきます。
グループディスカッション(GD)対策⑦グループの人と始まる前に話す
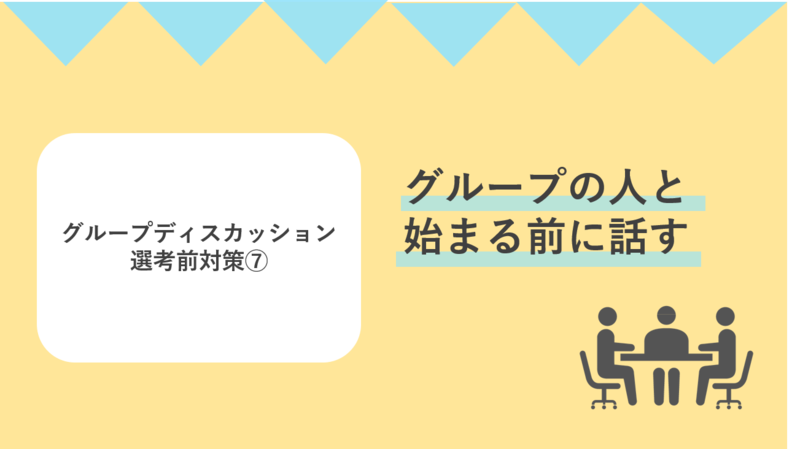
このコンテンツは会員(無料)の方のみご覧になれます。
また、会員(無料)の方は81698枚のエントリーシートを全て閲覧可能になります。
(無料会員登録はこちら)
グループディスカッション(GD)対策⑧発言回数が少ない人に発言機会を与える
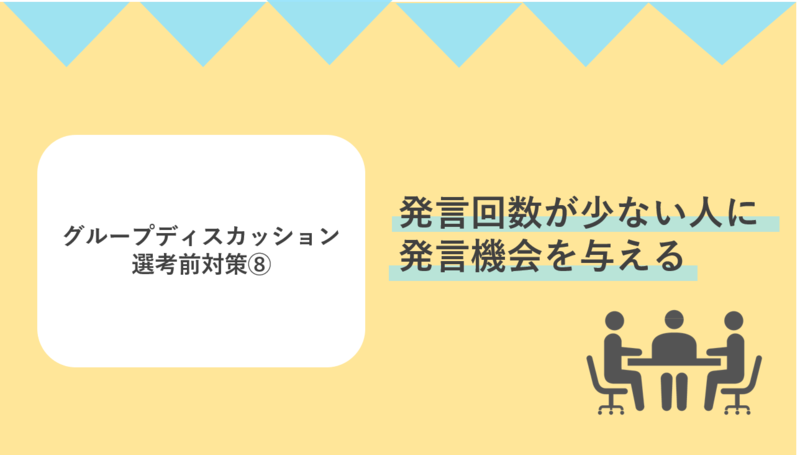
このコンテンツは会員(無料)の方のみご覧になれます。
また、会員(無料)の方は81698枚のエントリーシートを全て閲覧可能になります。
(無料会員登録はこちら)
グループディスカッション(GD)対策⑨自分一人が長く話しすぎないように注意する
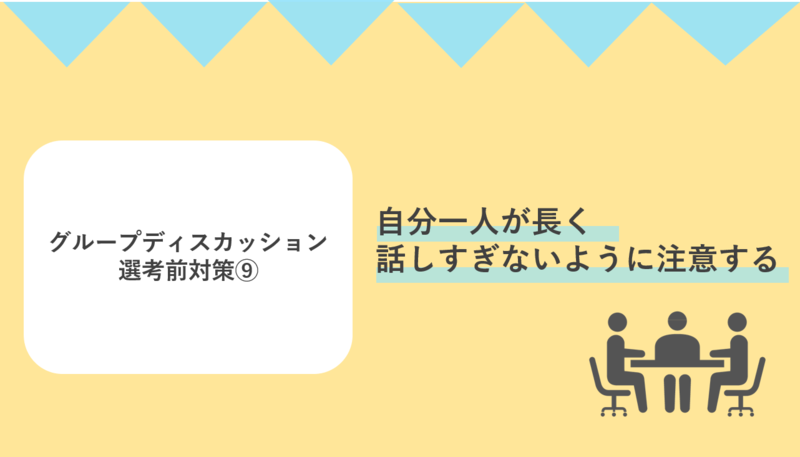
このコンテンツは会員(無料)の方のみご覧になれます。
また、会員(無料)の方は81698枚のエントリーシートを全て閲覧可能になります。
(無料会員登録はこちら)
最後に
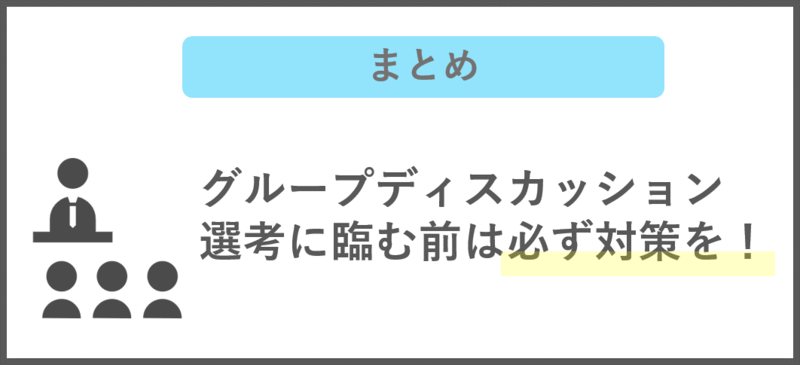 本記事ではグループディスカッション(GD)の選考前と選考中の対策・コツについて紹介しました。グループディスカッション(GD)選考に通過するためにはしっかりと対策をすることが大切です。
本記事ではグループディスカッション(GD)の選考前と選考中の対策・コツについて紹介しました。グループディスカッション(GD)選考に通過するためにはしっかりと対策をすることが大切です。
グループディスカッション(GD)の対策・コツについて理解できたら、次はグループディスカッション(GD)のテーマについて理解しましょう。
以下の記事からグループディスカッション(GD)のテーマについて学ぶことができます。
1.【まず始めにこれを読もう!】GDとは?基礎知識を解説
2.GDの対策方法・コツ
3.GD頻出テーマと業界別の過去に出題されたテーマ
4.GDのテーマごとの進め方
5.GDの役割別(司会・書記・タイムキーパー)の対策方法
6.一人でも複数人でも出来るGD練習方法(11選)


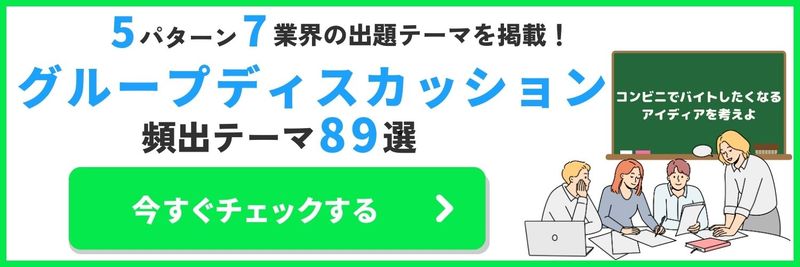





.png?1687158341)

