【第2章:某日系大手人事が語る】「クラスの人気者を採用したい」
17,828 views
最終更新日:2023年11月06日

※本記事は、全3回のシリーズの2本目になります。
もしまだ第1章から見ていない方がいれば、[【第1章:某日系大手人事が語る】「インターンに参加するやつは出世する」からご購読ください。
全3回に渡ってお届けしている「某日系大手人事が語る」シリーズ。
第1章では「インターン」をテーマに、お弁当の決め方・インターン組の出世ルートといった人事の立場でしか知り得ない情報について触れていきました。
第2章のテーマは「企業が欲しい人材」。
就職四季報や採用HPにも記載されているところが多い内容ですが、実際のところ人事の目線からはどのような基準を設けているのでしょうか。
今回も引き続き、某日系大手企業で人事の経験がある谷元さん(仮名)にお話しを伺い 、採用活動の裏側について深堀っていきます。
結局のところ...どういう人を採用したいんですか?
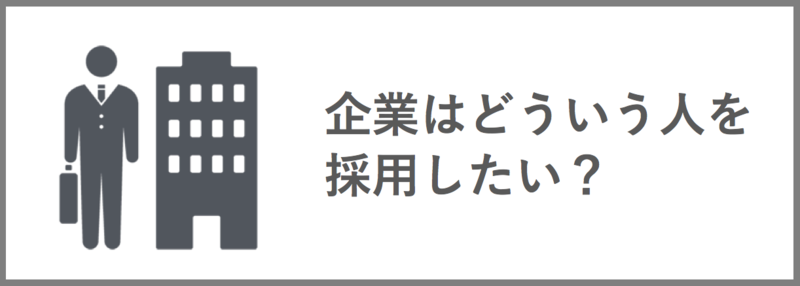 就職活動で選考を突破するのに最終的に必要なのは、採用基準を満たすことです。
就職活動で選考を突破するのに最終的に必要なのは、採用基準を満たすことです。
ひとたびスクリーニング基準を満たしたなら、あとは実力勝負。
学歴や資格についてあれこれ憂慮するよりも、採用基準を満たすための取り組みに注力しましょう。
採用基準はいわゆる「求める人物像」に近似しています。
では、人事の目線ではどのように求める人物像を設定しているのでしょうか。
採用HPに記載されている「求める人物像」に意味はあるか
unistyleでは繰り返しお伝えしている話にはなりますが、企業は自社の利益に貢献できる人材を採用したいと思っています。
経営資源の一つとしてヒトに投資している以上、それだけ多くのリターンを求めるのは自然な考え方でしょう。
企業の求める人材は、多くの場合採用HPに記載されています。もちろん、「弊社の利益に貢献できる人材を採用します!」と直接書くわけではありませんので、各企業独自性を盛り込みながら提示する形になっています。
有名企業の求める人材
以下では、有名企業の求める人材を「就職四季報(2021年版)」から抜粋しました。
【トヨタ自動車】
周囲を巻き込み最後まで徹底的にやり抜く人
【電通】
【三菱商事】
では、採用HPや就職四季報に記載されているこういった内容というのは、どれだけ妥当性があるものなのでしょうか。
この点について谷元さんによると、
「正直どこで『求める人材』とやらが決まっているかはわからないけど、四季報とか採用HPに書いてあることはまあ納得感あるよ。面接のときとかも、大枠の求める人材像から導かれた『こういう基準で見てくださいリスト』みたいなものがあって、一応それに沿って評価する企業はけっこうあるって聞くしね。だから、それの情報を把握はしておいた方がいいと思う。」
という話でした。
unistyleでは直接的に採用HPや四季報に書いてあることに寄せるというよりは、ESの設問や面接の内容から考察することを推奨していますので、関連する記事も一読していただければと思います。
一人事として、「ウチに来て欲しい!」と思う就活生とは?
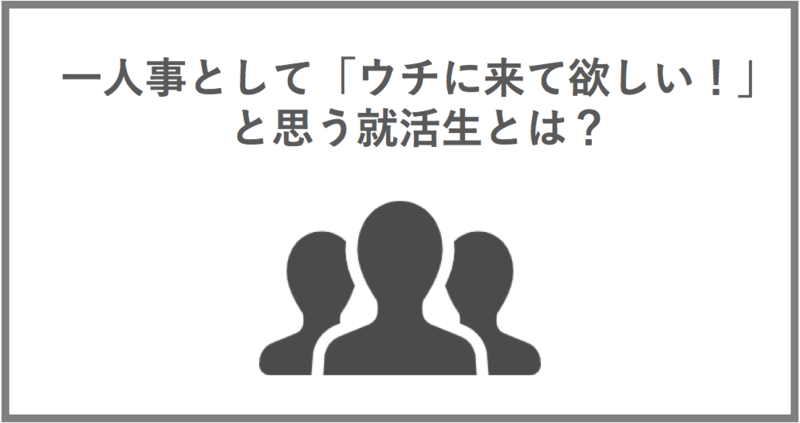 ここまで見てきた求める人材というのは、会社として決めた人事の間で共有されている規定なようなものです。
ここまで見てきた求める人材というのは、会社として決めた人事の間で共有されている規定なようなものです。
とは言え、実際の選考では全ての人事や現場社員が見るわけではなく、あくまで数名程度の個人が直接的な評価をしていくことになります。
そうなると気になるところが、選考官が個人としてどういう学生を評価したいかという点でしょう。
「誰を通すか」は複数人の話し合いによって決めることが多いでしょうが、結局は実際に面接した人の所感や報告内容によるところが多いと推察されます。
「楽しかった」と人事に思わせられる就活生は強い
「うーん何というか、直感的に『この子と話して楽しかったな』と思うような就活生は通しちゃうよね(笑)。特に選考序盤のリクルーター面談や現場社員との面接はこの傾向が顕著だと思うよ。」
面接とはアンケートのような一問一答の回答の場ではなく、就活生と面接官のコミュニケーションの場だという話は有名ですが、実際にそれが出来ている人はそれほど多くありません。
特に序盤の面接では「一緒に働きたいか」という観点で若手社員が見ていることが多いと言われています。
単純にコミュニケーションを取った時間が楽しいものと感じられたのであれば、多少の回答内容の粗さ等に関係なく通そうと思うようになるのではないでしょうか。
どうやら現場と人事が見ている視点は異なっているようで、現場の人は「こいつが自分の部下なら面倒を見たい」と思う学生を、人事は「将来的に経営層として能力を発揮できるのか」という学生を評価しているようです。
目指すべきは、クラスの人気者?
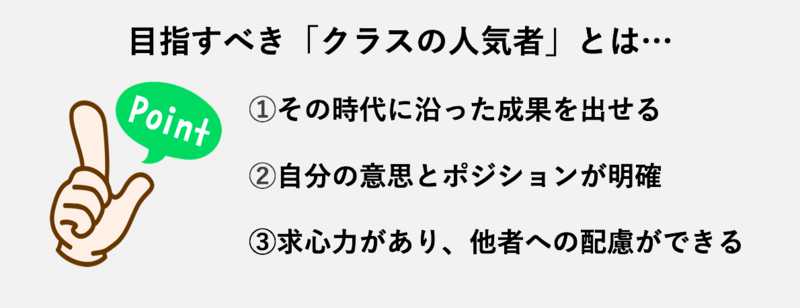 先ほど「一緒に働きたいか」という観点について指摘しましたが、現場実践型インターンでもしない限り、実際に自社で働いている姿を入社前に見ることは出来ません。
先ほど「一緒に働きたいか」という観点について指摘しましたが、現場実践型インターンでもしない限り、実際に自社で働いている姿を入社前に見ることは出来ません。
そうなってくると、面接の場で「楽しかった」「一緒に働きたい」と思わせるには、ある種トーク力や話のうまさなようなものが重要になってくるようにも思えます。
しかし、谷元さんは以下のように述べています。
「前提として、トーク力=生まれもったセンスみたいなものって考えている人は多いけど、僕は違うと思う。話が上手い人・面白い人というのは、その人のキャラとか以上に結局自分の頭ですごく考えていいアウトプットが出来るように努力しているよ。イメージすると、小学校のクラスの人気者みたいな感じかな。」
「クラスの人気者」という言葉が唐突に出てきました。
これを最初に聞いた時点では、なぜクラスの人気者のような人を人事が採用したいと考えるのかあまりイメージ出来ていませんでした。
しかし話を進めるうちに、「人気者を採用したい」というのは以下のような意味があるのではと考えました。
「クラスの人気者」の意味(1)その時代に沿った成果を出せる
小学生→足が速い奴がモテる
中学生→悪そうな奴がモテる
高校生→イケメンがモテる
大学生→面白い奴がモテる
社会人→金を持ってる奴がモテる
Translate Tweet
2:10 PM · Feb 10, 2013 February 10, 2013
モテる=人気者とは必ずしも言えませんが、このツイートにあるように、世代によって周囲からの評価を集める要素というのは変わってきます。
極端な話、30代にもなって「自分は足が速い」と主張しオフィスをダッシュされても困るでしょう。
人気者の要素として多く共通しているのが、「時代に沿った形で何らかの成果を出せる」という点です。
もちろん「イケメンかどうか」のような成果とは呼べないものもありますが、足が速い・勉強が出来る・リーダーとしてクラスを引っ張れる・年収が高いといったようなものは成果に該当します。
就職活動でもこれと近しいことが言え、学生時代に何らかの成果を出したことはそれ自体が評価の対象になり得ます。
谷元さんの話では、
僕ら人事も毎年たくさんの学生さんを見ているからさ、「〇〇くん/さんって△△の人だよね」みたいに一対一でわかりやすい紐づけが出来る人は印象に残りやすかったな。
「成果」というのは何もインカレやビジネスコンテスト等で優勝といった輝かしいものだけでなく、自分次第で人事に効果的に伝えることが可能です。
例えば上記のゴリゴリ体育会系学生の場合、「お菓子作りが趣味です!」と述べるよりも「お菓子作りが好きでスイーツコンシェルジュ検定ベーシックまで取得してしまいました!」と述べた方が格段にインパクトが強まると思います。
例えばこの記事にあるように、「面白資格を取得する」というそれほど労力がかからない成果と「見た目がゴリゴリの体育会系」という要素を掛け合わせることで谷元さんの言う「わかりやすい紐づけ」に近づくと言えるでしょう。
更にトレーニングでベンチプレスを上げているとしたら、「ベンチプレスで〇〇kgを上げるスイーツコンシェルジュ検定の子ね」のように印象付けを強化することが出来ます。
ここで重要なのは、「見せ方」です。
「クラスの人気者」の意味(2)自分の意思とポジションが明確
皆さんのこれまでの学生生活において、クラスの人気者・中心人物とはどのような特徴があったでしょうか。
もちろん、先述した足が速いを始めとした成果というのも一要素になります。
それとは別に、その人の普段の周囲への態度やスタンスのような面ではどうでしょうか。
人気者は多くの場合、いわゆる「キャラ」がはっきりしていることが多かったと思います。いじられキャラ・天然キャラ等種類は様々ですが、何らかのポジションを取ることが出来る人は自然と組織の中心にいることが多くなります。
これについても就職活動において応用させることが可能です。
例えば、グループディスカッションの評価要素の一つとして「主張力」があります。
進行の中で自分のポジションを明確にすることは、議論の中心に立つために必要な要素になります。(もちろん論理性の担保が議論を崩壊させないための前提です。)
他にも面接においても、場面にもよりますが「自分はこうだ」という意思をはっきりと伝えることは重要です。
「自分がどの部署に携わりたいかはまだ入社していないのでわかりません」
「自分の強みは〇〇な気がしますが、私が勝手にそう思っているだけかもしれないので違うかもしれません」
これらの言っていることは厳密には間違っているわけではありません。 確かに入社してから自分がやりたい仕事が変わることは大いにありますし、自分が強みと思っていることが100%そうと言えるかはわからないでしょう。
しかし、他の就活生よりも評価され内定を得るためには、「自分はこれがやりたいんだ」「自分はこれが出来るから御社に貢献できるんだ」と確証が無くともポジションについてははっきりさせるべきです。
多くの場合これまでビジネスでの実績が無い学生を採用する活動なわけですから、多少粗さがあっても曖昧過ぎる表現は避けるべきでしょう。
歯切れの悪い回答は自身の無さや嘘っぽく聞こえてしまうこともあり、人事は常に学生が本音で話しているかを気にしています。
自分の思いははっきりと伝えましょう。
「クラスの人気者」の意味(3)求心力があり、他者への配慮が出来る
先ほど「人気者はポジションが明確」と言う指摘をしましたが、当然自分の言いたいことを好き放題主張していれば何でもいいというわけではありません。
「自分はこうだ」とポジションを取りつつも、人気者には他人が気分よくなるような話し方や気配りが出来る人が多い印象があります。
谷元さんの「楽しかった面接は通したいと思ってしまう」という話もこれと関連しています。自分が評価が高そうな回答を打ち返そうとすることだけに必死になるよりも、面接官が気持ちよく話せそうな気配りも同時に出来る就活生は多くないと感じます。
よく、「小学校のときのクラスの立ち位置が自分が最も自然にいられるポジションだ」という話がありますが、あながち間違いではないと思っています。特に小学校は学力等のスクリーニングが無く、クラスとは学区という区切りで機械的に集められた異質な個人の集合体です。
そんな中であらゆるポジションの級友から支持を集められる求心力は、他者への気配り力と関連性があると考えられます。谷元さんが "小学校の" クラスの人気者をわざわざ言っていたのもこのような考えに基づくのかもしれません。
面接の場がただの自分語りになっていないか、もう一度見直しましょう。
※注意※「勘違い系人気者」になっていませんか?
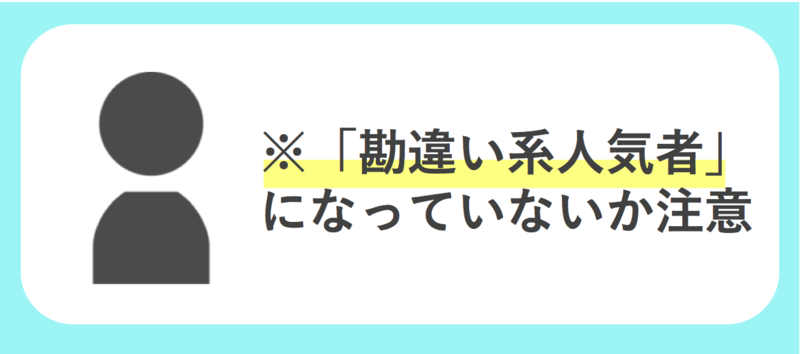 ここまで散々「人気者は就活で強い」かのような話をしたため、皆さんの中にはもしかすると「自分はサークルで人気者だから就活強者だ!」のように考えた方もいらっしゃるかもしれません。
ここまで散々「人気者は就活で強い」かのような話をしたため、皆さんの中にはもしかすると「自分はサークルで人気者だから就活強者だ!」のように考えた方もいらっしゃるかもしれません。
ここで間違って欲しくないのは、大学生活における「人気者」とはある意味必然的にそうなりやすいものだということです。
そんな居心地の良い環境にどっぷりと浸かり何となくちやほやされていた大学生が、いざ職に就くための活動(≒内定を獲得するための活動)、言ってしまえば内定という限られた椅子を奪い合う競争である就職活動になると全く優位性を確保できず苦戦を強いられるという話はしばしば耳にします。
「自分は他人より優秀だ」という平均以上意識からの脱却が内定獲得への第一歩の記事に書いてあるように、大学生活は基本的に自分が所属するコミュニティーを自分で選ぶことが出来ます。
自分が人気者になりやすい環境を選び、そこで内輪ネタでわいわいやって人気が高"そう"な人が就職活動で評価されるかと言えばそうとも言い切れないでしょう。
もちろん、自分が高い評価を得られそうな環境に身を置くこと自体は全く悪いことではありません。むしろ、得意を仕事にし結果を出していくことは自分のためにもなります。
何をもって人気者とするかの明確な定義は無く、評価のされ方は年代や環境によって大きく異なります。くれぐれも「勘違い系人気者」として慢心することのないようにしていただければと思います。
最後に
 もちろん環境が変われば人も変わっていくわけなので、学生時代に人気者でなくても就職活動や社会人になってから大きく飛躍するということは往々にしてあります。
もちろん環境が変われば人も変わっていくわけなので、学生時代に人気者でなくても就職活動や社会人になってから大きく飛躍するということは往々にしてあります。
皆さんも「人事を楽しませる人気者」というイメージを頭の片隅にでも置いておくと、面接の場でうまくいくことが増えるかもしれません。
次回第3章は最終回として、トレンドワードである「働き方改革」と人事の目線を掛け合わせます。
全章通して読むことでより一段と学びが深まりますので、是非合わせてご覧ください。






.png?1554213735)



