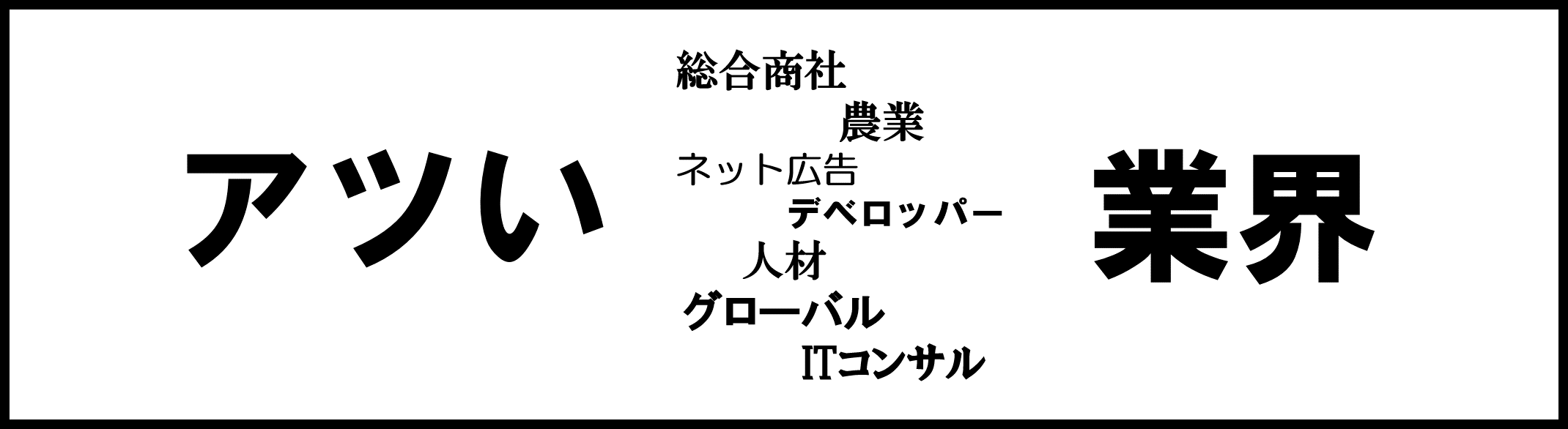【20卒上智理工学部】デニナギくんの就活体験記vol.5|2018.11 interview
6,096 views
最終更新日:2022年03月29日

毎月行っているデニナギくんへのインタービューも今回で5回目になります。
前回はNHKの技術職のインターン選考を見事通過し、参加が確定していました。参加してみた感想や他の活動に関しても探っていきたいと思います。
上智大学 デニナギくんの履歴書
デニナギくんの履歴書
└男性
◆大学
└上智大学理工学部に現役入学。
◆趣味
└サッカー(小学4年から現在まで)。ポジションはボランチ。プレーするだけでなく観戦するのも好き。
◆サークル
└サッカーサークル。週3回の活動や大会合宿にも積極的に参加している。
◆アルバイト
└飲食チェーン店で大学1年生から働いている。主にホールを担当、たまに調理も行う。2018年2月からベンチャー企業のインターンをしている。
◆留学
└なし。海外経験もないが、海外で働くことに対して漠然とした憧れはある。
◆資格
└特になし。TOEICも受けたことがないが、今後受けようと考えている。
◆就活をはじめた時期
└2018年6月頃
◆志望業界
└現段階では定まっていない状況。何に興味があるかも分からないため、インターンを通して探そうと考えている。
◆希望職種
└こちらも明確に定まっていない。ただ、自身の適性を鑑みて、営業は向いていないと感じている。
本インタビューはunistyle編集部のむたか(@mutaka_unistyle)とくらもん(@esquestion)にて行っております。
11月の活動を振り返って
インターンへの参加
 「前回のインタビュー以降はインターンの参加や選考などはあった?」
「前回のインタビュー以降はインターンの参加や選考などはあった?」
 「前回の選考でも話したNHKのインターンへの参加をしました。また他では野村総合研究所の選考でテストセンターを受けたり、TOEICを受けたりしていました。」
「前回の選考でも話したNHKのインターンへの参加をしました。また他では野村総合研究所の選考でテストセンターを受けたり、TOEICを受けたりしていました。」
 「NHKのインターンはどんな感じだった?」
「NHKのインターンはどんな感じだった?」
 「一言で言うと楽しかったです。今まで行ったインターンと比較すると実習が多くあったため、学びになりました。具体的な活動としては、中継撮影の実習、音楽番組作成の実習、データ放送で使うデジタルコンテンツ作成の実習などを行いました。」
「一言で言うと楽しかったです。今まで行ったインターンと比較すると実習が多くあったため、学びになりました。具体的な活動としては、中継撮影の実習、音楽番組作成の実習、データ放送で使うデジタルコンテンツ作成の実習などを行いました。」
 「インターンの内容に関しては満足できたみたいだね。本選考は受けようと思う?」
「インターンの内容に関しては満足できたみたいだね。本選考は受けようと思う?」
 「受けようと思っています。インターンからの選考ルートではありませんが、早期選考があるそうなのでそこから挑戦したいと思います。」
「受けようと思っています。インターンからの選考ルートではありませんが、早期選考があるそうなのでそこから挑戦したいと思います。」
インターン参加以外の活動
 「野村総研の選考でテストセンターを受けたみたいだけど、出来はどうだった?」
「野村総研の選考でテストセンターを受けたみたいだけど、出来はどうだった?」
 「手応えはまずまずという感じですかね。対策をしていなかったのであまりできないと思っていたのですが意外とスラスラ解けました。問題としては漢字が一番難しかったなと思いました。」
「手応えはまずまずという感じですかね。対策をしていなかったのであまりできないと思っていたのですが意外とスラスラ解けました。問題としては漢字が一番難しかったなと思いました。」
 「TOEICを受けたみたいだけど、受けようと思った理由は?また出来なども教えてください。」
「TOEICを受けたみたいだけど、受けようと思った理由は?また出来なども教えてください。」
 「TOEICのスコアはないよりあったほうがいいと思ったので受けました。出来としては、文法は割と解けましたがリスニングがあまりできませんでした。1月にもまたテストがあるので、対策をして挑みたいと思います。」
「TOEICのスコアはないよりあったほうがいいと思ったので受けました。出来としては、文法は割と解けましたがリスニングがあまりできませんでした。1月にもまたテストがあるので、対策をして挑みたいと思います。」
・インターンで志望度の上がったNHK技術職の選考を今後受ける予定
・テストセンター、TOEICを初めて受けた
12月にやろうと思っていること
 「これからやろうと決めていることは何かある?」
「これからやろうと決めていることは何かある?」
 「そこまで具体的には決めていませんが、とりあえずは引き続きインターンに応募しようと思っています。」
「そこまで具体的には決めていませんが、とりあえずは引き続きインターンに応募しようと思っています。」
 「応募しようと思っている企業などはある?」
「応募しようと思っている企業などはある?」
 「金融業界で、東京海上日動と三井住友銀行の2社には応募する予定です。」
「金融業界で、東京海上日動と三井住友銀行の2社には応募する予定です。」
 「銀行は前にもインターンを受けて興味がありそうだったもんね。では、インターン以外で何かやろうとしていることはある?」
「銀行は前にもインターンを受けて興味がありそうだったもんね。では、インターン以外で何かやろうとしていることはある?」
 「TOEICの勉強もしようと思っています。前回の結果では企業に提出するにはまだまだだと思うので、ある程度良い成績が出せるように勉強しておきたいです。」
「TOEICの勉強もしようと思っています。前回の結果では企業に提出するにはまだまだだと思うので、ある程度良い成績が出せるように勉強しておきたいです。」
・東京海上日動と三井住友銀行のインターンに応募する予定
・スコアアップのためにTOEICの勉強もする予定
今就活で悩んでいること
 「最近就活で悩んでいることはある?」
「最近就活で悩んでいることはある?」
 「志望業界がうまく絞れないことに悩んでいます。以前からもあまり絞っていませんでしたが、そろそろ本格的に絞っていかなければいけないのかなと思い少し焦っています。」
「志望業界がうまく絞れないことに悩んでいます。以前からもあまり絞っていませんでしたが、そろそろ本格的に絞っていかなければいけないのかなと思い少し焦っています。」
 「業界を絞れない理由などはある?」
「業界を絞れない理由などはある?」
 「理由としては、多くの知識をつけた分だけ自分の市場価値が上がると考えているのと、自分が知らない知識を知ることが好きだからです。」
「理由としては、多くの知識をつけた分だけ自分の市場価値が上がると考えているのと、自分が知らない知識を知ることが好きだからです。」
 「なるほど、では今のところ受けようと思っている業界や受けない業界などはある?」
「なるほど、では今のところ受けようと思っている業界や受けない業界などはある?」
 「業界で絞っているわけではありませんが、インターンに参加して印象の良かったNTTデータとNHKは受けたいと思っています。また受けない業界としては人材業界と外資系は受けたくないなと思っています。理由としては、人材業界はそこに就職した先輩がすごく忙しそうだったため、外資に関しては行けないだろうと思っているためです。」
「業界で絞っているわけではありませんが、インターンに参加して印象の良かったNTTデータとNHKは受けたいと思っています。また受けない業界としては人材業界と外資系は受けたくないなと思っています。理由としては、人材業界はそこに就職した先輩がすごく忙しそうだったため、外資に関しては行けないだろうと思っているためです。」
 「受けようと思っている2社に関しては、どのような点から受けようと思っている?」
「受けようと思っている2社に関しては、どのような点から受けようと思っている?」
 「社員さんが仕事をしていて楽しそうだった点と、色々なことができそうで面白そうと思った点です。ただ懸念点もあって、インターンの時は面白そうと思っても、正社員になった時に同じような仕事の楽しさがあるかどうかが不明確だなと思っています。」
「社員さんが仕事をしていて楽しそうだった点と、色々なことができそうで面白そうと思った点です。ただ懸念点もあって、インターンの時は面白そうと思っても、正社員になった時に同じような仕事の楽しさがあるかどうかが不明確だなと思っています。」
 「他には何か悩んでいることはある?」
「他には何か悩んでいることはある?」
 「学チカでサッカーのことを話そうと思っているのですが、まだどういう風に伝えていくのがベストなのかがわからず少し悩んでいます。あとは小さいことですが、親がOB訪問しなさいなどと言ってくるので軽くストレスです。(笑)」
「学チカでサッカーのことを話そうと思っているのですが、まだどういう風に伝えていくのがベストなのかがわからず少し悩んでいます。あとは小さいことですが、親がOB訪問しなさいなどと言ってくるので軽くストレスです。(笑)」
・業界、企業選びがまだ上手くいっていない
・学チカで話すことの伝え方がわからない
・親からのプレッシャーがあり軽くストレス
unistyle編集部より
積極的にインターンに参加し、企業の人や雰囲気、仕事内容などといった会社の中身をキャッチアップしているところは良いと思います。これからも引き続きインターンに参加すると思いますが、継続して欲しいと思います。
業界・企業を絞れないと悩んでいましたが、就活生はこれによく悩む印象があります。理由としては2パターンあると思います。
一つ目は、「どうありたいか」が考えられていないためです。デニナギくんの場合はこちらに当てはまると思います。
多くの学生が、「どうなりたいか」よりも「何をしたいか」がわからないから企業を選べないと嘆いていますが、実際にはその「何」の部分は重要ではありません。やりたいことはどうありたいかの手段でしかないからです。
自分が将来的にどのような働き方をしていたいかを考え、そこから逆算することによってこれからの仕事として何を選ぶべきかが自ずと見えてくると思います。
海外勤務、転職のしやすさ、結婚など仕事以外の面への影響、福利厚生など、仕事の内容以外でも見るべきポイントは多いと思います。そういった面からも考えることである程度業界を絞れてくるのではないでしょうか。
二つ目は、他にもいい企業があるんじゃないかと思ってしまうためです。
「こうなりたい」という像がありつつも選択肢を絞れないのは、他にも選択肢があるのではという思いがあるからだと思います。
こちらの場合は業界・企業研究をより深めることで解決できると思います。自分の「こうなりたい」という理想像が明確なのであれば、あとはそれにあった企業を見つけにいけると良いでしょう。
十分に業界研究ができれば、自分にあった業界がどこなのかはすぐに見えてくると思います。
デニナギくんへのオススメ記事
→そもそもなぜ業界研究をするのかというところから考え、業界研究の方法を紹介しています。業界研究で悩んでいる方には是非読んでいただきたいと思います。
【企業選びの軸選定法】二項対立で決める企業選びの軸の7つの事例
→企業選びの軸を二項対立によって決める方法を紹介しています。企業選定をするための1つの方法として実践してみて欲しい内容です。