メガバンクから日系コンサルへ、早慶レベルの学生にとっての滑り止めの変化の兆候
38,077 views
最終更新日:2023年10月25日

先日、意識調査として下記のようなアンケートを実施しました。
メガバンクOPコース(三菱東京UFJ、SMBC、みずほ)と日系コンサル(アビーム・ベイカレント)ならどっちに就職したい?
— happytarou0228 (@happytarou0228) 2016年10月27日
結果はご覧の通り、メガバンクのオープンコース56%に対して、日系コンサルティングファームが44%とだいぶ拮抗する結果となりました。10年前ではメガバンクのオープンコースの方が人気が高かったように思いますが、好調なコンサルティング業界に押される形で就職での人気が下がっているように感じます。
これまでの早慶レベルの学生の就職活動
早慶レベルの学生を一般化するのも何ですが、多くの学生の就職活動のパターンは下記のようなものであると考えられます。
①外資系投資銀行もしくは外資系コンサル(戦略ファーム中心)が最難関
②その下に総合商社、不動産ディベロッパー、広告代理店などが続く
③その滑り止めとして大量採用のメガバンク・証券会社・生損保のOPコースが続く
こういった序列を何となく意識しながら自分のスペックと志向性を照らし合わせて就職活動をする学生が多いというのが実感です。もちろん滑り止めと書いていますが、下記の記事の通り、滑り止まらないことも少なくありません。
今回のアンケート結果はこの③の序列に日系コンサルティングファームが今後食い込んでくるのではないかという結果となっています。
メガバンクの収益低下・仕事内容のリテール偏重、コンサルティング業界の好業績
メガバンクはマイナス金利の適用以前から、貸出金利の低下に伴う収益性の低下が問題となっていました。マイナス金利の適用により更なる収益性の低下が懸念されています。その収益性の低下を補うためにも、生命保険の窓口販売や投資信託の販売など手数料収入の増加に注力していました。それでも2016年2月には金融庁から生命保険の窓口販売における手数料を開示するように要請がきているなど逆風が吹いています。
またこれまでは銀行の業務というと企業向けの貸出業務がメインでしたが、近年では個人・企業向けに投資信託商品を販売する仕事が増えており、リテールに近い仕事が増えてきました。企業の成長性を分析し、リスクを見極め貸し出す法人向け業務から、法人の社長を相手にした個人向けの投資信託商品の販売とリテールに近い業務に変化してきたことも、人気低下の一因と言えるかもしれません。
一方でコンサルティング業界、特にアクセンチュアを筆頭にした総合コンサルは、戦略の立案だけでなく、細かい業務にまで入り込んでシステム導入や業務変革を担ってきたことを背景に業績を伸ばしています。日系コンサルのアビームおよびベイカレントもシステム導入まで入り込む総合系コンサルとして、人気を高めていることが伺えます。
学生は世の中のことをわからないから、学生の就職人気ランキングは無意味との声がありますが、思っている以上に学生は世の中の景気や動向に敏感に反応しています。それもそのはずで、各社の説明会や業界研究を通じて今どの業界の調子がいいのか、悪いのか、社会人以上に触れているからというのが一つの理由です。
今回のアンケート結果のメガバンクと総合コンサルの中でも2番手グループであるアビームコンサルティング、ベイカレントコンサルティングの人気が拮抗したのも、逆風吹き荒れるメガバンクと好業績な総合コンサルの人気を表したものと考えられます。
メガバンクOPと日系コンサルのセカンドキャリアの違い
最近のメガバンクOPの仕事はリテール営業に近い仕事が多く、転職先も基本的には営業を担うケースが多いといえます。一方で企業の戦略を業務システムに落とし込む日系コンサルにおいては、営業というよりもシステム部門や経営管理部門などのバックオフィスが転職先としてもメインになります。また総合系コンサルから、ベンチャーやIT系企業のプロジェクトマネージャーになるケースも少なくありません。新卒で入った会社の職種によって、セカンドキャリアはだいぶ変わります。あまり考えずに有名大企業だからと選択してしまうと、本来営業職にはあまり向いていないにも関わらず、転職でも営業職の転職を勧められるケースが少なくありません。もちろん第二新卒などのポテンシャル採用であればキャリアチェンジも可能ではあるものの、キャリアチェンジした場合、それまでのキャリアはリセットされてしまうケースが少なくありません。
何となく、決まった定形の商品を販売することに向いているのか、相手のニーズに対して自らの提案で形にしていく仕事に向いているのか、過去の経験や自分自身の志向性から考えてみると、メガバンク・日系コンサルのどちらのキャリアが自分に向いているか予め検討をつけられるかもしれません。
最後に
もちろん、現状コンサルティング会社が伸びているのは事実であるものの、これがいつまで続くのかはわかりません。一方で自分自身に向いていることややりたいことは時代や企業の業績に関わらず、何となくの方向性があると思われます。仕事としてやってみたいこと、惹かれることに学生のうちから真摯に向き合うことが、その後のキャリアに大きくプラスになるので、今回の記事も参考にぜひ考えてみてください。
photo by Jes






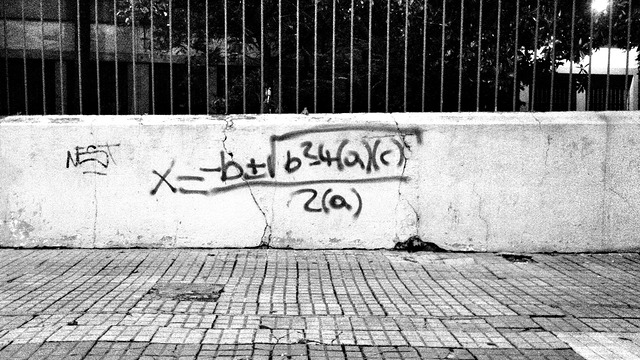
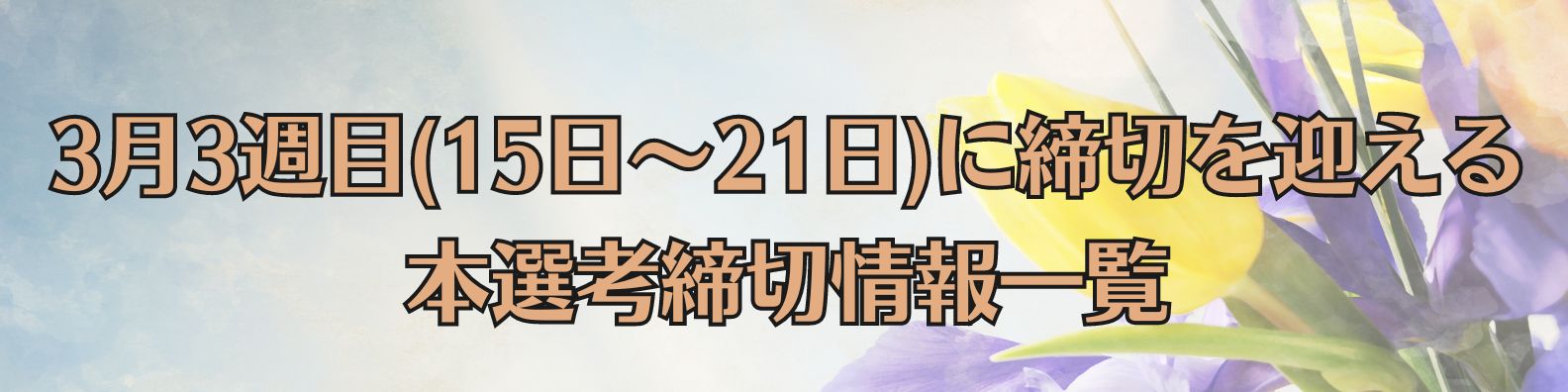
.png?1590043399)
