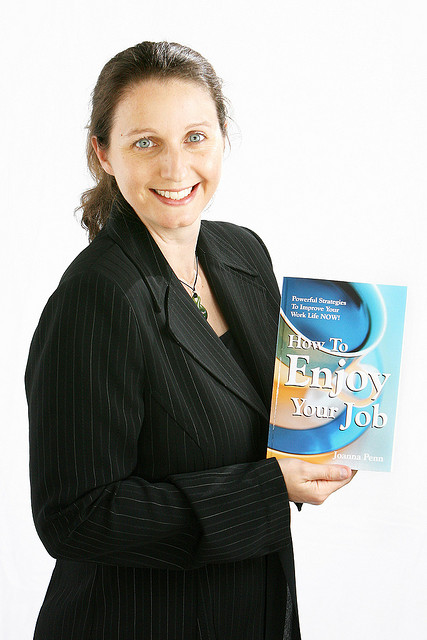メガバンクは滑り止め!?慶應生による慶應生の就職活動の実態
87,199 views
最終更新日:2023年10月25日

こんにちは。慶應義塾大学の16卒就活生です。
就職活動に強いと言われている慶應義塾大学。
各企業には三田会と呼ばれる慶應OBの大規模なネットワークが存在しており、上場企業の社長になりやすい大学学部にもTOP5に経済、法、商の3学部がランクインしています。
実際に他大学の学生に聞いてみても、「慶應の人たちはみんな3年に入った時から就職活動を意識し始めているんでしょ??」というような声をよく聞きます。本日はそんな慶應生の就職活動の実態を見ていきたいと思います。
慶應就活生の分類
慶應生を見ていると4つのパターンに分類されると考えられます。
①トップ層(5%程度)
慶應に入った時から周りに流されたりすることもなく周りが遊んでいる間に、長期留学や社会人との交流など自分自身の力を意欲的に伸ばしている学生群。こういった学生の中にはサマー、ウィンターインターンを通して外資系コンサルや投資銀行への内定を取っている学生もいます。
②上位層(25%程度)
3年生になった時から就職活動を意識し出している学生群。ずば抜けて特殊な経験をしているという学生はそこまで多くないですが、夏からインターン等の選考に参加しつつ、外資系のトップ企業ではないものの内定を確保している学生が多いという印象です。この学生群が周りの大学生から見た慶應生の特徴を体現しています。
③マス層(60%程度)
3年の冬休み〜就職活動の解禁と同時期に就職活動を強く意識し出した学生群。そろそろやらないとな…と考えながらも特にこれといって準備をしたわけでもないため、とりあえずメジャーなメガバンク、BtoCメーカー、生保、損保、広告、商社、不動産等に大量エントリーし説明会に奔走しながら決めていくという印象です。
④ベンチャー志向(10%程度)
長期インターンしているベンチャーにそのまま就職、もしくは自分自身で起業をする学生群。
慶應生から見た慶應生の特徴
他大学の学生から見た慶應生のイメージは「意識が高い」、「就活に積極的」、「面接やグループディスカッションで積極的に話しかけてくる」といったものから、「意識が高くやたら仕切ろうとしてうざい」といった感じでしょうか。実際に他大の友人に聞いても「行ったインターンの参加者は半分くらい慶應生だった。」であるとか、「すごいプレゼンうまい学生の多くは慶應生だと思う。」としばしば耳にします。私自身も夏頃からサマーの選考を受けたりとしていましたが、確かに他大学よりも慶應生と会うことは多かったように思えます。
しかしながら先に分類した学生のうち、世間的慶應生は①②のおよそ30%程度です。冬休み頃まではバイト漬け、サークル漬けという学生も多くいますし、就職活動を終えた先輩からも「冬くらいから自己分析はじめて企業絞っていけば大丈夫だよ。」と聞くこともよくあります。
他大学と比べると意識高く活動している学生が多いことは確かではあると思いますが、かといってそこまで多くの学生が意識高く活動しているわけではないというのが実際の感覚です。
メガバンクは滑り止め!?〜慶應生の就活観〜
まずは先日あげた慶應生の就職活動意識調査を見てみましょう。
実際に慶應生の就職活動意識調査を行ったところ、第1志望群にはTOP5社中に総合商社が4社、就職検討先には上位5社全てを総合商社が占める結果となっています。加えてデベロッパー、大手広告代理店も高順位です。また、メガバンクは第1志望群の上位には入ってはいないものの、検討している就職先の質問では11位に三菱東京UFJ銀行、12位に三井住友銀行が入っており、大きく順位を伸ばしています。
この結果から見ると慶應生は「メガバンクは採用人数も多いし滑り止め感覚、第一志望は総合商社、広告代理店、デベロッパー」という考えを持っているように思えます。
この考えの背景には以下のデータが参考になるでしょう。
学部によって差はあるものの、全学部で見ると上位3社はメガバンク、上位20社で見ると伊藤忠商事を除く5大商社がランクインしています。一般の慶應生でもメガバンクを中心とした金融業界に進んだ先輩は身近にいることもあって「自分でも普通に就職活動していればメガバンクくらいにはいけるだろう、もしかしたら商社にもいけるかもしれない!!」と考えているようです。
しかしながら以下のデータを見てください。
慶應は上位400社就職率がおよそ40%、つまり5人に2人が所謂有名企業に行く計算です。
ここで先に挙げた慶應生の分類を思い出していただきたいのですが、①トップ層②上位層を合わせると約30%程度となります。もちろんこの学生群全員が全員有名企業に行けるとは限りませんが、マス層よりも多くの学生が選考を通過していくことは確かです。
また、以前アップした早慶東大の総合商社志望者の入社率も参考にしたいと思います。
およそ20人に1人が内定を得ています。大体これは先に挙げた①トップ層の割合と同じ程度です。先のデータと同じようにこの学生群全員が商社に行けるとは限りませんが、上位層に最も人気の業界であるからこそ、能力部分と就職活動スキルの両方を兼ね備えた学生が行くことは確かです。
またこれは実感ではあるのですが、実際に選考が始まるに連れて、メガバンクは滑り止め!!と言っていた多くの学生たちが、とりあえず大手の金融に行けたらいいかな、であるとか、商社やマスコミなどの人気業界に行けるのは体育会系だったり長期留学者だけ、と現実に打ちひしがれていることも学内ではよく見られます。
最後に
データとリアルな就活生の声から慶應生の就職活動事情をお届けしました。
最後にも書きましたが、慶應生は就職活動が始まる前と後ではテンションは全く違います。これは他の大学の学生にも言えるものだと思いますが、周りよりも早く就職活動を意識している人ほど、ぶれずに活動しているように思えます。現在3年生の17卒の方もこれからインターン等が始まると思いますが早期から準備することをお勧めします。
photo by Paul Trafford






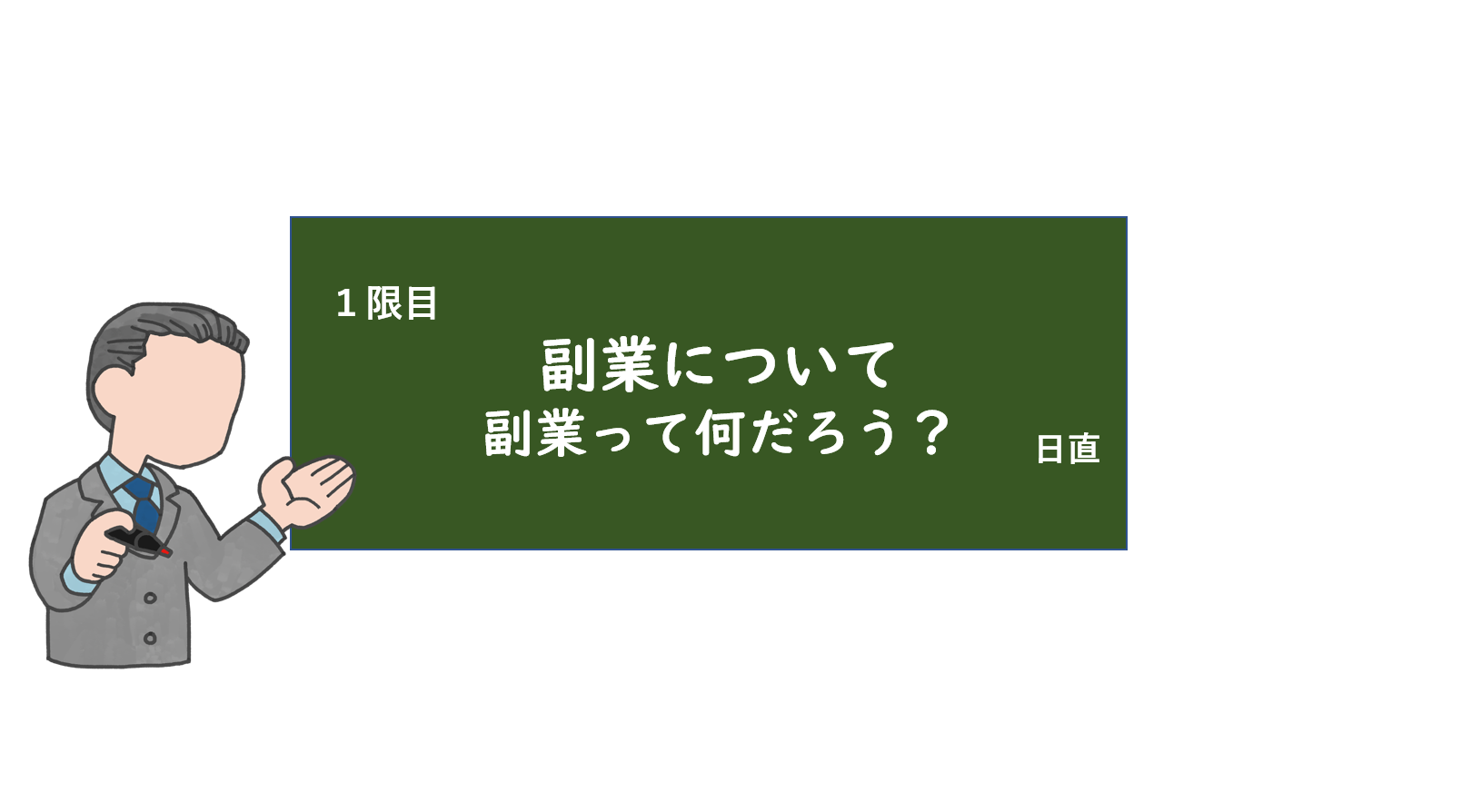
.png?1721207175)