初任給と平均年収に惑わされるな!就活で給料を調べる際に見るべき4つの項目とは
165,251 views
最終更新日:2024年10月21日
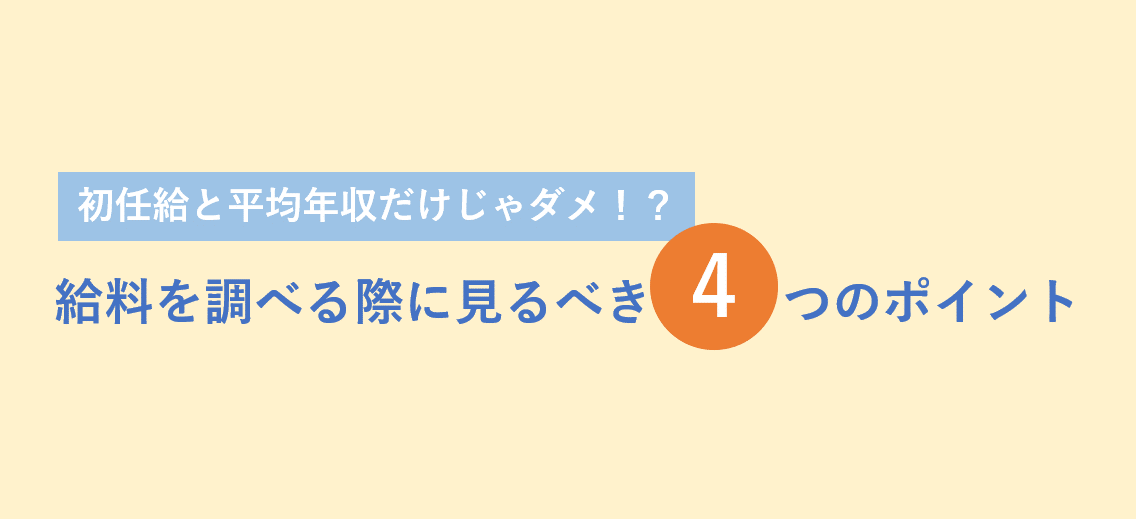
「企業規模・仕事内容」などと並び、企業選びの際に就活生が重視する項目の一つである"給料"。
「給料よりも仕事のやりがいがとにかく大事!」などという声も耳にすることはありますが、やはり企業選びの際に給料を重視する就活生は多く、実際の以下のような調査結果も出ています。
1位.安定している会社:39.6%
2位.自分のやりたい仕事(職種)ができる会社:35.7%
3位.給料の良い会社:19.0%(前年比3.6pt増)
4位.これから伸びそうな会社:13.0%
5位.勤務制度、住宅など福利厚生の良い会社:12.8%
︙
︙
【参考】
2020年卒マイナビ大学生就職意識調査
調査対象:2020年3月卒業見込みの全国大学3年生、大学院1年生(調査開始時点)
調査期間:2018年12月1日~2019年3月21日(2019年卒は2018年2月1日~2018年4月10日)
有効回答:48,064名(文系男子13,341名、文系女子19,811名、理系男子8,789名、理系女子6,123名)
上記の調査結果を見ても分かる通り、企業選びの際に「給料」を重視している就活生は少なくありません。
その一方で、各社の給料事情を見る際に「初任給と平均年収」しか見ていない就活生が多数いるのも事実です。
別に初任給と平均年収だけを見て給料事情を把握することが悪いという訳ではありませんが、「給料」を重視している就活生にとっては、本質的な分析になっていない場合があります。
そこで本記事では、"本質的な給料の見方"を理解するにあたり、「就活生がしがちな誤った認識、給料事情を知るにあたり見ておくべき項目、情報の入手方法」などを解説していきます。
そもそも就活生は給料を調べる際、どんな情報を見ているのか?

記事の冒頭でも述べましたが、各社の給料を調べる際、多くの就活生が見ている項目は"初任給と平均年収"の二つではないでしょうか。
- 初任給とは?
→学校を卒業して会社に雇用されるようになった人が、最初にもらう給与のこと。 - 平均年収とは?
→国・業界・企業など、指定された範囲内での総給与所得を給与所得者数で割った金額のこと。
この二つは、就活に関する様々な書籍や各就活媒体によく掲載されている情報にはなりますが、掲載されている数値をそのまま受け取ってしまうと、誤った認識をしてしまう恐れがあります。
その理由を以下で説明します。
初任給に関して誤った認識をしてしまう場合
初任給は月給で表されることが多く、「修士:248,000円・大卒225,000円」などと表示されている場合がほとんどです。
ですが、これらはあくまでも「基本給・額面」と呼ばれるものであり、実際にもらえる給料(いわゆる手取り)とは異なります。
なぜかというと、基本給・額面から「税金(所得税・住民税など)・社会保険料(年金・健康保険料)」などが引かれるためです。
※ただ、企業によっては基本給・額面に「残業手当・インセンティブ」がつく場合もありますので、一概に「基本給・額面>実際にもらえる給料(手取り)」という訳ではありません。
そのため、単純な月給以外にも以下のような観点で給料を見る必要があります。
- ボーナスはどの程度あるのか
- 残業手当は別途支給されるのか、固定残業代(みなし残業)なのか
- 福利厚生はどの程度あるのか
ボーナスはどの程度あるのか
ボーナスに関しては、「(1)何ヶ月分支給されるのか?(2)平均額はいくらなのか?」を認識しておくべきでしょう。
平均年収はボーナスを含めた金額となっていますが、月給には含まれていません。そのため、ボーナス制度のある企業は「月給×12ヶ月=年収」という構図にはなりません。
企業によっては年間賞与(ボーナス)が500万を超える企業もありますし、より詳細な給料を知りたいのであればボーナスの仕組みもしっかりと理解しておくべきでしょう。
ただ、ボーナスは「企業の業績・個人の成果」によって変動があるため、あくまでもおおよその指標として認識するのが望ましいかと思います。
残業手当は別途支給されるのか、固定残業代(みなし残業)なのか
こちらに関しては、いわゆる「基本給に残業代が含まれているか否か」という内容になります。
例えば、基本給が同額である2つの企業が存在したとします。一方の企業の基本給には残業代が含まれているが、もう一方の企業は基本給とは別途で残業代が出るとします。
このような2社が存在した場合、残業時間次第で後者の企業には基本給からの上乗せがあるため、ほぼ確実に後者の企業の方がもらえる金額は多くなるという訳です。
そのため、「提示されている基本給の額=その企業の給料」と単純に認識してしまうことは浅はかだと言えるでしょう。
各社の残業制度に関しては、新卒採用HPなどに必ず掲載されていますので、給料事情を調べる際にはこちらも併せて確認しておきましょう。(※ここでは、みなし残業の是非を述べている訳ではありません)
福利厚生はどの程度あるのか
就活生の中には「福利厚生=オマケ」程度に認識している方も一部存在しますが、実際はそんなことはありません。
有名なものであれば「家賃補助(住宅手当)、家族手当」などが挙げられますが、これは見方を変えれば「福利厚生=給料の一部」と言い換えることもできます。
ここで一つ具体例を出します。
福利厚生は特にないが手取りが25万円のA社、一方で家賃補助4万円の福利厚生はあるが手取りが23万円のB社があったとします。(ボーナスやインセンティブなどは考慮しない)
福利厚生・手取り以外の条件が全く同じだった場合、皆さんはどちらの企業を選択するでしょうか。
おそらく、多くの方がB社を選択するかと思います。ただ、福利厚生は給料とは別途で記されていることが多いため、採用HPに記されている金額だけで優劣を判断してしまうと、誤った認識をしてしまうという恐れがあるという訳です。
このように、福利厚生は給料に関する非常に重要な要素となりますので、給料を確認する際にはしっかりと目を通しておくべきでしょう。
平均年収に関して誤った認識をしてしまう場合
「誤った認識をしてしまう」と記載しましたが、ここでは「平均年収を見ることは止めたほうがよい!」ということを言いたい訳ではありません。
ここでお伝えしたいことは、"平均値と中央値を混合していませんか?"ということです。
おそらく、平均値と中央値を混合している就活生の方はほとんどいないとは思いますが、念のため両者の違いをお伝えします。
- 平均値
→複数のデータを足し合わせ、そのデータの個数で割った値のこと - 中央値
→複数のデータを小さい/大きい順に並べ、その中で真ん中に来る値のこと
では、この平均値と中央値の違いをより理解していただくために、具体例を用いて説明していこうと思います。
社員が計10名在籍しているA社という企業が存在します。社員の年齢・役職はまちまちなのですが、全社員の年収は下から「300万、300万、300万、300万、300万、300万、300万、600万、600万、900万」となっています。
【A社の平均値と中央値は?】
では、A社の年収の平均値と中央値はどれだけの差があるのでしょうか?
⇩
◆平均値
(300万×7人+600万×2人+900万×1人)÷10人=420万
◆中央値
小さい順、大きい順のどちらで並べたとしても「300万」が中央値となる
⇩
このように平均値と中央値では、120万円の差が出ます
上記はあくまでも極端な例にはなりますが、このように平均値と中央値のどちらで給料を見るかにより、給料が大きく異なる場合があるという訳です。
特に、「役員の給料が非常に高額であり、一般的な正社員の給料と大きな乖離がある企業」は上記のような傾向が強いと言われています。
「平均年収のカラクリ」というと少し大げさかもしれませんが、"平均値=中央値"と誤認識しないように意識していただければと思います。
では、就活生が本当に見ておくべき情報とは?

上記で、「初任給と平均年収の数値をそのまま受け止めるのはマズイ」という内容を紹介しましたが、とは言ったものの他にどんな項目を見ればいいか分からないという就活生もいると思います。
これに関しては取り上げだしたらキリがないのですが、より重要な項目は以下の4点に大別されると考えています。
- 年収の中央値
- 平均勤続年数(平均年齢)
- 昇給率・昇給額
- 給料の上限
上記4点を網羅することで、より本質的に給料を理解することができます。
それでは上記4点の各項目について詳しく見ていきます。
【給料に関して見るべき項目(1)】年収の中央値

上記でも述べましたが、「給料(年収)の中央値」を見ることは非常に重要となります。
先ほどの説明に補足するのであれば、"その企業の中央値である給料は、その企業の平均年齢時にもらえる金額"と言い換えることができます。(もちろん100%正値という訳ではありませんが)
【給料に関して見るべき項目(2)】平均勤続年数(平均年齢)
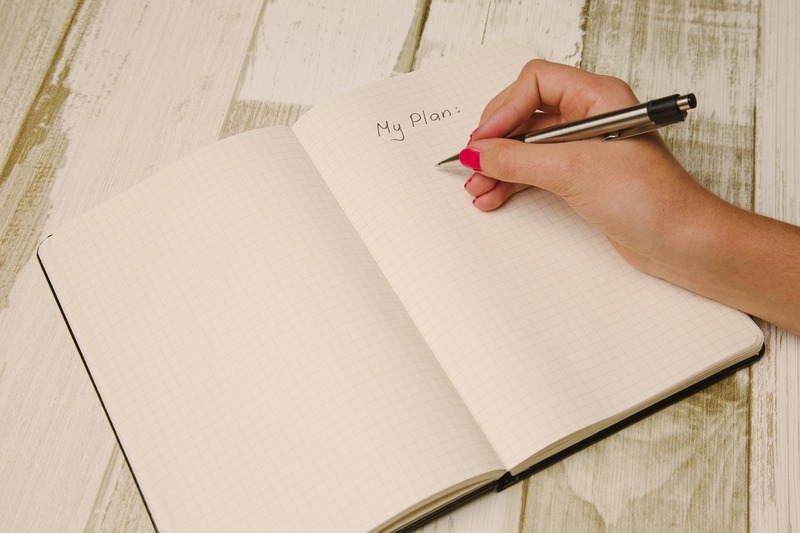
給料とは一見関係のないように見える平均勤続年数(平均年齢)ですが、給料を見る際の重要な指標となります。
基本的に給料と平均勤続年数(平均年齢)は「比例関係」にあり、"平均勤続年数(平均年齢)が高ければ高いほど、給与(平均年収)も高くなる"という構図になっています。
ここで一つ具体例を出します。
平均年収(中央値)が同額のA社とB社があります。平均年収(中央値)は同額ですが、A社は平均勤続年数が20年・平均年齢が44歳です。一方でB社の平均勤続年数は10年・平均年齢は35歳です。
この両社を見て、読者の方はどのような印象をお持ちになったでしょうか。
おそらくほとんどの方が、A社よりもB社の給料を魅力的に感じたことでしょう。先ほども述べた通り、給料と平均勤続年数(平均年齢)は比例関係にあるため、より若い年齢で同額の給料をもらえるB社の方が、相対的に考えて魅力的に感じるのではないでしょうか。
つまり、給料と平均勤続年数(平均年齢)は相関関係にあるとも言えます。
また、「●歳までに●●●万の年収を目指す!」など、時期と金額をセットにした目標を持っている方にとっても平均勤続年数(平均年齢)は重要な指標となります。
平均年収や年収の中央値が同様でも、企業によってその金額に到達する年数(年齢)は異なりますので、そういった目標を持っている方は「平均勤続年数(平均年齢)」に目を向けることも忘れないようにしましょう。
【給料に関して見るべき項目(3)】昇給率・昇給額

就活生の皆さんであればすでにご存知のことだとは思いますが、基本的に「役職や年次」が上がれば給料は増加します。
その給料が上がるという際に重要となるのが"昇給率・昇給額"です。
- 昇給率
→昇給後の給料が昇給前に比べてどの程度増加したのかを表す割合(%) - 昇給額
→その年の月給が前年(昇給前)に比べてどの程度増加したのかを表す金額(円)
この昇給率・昇給額は「キャリアプラン」に密接に関連しています。
よく目にする「3年目は●●●万円、7年目は●●●万円…」などという金額は、この昇給率・昇給額をもとに計算されている場合がほとんどです。
また、日系大手と言われる企業では「●年目から●年目にかけて●円上がる」などと明確に決まっている場合もあるため、おおよその昇給モデルは把握できるでしょう。
ただこの辺りのセンシティブな情報は口外できない場合があり、現役社員に質問しても回答してくれない可能性がありますので、可能であれば人事の方などに質問していくのが最善かもしれません。
【給料に関して見るべき項目(4)】給料の上限

給料の上限に関しては、「新卒入社した企業で定年までずっと働き続けたい」と考えている就活生の方に見ておいていただきたい項目になります。
上記のような考えを持っている就活生は年々減少しているようですが、日系大手志望者を中心にまだ一定数はいると思われます。
給料の上限とは、簡単に言うと「その企業の社員として稼ぐことのできる最大限度の給料」のことを指します。
日系大手などでは、上限の金額はある程度決まっており、どれだけ優秀な人であろうとその金額を超すことはほぼないと思ってもらって構いません。(社長や取締役などに就任すれば別ですが、本記事ではそういった事例を除いた上で説明しています)
ただ、成果主義の側面が強い外資系企業・ベンチャー企業、またヘッドハントなどで採用した中途社員などは上記の事例に当てはまらない場合もありますので、全ての企業・社員に当てはまる訳ではないということを認識していただければと思います。
ここで一つ具体例を出して説明します。
某外資系投資銀行に務めているAさんという方がいます。Aさんは非常に優秀な方であり、30代前半にも関わらず1,500万程度の年収を稼いでいます。
では、仮にこのAさんが地方の中小企業に転職し、前職と同様にバリバリ働いて成果を挙げていたとして、1,500万程度の年収を稼ぐことはできるでしょうか。
答えは「NO」です。上記でも述べましたが、その企業の社員として稼ぐことのできる最大限度の給料はあらかじめ決まっていることが多いため、Aさんがどれだけ優秀な方であろうがその金額を超すことは中々難しいためです。
このように「給料の上限」というものは決まっていることが多いため、「将来的に年収1,500万を目指したい!」と考えていても、どの企業に入社するかによって入社時点で実現可能性が0になってしまう可能性もあると言えるでしょう。
基本的にどの企業も「50代前半が年収のピーク」と言われているため、この年代のモデル年収を聞けば"各社の給料の上限"を知ることができるはずです。
とは言え、どのように情報を入手すればいいの?

ここまで、「給料に関して就活生が見ておくべき情報」を紹介してきました。
とは言ったものの、どのように情報を入手すればいいのか分からない就活生も多いのではないでしょうか。
実際、数ある就活関連の書籍や就活媒体に上記のような情報は見られず、せいぜい「初任給と平均年収」程度しか掲載されていないというのが実情です。(逆の発想をすれば、初任給と平均年収しか掲載されていないからこそ、多くの就活生がその2つの項目しか見ていないと言うこともできますが)
では、どうすれば情報を入手できるのか。
その方法としては、主に以下の2点が挙げられると考えています。
- OB・OG訪問
- 口コミサイト(OpenWork・キャリコネなど)
OB・OG訪問
OB・OG訪問は、最も効果的な方法且つ信憑性の高い情報を得ることができます。
やはり実際の社員であれば社内の実情に詳しいですし、人事や採用担当には聞きづらい質問にも答えてくれる可能性が比較的高いためです。
ただ、給料などのお金に関する質問はセンシティブな側面もあるため、質問の仕方には注意が必要です。
以下に質問例を挙げていますので、こちらも参考にしながら自身のOB・OG訪問に取り入れていただければと思います。(あくまでも一例になります)
- 「年収の中央値」を知りたい場合の質問
⇩
御社の社員の平均年齢は●歳くらいだとお聞きしましたが、そのくらいの年齢の方はどの程度の給料をいただいているのでしょうか? - 「平均勤続年数(平均年齢)」を知りたい場合の質問
⇩
御社(●●部署)の社員の方は、どのくらいの期間御社に務めていらっしゃるのでしょうか?/御社(●●部署)の社員は、どのくらいの年齢の方が多いのでしょうか?
※ただ、平均勤続年数(平均年齢)は採用HPや就活関連の書籍に記載されている場合が多いため、必ずそれらを確認してから質問するようにしましょう。 - 「昇給率・昇給額」を知りたい場合の質問
⇩
20代(30代…)では、毎年どの程度昇給するのか教えていただきたいです。/私は、働くからには成果を出して役職も上げていきたいと考えているのですが、それに際して一つ役職が上がるごとにどの程度昇給するのか教えていただけないでしょうか? - 「給料の上限」を知りたい場合の質問
⇩
御社に入社できた場合、御社でずっと働き続けたいと考えているのですが、その場合年収はどの程度まで到達するのでしょうか?
また、以下にOB・OG訪問に関する参考記事を掲載しておきますので、こちらも併せてご覧ください。
口コミサイト(OpenWork・キャリコネなど)
口コミサイトを閲覧することも、情報を入手するための有効的な手段の一つとなります。
その中でも今回は"OpenWorkとキャリコネ"をオススメしたいと思います。
それぞれの特徴は以下の通りです。
OpenWorkは、国内最大級の就職・転職クチコミサイトになります。現職・退社済みの社員からの口コミ情報をもとに、その企業の「会社評価スコア・平均年収」などがリアルに示されています。
平均年収や年収範囲が掲載されているのはもちろんのこと、「給与制度・評価制度」に関する口コミも多数掲載されているため、かなり具体的な情報を入手することができます。
口コミサイトの中では「質・量」ともに国内トップレベルのサイトであるため、参考になる情報は多々あるでしょう。
OpenWorkを閲覧したい方はこちらから
OpenWorkと同様、キャリコネも就職・転職クチコミサイトになります。現職・退社済みの社員からの口コミ情報をもとに、「働きやすさ・テーマごとの口コミ」などが掲載されています。
回答者の平均年収に加え、「給与に関する口コミ・世代別最高年収」なども示されているため、かなりリアルな給料事情を知ることができます。
キャリコネに掲載されている情報で不足があればOpenWorkで補填する(逆も然り)といった使い方をすれば、かなり有意義に情報収集することができるでしょう。
キャリコネを閲覧したい方はこちらから
両サイトとも「退職済み社員からの口コミが多いゆえにネガティブ情報が比較的多め・企業によってはn数が少ない場合がある・最新の口コミばかりではない」という側面があります。
それゆえに「給料に関する情報に関しても不満の声が比較的多め・口コミ投稿時と現在では企業の実情が変化している可能性がある」などの留意点はあります。
そのため、OB・OG訪問での情報収集に比べ、どうしても情報の信憑性は薄くなってしまうというデメリットはあります。
ただ、簡単且つ効率的に情報をするにはもってこいの手段となりますので、OB・OG訪問と口コミサイト、両者の特徴をそれぞれ理解した上で自身の状況や得たい情報に応じて使い分けていただければと思います。
また、待遇などを含めて、もう少し詳しい情報が欲しいという就活生には就職エージェントneoがおすすめです。
アドバイザーから、志望業界・志望企業の選考フローに合わせたアドバイスを受けられます。
少しでも興味があるという方は、下記の画像をクリックしてサービスを利用してみてください。
まとめ

本記事では、「就活生が見るべきお金に関する情報・情報の入手方法」など、"給料の見方"を包括的に解説しました。
企業選びを進めるにあたり、給料に関する情報は切っても切り離せない事柄だと思いますが、本質的な部分まで理解している就活生は少ないように感じます。
表面的な情報に惑わされず、給料の見方を正しく理解していただくためにも、ぜひ本記事の内容を頭に入れた上で企業選びを進めていただければと思います。
また、下記に「給料にまつわるunistyleの記事」をいくつかピックアップして掲載していますので、こちらも併せてご覧いただければと思います。


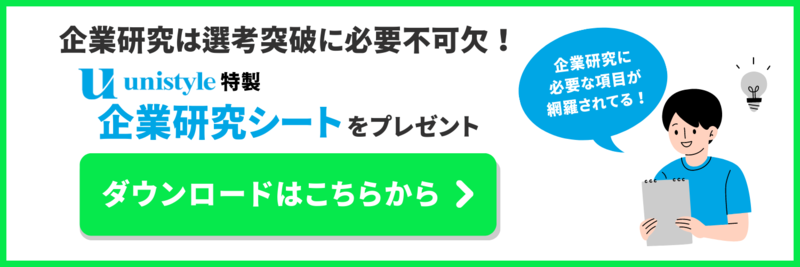

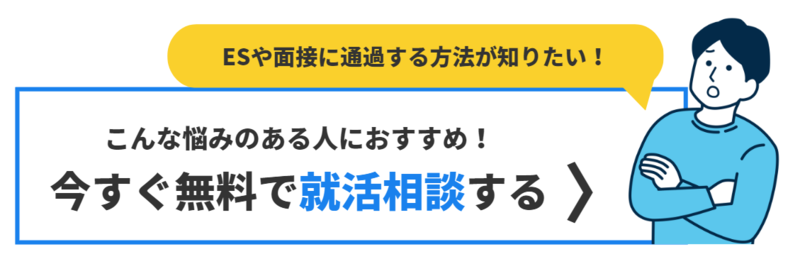


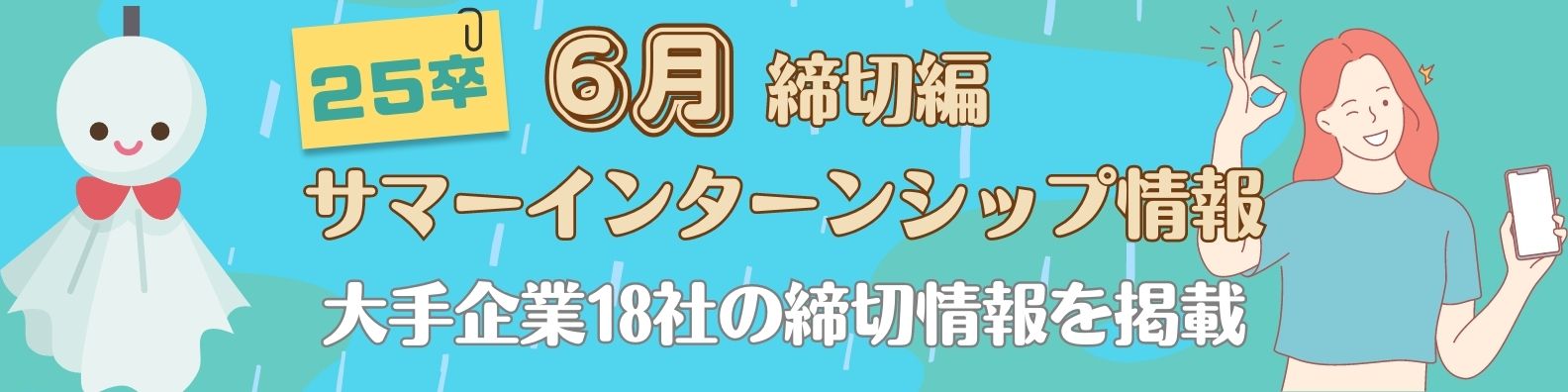
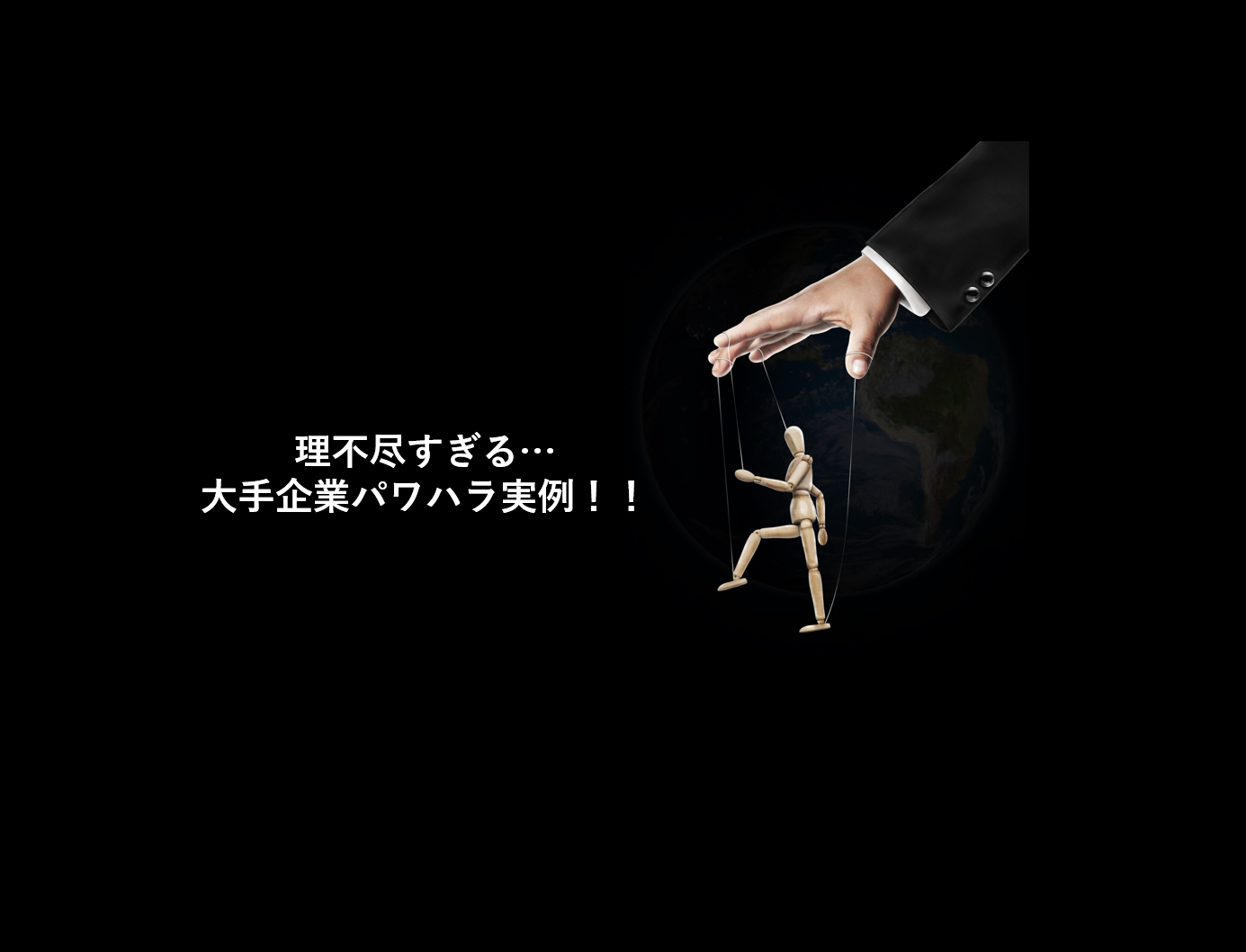
aaa.png?1572597471)
