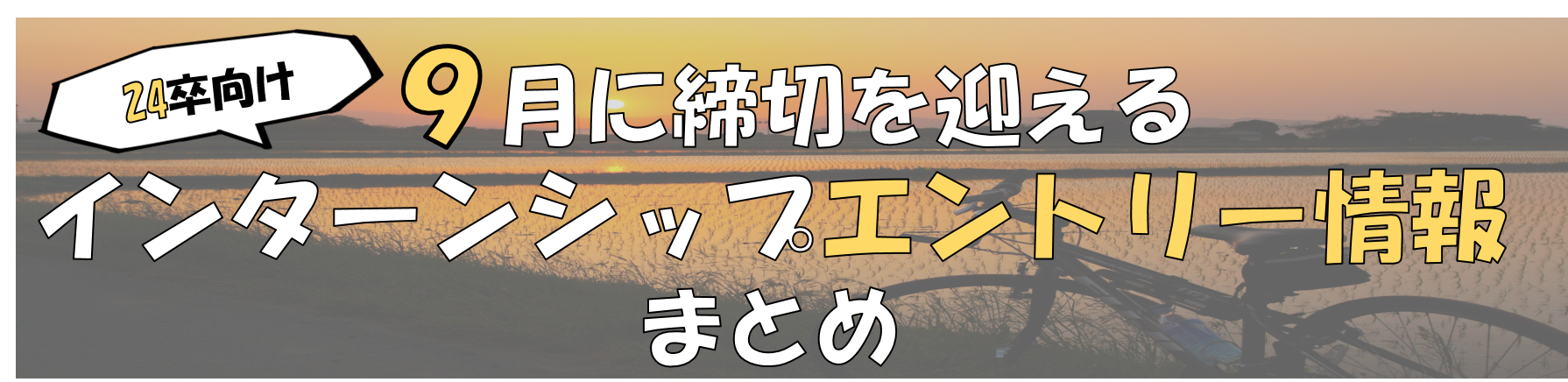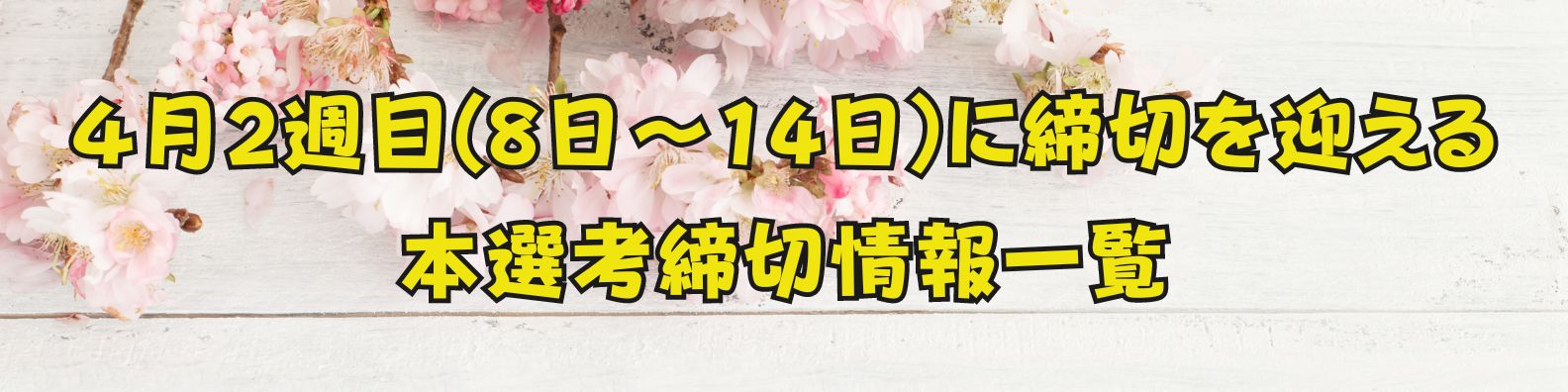コンサルのスキルは就活にも役立つ!書籍『コンサル一年目が学ぶこと』から学ぶこと
19,311 views
最終更新日:2023年10月30日

1.【業界研究】外資コンサルの仕組み・大手企業ランキング・選考対策まで一挙大公開!
2.【業界研究|コンサルティング】コンサルティングとは?から選考対策までを徹底解説
3.【業界研究】外資コンサル大手企業一覧まとめ
4.【業界研究】外資コンサルの年収ランキングを大公開!
今回ご紹介するのは『コンサル一年目が学ぶこと』という書籍です。
タイトルからコンサルティングファームでの仕事術を述べたものかと思いきや、コンサルから他業界に移った著者の目線から見た、どんな仕事にも言える普遍的なことがらが書かれています。
コンサル志望者・内定者の方はすでに本書や類似内容の書籍を読んでいると思っており、むしろそれ以外の業界を志す方に本書を読んで欲しいと思いコラムにしました。内定者の方にもおすすめです。
【著者紹介】
大石 哲之(おおいし てつゆき)1975年東京生まれ。慶應義塾大学環境情報学部卒。アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア)に入社後、戦略グループのコンサルタントとして、全社戦略の立案、マーケティング、営業革新などのプロジェクトに携わる。その後、株式会社ジョブウェブを起業し、取締役副社長。同社退社後は、個人コンサルタントとして独立、本の執筆も開始。株式会社ティンバーラインパートナーズを設立し、現職。
コンサル目線での仕事術に関するもの以外にも、下記のような就活生向けにキャリアについての書籍も執筆していますので見てみてください。
職業・業界不問の15年後も役立つ30のスキル
本書では、合計30個のスキルを4つの章に分類して説明しています。
第1章:コンサル流話す技術
(1)結論から話す
(2)Talk Straight 端的に話す
(3)数字というファクトで語る
(4)数字とロジックで語る
(5)感情より論理を優先させる
(6)相手に理解してもらえるように話す
(7)相手のフォーマットに合わせる
(8)相手の期待値を把握する
(9)上司の期待値を超える
第2章:コンサル流思考術
(10)「考え方を考える」という考え方
(11)ロジックツリーを使いこなす
(12)雲雨傘 提案の基本
(13)仮説思考
(14)常に自分の意見を持って情報にあたる
(15)本質を追求する思考
第3章:コンサル流デスクワーク術
(16)文書作成の基本、議事録書きをマスターする
(17)最強パワポ資料作成術
(18)エクセル、パワーポイントは、作成スピードが勝負
(19)最終成果物から逆算して、作業プランを作る
(20)コンサル流検索式読書術
(21)仕事の速さを2倍速3倍速にする重点思考
(22)プロジェクト管理ツール、課題管理表
第4章:プロフェッショナル・ビジネスマインド
(23)ヴァリューを出す
(24)喋らないなら会議に出るな
(25)「時間はお金」と認識する
(26)スピードと質を両立する
(27)コミットメント力を学ぶ
(28)師匠を見つける
(29)フォロワーシップを発揮する
(30)プロフェッショナルのチームワーク
次から、各章の内容のエッセンスを実際の就職活動の例に当てはめながら説明していきます。
①話す技術:「結論から」「端的に」「ファクトベースで」話す
ビジネスの場面においては短時間で相手に必要な情報を齟齬の無いよう伝えることが求められます。
そのために徹底すべきこととして、本書以外でもコンサル関連含む多くの書籍で繰り返し書かれているのが「結論から話す」「端的に話す」「数字など、事実に基づいて話す」ということです。
変な駆け引きをせず、言い訳をせず、言われたことにきちんとストレートに答えること。相手の信頼を得るために非常に大事なこととして、いまも常に心がけています。
(『コンサル一年目が学ぶこと』p.20より)
面接などでも、都合の悪いことを突っ込まれた際にはぐらかして答えがちだという方は特に意識して欲しいと思います。
例:成績の悪さについて言及された際の反応
【はぐらかして答える】
「すみません。。。それでも部の中では自分は割と授業には出席する方でしたし、ゼミ活動にも参加していましたし、できる範囲で勉強はしていたのですが、部活で毎日忙しくて一部おろそかになっていたところもあったかもしれません(以下続く」
【ストレートに答える(PREP法)】
①Point「おっしゃる通り、学業成績は正直芳しくありません」
②Reason「部活動を最優先と考え、最低限の勉強量で進級してきたためです」
③Example「平日はほとんど毎日練習をしていまして、その結果レギュラーを獲得し試合でも成果を上げられたので、自分の中では後悔はありません」
④Point「そうしたわけで成績は悪いのですが、単位数は何とか計画的に取得できている状況です」
ビジネスの場面においても、特に新人の頃は上司から仕事の進捗を聞かれることが多くあります。また、聞かれるのは往々にして仕事がうまく進んでいない時だとも思っています。
真っ当な企業であれば、進捗確認の目的は部下を詰めることではなく、仕事を前に進めるためですので、誤魔化さずにイエス・ノーをきちんと答えることが重要です。うまくいっていないのであればその理由を明確にし、何がネックになっているのか、どうすればうまくいくのか、上司とのコミュニケーションを通して改善・解決策を探っていくのが仕事の基本になります。
上司:「分析グラフができていないというけれど、何が問題なんだ?」
部下:「はい、グラフ化しようとしても、データ自体に問題があって集計できるようになっていないんです。これをいま直しています」
上司:「なに?データに問題があるのか?時間はどのくらいかかる?」
部下:「1週間くらいかかるかもしれません」
上司:「それはまずい。その分析は今週中にやる必要がある。1週間では困るので、別の人もヘルプさせるから、2日で仕上げられるか?」
(『コンサル一年目が学ぶこと』p.25より)
②思考術:常に自分の「仮説・意見」を持って情報にあたる
最近はメディアやSNSなど多くの情報が周囲にあふれていますが、結局ビジネス能力を向上させるには「考えること」が必要だと言えます。考える、というのは「仮説」と「意見」を持つことです。
漫然と情報に触れていると、他者の意見を鵜呑みにしてしまったり、そもそも頭に情報が残らないためインプット自体ができていないといったことになりがちだと思っています。
普段から自分なりに考えるクセをつけておくことで、面接においても深いレベルの回答ができるようになるものと思います。面接では口八丁なタイプの人ばかりが評価されがちという議論も見かけますが、物事を普段からどの程度の深さで考えているのかを見られている側面も大いにあると感じています。
参考:面接で問われているのは瞬発力ではなく、普段から物事を考える力
他にも、業界問わず頻出な「最近気になるニュース・サービスは?」といった質問についても、情報をぼーっと眺めているだけでは浅い回答に終始してしまうと思っています。
なお、自分なりの考え方を構築する際にも、ゼロベースである必要はなく、他者の考えを参考にするとよいと感じます。
参考:「ギリシャ問題」「アベノミクス」について回答を求められたら?就活生必携アプリ「NewsPicks」とは
最初は、稚拙だったり、間違いだらけだったりしてもかまいません。とにかく、自分だったらこう思うという筋をもって、本を読んだり、有名人のツイートに接したり、記事を読んだりすること。
(『コンサル一年目が学ぶこと』p.140-141より)
③デスクワーク術:「最終アウトプット」のイメージを持ってプランニングする
例年、エントリーシートを書くのに四苦八苦している方は多くいることと思います。ゼロから文章を作成するのが大変ということだと思っていますが、執筆開始の時点で最終アウトプットの骨組みを作るようにすることで、格段にラクになるのにと感じています。
本書の中では効率的な作業プランニングの方法として「空(から)パックを作る」というものを挙げています。
どういうことかというと、最初にアウトプットのイメージ(見出し)を作成して、そこに必要な情報を入れていくというものです。
最終成果物のタイトルだけを書いた、中身が空(から)のパワポをつくり、中身を埋めていくためのタスクを洗い出す。
(『コンサル一年目が学ぶこと』p.184より)
unistyleにおいても、自己PR・学生時代頑張ったこと・志望動機などの頻出設問についてはフレームワークに当てはめて考えることを推奨しています。フレームワークに則るメリットとしては、思考を整理できる、論理的に伝えられる、執筆の省力化ができるといったことなどが挙げられます。
◆フレームワークに則った自己PR執筆準備の例
①強み:
社交性と向上心から周りを巻き込む行動力があること。
②強みの原点:
小学校〜高校までで3回の転校経験から、新しい環境でもすぐに周囲に溶け込めるように働きかけるようになった。
③強みが発揮された具体的エピソード:
個人作業が多くなりがちな研究室活動において、全日本学生ロボットコンテストに向けてチームを結成、代表として運営し、コンテストでは初出場ながら50校中16位という結果を収めた。
④強みの方法論:
新しい環境でも、自分から積極的に周囲に働きかけることで周囲を巻き込んでいくことができると考えている。
⑤強みを社会でどう活かすか:
仕事においても主体的に行動し、積極的に周囲に働きかける中で、社内、取引先、顧客などとの信頼関係を構築していきたい。
▼参考記事
・内定レベルの自己PRが簡単に書ける自己PRのフレームワーク
・内定レベルの学生時代頑張ったことが10分で書ける学生時代頑張ったことのフレームワーク
・内定レベルの志望動機が10分で書けるフレームワーク
④マインド:顧客への「価値提供」にコミットする
コンサルタントが使う表現で「ヴァリュー(付加価値)を出す」というものがあります。
仕事のヴァリューを規定するのは相手であり、相手に喜んでもらえない仕事は単なる自己満足に過ぎないと言えます。
ところで、「御社のサービス・製品が好きだから志望してます」という話をする方は結構多いと思っていますが、多くは「いち消費者目線」に過ぎず、評価されないと感じています。
サービス・製品に愛着があるのはよいことかもしれませんが、社会に出れば、生産者として常に試行錯誤を重ねてよりよいものを消費者へ届けて満足を得るというマインドセットの方をより大切にして欲しいと思います。
また、「信頼関係構築のために大切なことは何か?」という問いに対しても、本書は一つの回答を示しています。「コミットメント(約束)」という考え方です。
クライアントと約束したものは、どんなことがあろうとも、やってくる。
そこに信じられないほど強いコミットメントをもっている。
そして、常にクライアントの期待値を上回るものをもっていく。
それを実直に繰り返すことによって、信頼を得る。
(『コンサル一年目が学ぶこと』p.251より)
約束を守り、期待に応え(期待を超え)続けることの積み重ねが信頼関係構築のために最も重要だということを語っています。
「信頼を築くには、密なコミュニケーションが大事」といった回答をする方もいることと思いますが、どれだけ話してもどうも信頼できないといった類の人も世の中にはおそらくいます。
「矢面に立ち頑張る姿を見せる」というのも、半分正解だと感じる一方で、頑張ったけどできませんでしたという状態が続いた時に果たして信頼を得られるのかという疑問が残ります。頑張ることは間違いなく必要ですが、頑張ることにコミットするのでは不十分だと言えます。
相手のヴァリューにコミットするのは社会に出てからも容易なことではありませんし、学生のうちからその意識を持っているという方はほとんどいないと思っています。
働くようになってから、自分自身と環境の両面でコミットメント力というのは醸成されていくものだと本書では語っていますので参考にしてください。
◆自分でこの仕事を選んでいる、という意識がコミットメントを高める。
◆コミットメントは伝染するので、社内ではコミットメントの高い人の近くにいる。社内外問わず、メンターを作る。コミットメントが高い人に影響を受けられる環境を作ることが重要。
(『コンサル一年目が学ぶこと』p.256-257より)
最後に
『コンサル一年目が学ぶこと』というタイトルの書籍ですが、どんな業界・業種で働く上でも重要な示唆のある内容だと感じました。まずは本記事や書籍を読んでいただいて、その上でぜひ行動に移して、そして継続して欲しいと思います。
ちなみに、本でもセミナーでも何でも、情報を得て実際に行動できる人が30%、行動を継続できる人がさらにその30%などと言われているようです。
photo by Martin Thomas