【20卒慶應義塾経済学部】すーりなさんの就活体験記vol.2|2018.8 interview
8,750 views
最終更新日:2023年11月01日
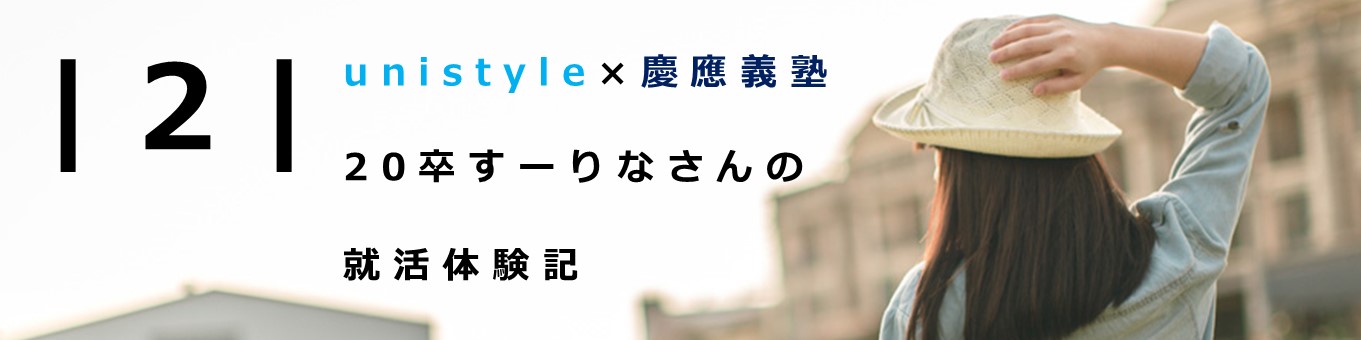
前期末テストもひと段落し、20卒の皆さんはインターンシップ選考が本格化してきた時期ではないでしょうか。
今回は慶應義塾大学経済学部のすーりなさんに2018年8月にインタビューした内容を掲載します。
【20卒慶應義塾経済学部】すーりなさんの就活体験記|2018.7 interview
慶應義塾大学 すーりなさんの履歴書
すーりなの履歴書
◆性別
└女性
◆大学
└慶応義塾大学経済学部に高校からの内部進学で合格。慶應以外は受けておらず検討もしていなかった。
◆趣味
└テニス(大学からサークル)・ピアノ(小さい頃から親の教え)・映画・旅行(国内も海外も)・ディズニー
◆サークル
└テニスサークルに所属。現在一般会員で今後幹部になりたいなどもそこまでない。
◆アルバイト
└居酒屋(3年半)・塾講師(4年)で働いている
◆留学
└半年カナダへ。海外に対しての興味はそこまでなく、海外で働きたいという欲はない。
◆資格
└自動車免許と英検2級。英検は高校時代に取得したもの。
◆就活をはじめた時期
└2018年6月頃
◆志望業界
└7月時点ではディベロッパーを希望。それ以外は見ていない。
◆希望職種
└まだぼんやりしているが営業。そもそも営業以外をあまり知らない。
本インタビューはunistyle編集部のむたか(@mutaka_unistyle)とくらもん(@esquestion)にて行っております。
7月の活動を振り返って
自分の活動量・内容について
 「7月の就職活動について教えてください。」
「7月の就職活動について教えてください。」
 「結局インターンESを数社提出したくらいですね。インターンにはまだ参加できていません。ただ、いくつかインターン選考には参加しました。」
「結局インターンESを数社提出したくらいですね。インターンにはまだ参加できていません。ただ、いくつかインターン選考には参加しました。」
 「ESは結局どこの企業に提出したの?選考状況と併せて教えて下さい。」
「ESは結局どこの企業に提出したの?選考状況と併せて教えて下さい。」
 「ESを提出したのは、三菱UFJ銀行と東京海上日動、森ビル、NTT都市開発、東急不動産、野村不動産の6社です。東京海上日動と野村不動産、三菱UFJの3社は書類通過して、他はまだ結果待ちというところです。」
「ESを提出したのは、三菱UFJ銀行と東京海上日動、森ビル、NTT都市開発、東急不動産、野村不動産の6社です。東京海上日動と野村不動産、三菱UFJの3社は書類通過して、他はまだ結果待ちというところです。」
 「どういう基準で提出する企業を選んだの?あとインターン選考に参加したということだったけど、面接とかGDには参加した?」
「どういう基準で提出する企業を選んだの?あとインターン選考に参加したということだったけど、面接とかGDには参加した?」
 「前回も言ったように、興味があるデベロッパーを中心に提出しました。視野を狭めたくないので、金融もいくつか提出してみたという感じです。選考に関しては、東京海上日動の集団面接と野村不動産のGDに参加しました。」
「前回も言ったように、興味があるデベロッパーを中心に提出しました。視野を狭めたくないので、金融もいくつか提出してみたという感じです。選考に関しては、東京海上日動の集団面接と野村不動産のGDに参加しました。」
・ES提出を中心に活動。提出数は6社ほどでディベロッパーと金融を中心に受けている。
・まだインターン本番への参加はしておらず、インターン選考に数回参加。
インターン選考について

「集団面接とGDに参加したということだけど、それぞれの選考内容について簡単に教えて下さい。」
 「東京海上日動のGDは8人程度の集団面接で学生時代頑張ったことについて聞かれました。野村不動産は6人程度のGDで3つの開発計画の中から1つを理由付けと共に発表するというものでした。」
「東京海上日動のGDは8人程度の集団面接で学生時代頑張ったことについて聞かれました。野村不動産は6人程度のGDで3つの開発計画の中から1つを理由付けと共に発表するというものでした。」
 「インターン選考全体を振り返ってみて何か反省はある?」
「インターン選考全体を振り返ってみて何か反省はある?」
 「反省というか、ESをもっと提出すればよかったなと思っています。テストが忙しくてES提出どころじゃなかったというのが正直なところです。同様に、もっとESを提出して面接とかGDを練習すればよかったなと後悔しています。」
「反省というか、ESをもっと提出すればよかったなと思っています。テストが忙しくてES提出どころじゃなかったというのが正直なところです。同様に、もっとESを提出して面接とかGDを練習すればよかったなと後悔しています。」
 「確かに、テストと被るとES提出もかなり大変だよね。何かGDに関して反省点はあるかな?」
「確かに、テストと被るとES提出もかなり大変だよね。何かGDに関して反省点はあるかな?」
 「GDは全然話せなかったというのが反省点ですね。自分自身でも全然出来なかったなという感覚です。周囲の人はこなれている感じで何か言おうとすると遮られてしまってなかなか発言出来ませんでした。あと面接では書いたESを保存するのを忘れていて、何をガクチカに書いたか分からなかったのも良くなかったですね。」
「GDは全然話せなかったというのが反省点ですね。自分自身でも全然出来なかったなという感覚です。周囲の人はこなれている感じで何か言おうとすると遮られてしまってなかなか発言出来ませんでした。あと面接では書いたESを保存するのを忘れていて、何をガクチカに書いたか分からなかったのも良くなかったですね。」
 「GDに関してはまずは場数を踏むことが大事だね。あとESに関しては何を書いたかくらいは覚えておかないと一貫性がないと捉えられかねないから、内容は保存しておいた方が良いね。面接は集団面接ということだけど、すーりなさんは何の経験について話したの?周りの人はガクチカとしてどんなことを話してた?」
「GDに関してはまずは場数を踏むことが大事だね。あとESに関しては何を書いたかくらいは覚えておかないと一貫性がないと捉えられかねないから、内容は保存しておいた方が良いね。面接は集団面接ということだけど、すーりなさんは何の経験について話したの?周りの人はガクチカとしてどんなことを話してた?」
 「私は、居酒屋でのバイトの話をしました。他の人は、部活のこととかボランティアのこととかを話している人が多かった気がします。飛び抜けてすごい経験をしている人はいなかった印象です。」
「私は、居酒屋でのバイトの話をしました。他の人は、部活のこととかボランティアのこととかを話している人が多かった気がします。飛び抜けてすごい経験をしている人はいなかった印象です。」
 「エピソードの内容自体で大きく差がつくようなことはあまり無いみたいだね。マリンの面接はフィードバックを貰えると聞いたけどどんなことを言われた?」
「エピソードの内容自体で大きく差がつくようなことはあまり無いみたいだね。マリンの面接はフィードバックを貰えると聞いたけどどんなことを言われた?」
 「やったことの内容は分かるけど、その中で困難だったことや苦労したことが伝わってこないと言われました。一応、unistyleのガクチカのフレームワークに沿って考えていったのですが。。。」
「やったことの内容は分かるけど、その中で困難だったことや苦労したことが伝わってこないと言われました。一応、unistyleのガクチカのフレームワークに沿って考えていったのですが。。。」
・GDと集団面接にそれぞれ1度ずつ参加。手応えは今一つのよう。
・選考の経験が少ないため、まずは場数をこなす必要があると思われる。
周りの活動量・内容について
 「友人たちはどう?どのくらい就活してる?」
「友人たちはどう?どのくらい就活してる?」
 「うーん、そうですね。。みんな結構インターンは出しているみたいですけど、そこまで詳しくわかりません。私が1年遅れているので周囲に就活をしている友達がいないし、そもそもあまり周囲と就活状況の共有とかはしないですね。」
「うーん、そうですね。。みんな結構インターンは出しているみたいですけど、そこまで詳しくわかりません。私が1年遅れているので周囲に就活をしている友達がいないし、そもそもあまり周囲と就活状況の共有とかはしないですね。」
 「1年遅れているということは、友達で就活が終わった人も多いと思うんだけど、どういう業界・企業にいった人が多いの?」
「1年遅れているということは、友達で就活が終わった人も多いと思うんだけど、どういう業界・企業にいった人が多いの?」
 「特にこの業界が多いというのはありませんが、強いて言うならばサークルは銀行とか金融が多い印象です。商社とかITもいますね。」
「特にこの業界が多いというのはありませんが、強いて言うならばサークルは銀行とか金融が多い印象です。商社とかITもいますね。」
・周囲と比較して大きく出遅れているということはなさそうだが、個人差が大きい模様。
・インターンシップに参加した学生も出てきた印象。
7月と8月を比較した変化
企業選びの軸
 「インターン選考に参加したことで就活の軸は少しでも明確になった?以前聞いたときは何も固まっていないということだったけど。」
「インターン選考に参加したことで就活の軸は少しでも明確になった?以前聞いたときは何も固まっていないということだったけど。」
 「いえ、まだ決まっていません。というか、特段軸を作る必要性も感じていません。周囲の人に聞いても、受けている業界、企業に合わせて軸そのものを変えている人が多くて、後付けのイメージが強いです。そもそも軸が必要なのかという疑問もあります。また、決めるにしても、軸となり得る要素が多すぎてどう絞っていけば良いのかも分かりません。」
「いえ、まだ決まっていません。というか、特段軸を作る必要性も感じていません。周囲の人に聞いても、受けている業界、企業に合わせて軸そのものを変えている人が多くて、後付けのイメージが強いです。そもそも軸が必要なのかという疑問もあります。また、決めるにしても、軸となり得る要素が多すぎてどう絞っていけば良いのかも分かりません。」
志望業界・職種
 「以前は、ディベロッパー志望ということだったけど、他に興味がある業界はあった?」
「以前は、ディベロッパー志望ということだったけど、他に興味がある業界はあった?」
 「いえ、志望業界に関しても志望職種に関しても特段変化はありません。まだインターンシップにも参加してないので、他の業界についてもよく分かっていません。」
「いえ、志望業界に関しても志望職種に関しても特段変化はありません。まだインターンシップにも参加してないので、他の業界についてもよく分かっていません。」
ガクチカ・自己PR
 「学チカ、自己PRについてはどうやって作ってる?」
「学チカ、自己PRについてはどうやって作ってる?」
 「unistyleのフレームワークを参考に作っていますが、これで良いのか分からないまま何となく作成しています。内容に関しては何を書くか悩んでいる状況です。いわゆるネタみたいなものが全然なくて。。」
「unistyleのフレームワークを参考に作っていますが、これで良いのか分からないまま何となく作成しています。内容に関しては何を書くか悩んでいる状況です。いわゆるネタみたいなものが全然なくて。。」
全体を通して
 「7月から就活を本格的にし始めたと思うけど、何か思うこととか感じたことはある?今の正直な気持ちを聞かせてください。」
「7月から就活を本格的にし始めたと思うけど、何か思うこととか感じたことはある?今の正直な気持ちを聞かせてください。」
 「正直に言うと、就活やりたくないなと思っています(笑)。面接とかGDへの恐怖心みたいなものはないのですが、落ちることで自分に自信がなくなってきます。ガクチカや自己PRに関しても固まっていないし、漠然とした不安を抱えています。」
「正直に言うと、就活やりたくないなと思っています(笑)。面接とかGDへの恐怖心みたいなものはないのですが、落ちることで自分に自信がなくなってきます。ガクチカや自己PRに関しても固まっていないし、漠然とした不安を抱えています。」
・企業選びの軸に関しては未だ明確になっていない。そもそも軸を設定する必要性を感じていない。
・ガクチカ・自己PRのネタ探しが難航している様子。ESの書き方よりもまずはエピソード探しをする必要がある。
8月にやろうと思っていること
 「ここまでを踏まえて、自己分析や業界企業分析等、何かやろうと考えていることはある?」
「ここまでを踏まえて、自己分析や業界企業分析等、何かやろうと考えていることはある?」
「7月は提出できたESが少なかったので、追加でESを提出しようと思っています。」
 「なるほど。まずはインターンに参加してみようということかな?」
「なるほど。まずはインターンに参加してみようということかな?」
 「そうですね。インターンにはできるだけ多く参加できればいいなと思ってます。」
「そうですね。インターンにはできるだけ多く参加できればいいなと思ってます。」
 「ES作成についてはどのように進めている?又は今後どのように進めていこうと思ってる?」
「ES作成についてはどのように進めている?又は今後どのように進めていこうと思ってる?」
 「できる限り自分一人でやろうと思っています。自分のESを他人に見られるのもあまり好きじゃないので。」
「できる限り自分一人でやろうと思っています。自分のESを他人に見られるのもあまり好きじゃないので。」
・とにかく提出するESの数を増やし、インターン参加を狙う。
・ES作成に関しては、誰かに頼るのではなく個人で進めていこうと考えている。
今就活で悩んでいること
 「今就活で困っていることとか悩んでいることはある?」
「今就活で困っていることとか悩んでいることはある?」
 「一番は、ガクチカのネタがないということですね。ESに書くことがなくて困っています。」
「一番は、ガクチカのネタがないということですね。ESに書くことがなくて困っています。」
 「塾講師のアルバイトやテニスサークルにも入っているみたいだから、そういった活動をガクチカとして書かないの?」
「塾講師のアルバイトやテニスサークルにも入っているみたいだから、そういった活動をガクチカとして書かないの?」
 「どちらも集団で何かを成し遂げた経験や目標を立ててそこに向かって努力した経験というのがないんですよね。自分自身のこういう強みを発揮しました!みたいなエピソードもないですし。自分自身、リーダーシップとか主体性がある方だとは思っていないので、集団で行なった経験があったとしてもそれをどう書けば良いかも分かりません。」
「どちらも集団で何かを成し遂げた経験や目標を立ててそこに向かって努力した経験というのがないんですよね。自分自身のこういう強みを発揮しました!みたいなエピソードもないですし。自分自身、リーダーシップとか主体性がある方だとは思っていないので、集団で行なった経験があったとしてもそれをどう書けば良いかも分かりません。」

「どうやってネタ探しをするか何か方法は考えてる?」
 「自己分析をして過去を振り返るしかないのかなとは思っています。まずは使えそうなエピソードを列挙するところからですかね。」
「自己分析をして過去を振り返るしかないのかなとは思っています。まずは使えそうなエピソードを列挙するところからですかね。」
・やはりガクチカのネタ探しに頭を悩ませている。
・自己分析を行い、ガクチカのネタとなり得るエピソードを探す予定。
unistyle編集部より
すーりなさんへのフィードバック
本格的に就職活動を始めて、インターン選考にも参加したようです。初めてのGDや集団面接にも臆することなく参加している点は、彼女の良い点と言えるでしょう。選考に参加するという一歩が踏み出せない学生がいる中で、まずはどのようなものか経験してみようという彼女の考え方は、チャンスを逃さないためにも重要なことです。
インターン選考に関しては「GDで発言をすることができなかった」、「ガクチカにおける困難、苦労が伝わらない」等反省点も多いようです。
GDの発言量については、上記でも述べたように"慣れ"による部分が大きいと思います。まずは場数をこなし、グループの中での自分の立ち位置を見つけることから始めるべきではないでしょうか。
誰しも得意、不得意があるはずなので、無理にリーダーや調整役などをやる必要はなく、自分に最適なポジションを担うよう心がけましょう。GDで最も重要なのは、チームとして良い結論を導くことですので、チームの成果を最大化するために自分に出来ることは何なのかを常に考えるようにしましょう。
ガクチカについては、そもそものネタ探しの段階から難航しているようです。エピソードのインパクトの大きさが評価に直結する訳ではありません。ガクチカで重要なのは、自分の人柄や考え方から企業で活躍できる人材であることを伝えることです。
そのため、「なに」をやったかも大事ですが、それ以上に大事なのは「どのように」取り組んだかということです。
もっとも、企業という組織に属する以上、自分一人ではなくチームで何かを成し遂げた経験の方が企業への適性をアピールできるでしょう。リーダーシップを発揮した経験でなくとも、自分自身が組織に対してどのように貢献できたかが伝わるエピソードであれば、あなた自身の強みを十分伝えることができると思います。
すーりなさんへのオススメ記事
今回、すーりなさんには日経大手の夏インターン選考の定番である「グループディスカッション」に関する記事を一読することをおすすめします。
【1】グループディスカッション(GD)完全対策!企業の意図・役割・議論の進め方まで
→グループディスカッションの評価基準や進め方、グループディスカッションの能力を高める方法をひと通り理解できます。選考突破の上で最低限抑えるべき点をまとめているので、まだグループディスカッションに参加経験がない方はもちろん、参加経験がある方も選考の前にも目を通して頂きたい記事です。
【2】グループディスカッションの対策|個人での対策方法と面接への活かし方
→グループディスカッションで出題されるテーマ・お題の具体例からこれらのテーマ・お題に対して、論理的に結論まで導くことのできる力を養うために必要な対策方法について説明していきます。
【3】グループディスカッションの評価基準とは
→グループディスカッションでは何が評価されているのか、評価項目を4つのポイントに分けて解説していきます。どのような行動が評価されるのかといった点にまで落とし込み、未経験の方にもわかりやすく説明していきます。
Vol.3は9月に公開予定
【20卒上智理工学部】デニナギくんの就活体験記vol.2|2018.8 interview
【20卒早稲田教育学部】あとむくんの就活体験記vol.2|2018.8 interview
【20卒早稲田政治経済学部】乃木鮭くんの就活体験記vol.2|2018.8 interview









