総合商社出身の起業家まとめ
41,915 views
最終更新日:2023年10月26日

ここ数年の就職人気ランキングで上位を独占している総合商社。16卒就活生対象に行ったUnistyleの意識調査においても第一志望群企業人気ランキング上位5社を独占しました。
そして今回はその総合商社から独立した起業家を紹介します。
総合商社は外資系投資銀行と比較すると給料は落ちるものの報酬、人材ともに非常に優れており、基本的には身を埋めるつもりで入社する人が多いです。
その充実した環境から自ら退き、独立した起業家が以下となります。(敬称略)
堀 義人(ほり よしと、グロービス経営大学院大学学長)
1985年 京都大学工学部卒業後、住友商事に入社
1992年 株式会社グロービス設立
1996年 グロービス・キャピタル設立
1999年 エイパックス・グロービス・パートナーズ(現グロービス・キャピタル・パートナーズ)設立
2006年 グロービス経営大学院を開学。学長に就任
若手起業家が集うYEO(Young Entrepreneur’s Organization 現EO)日本初代会長、YEOアジア初代代表、世界経済フォーラム(WEF)が選んだNew Asian Leaders日本代表、米国ハーバード大学経営大学院アルムナイ・ボード(卒業生理事)等を歴任。現在、経済同友会幹事等を務める。2008年に日本版ダボス会議である「G1サミット」を創設し、2013年4月に一般社団法人G1サミットの代表理事に就任。
27歳の時にハーバード・ビジネス・スクールに留学をし、その教育方法に衝撃を受けた同氏。そこでの主語は常に「自分」で、最後にその問いは、「自分は何をするために生まれてきたのか」という自らの生き方への問いかけにつながっていたそうです。グロービス経営大学院は学びの場とビジネスの現場の距離感を縮めて、経営者として必要なスキルと志を鍛え、「経営学を教える」大学院ではなく「経営者を育成する」として開学したとのことです。
安達 保(あだち たもつ、カーライル・グループマネージングディレクター兼日本共同代表)
1977年 東京大学工学部機械工学科卒業後、三菱商事に入社
1982年 マサチューセッツ工科大学にてMBA取得
1988年 マッキンゼー・アンド・カンパニー
1995年 同社パートナーに就任
1997年 GEキャピタル・ジャパンに入社。事業開発本部長へ
1999年 日本リースオート代表取締役社長に就任
2000年 ジーイーフリートサービス代表取締役社長に就任
2003年 カーライル・グループに参画。マネージングディレクター
日本代表に就任
三菱商事株式会社に10年間勤務。在籍中、1984年から1987年の3年間は第二電電(現KDDI)に出向。同社の立ち上げと長距離電話サービスの開始に貢献。マッキンゼーのパートナー就任後は主に製造業、ハイテク企業の製品市場戦略、企業ビジョンの策定に従事。現在、株式会社ベネッセホールディングス、ヤマハ発動機株式会社の非常勤取締役。2009年1月から2011年6月まで日本プライベート・エクイティ協会の会長を務める。
英語が話せなかったら上のようなキャリアを切り拓けなかったという同氏。なんと英語を勉強し始めたのは2歳の頃だったとの事です。特に中学生になってからは読み書きを中心とした勉強に力を入れ、学年でトップの成績だったそうです。大学4年生の時にはインターンを通じてスウェーデンの鉄鋼メーカで働いたものの、メーカーの研究所で働き続ける事は 性に合わないと感じ、三菱商事への入社を決めたそうです。
澤田 貴司 (さわだ たかし、株式会社リヴァンプ代表取締役社長兼CEO)
1981年 上智大学卒業後、伊藤忠商事入社。
1997年 ファーストリテイリング入社。常務取締役就任
1998 年 同社副社長に就任
2003年 キアコン設立、代表取締役社長に就任
2005年10月リヴァンプ設立、代表取締役に就任
伊藤忠商事では化学品営業、流通プロジェクトを担当。イトーヨーカ堂とセブンイレブン・ジャパンプロジェクトに参画、米国セブンイレブンの買収に携わる。ユニクロ時代は店長候補からスタートし、半年後には常務商品本部長に、翌98年に副社長に就任。営業部署の責任者としてユニクロの急成長に貢献。キアコンを畳もうと考えていた際に現ローソン社長の玉塚氏から電話をもらい、会社を芯から元気にする企業再生を請け負う株式会社リヴァンプを玉塚氏らと立ち上げた。
ユニクロ副社長時は柳井社長の後継者ともいわれたほどの人物です。伊藤忠商事からユニクロに移ったきっかけは経営破綻した米セブンイレブンをイトーヨーカ堂グループが買収する案件だったそうです。当時のイトーヨーカ堂の経営陣がアメリカに乗り込んで日本の近代化された経営手法を丁寧に伝達していく様子を見た同氏は旧態依然とした経営を変革出来たら百兆円以上にものぼる流通産業が劇的に変わると感じ、ユニクロへの入社を決意したとの事です。
内田 陽介(うちだ ようすけ、みんなのウェディング代表取締役社長兼CEO)
2000年 慶應義塾大学卒業後、三菱商事に入社
2000年 株式会社アイシーピー入社。シード・アーリー段階のIT系ベンチャー企業への投資後における育成を担当
2003年 株式会社カカクコム入社。その後カカクコム取締役、フォートラベル株式会社取締役を歴任
2013年 オフィス内田代表就任
2014年 株式会社みんなのウェディング代表取締役社長兼CEO就任
カカクコム在籍時には新規事業立ち上げ、価格.com運営などに携わる。株式会社コアプライス(現 株式会社カカクコム・インシュアランス) 取締役も歴任。
結婚式を生涯最良の思い出にしたいとする場合に業界からの一方通行でしか情報が得られない現状に疑問を感じた同氏はみんなのウェディングへの参画を決心したとの事です。みんなの願いを一緒に実現する会社を会社を目指していく上でウェディング関連市場に止まらず、インターネットによってイノベーションを起こし、ユーザーの利便性を向上させることができる領域に踏み込んでいこうとしているので今後も楽しみな会社です。
寺田 親弘(てらだ ちかひろ、SanSan株式会社代表取締役社長)
1999年 慶應義塾大学環境情報学部卒業後、三井物産に入社
2001年 情報産業部門で、シリコンバレー勤務も含め、日米のIT業界に精通
2007年 Sansan株式会社を設立。BtoBの名刺管理サービス「リンクナレッジ(現・Sansan)」を開始
2012年には、個人向け無料名刺管理アプリ「Eight」を開始
三井物産では情報産業部門にて、コンピュータ機器の輸入、システム開発、 Joint Venture立上等に従事した後、米国シリコンバレーに転勤となり、米国最先端ベンチャーの日本 向けビジネス展開を担当。帰国後は、自らが持ち帰ったデータベースソフトウェアの輸入販売を、社内ベンチャーとして立ち上げる。
ビジネスマンとしてキャリアをスタートした時に名刺のあまりの非効率さに衝撃を受けたという同氏。当時は様々なものがIT化を果たしていた事に着目した同氏は名刺の効率化を考えつき、起業をしたとの事です。
澤 博史(さわ ひろふみ、データセクション株式会社代表取締役社長兼CEO)
1991年 大阪市立大学理学部を卒業後、富士通に入社。
2004年 双日に入社
2008年 株式会社イーライセンス社外取締役に就任
2009年 データセクション株式会社の代表取締役に就任
富士通ではB to Cポータル(@niftyポータル)やB to Eポータル(B-Front)等のインターネット系のサービス開発を実施するなど、プログラミングから新規事業開発まで幅広い業務経験を持つ。その後、双日を経て大手事業投資会社にチーフプロデューサー(統括部長相当)として入社。ベンチャー会社への事業投資、企業のビジネスプラン作成から新規サービスの立上げ、M&A等に従事。
もともと富士通に入社する頃から起業家志向が強く、いずれは会社を立ち上げて世の中を変えられるような何かを作りたいと考えていたという同氏。「世界で通用するビジネスモデルとは何なのか」を色々と考え自分なりに三つ編み出したそうです。 一つ目はソーシャルメディアを分析し様々な発見を通じビジネスにつなげるもの。そして、アニメや音楽などのコンテンツビジネスモデル。最後にオンラインでのビジネスモデルだったそうです。そして、その延長線上で起業したようです。
天野 太郎(あまの たろう、オフィスバスターズ代表取締役社長)
1993年 名古屋大学経済学部卒業後、丸紅に入社
2002年 株式会社アトライを創業
2003年 株式会社オフィスバスターズを設立
丸紅では事務機器販売を担当し、ロシア・米国駐在を経る。アトライにて中古事務機の輸出事業を営む一方、株式会社テンポスバスターズと共同出資にて株式会社オフィスバスターズを設立し、代表取締役に就任。
起業を意識し始めたのは中学生の頃だったという天野氏。しかし下積みとして一度大企業に勤めてビジネスを学ぼうと考え、ビジネスを幅広く学べるという理由から商社への入社を決めたようです。途上国での取引先の一言から中古品の販売を行う事で社会問題の解決をできるような会社であるアトライを設立との事です。
船橋 力(ふなばし ちから、ウィル・シード代表取締役会長)
1994年 上智大学卒業後、伊藤忠商事入社
2000年 株式会社ウィル・シード設立。企業と学校向けの体験型・参加型の教育プログラムを提供を設立し代表取締役に就任
2012年 同社取締役会長、学校法人河合塾顧問に就任
伊藤忠商事ではジャカルタ地下鉄推進プロジェクトなどを手がけていました。その同時期にウィル・シードのコアコンテンツとなる「SEED」の前身にあたるゲームを実施する異業種交流会「LPC」を設立しました。
高校時代をブラジルで過ごした同氏。そこで受けた教育というのは、日本の詰め込み・暗記型のものではなくて、議論させたり、実際に何かを体験させたりすることが多く、そこで学んだ内容は現在の船橋氏にも多く残っているそうです。大学卒業後の世界旅行経験から学校教育をなんとかしたいという思いに至り、トレーディング・ゲームを学校現場に広げたいと考え、2000年に起業を決意したそうです。
河野 貴輝(かわの たかてる、株式会社ティーケーピー代表取締役社長)
1996年 慶應義塾大学商学部卒業後、 伊藤忠商事に入社
2000年 イーバンク銀行(現・楽天銀行)に入社
2005年 株式会社ティーケーピー設立。代表取締役に就任
学生時代、アルバイトでためた資金で株式投資を始め、痛手を被ったことで勉強不足を自覚し、財務会計ゼミで学ぶ。この世界でプロになることを目指し、卒業後は「目的別採用」を導入していた伊藤忠商事に就職、為替証券部に配属。4年間、ディーラーとして活躍した後、日本オンライン証券(現・カブドットコム証券)の設立にかかわる。2000年、上司とともに退職し、上司が代表として設立したイーバンク銀行(現・楽天銀行)に4年間在籍、取締役営業本部長などを歴任。2005年、独立し株式会社ティーケーピーを設立。
就活生の皆さんも一度はTKP貸し会議室を利用したことがあると思います。同氏は世の中の無駄な資産・事業を再生して新しいものに仕立て上げたいという思いから使われていないオフィスビルや結婚式場、ホテルなどのスペースをキャッシュ化することに着目したとのことです。TKPは、その命題に金融の知見やITを活用して事業化に成功、設立5年で売上高35億円と急成長しました。そしていまでは日本全国の主要都市に直営、運営受託含めて500室を超える貸会議室を展開しています。今後の成長にも期待ですね。
中松 義郎(なかまつ よしろう、発明家)
通称:ドクター中松
1953年 東京大学工学部卒業後、三井物産に入社
1959年 イ・アイ・イに入社。専務、副社長を歴任
1971年 同社社長との対立から独立し、ナコー(現在のドクター中松創研)を設立
2005年 ノーベル賞のパロディであるイグノーベル賞(栄養学賞)を受賞
5歳で最初の発明をし、14歳で灯油ポンプ、19歳でフロッピーディスク、カラオケ、ファクシミリ、カテーテル、無線消化器体内検査装置、人工心臓、燃料電池などで発明件数は3367件以上になり、エジソンの1093件を抜き世界第1位とされている同氏。
東京都知事選や衆議院、参議院選に挑戦し続ける同氏。実は三井物産の出身でした。奇抜な発明家として知られた事をきっかけにバラエティ番組での露出が増えたとの事です。選挙に出続ける理由として「元来、政治家は国のために働くもの。『国のため』という気概をどの程度が持っているかが重要なポイントだ」という発言をしていました。
戸並 誠(となみ まこと、実業家、政治活動家)
通称:マック赤坂
1972年 京都大学農学部を卒業後、伊藤忠商事に入社
1997年 レアメタル輸入販売会社「マックコーポレーション」設立
2004年 財団法人スマイルセラピー協会会長
2006年 日本スマイル党を結成し、政治活動を開始
2007年 港区議会議員選挙に出馬するも落選
2009年 政治団体の名称を現在のスマイル党に変更
大学生ならば一度は見かけた事があると思います。選挙に何度も出馬し、独特な政見放送と選挙活動から知られているマック赤坂さんは伊藤忠商事出身でした。伊藤忠商事に勤務していたころ、アメリカへ行ってハンバーグを食べると、よく「ビッグマック」といわれたそうです。そして一番弟子にはマック赤坂見附さんがいるとの事です。
最後に
以上、総合商社出身の起業家を紹介しました。外資系コンサルや外資系投資銀行出身の起業家についてはイメージがあるけれど総合商社出身の起業家はイメージがないという方の参考になれば幸いです。今回はどのような想いで起業されたのかといった点にも焦点を当ててご紹介しましたので、今後のキャリアや就職活動の選択の参考にしてください。
photo by Kay Kim


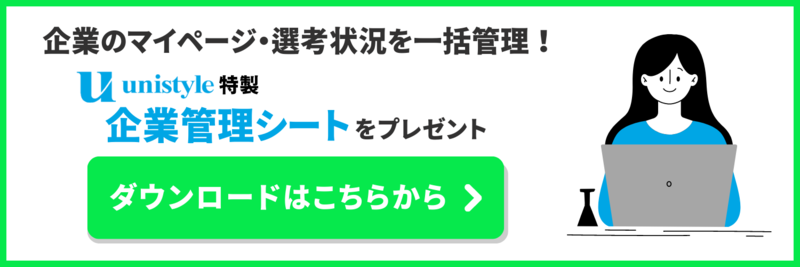



.png?1720673623)




