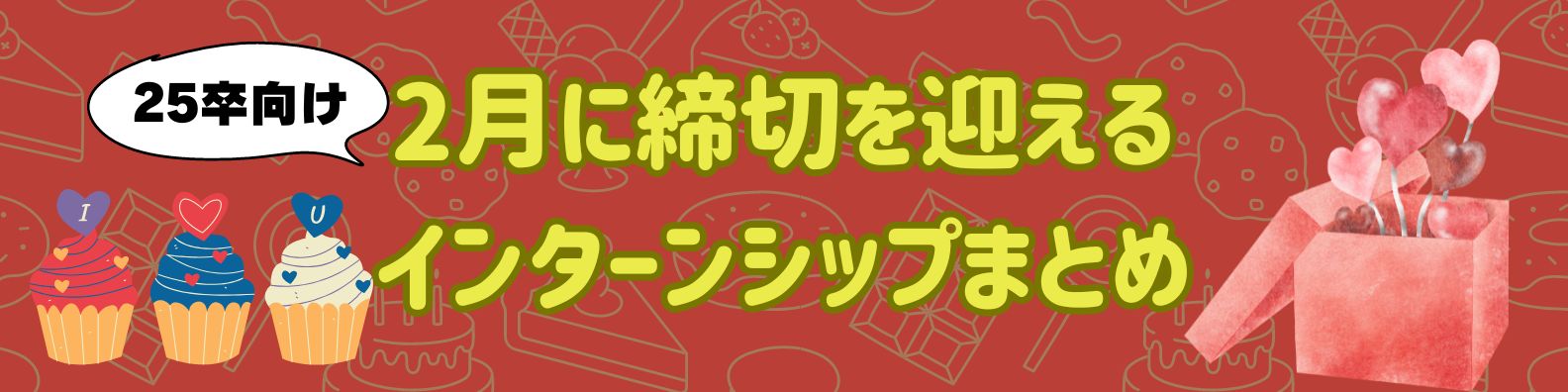東京海上日動火災保険のインターン面接は最高の自己分析ツール
125,556 views
最終更新日:2024年10月25日

16卒就活生です。
今回は夏インターンついての記事です。
外資系の企業を筆頭に通過難易度の高い企業がひしめいていますが、今回はその中から筆者が実際に体験して、落選はしたものの、その後のインターン面接や本選考で良い結果を出す糧となり、ぜひみなさんに自己分析ツールの一つとして強くオススメしたい東京海上日動火災保険のインターン面接に関して書かせてもらいます。
東京海上日動火災保険のインターン実施時期

夏、冬、春と3回チャンスがあります。
ただ例年の傾向でいうと、夏と冬のインターンは5日間、春のインターンは2日間となっていますので、ぜひ夏からチャレンジして欲しいと考えています。
東京海上日動火災保険のインターン選考フロー

(1)書類選考
まずはエントリーシートです。学生時代の取り組みに関して200字程度で簡単に訊かれます。結論ファーストで読み手が最後まで目を通すような書き方をしましょう。
(2)1次面接
研修会館にて簡単な説明会とグループワークが行われます。しかしこのグループワークに関しては社員はほとんど見ていない為、ほぼ選考には関係ないと考えて良いでしょう。
グループワーク後は別室にてグループ面接に移ります。非常にフランクな雰囲気で行われますが、面接を初めて受ける学生が多いので学生側は非常に緊張しています。仏像のような学生もいます。
こちらのコラムで紹介されているようなミステリアス就活生もいるので注意してください。
グループ面接は6人〜8人で五十音順に1人5分という時間を与えられて一人ずつ進みます。
ここで訊かれるのは「学生時代頑張ったことに関して」です。ここではコミュニケーションがしっかりとれているか、質問に対して適切かつ簡潔に答えられているかが選考の基準です。
なるべく面接官に多くの質問をしてもらうことが通過の鍵です。通過者には後日、最終面接の案内が届きます。
(3)最終面接
こちらについては次の項目で詳しくお伝えします。
東京海上日動火災保険の最終面接で問われること

学生一人に対して面接官一人か二人で行われます。時間は30分程度です。
この面接は特徴的で、就活生がどのような人生を送ってきたかを訊かれ、それに対していかに自分を分析できているかを問うものです。ちなみに志望動機と金融に関する知識は一切問われません。
以下質問例です。
質問例
・幼少期をどういった環境で過ごし、何を考えてきましたか?
・
小学生の時はどんな子供でしたか?
・
自分の強みや弱み(複数)はなんだと思いますか?
・
人生の数ある決断を、どういった思考のも...
このコンテンツは会員(無料)の方のみご覧になれます。
また、会員(無料)の方は82188枚のエントリーシートを全て閲覧可能になります。
(無料会員登録はこちら)
最後に

筆者は冬のインターン面接で落ちましたが、そこでの教訓を糧にその後の他社のインターン選考および本選考で面接官が何を求めているのかがわかり、自己分析にも活かすことができました。
インターン自体も参加すると本選考での1次面接が免除されたり、人事に顔を覚えられたりと良いことづくめなので、就活生にはオススメのインターンです。





.png?1719197661)