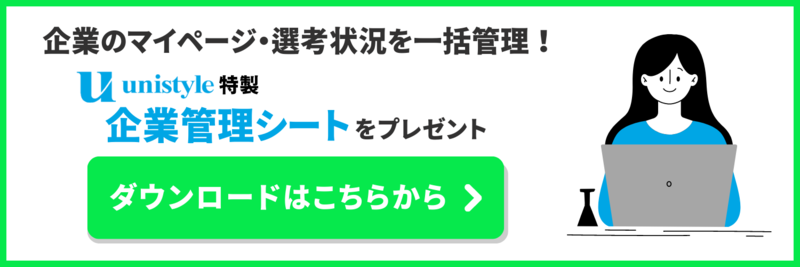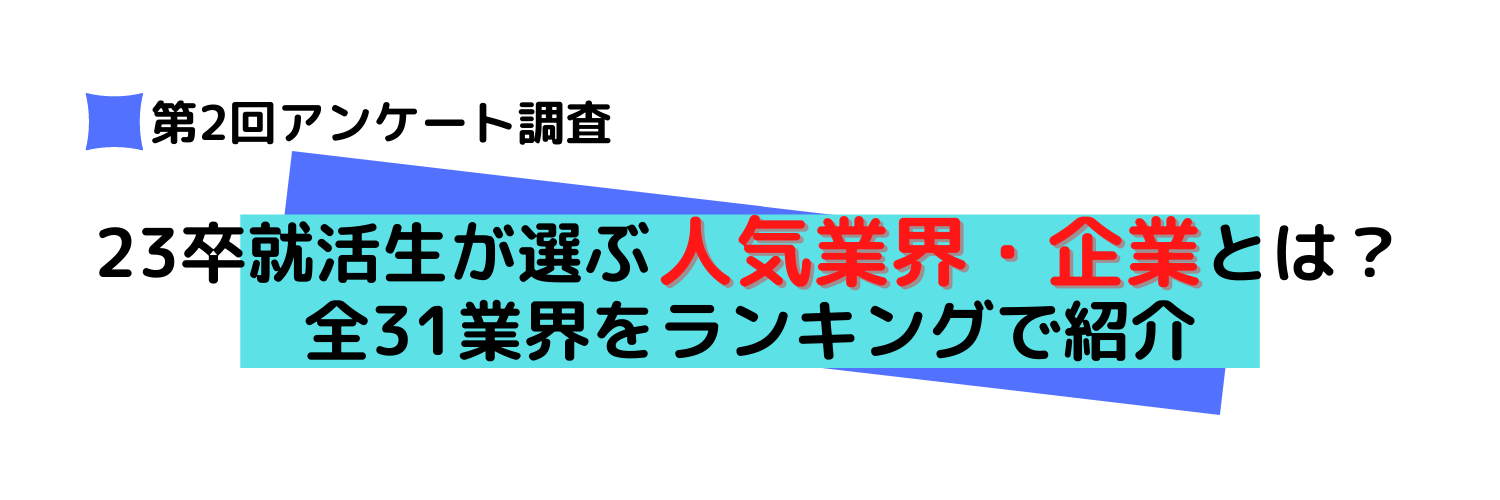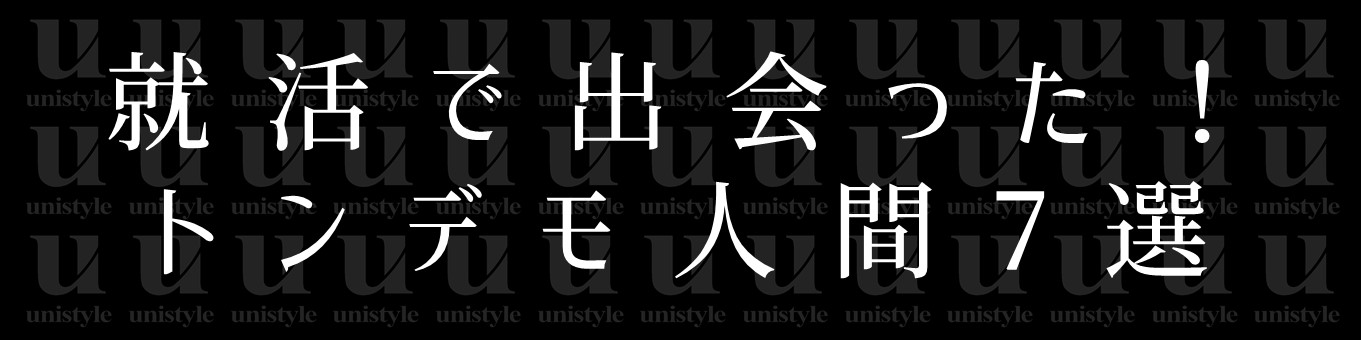書評:『絶対内定シリーズ2018インターンシップ』
15,897 views
最終更新日:2023年09月28日
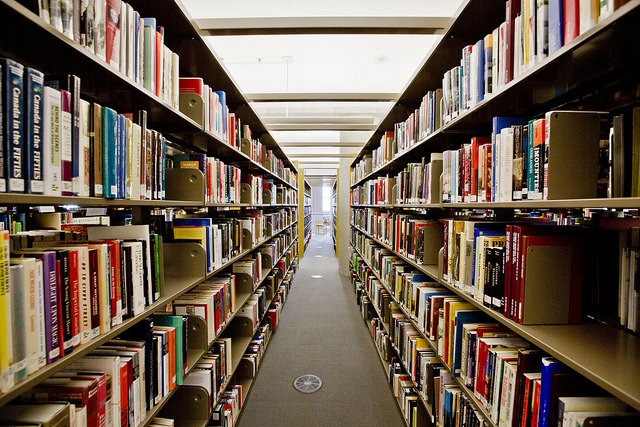
こんにちは、17卒の金融機関内定者です。
今回は、毎年多くの就活生が読んでいると思われる『絶対内定』シリーズの最新作を紹介します。インターンシップに関する情報が網羅されているため、これからサマーインターンシップへの参加を検討している方には非常に参考になる一冊だと思います。
私自身の話ですが、全く興味のなかった金融業界のサマーインターンシップに参加して志望業界の幅が広がり、最終的に金融機関への入社を決断しました。サマーインターンシップがなければ私の就職活動の方向性も全く違うものになっていたと思います。
インターンシップは今後のキャリア選択の上でもかなり影響度の高い要素であり、後輩の皆さまにも積極的に参加して欲しいですし、また、インターンシップを選ぶ際には本コラムで紹介する『絶対内定シリーズ2018インターンシップ』が役に立つと思っています。
(※本コラムは『絶対内定』およびキャリアデザインスクール我究館のPR記事です)
『絶対内定シリーズ2018インターンシップ』は、以下のような背景でインターンシップの指南書として発売されました。
・近年ではインターンシップを開催する企業、参加する学生がともに増加しており、インターンシップに参加する学生は約4割にも達している。
・大手企業の約8割がインターン生に内定を出しているということもあり、就職活動においてはインターンシップが切っても切れない関係となっている。
※「就職白書2016」リクルートキャリア就職みらい研究所調べ
また、本書では次から紹介するように、インターンシップの意義から具体的な選考対策、さらには参加後の反省ポイントまで網羅して伝えています。
インターンシップに参加する4つのメリット
インターンシップに参加することによる特徴的なメリットとして、本書では下記を挙げています。
「より具体的な企業研究ができる」
「本選考で優遇されることがある」
「学歴・英語力などで不利な学生にもチャンスがある」
「『学生時代がんばったこと』としてアピールできる」
私自身1週間のサマーインターンシップに参加して、グループワークの中で業務の理解を深めることができ、同時並行で業界研究をすることができました。また、インターンシップ後も色々な部署の方のお話を聞く機会が得られました。
そして本選考の際には1次面接が免除され、インターンシップのメリットを感じました。
インターンシップの選び方
本書では、「絞って参加 or とにかく多く参加」など8つの判断基準が書かれています。判断基準によって、インターンシップに向けた自分なりの戦略が得られると思います。また、そもそもの判断のためには自分が将来どうしたいのかについて考えておく必要があると思います。
また本書では、次のような「ヤリタイコト」を具体化するための5つのステップを紹介しています。
(1)「ヤリタイコト」をコトバにする
(2)「どこの、誰の、何のための」ヤリタイコトなのかをコトバにする
(3)「ヤリタイコトが実現できる業界」を探す
(4)インターンで知りたいことを言語化する
(5)自分が知りたいことを明確にできるインターンを探し、参加する
なお、インターンの段階ではまだ具体的にこの仕事をーーというところまで明確にする必要はなく、まずは自分の考えをコトバにするところから始めてみようとも伝えています。
私自身、サマーインターンシップの時期にはまだまだ世の中にどんな仕事があるのかもわからずにいました。何となくでもいいので、こんな働き方をしてみたいということを言葉に落とし込んでみるというのは考えを深める上で有効だと思います。
各種選考対策
エントリーシート、面接、グループディスカッション、グループワークなど一連の選考対策についても記載されています。
エントリーシートや面接については頻出の設問・質問およびその意図を説明しており、それ以外も全体を通して採用担当者の目線でどういった学生が評価されるのかを伝えていっています。
独りよがりに闇雲な選考対策をするよりも、本書などを参考に、企業が欲しいと感じる人材はどういったものなのかを考えた方が筋のいい対策になるように思います。
うまくいかなかったときどうするか
「1dayばかり参加して得られるものがなかった」
「なんとなく5daysをいくつか受けていたら秋になっていた」
「行きたいと思っていた企業のインターンに落ちてしまった」
「そもそも行きたい企業がインターンを実施していない」
これらの場合についてそれぞれ起こすべきアクション、心の持ち方について書かれています。
個人的には、これらがうまくいかなかったと捉えるかどうかもその人次第であると思います。例えば「行きたいと思っていた企業のインターンに落ちてしまった」場合、そもそも自分がその企業やその業界とマッチしているのかどうかを考え直すきっかけになると思います。
情報過多に陥らず取捨選択することが大事
どの企業のインターンシップに参加しようか、そもそも参加するかどうかなど、悩んでいる方はたくさんいらっしゃると思います。
本書に書いてある通り、「現時点でベストと思えるヤリタイコトや目標」・「8つの判断基準」を念頭に置いてインターンシップ選びをすると、参加してよかったと思えるインターンや結果(内定)につながるインターンが見つかるのではないでしょうか。
就職活動の時期には、先輩から色々な話を聞くことがあると思いますし、また、インターネット上にも情報があふれています。あるいは、本書のような就活関連本を読まれることもあると思います。
その中で情報を取捨選択しながら、インターンシップはもちろんその先のことも考えて意思決定をしていただければと思います。
最後に:『絶対内定』シリーズ著者 熊谷智宏氏とは
本書含む『絶対内定』シリーズの著者である熊谷智宏氏は、キャリアデザインスクール「我究館」の館長です。新卒でリクルートに入社後、我究館を運営している株式会社ジャパンビジネスラボに参画し、これまでに2,800名以上の学生・社会人の就職・転職をサポートしています。
unistyleでも我究館についてのコラムを複数掲載しているので、以下も読んでいただければと思います。
なお、我究館では無料説明会を開催しています。下記のリンクから申し込めるので、興味のある方は足を運んでいただければと思います。
photo by GoToVan