【第4回:現役コンサルタントが語る】「コンサルタント」という言葉の響きに憧れを感じた時に読む話
36,023 views
最終更新日:2023年10月27日
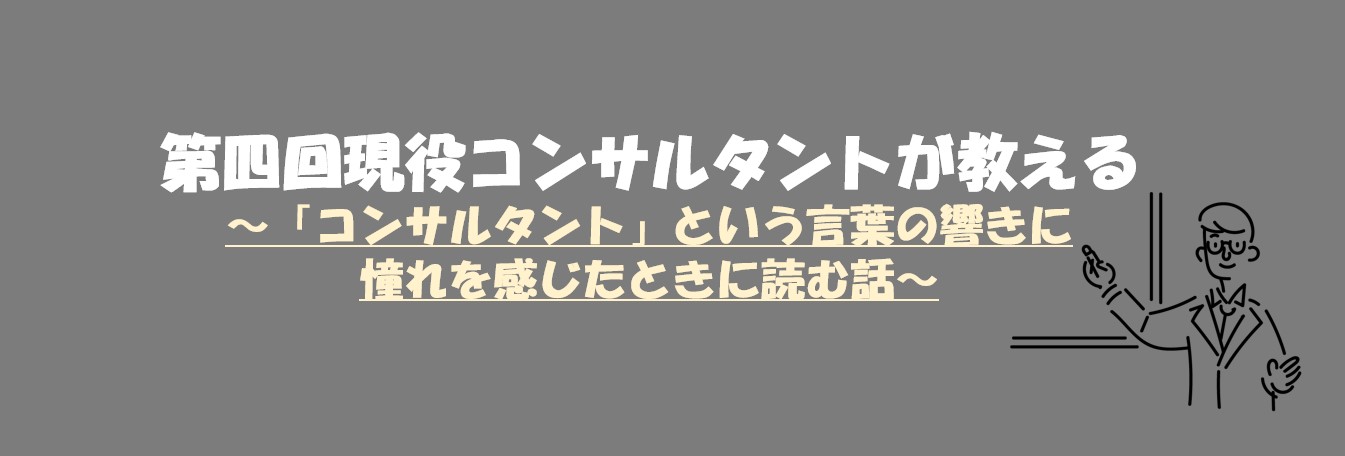
株式会社コーポレイト ディレクション(CDI)の現役コンサルタントによる全4回のシリーズ寄稿です。
**********
【前回の記事はこちら】
▶︎▶︎▶︎【第3回:現役コンサルタントが語る】解を導くのがコンサルの仕事か?
**********
戦略コンサルタントは、難しい問題にもパキパキと答えを出していくスマートな仕事、という憧れを抱いたことのある方もいるかもしれません。しかし、これまでの3回分のコラムを読んでくださった方であれば、戦略コンサルティングとは愚直に考え続けることが求められ、決してスマートな仕事ではないことがお分かりいただけたと思います。
すでにいい具合に「憧れ」を崩せているとは思うのですが、今回はさらに追い打ちをかけるべく(笑)、どういう心構えでこの業界に飛び込んでいただきたいか、お伝えしたいと思います。
「自分の頭で考え続ける」ことのプレッシャーに耐えられるか?
第3回のコラムでは、戦略コンサルタントの本質的な価値は解を導くことではなく認識を示すことであること、また、認識を示すことがいかに大変かについて、お伝えさせていただきました。
認識にかかわるプロセスは、新米コンサルタントも熟練コンサルタントも平等にかかわることが求められます。
とはいえ、新米コンサルタントが最初から議論をリードできることはそうそうありません。ではどうすれば勝負できるかというと、事前にとにかく時間を取って深く考えてから議論の場に臨む、くらいしか方法はありません。概念的には、能力×掛けた時間=アウトプットの質、ですから、能力が不充分なうちはとにかく掛けた時間で勝負するしかありません。
しかしながら、新米コンサルタントはそれと同時に基礎力としての「解を導く力」も身につけていかなければなりません。いくら始めに「こうだと思う」と認識することが本質とはいえ、その後で思ったことが正しいと証明できなければ意味が無いからです。前回のコラムで挙げた例で申し上げると、解を導くための「高校までの勉強」と、解くべき問いを立てるという「大学の研究」を同時にやることが求められます。
よって、新米コンサルタントとして入社すると、まずは時間的プレッシャーと、自分の頭で考えて自分の言葉で何か言わなければならないという精神的プレッシャーにさらされることになります。新米コンサルタントの生の声として、「調査分析の作業に追われて大変だ」という言い方をされることがありますが、本質は少し違っていて、「調査分析の作業に追われながら、自分の頭で考え続けなければならない」ことが大変さの根源です。
作業時間の確保は最悪体力で何とかなりますが、自分の頭で考え自分の認識を示すことには、精神的なプレッシャーも伴います。プロジェクトチーム(およびそのメンバーである自分)の認識・発言で、クライアントの重要課題に関する明暗が分かれる。「そもそもこの『問い』を解くことが本当に正しいのだろうか」「本当にこの提言でよかったのだろうか」。こういった思いは、経験年数にかかわらずどんなコンサルタントでも常に持っている孤独な不安であると思います。常に不安と向き合っているからこそ、極端な話、報告の前日であっても、伝えるべきメッセージが違うと思えば報告書の大幅な組み直しも辞しません。
この考え続けるプレッシャーに耐えられるか、もしくはその状況すら楽しんでしまえるかは、コンサルタントとしてきわめて重要な資質になります。第2回のコラムで、考えることが好きな人を好評価しているとお伝えした根本的な理由は、ここにあります。
「腰を据えて」取り組む覚悟はあるか?
解を導く力は技能に近いので、一定以上の能力を持つ人であれば、しばらく時間を掛けて真面目に取り組めばできるようになる属性の能力です。一方、認識する力とそれを伝える力は、明確な正解が無い分、すぐにできるようになるものではない上、どこまで行っても究めきったというゴールが無い属性の能力です。
コンサルティングの本丸である認識の領域で充分なパフォーマンスをするには、個人的な目安としては最低でも3年以上は腰を据えて取り組む必要があると思いますし、そこから先は何年働いてもゴールは無いと思っています。無論、ただ年数を過ごせば良いわけではなく、その間ずっと、前述の精神的プレシャーにさらされ続けることになります。
実際に、私自身もコンサル業界の平均勤続年数と言われる3年よりも長く働いていますが、できるようになったことが増えた分だけ(あるいはそれ以上に)できないことが見えてきて、特に認識を示すという点では、まだまだ先は長いという思いです。(私が根から優秀なタイプではないので時間がかかっているという要因もあるでしょうが(笑))。
もちろん、3年経たずに他にもっとやりたいことが見つかって業界を離れる人もたくさんいますし、私達もそういう場合は喜んで送り出しています。ですがそれはあくまで結果論であり、入社する時点から数年での転職を前提にしている人は、じっくり考え続けるというこの仕事には合わないと考えます。何より、コンサルティングの本丸である認識を示す仕事に特に興味が無いまま入社し、深く携わることなく短期間で出て行ってしまうのは、単純にもったいないと個人的には思います。
CDIのように少人数採用のファームは特に、入社前に「腰を据えて」取り組む覚悟があるかどうかをしっかり見極めるために、採用される側とする側が悪い面も含めて「本音で」語り合って合意形成することを大切にしています。過去に多数の企業の選考を受けたことのある弊社の中途社員の中には、「面接でこんなにネガティブキャンペーンをされた会社は他に無かった」と言う人もいるほどです(笑)。
戦略コンサルは「勉強の場」として目指す場所ではない
ここまで考えると、よく言われるような「勉強になりそうだからとりあえずコンサル」といったモチベーションだけで続けられるような仕事ではないことがお分かりいただけると思います。
こういった場合に勉強したいこととして挙げられる内容も、表面的であると感じることが多いです。「パワーポイントやエクセルができるようになりたい」という方には、それができて何になりたいのかを問いたいですし、「とりあえずMBA(注)を取りたい」という方にも、それによってどうなりたいのかをしっかり考えてもらいたいと思います。
MBA取得に関しては、もちろん知識・人脈等あらゆる面でプラスがあるのは確かですが、コンサル出身者に限らずMBAホルダーが増え、MBAを持っていること自体では明確な価値を認められなくなってきているのも事実です。また当然ながら、MBAを持っていなくてもビジネスのあらゆる領域の最前線で活躍している方はたくさんいます。
大事なのは、膨大なお金と時間を掛けてMBAを取得して、その結果どんな自分になりたいのかを徹底的に問い続けることです。それによって初めて、コンサルからMBAを取得することの、自分だけの価値を見出すことができます。
将来自分で事業をやるための勉強として、まずはコンサルを経験したいというモチベーションも聞かれます。これに関しては、自分で事業をやることとコンサルタントであることは根本的に性質が異なるので、経営者としての勉強という目的は、コンサルタントとしての経験では充分には達成できないと考えます。例えるならば、経営者は自分でレールを敷きその上を自分が走る仕事、コンサルタントはレールを走る経営者と並走する仕事です。並走者としてのコンサルタントは、基本的に表に立つことはありません。経営者が社員の誰にも言えない孤独・悩みを打ち明けることができ、時には耳の痛いことも言ってくれる、そんな「良妻」とも言うべき立場です(笑)。
初めから経営者になりたいという明確な目的があるのならば、とにかくレールの上を自分が走る経験を積むべきです。今は学生さんでも起業しやすい環境ですし、そういった機会を積極的に活用して失敗も積み重ねながら実践経験を積む方が近道ではないでしょうか。
ただ、繰り返しになりますが、結果的に短期間でコンサル業界を離れ他の様々なフィールドで活躍する人(起業する人も含め)はたくさんいますし、それは非常に奨励すべきことです。コンサル業界が優秀な人材のプールになっていると言われるのも、同じく結果論です。初めからスキルをつけることだけを目的にコンサル業界を目指すのは筋違い、目的と結果を混同しないでいただきたい、ということです。
「自分の言葉」で就職活動をしてほしい
ここからはかなり個人的な思いになりますが、戦略コンサルで勉強しておいた方が良いのではないかという考え方が出てくるのは、就職先を選ぶときに、自分がやりたいことをベースにして考えるのではなく、他人からの評価をベースにしているからではないかと思います。
「新卒で○○に入っておいた方がいいですか?/××に入るのはやめた方がいいですか?」といった質問を受けることがたまにありますが、「あなたのやりたいこと」がわからないと、答えられません。
やりたいことがまだわからなければ、今の時点で何となくでも興味のあることや、他人から評価されやすいことをとりあえず選んでみるというのも一手です。大事なのは、わからないなりに自分で基準を決めて自分で選択することです。
これはコンサルに限った話ではないと思いますが、面接官は、あなたが何に対してやる気のスイッチが入るのかや、何に対して憤りを感じるのかなど、生き方の価値観を丸ごと知りたいと思っています。特にCDIのように、規模が小さく、ひとりひとりの考える力というきわめて定型化しにくいものに頼っている企業は、なおさらです。
余談になりますが、3年以内で辞める新社会人が多いことの一因は、企業も学生も、ノウハウ化された型に頼った採用・就職活動をしていることによって、お互いの本音をきちんとわからないまま採用をしてしまっていることにあると思います。だからお互い後になって、「こんなんじゃなかった」という結果になってしまうのではないでしょうか。
ですので、ぜひ自分の言葉で就職活動をしていただきたい、と思います。業界本に書いてあることや面接の問答例に書いてあるような言葉しか出てこない人は、自分の頭で考えていないな、と思ってしまいます。奇をてらって変わったことを言わなければならないということでは決してありません。「本当にやりたいことはまだわからないけれど、コンサルの●●というところに興味があるので、とりあえず受けてみました」でも構いません。正直なあなたの体験を、あなたの言葉で、教えてほしいです。
今回の連載は、ここで結びとなります。これまで4回に渡ってお付き合いいただいたみなさま、本当にありがとうございました。
外側からは見えにくい業界の中身をお伝えするのが本連載の目的ではありましたが、「認識を示す」話など、実際に何年か働いてみないとわかりづらい部分は、結局抽象的にならざるを得なかった面もあります。しかし、学生さんの段階では中身をすべて理解している必要はなく、興味を持っていただければ充分だと思います。
戦略コンサルティングという業界についてもっと知りたいという興味を持ってくださった方、ここから先は働きながら学ぶ領域です。ぜひ門を叩いてみてください。採用選考でお待ちしています。
シリーズ一覧
▶︎▶︎▶︎「売上2倍」系GDの背後に見える、表面的ディスカッション力の横行
▶︎▶︎▶︎【第2回:現役コンサルタントが語る】コンサルの面接・GDで評価されない典型と「処方箋」
▶︎▶︎▶︎【第3回:現役コンサルタントが語る】解を導くのがコンサルの仕事か?
▶︎▶︎▶︎【第4回:現役コンサルタントが語る】「コンサルタント」という言葉の響きに憧れを感じた時に読む話
【筆者紹介】

佐藤 沙弥(さとう さや) 京都大学経済学部卒業後、株式会社コーポレイト ディレクション(CDI)に入社。 IT事業会社の新規事業開発支援、食品会社のマーケティング戦略立案、サービス事業会社の店舗網再構築のアドバイザリーなど、消費者向けサービス提供会社のプロジェクトを中心に経験。CDIの新卒採用活動にも携わる。
(注)MBA:Master of Business Administrationの略称で、経営学修士号の意。 ビジネススクールと呼ばれる経営大学院で、通常1〜2年の間に必要な単位数についてある一定以上の成績を修めることで取得可能。










