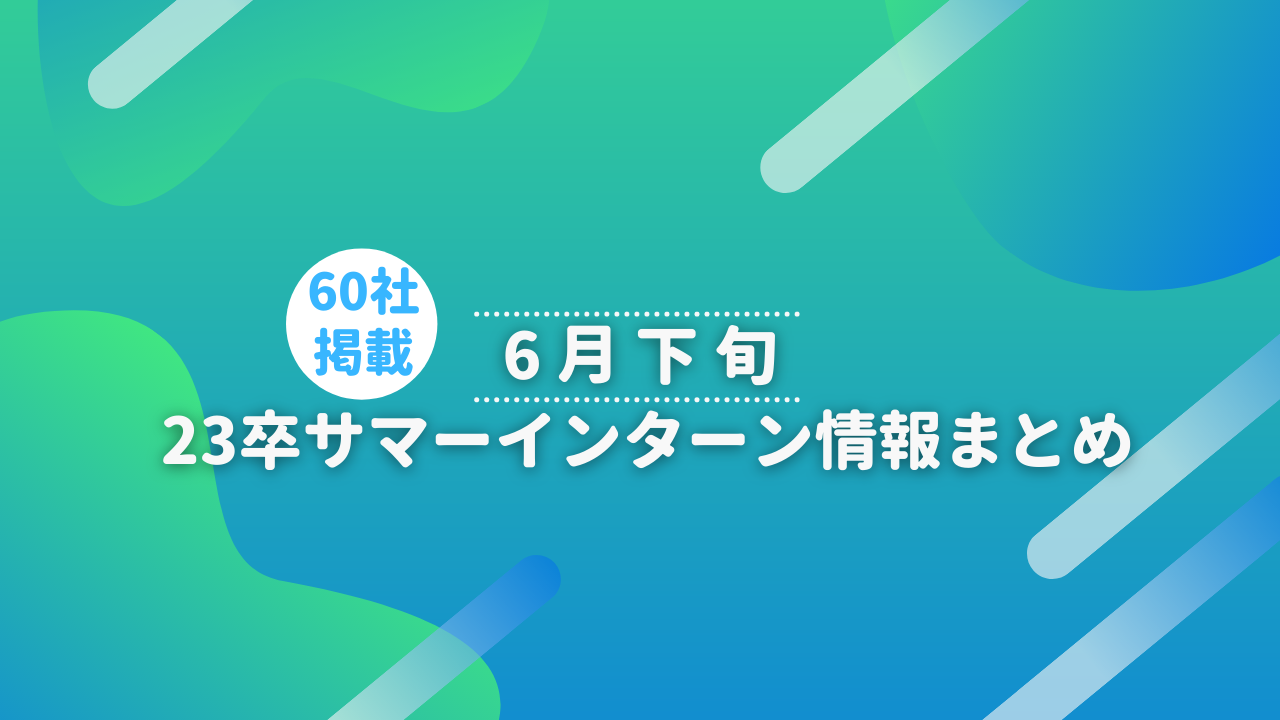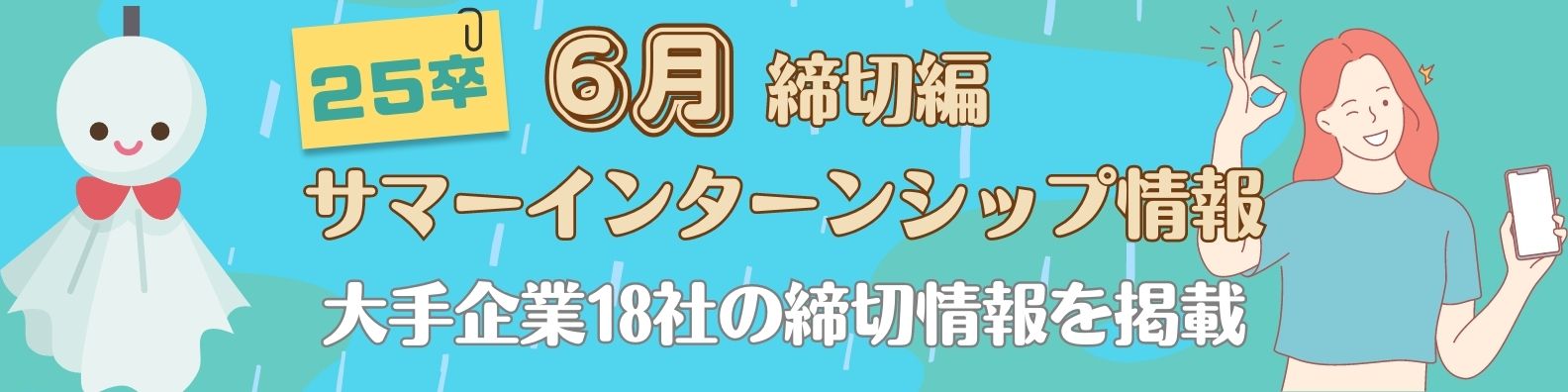【第3回:現役コンサルタントが語る】解を導くのがコンサルの仕事か?
32,046 views
最終更新日:2023年09月25日
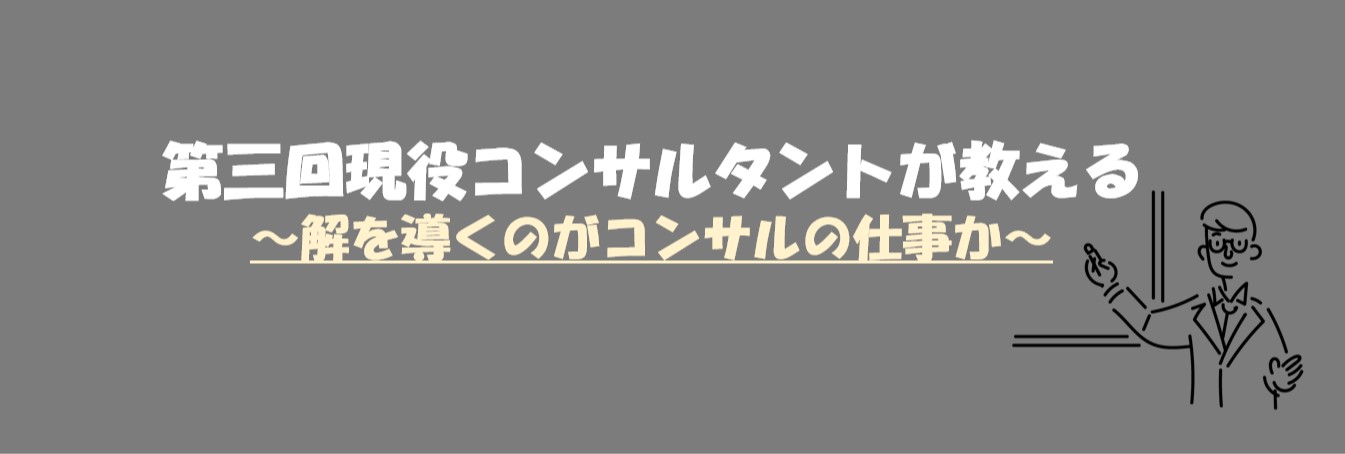
株式会社コーポレイト ディレクション(CDI)の現役コンサルタントによる全4回のシリーズ寄稿です。
**********
【前回の記事はこちら】
▶︎▶︎▶︎【第2回:現役コンサルタントが語る】コンサルの面接・GDで評価されない典型と「処方箋」
**********
これまでの2回のコラムでは、私達が面接・グループディスカッションにおいて何を評価しているかという話を通して、コンサルタントに求められる素養とは「答えの無い問題を前にしてその場で考え議論する力」であるとお伝えしてきました。今回はなぜこういった素養が求められるのかについて、コンサルタントの本質的な提供価値とは何か、という観点からお伝えしたいと思います。
グラフを見て、何を想像するか?
戦略コンサルタントという仕事の説明として、どのような言葉を思い浮かべますか?
「数々のノウハウから経営のアドバイスをする仕事」「戦略を描いて実行にまで落とし込む仕事」「綿密な調査分析に基づき正しい戦略を立てる仕事」・・・本やインターネットなどでよく出回っているものも含めて色々な表現の仕方がありますが、どうやら「解を導く」ことにフォーカスしているのが共通項であるように思います。私の意見では、上記のどれも間違いではないながらも、本質は少し別のところにあると感じています。
コンサルタントが受ける相談はどれも困難な経営課題ですが、難しい問題を前にして本当に難しいのは、問題を解くことそのものではなく、解くべき問いを立てることです。悩んでいるが、何を解決すれば悩みが解消されるのかわからない、という状況だと思ってみてください。学問の世界を想像すればイメージがつきやすいと思いますが、高校まで(場合によっては大学初等まで)は解を出すための「方程式の解き方を学ぶ」過程である一方、大学の研究とは「解くべき問いを立てる/立て続ける」ことであり、これこそが学問の本丸であることに似ています。
より経営的な観点から、解くべき問いを立てることの難しさ/大切さを考えてみましょう。ある画期的な業務支援システムを独自に開発した中堅IT企業を想像してみます。当社はこの独自システムを企業向けの営業によって販売することで順調に売上を伸ばしてきましたが、この数年で急に売上が横ばいになってしまいました。このシステムの売上高のグラフを思い浮かべてみましょう(10年前に販売を開始し毎年倍々くらいに売上が拡大してきたのが、3年前から急に横ばいになった、というようなイメージです)。このグラフを見て、みなさんは何が起きていると想像しますか?
まず思いつくのは、営業力の限界だと思います。売上の拡大に伴って、営業人員が足りなくなっているとか、全体としてのレベルが落ちてきている、といったことです。これが問題だとすれば、「解くべき問い」は、営業をいかに強化するかです。
もっと他の可能性は考えられないでしょうか?
例えば、このシステムに対するニーズを抱えている企業がそもそも限られていて、もうほとんど取り込みつくしてしまっている。つまり、いまの商品コンセプトが限界を迎えているという可能性です。もしこれが本当だとすれば、営業力を強化しても、そもそもニーズを持っている人を取りつくしてしまっているわけですから、効果はほとんどありません。この場合の「解くべき問い」は、新しいコンセプトを持つ商品をいかに開発するかかもしれませんし、もしかしたらビジネスモデルの転換まで検討しなければならないかもしれません。
戦略コンサルタントの本質的な価値は、「認識」を示すこと
実際のプロジェクトでは、こういった仮説を立てては検証し、を繰り返していきます。仮説を立てる能力が「解くべき問いを立てる」力、検証する能力が「解を導く」力です。大事なのは、仮説を立てる能力は検証する能力とは全く異なっており、自分なりの物の見方や認識を示すことが起点になっているということです。急に売上が横ばいになっているグラフを見て、「コンセプトが限界に来ているのではないか」と「認識」するかどうか。
認識するということ、さらにそれを示しクライアントの認識を変えることこそが、コンサルタントの本質的な提供価値だと思います。コンサルタント自身の認識が起点になって初めて戦略の絵を描くことができますし、クライアントの認識を変えることで初めて本当の実行支援があります。実行支援と一口に言っても、常駐でコンサルタントを派遣することだけが実行支援ではありません。クライアントの認識を根底から覆すことに徹底的にコミットし、それによってクライアント自身を動かす。これも立派な実行支援、個人的にはむしろ、これこそが実行支援の本質だと思っています。
解を導く力も当然必要ですが、コンサルタントの能力としては基礎力に近い位置づけです。これが、解を導くことはコンサルタントの提供価値の本質とは少し違うと申し上げた理由です。
「認識」をぶつけ合える「同志」に参画してもらいたい
実際のプロジェクトで「認識」が問われるのは、特にプロジェクトの始めです。プロジェクト開始直後、場合によってはさらにその前の受注時に、最終的な提言の仮説(私達は「初期仮説」と呼んでいます)を立てその検証に入っていくので、この初期仮説の筋の良し悪しでプロジェクト期間の過ごし方も最終的な提言の質も大きく変わってしまいます(もちろん、初期仮説が正しいとは限らない、むしろ何らかの欠陥があることがほとんどなので、検証しながら常に仮説をブラッシュアップしていくというサイクルは常に継続していきます)。
現象をどう認識しどういう仮説を立てるかというプロジェクトの肝となるプロセスには、プロジェクトメンバー全員でじっくりと取り組んでおり、全員で会議室に数時間缶詰め、ということもザラです。こういった一見非効率にも見える時間の使い方をするのは、認識する、という行為の前には、新米コンサルタントも熟練したパートナー(注)も完全に平等であり、ひとりひとりの異なる認識が合わさって初めて仮説がより筋の良いものに昇華していくためです。
よって、採用においても、言った通りに手を動かしてくれるいわば「駒」のような人ではなく、同じ立場で一緒に考えてくれる「同志」を募集したいというのが私達の思いです。個人的な体験を挙げると、例えばGDの後に「コンサルタントだったらどう考えるんですか」と答えを聞いてくる学生さんは、勉強熱心なのはとても結構なことですが、それだけでは残念ながらあまり一緒に働きたいという気持ちにはなりません。「自分は●●というように考えたのですが、どう思いますか/議論させてください」というように、お互いの認識のぶつけ合いを前のめりに求めてくるような人と、ぜひ一緒に働きたいと思います。
より話を広げると、コンサルタントという第三者としての認識の価値の一つは、相手が常識と思っていることに対して、いかに素朴な、しかし本質的な疑問を投げかけられるかというところにあります。クライアント、ひいては社会に対して、自分自身の素朴な認識を投げかけ続けるのも、コンサルタントとしての一つの在り方です。
よって、日頃から身の周りのことにアンテナを張って「これはおかしいのではないか」という素朴な疑問を抱き、自分自身の見解を持っているような人も、ぜひ一緒に働きたいです。例えば私個人の場合は、就職活動の「受験勉強」的な側面に、学生の頃から強い疑問を抱いています。就活本や就活塾なるもので面接の答えを勉強したり、業界や個別の企業に対して偏差値的なランクが付いたりする。こういった状況下で、学生が本当にやりたい職業を選んだり、社会で本当に活躍できる人材を選び育てたりすることが果たしてできるのだろうか、という思いは、個人的に投げかけ続けていきたいことの一つです。もちろん就職活動以外のことでも何でも構わないので、自分の見解を自分の言葉で語りたい人に、ぜひ参画いただきたいと思います。
(一応補足すると、就活本や就活塾も使い方次第でとても有効なツールになるとは思います。そもそも何が聞かれるかを知っておくとか、場馴れをするとか、そういった目的で活用するのが一つの付き合い方だと思います)
相手の認識を変えることの「タフ」さ
ここまでは自分たちがどう認識するかという話ですが、その先には相手の認識を変える、というさらに高い壁が待っています。相手の認識を変えるために、私達の日々の仕事の中では、「何を言うか」と同じくらい、「どう伝えるか」に時間をかけることを意識しています。
百ページ以上に渡ることもある報告書の中で、クライアントの認識を変えるための鍵になる重要なスライド(私達は「キースライド」と呼んでいます)はせいぜい数枚ですが、プロジェクトの最終段階になると、チームメンバーで議論を尽くしながらその数枚を作っては捨てを繰り返してブラッシュアップしていきます。学生のみなさんにはどうしてもイメージがつきにくい部分かもしれませんが、日々膨大な業務に追われる社長に対して、一瞬で正確にメッセージを伝え認識を覆すためには、ひとつひとつの言葉の使い方、概念的な絵の描き方、ストーリーのつなげ方等に、一切の妥協は許されません。
この過程に入りずっと一つのことを深く考え続けていると、一度思いついた伝え方のアイデアを「捨てたくない」という無意識的な自己防衛反応が出たり、深く考えているがゆえに聞く側の視点に立つことが難しくなったり、といった葛藤も生じます。それを乗り越えて、真に認識を変えることのできる伝え方に至ることは本当に難しいです。
さらに、「どう伝えるか」を考える時間を確保しようといくら意識しても、やはり実際にはその前段である「何を言うか」を徹底的に考えることの方に時間がかかってしまっていて、時間の余裕が無いことがほとんどです。タイムリミットからくる心理的プレッシャーの中で、最後の最後まで「どう伝えるか」を考え続けることは、相当なタフさが求められます。
このように、伝え方のブラッシュアップは、頭の中が本当にぐちゃぐちゃになり続ける(笑)とても辛いプロセスで、いわゆる下っ端仕事であるヒアリング調査やエクセルでのデータ分析など全く取るに足りないと感じるほどです。しかし、チーム内で「これだ!」という深いメッセージを出せたときの達成感、そして何よりクライアントがすっと腹落ちする形でこちらの認識が伝わったときの感動は、何にも代えがたい、コンサルタントのやりがいの一つです。
CDIが大切にしている、認識の伝え方の「幅」
認識の伝え方に正解はありません。しいて言うならば、クライアントが最も納得してくれる伝え方が正解です。コンサルタントによって、クライアントによって、本当に色々な伝え方があるなと私自身日々驚かされていますし、その許容の幅がとても広いことは、CDIの一つの特徴ではないかと思います。
例えば、私が入社して一番驚いたのは、ダイレクトにメッセージを書くことをあえてせず、偉人の言葉や、哲学書や歴史書からの引用文だけが書いてあるスライドを挟むという戦法(笑)です。時代を経て生き残ってきた言葉を借りて、メッセージの輪郭をぼんやりと浮かび上がらせると同時に、時間を掛けて咀嚼するとメッセージの核がすとんと腹落ちする、そんな伝え方だと思います。
このような表現に初めて出会ったときには、客観的事実を元に戦略を語るコンサルタントが、アウトプットに先人の言葉を借りることもあるのか、とショックにも近い感覚を抱いたことをよく覚えています。こういった「離れ業」は、基本を忠実にマスターしていることが大前提ですし、何十年と経験のある熟練したコンサルタントでなければ深みが出ませんので、非常に使う人を選ぶ「芸当」です(当然、今の私にはとてもできません笑)。よって、「離れ業」は本当にたまにしか登場しませんが、「自分だけの自由な方法で認識を伝えることこそが、戦略コンサルタントの価値である」というCDIが大切しているひとつの在り方がよく表れている例だと思います。
ここまで読んでいただいて、「認識を示す」仕事を、面白そうと思っていただけたでしょうか。それとも、何だかよくわからない、面倒そうだなぁという印象でしょうか(笑) 。あなた自身は、どう「認識」しますか?
シリーズ一覧
▶︎▶︎▶︎「売上2倍」系GDの背後に見える、表面的ディスカッション力の横行
▶︎▶︎▶︎【第2回:現役コンサルタントが語る】コンサルの面接・GDで評価されない典型と「処方箋」
▶︎▶︎▶︎【第3回:現役コンサルタントが語る】解を導くのがコンサルの仕事か?
▶︎▶︎▶︎【第4回:現役コンサルタントが語る】「コンサルタント」という言葉の響きに憧れを感じた時に読む話
【筆者紹介】

佐藤 沙弥(さとう さや) 京都大学経済学部卒業後、株式会社コーポレイト ディレクション(CDI)に入社。 IT事業会社の新規事業開発支援、食品会社のマーケティング戦略立案、サービス事業会社の店舗網再構築のアドバイザリーなど、消費者向けサービス提供会社のプロジェクトを中心に経験。CDIの新卒採用活動にも携わる。
(注)パートナー:コンサルタントとしてのキャリアパスの最終点であり、コンサルティングファームの「共同経営者」のポジション。パートナーの仕事は大きく分けて2種類あり、1つは顧客開拓とプロジェクトの受注(=営業)、2つ目は人材育成なども含めたコンサルティングファームそのものの経営全般。