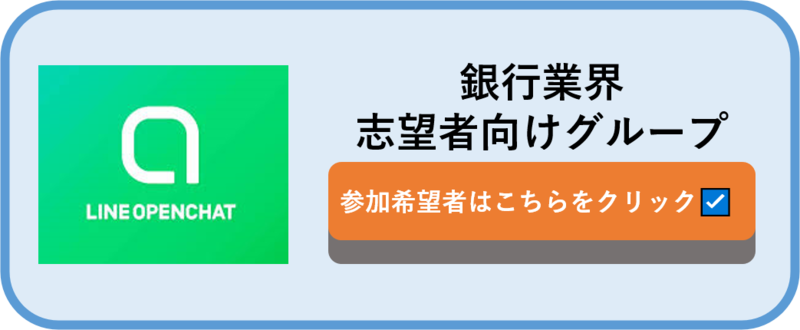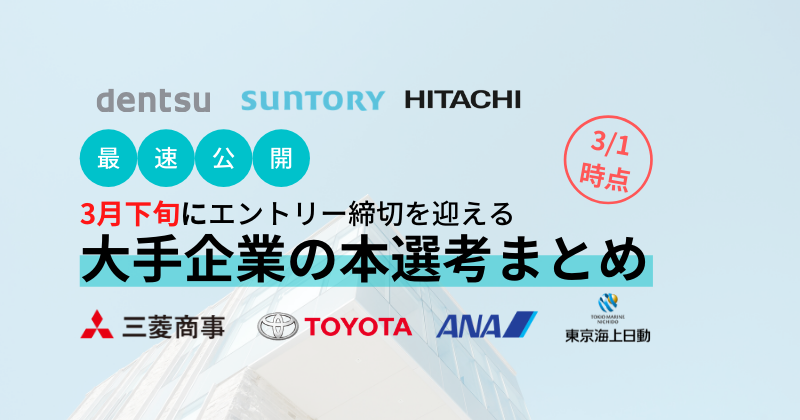【メガバンクインタビュー】三菱UFJ・SMBC・みずほ社員のキャリアにまつわる取材記事をまとめました。
19,728 views
最終更新日:2024年07月29日

情報収集ツールとして、説明会やインターンシップ、OB訪問など様々ありますが、今回は効率的に情報収集をオンラインでしたいメガバンク志望者のために、多種多様なWEBサイトからメガバンク社員にまつわる取材記事をunistyleでまとめました。
各社の採用HP上における情報は既にチェックしていると思いますので、外部サイトの記事をまとめております。
是非ブックマークして読み進めてもらえると幸いです。
三菱UFJ銀行

「銀行の出世は×をつけられないことが重要」三菱東京UFJ銀行の元行員が語る内情1(20代~30代のキャリアを考えるブログ)
三菱UFJ銀行から某投資銀行に転職した行員に対してインタビューした記事です。元行員ということもあり、邦銀の出世レースの内情や組織内構造など、就活生にとってブラックボックスであった情報が赤裸々と語られています。全3編に及ぶ記事ですが、全ての内容に目を通す価値は十分あると言えるでしょう。
AIの時代、それでも自分が三菱UFJ銀行に行く理由(就活Hack)
地方大大学生の18卒で三菱UFJ銀行への内定を獲得した方にインタビューした内容を全文吹き出し形式でまとめた記事です。地方出身者ならではの就職活動への取り組みや、アルバイトやサークルと言った平凡な経験を上手くアピールする方法といった内容は数多くの学生にとって必見であると言えるでしょう。
元メガバンク人事の就活攻略〜三菱UFJ銀行〜人気の割に内定しやすい!(Real Voice of Recruiter)
こちらはインタビュー記事ではありませんが、元三菱UFJ銀行員で採用戦略担当をしていた方が銀行の基本や銀行あるあるまで、非常に多くのジャンルを赤裸々に教えてくれる記事です。銀行の事業やメガバン比較もわかりやすく解説しているので、業界研究がまだの方にもおすすめできる記事になっています。
【本音座談会】私たちはなぜ30代でメガバンクを辞めたのか—— 三菱UFJからSansan、ユーザベース、マネフォへ転職(BUSINESS INSIDER JAPAN)
「目の前のお客様を助けてあげられない」「自分で仕事をコントロールしたい」。就活生から人気のメガバンクですが、このように様々な理由で転職を決断した人たちがいます。本記事は30代でメガバンクを辞めた3人の方の座談会の内容をまとめていますので、マイナス面まで含めた銀行の業務理解に役立つでしょう。
三井住友銀行

【三井住友銀行】主体性が求められる状況下で、自己成長を実現し続ける(type就活)
三井住友銀行人事部の社員に対しての、「就職活動の状況」「最も成長を感じた業務」といった質問内容のインタビューの回答を基にまとめられた記事です。特に、三井住友銀行の社員の「一人あたりの責任感と熱量」について具体的業務を交えながら強調しており、このような社風に興味を持っている方には有益な情報でしょう。
三井住友銀行が4000人分削減を急ぐワケ(BLOGOS)
単純な事務作業をRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)やAIの導入により削減し、銀行員が要らなくなると言われている現在。本記事では、三井フィナンシャルグループ会長がその真の狙いや、今後銀行員に求める素質を解説しているため、銀行志望者は必見の価値があるといえるでしょう。
三井住友銀頭取インタビューで知る!変わる銀行ビジネス(あさがくナビ)
三井住友銀行の頭取に対してマイナス金利下においてメガバンクや地方銀行が生き残っていくための活路についてインタビューした内容を基にまとめられた記事です。銀行志望者はもちろん、今後の銀行業界に不安を持ち敬遠してしまっている方も是非一度は読んでみてください。
みずほ銀行

求む「みずほをぶっ壊す人」-自己否定からの変革、採用様変わり(Bloomberg)
銀行を取り巻く経営環境の悪化の中で、各行は新たな求める人材像を掲げていますが中でも最もみずほ銀行がその傾向が強いように感じます。その主眼に置かれているのは「リーダーシップ」であり、19卒からのESでもその傾向を伺えます。本記事では、新たなみずほの採用戦略について述べているため、みずほ銀行志望者には有益な情報と言えるでしょう。
インタビュー 坂井辰史・みずほフィナンシャルグループ社長 キャッシュレス推進を牽引 変化を起こす組織に変える(d menu)
みずほ銀行頭取坂井辰史氏に今後のみずほの組織戦略や求める人物像についてインタビューした記事です。みずほ銀行は経営環境の変化に対応するため社長も前線に出て、新たな人材を求めています。みずほ銀行志望者はいち早くその人材戦略を知るためにも必読であると言えるでしょう。
みずほ銀行の企業研究ページ(内定者ES・選考レポート・選考対策記事)はこちら
さいごに
unistyleでもメガバンクに関する記事をいくつか公開しております。
こちらも是非併せてご一読ください。
三井住友銀行(SMBC)のES徹底解説!選考通過者の志望動機・ガクチカ分析
みずほFGのES徹底解説!選考通過者の志望動機・ガクチカ分析
銀行業界の情報収集に役立つ!就活生向けLINEオープンチャットを紹介
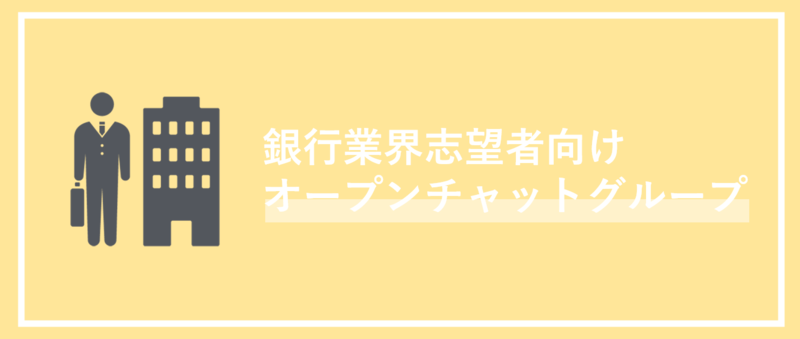
unistyleでは業界別の就活用LINEオープンチャットを運営しており、数多くの就活生が匿名で就活に関する情報交換をしています。
実際に銀行業界志望者向けのグループでも、各社の選考に関するトークが活発に交わされています。
下記の画像をクリックすることで参加用ページに飛び、ニックネームとプロフィール画像を登録するだけで参加することができますので、興味のある方はぜひご参加ください。