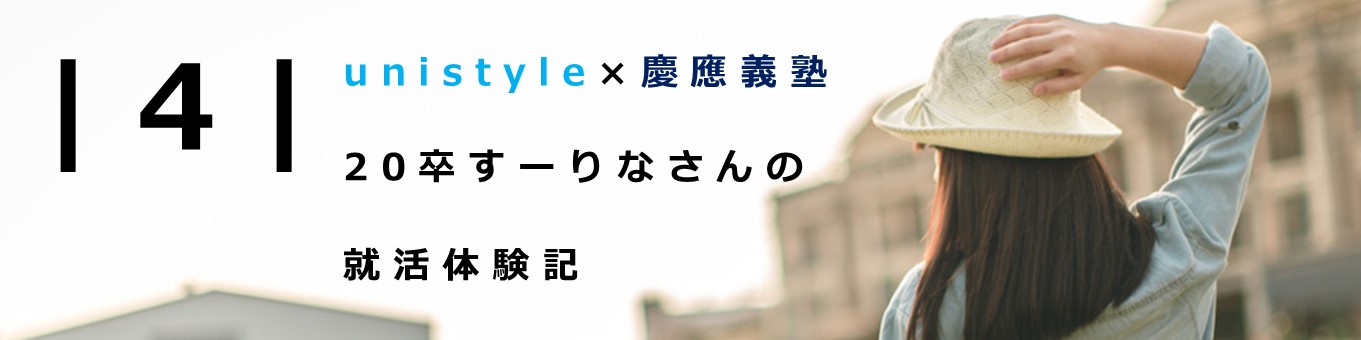ファーストキャリアで人生は決まらない〜納得のいく就職活動を行うために〜
27,756 views
最終更新日:2024年10月07日

100人が100人希望する会社に入れないことは分かっている。仮に70人が希望する会社に入れるとすると、自分は希望する会社に入れない残りの30人かもしれない…。
就職活動に力を入れていけばいくほど、「もし希望する会社に入れなかったらどうしよう」と時には不安に煽られることもあるかと思います。
全員が、入りたい企業に入れないことは就活を始めた頃は分かっていたけれど…就活にのめり込むほど認識が変化し、入れないのは自分ではないかと不安に煽られる…
本記事では、最初の勤め先が絶対ではないことを認識していただき、改めて自身のファーストキャリアについて考えるきっかけにしていただきたいと思います。
就職における勝ち組とは?

まず始めに、就職活動における”勝ち組”とはどのようなものでしょうか。
外資系コンサルや総合商社のようないわゆる入社が困難だと考えられる企業から内定をもらうことでしょうか。スポーツや勉強と同じで、就職活動でも”勝ち”を目指したいものです。
大学受験は偏差値で選ぶ
一般入試で大学進学をした多くの方が”偏差値”を基準に大学を選んだのではないでしょうか。
もちろんある特定の教授がいるから、このスポーツが強いからなどの理由で選んだ方も中にはいるかと思います。複数校から合格をもらった場合、一般的には偏差値の高い大学への進学を選択するでしょう。
A大学法学部(偏差値70)
B大学経済学部(偏差値60)
おおよその学生がA大学を進学先として選択すると思われます。しかし、経済を強く勉強したく、A大学を蹴ってB大学に進学する人の割合は少数でしょう。
就職にも偏差値はあるけど…
大学受験の偏差値は身近な存在である一方、就職活動にも”偏差値”なるものが存在します。
では同様にどちらの企業を選択しますか?
これは意見が割れると思います。メーカーで働くことに強く惹かれており、中でも日産自動車で働くことを希望する人は日産自動車を選択するでしょう。
一方、IT業界に強く惹かれており、将来はSIerとして活躍したい人であればNTTデータを選択するのではないでしょうか。
では、上記2社どちらを選ぶのが”勝ち組”なのでしょうか。大学受験同様、偏差値だけで測るのならば日産が勝ち組となるでしょう。
しかし、大学受験と異なり”偏差値が高い=勝ち組”の構図は就職活動では通用がしません。いくら入る事が難しい企業で、誰からも賞賛される企業に入社しようとそれが自分のやりたい事とマッチしていなければ本当の意味での”勝ち”は得られないでしょう。
話が若干逸れてしまいましたが、企業に甲乙がつける事が難しいことを踏まえると、”希望する会社に入れなかった=負け組”と単純に考えることは決してできないように思われます。
10年後企業がどうなっているかは分からない

これは合同企業説明会やインターンシップなどで一度は聞いた事があるのではないでしょうか。
今後50年、私たちが働いていく中で今ある企業が”生き残っている確率”を測ることは不可能です。たとえ、今有名企業であっても東芝の例のように窮地に立つことも想像に難くはありません。
1位:日本航空(JAL)
2位:伊藤忠商事
3位:全日本空輸(ANA)
4位:三菱UFJ銀行
5位:トヨタ自動車
引用:【就職希望企業ランキング】2019年卒の就活生が選ぶ人気企業とは?
上の表から面白い結果が読み取れます。
こちらは19卒の就職希望企業ランキングとなっています。
JAL・ANAの両航空会社の合説でのあまりの人の多さに筆者も驚いてしまいました。この上位5社のどれかに入社した際には羨望の眼差しを浴びることになるでしょう。
JALの経営破綻・銀行の破綻・カーシェアの脅威
一方で、これらの企業に入ったからといって一生安泰な生活が送れる訳ではないとも想像できます。
人気1位を獲得しているJALは2010年と比較的最近に経営破綻を経験しています。
経営破綻の際には1500人にも及ぶ人員整理を実施しており(パイロット・CA含む)、JALを希望して入社したもののこのような結果になるとは当時の内定者は想像していなかったと思われます。
他にも銀行業界の縮小も耳にしたこともあるのではないでしょうか。
理由は様々述べられており本稿では詳しく説明をしませんが、ハーバードビジネスレビューによると、今後10年以内にイノベーションを起こせない銀行の92%が潰れるとされているそうです。
メガバンクに務めたからといって100%安泰ではないことがわかります。
同様に世界のトヨタもカーシェアなどのサービスの登場により、従来の車の製造・販売企業からサービス事業への転換を進めおり、従来の様相を変えつつあります。
自分が希望する企業が未来永劫繁栄しているという保証はないため、長い目で見た所、自分が一番に希望した企業よりも実際に働いている企業の方が良かったということも十分ありえるのです。
転職率は9.9%。第二新卒って聞いた事がありますか?

それでも強く入りたい企業に入れなかった場合のショックは大きいかと思います。
「自分の希望とは違う企業で一生働くのか…」という不安が一種の原因となっており、このような気持ちになるのではないでしょうか。
転職は今やアタリマエ
私の属する慶應義塾大学の入学式ではいろいろな様相の新入生を見る事ができます。
希望する慶應に合格し、これからの学生生活への期待で満ち溢れている笑顔の学生・「なんで私が慶應に?」と言わんばかりの暗い表情で自分が通う予定であった遠く駒場の地を眺めているかのような学生・高校に通うのと同じテンションではしゃいでいる内部生で構成されています。
大方入社式もこのような様相を呈しているのではないでしょうか。
大学と企業とで比較した際に大きく異なるのは転職(転校?)率ではないでしょうか。
先ほどの例の続きになりますが、遠く駒場の地を目指していた学生も半年ほど経つと現状が気に入ってしまい、それまでの暗い表情が一変、楽しそうに学生生活を送っています。
中には再受験のために勉強している学生もいましたが非常に少数でした。一方企業の1年の転職率は9.9%(10人に1人)と高い数値を示しています。加えて生涯の転職率は28.8%(1回)・19.1%(2回)とこちらも同様に高い結果を示しています。
仮に希望する企業に入れなかったとしても転職率を見る限りチャンスは何度でもあるように思います。
”第二新卒”と呼ばれるように企業は経験豊かな人材を中途採用として重視するようになってきています。
最初の企業で経験を積み、それでもまだ志望する企業が変わらないのであれば再度挑戦するチャンスは十分あるのです。
納得のいく就職活動を行うために

最初の勤め先がそこまで重要ではないと言われても、本音は建前は違います。
建前として”最初の勤め先≠絶対”だと分かっていたとしても本音は希望する企業に入りたいものです。勘違いしてはいけないのが、ファーストキャリアが絶対ではないからといって、中途半端に就職活動をしても大丈夫という訳ではないということです。
30/100は失敗なんかではない
冒頭の例で100人新卒がいたところ、70人は希望する企業に30人は第一志望ではない企業に務めることになると仮定しました。
就職活動を行うのは自分の希望する企業・業界に進みたいからであり、上記の70人になるために行なっています。もちろん一生懸命やったが、30/100になる可能性もありえます。
しかし、大切なのは30/100が決して失敗ではないということです。もちろん希望する企業に入社することに越したことはありません。
一方で先ほど記載した”将来その企業が残っている確率”・”高い転職率”を考慮していればそれほど悲観的になる必要もないのではないかと思われます。
むしろ、想像していなかった発見や貴重な経験を積むことができる可能性もあります。
日本の低い転職率
先ほど、日本の転職率は9.9%と高い数値であるとしましたが、それは過去の日本のデータと比較した結果であり、世界的に見ると低い数値です。
得に新卒一括採用・終身雇用の制度がないアメリカでは生涯転職平均数が12回と言われています(長く企業に務めることは適応性が低いとして忌避される傾向があるようです)。
日本では今でも”転職”に対するマイナスイメージが残っているようにも思われます。
一方で、”働き方改革”の一貫で、終身雇用の撤廃や中途採用の増加などより米国に似せたフレキシブルな変化を遂げ始めているともいえます。
そのため、将来的には長く一つの企業に務めることは珍しいなんて変化も起こるかもしれません。
ファーストキャリアは人生を100%決めない
ファーストキャリアが大事であるという事実は、なんと言われようと変わりません。
例えば、社会に出た際の”価値観”・”考え方”は最初の企業の影響を大きく受けることになります。
一方で、裏を返せばファーストキャリアの重要性はその程度であり、人生を100%決める要因にはなりえないのではないでしょうか。
誰もが希望する企業に入れないことを念頭に置きながら、”やるだけやったんだからこの企業に行くことに納得できる”と強く言い切れるように就職活動に真摯に取り組むことが大切ではないでしょうか。
後から”これをやっておけばよかった”・”もっとこうしておけばよかった”と後悔するために、現状の就職先に不満や不安を抱くのであり、今のうちから後悔のないように取り組むことで納得のいく就職結果を得られるでしょう。
まとめ

本記事では、最初の勤め先が必ずしも自分の人生を左右するものではないことに対し考察を深めてきました。
①希望する会社に入れない≠負け 就活に負けはない
②10年後に安定している企業は分からない
③高い転職率は社会に出た後もチャンスを与える
もちろんファーストキャリアが大事ではないと断言している訳ではありません。後悔しない就職活動を送るためにも自分の将来に対し真摯に向き合う事が大切です。ただ、少しだけ肩の力を抜いても大丈夫ではないでしょうか。






.png?1626319618)