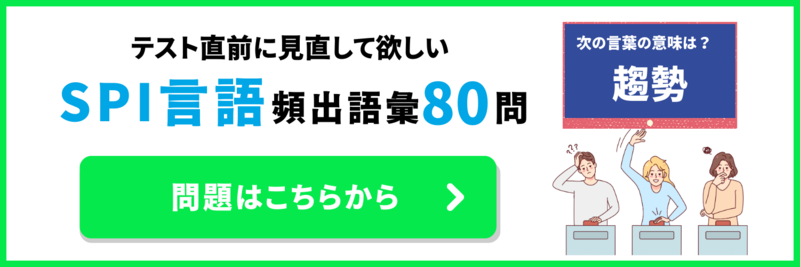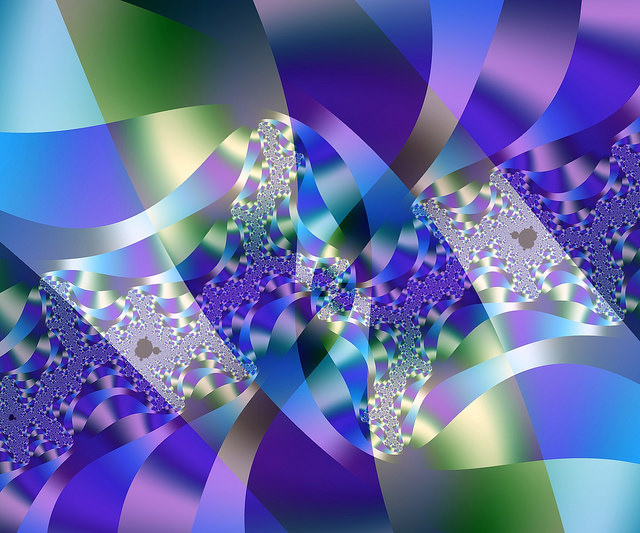Webテストの答えを使うのはNG-解答集や替え玉受験など不正行為のリスクも解説-
636,010 views
最終更新日:2024年10月07日
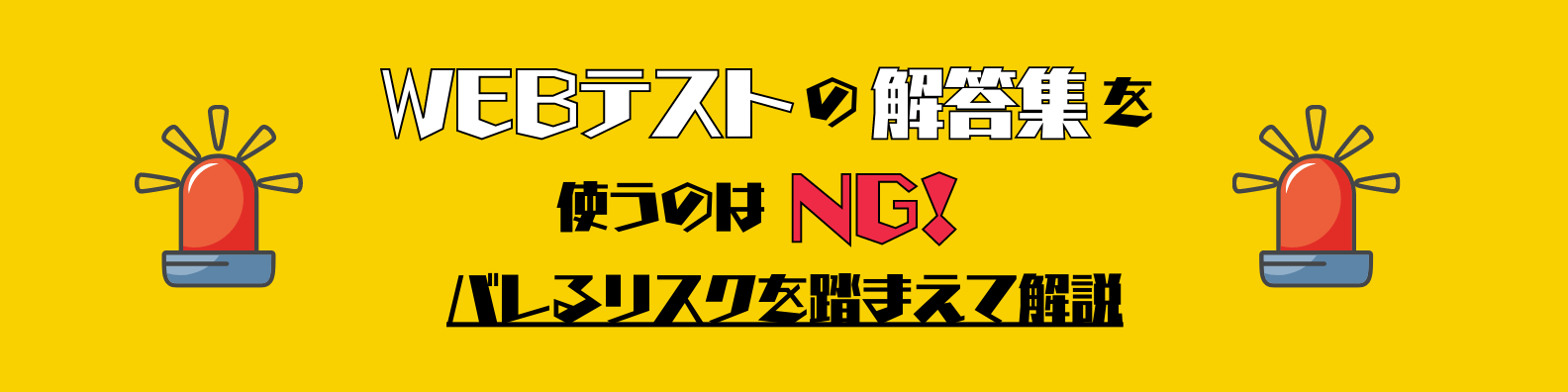
本記事では、「Webテストの答えや解答集を利用する」といったテーマを取り上げ、不正をしてはいけない理由や不正を行うリスクについてお伝えしていきます。
Webテストの不正にまつわる実態-以前までは答えや解答集を入手できた?-
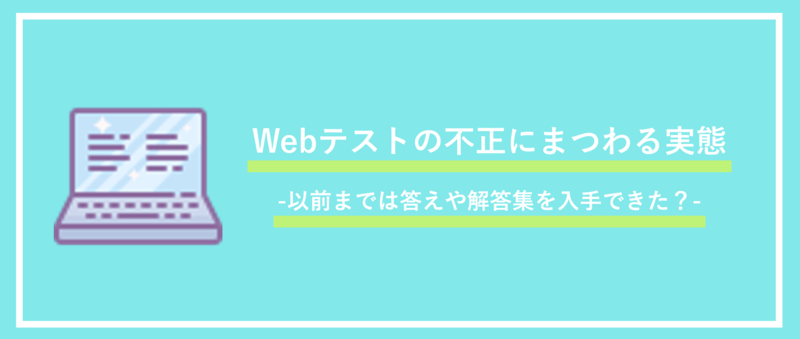 多くの企業が採用活動に使用しているWebテスト。そんなWebテストですが、以前まではWebテストの答えが出回っていたり、Webテスト代行サービスを利用していたり、友達と協力して問題を解くなどの不正が横行している実情がありました。
多くの企業が採用活動に使用しているWebテスト。そんなWebテストですが、以前まではWebテストの答えが出回っていたり、Webテスト代行サービスを利用していたり、友達と協力して問題を解くなどの不正が横行している実情がありました。
しかし最近では企業側がWebテストの不正を取り締まるようになり、実際に下記のような事件も発生しています。
大前提、unistyleとしては替え玉受験や解答集を利用するといったWebテストの不正は容認しておらず、自力で受験することを推奨しています。
ここではWebテストの答えを利用するリスク等を説明する前に、まずはWebテストの答えにまつわる実情をご紹介します。
昨今、大手・ベンチャー問わず多くの企業が選考フローにWebテストを採用しており、大半の就活生が就職活動においてWebテストを受験します。
しかしWebテストを採用する企業が増加する一方で、不正行為をして受験しようとする就活生を見受けるようになってきたのも事実としてあります。
冒頭でも替え玉受験の件に触れましたが、自力で受験せずに他者に協力を仰いだり、答えが書いてある解答集を見ながら受験する就活生も存在していました。
しかし、下記事例からも分かるように、近年では替え玉受験や代行サービスといったWebテストの不正が問題視されており、逮捕者が出るといった事件も発生しています。
また、解答集などを自作してWebテスト対策に取り組むこと自体は全く問題ありませんが、解答集を見ながら本番のテストを受験することは明確な法令違反になります。
そのため、Webテストの替え玉受験・代行サービスを利用することは絶対に避けるべきですし、解答集に関しても対策・練習のためのものと位置づけた上で本番のテストは自分の実力でルールに則って臨むようにしましょう。
なお、Webテスト以外にもESや面接に不安があるという就活生には就職エージェントneoがオススメです。アドバイザーから、ESや面接を通過するコツに関してアドバイスがもらえます。
少しでも興味があるという方は、下記の画像をクリックしてサービスを利用してみてください。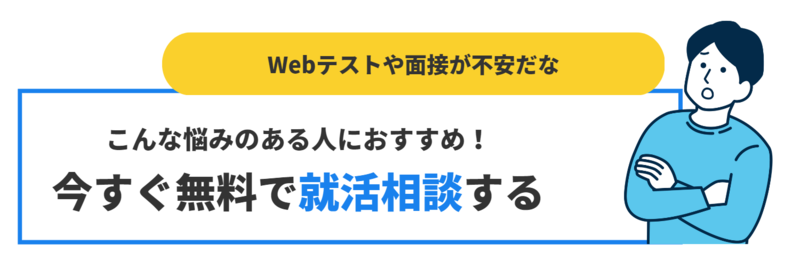 そこで続いてはWebテストの答えを利用するリスクをより詳しく理解していただくため、5つの観点から解説していきたいと思います。
そこで続いてはWebテストの答えを利用するリスクをより詳しく理解していただくため、5つの観点から解説していきたいと思います。
Webテストの答えを利用するリスク
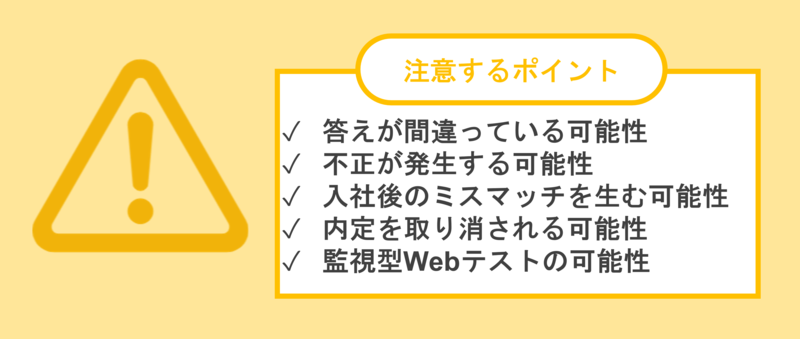
Webテストの答えを入手する行為は不正と言えますが、実際にWebテストの答えを入手することにはどのようなリスクがあるのか、以下で説明していきます。
入手したWebテストの答えが正解とは限らない
Webテストの答えはネット上で入手することも可能ですが、その入手したWebテストの答えが正解とは限りません。
解答集や代行サービスも100%正解を保証しているわけではありませんし、そもそも自分が問題を理解していないと、問題に対して解答すべき答えとは異なる間違えた解答を入力してしまう可能性もあります。
つまりWebテストの答えを入手したとしても、解答が100%正しく、100%合格するとは言い切れません。
入手したWebテストの解答から不正が発覚する
正答率が圧倒的に低い問題を簡単に答えられていたり、満点を取らないために意図して間違えた解答をした問題が正答率が高い問題だった場合、企業から疑いの目をかけられても仕方ありません。
また、Webテストでは能力適性検査と共に性格適性検査も行われます。その解答から得られたどんな人物なのかというデータはそのまま記録されます。
性格適性検査を代行サービス先の人が受けた場合、自分と全く同じ人格を作り出すことは不可能です。そのため本人が提出しているESやその後の面接での人物像とWebテストの結果から得られる人物像が一致していない場合、採用担当者から疑われる可能性もあります。
入社後のミスマッチを助長する
不正をして入社しているということは、ありのままの自分を伝えきれていないまま入社しているということです。
例えば、
・同期と比較した際に、能力面で明らかに劣っていて、仕事で結果が出ない。
・企業が配属を決定する際に、Webテストを参考に配属をした結果、適性がない部署に配属になってしまう。
このようにWebテストの答えを利用し合格してしまったことで、自分の実力や適性に適していない企業に入社してしまいミスマッチに繋がってしまう可能性があります。
不正がバレた場合、内定を取り消される可能性がある
Webテストの答えを入手して受験し不正がバレてしまった場合、内定が取り消しになってしまう可能性もあります。
不正をしたまま内定を得ていたとしても、不正がバレないか不安になったり、罪悪感を感じ自己申告をするという人も多くいると聞きます。友人からのリークでバレてしまったというエピソードもあるそうです。
不正をしたときは大丈夫と思っていても、後になって企業にバレてしまい内定が取り消されてしまう可能性があるため、非常にリスクが高い行為と言えるでしょう。
監視型テストであれば、替え玉受験やカンニングを検知される
Webテストの不正受験が蔓延している現状を受け、最近では監視型のWebテストが開発されています。
例えば、ヒューマネージ社とユーザーローカル社が共同開発したオンラインAI監視型Webテスト『TG-WEB eye』では、AIが受験中の就活生の行動を監視し、不正が疑われる場合は受験結果とともに報告されるという仕組みが用いられています。
監視型テストを採用している企業はまだそこまで多くはないかと思いますが、今後採用する企業が増加する可能性は充分にあります。
どのように不正を検知しているのか、通常のテストと監視型テストを見分ける方法はあるのか等、まだまだ不透明な部分はありますが、就活生の皆さんはこういったテストが存在することを認識しておくべきでしょう。
これらの理由から、Webテストの答えや解答集を使用することにはリスクがあり、不正はするべきではないということが理解していただけるでしょう。
Webテストの答えを入手できる現状を企業はどのように思っているのか
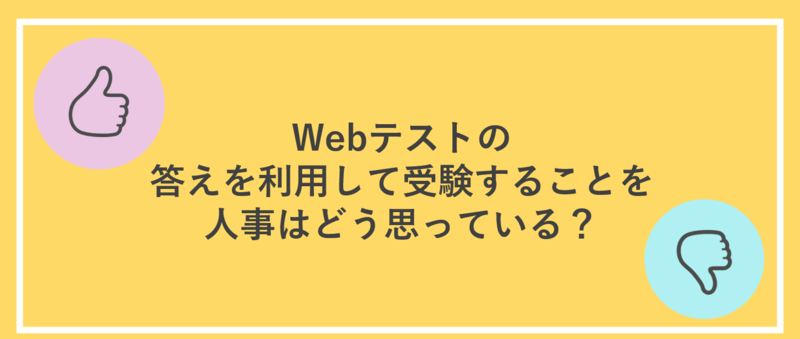
ここまでで紹介してきた通り、Webテストの答えを利用したり替え玉受験をするのは明らかな不正行為ですが、企業はこの事実をどのように受け止めているのかを以下でご紹介します。
企業側もWebテストの答えが横行しているのは把握している?
このコンテンツは会員(無料)の方のみご覧になれます。
また、会員(無料)の方は81698枚のエントリーシートを全て閲覧可能になります。
(無料会員登録はこちら)
Webテストの不正行為の取り締まりは年々厳しくなっている?
このコンテンツは会員(無料)の方のみご覧になれます。
また、会員(無料)の方は81698枚のエントリーシートを全て閲覧可能になります。
(無料会員登録はこちら)
最後に-不正行為はせずに正攻法でWebテストに臨もう-
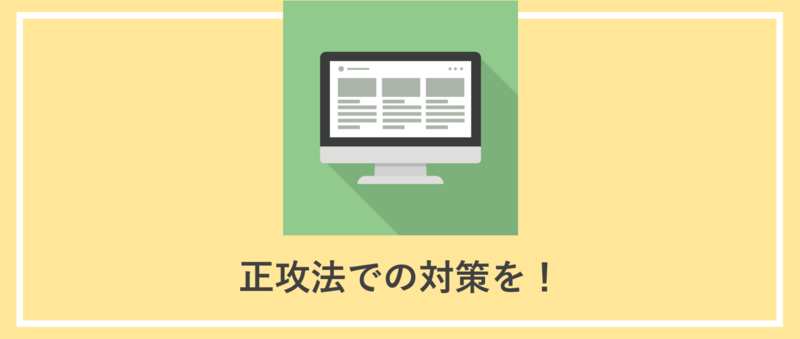
本記事ではWebテストの答えや解答集を利用することの是非に関するテーマを取り上げ、不正をしてはいけない理由やリスク等を解説してきました。
何度もお伝えしていますが、解答集の利用や替え玉受験等のWebテストの不正は違法行為であり、unistyleとしては正攻法での対策を推奨しています。
Webテストの設問には正解がありますが、取り組み方法には明確な正解はないため、基本的な対策方法はこちらの記事を参考にしてみてください。
また、最近ではWebテストをお試し受験できるサイトもあります。下記の記事にまとめているので、Webテストの雰囲気を感じてみたいと思っている方は下記のリンクから試してみてください。
その他、Webテストの対策全般にまつわる内容に関しては下記の記事一覧からご確認ください。