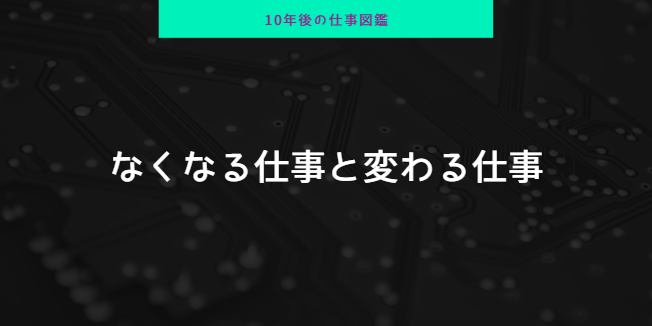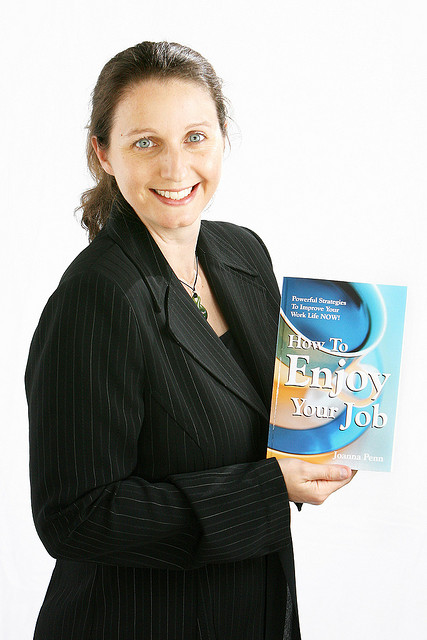市場価値を高めたい就活生必見『10年後の仕事図鑑』から見る仕事の変化「仕事にできる趣味を3つ持て」
15,796 views
最終更新日:2023年10月30日

こんにちは。Unistyle編集部のせいちゃんです。
就活をしていると「市場価値」という言葉をよく耳にします。「市場価値の高い人になりたい」と将来のビジョンを語る学生も多いでしょう。ただ、その「市場」の動きを理解した上で語らなければ、的外れなものになってしまいます。
今回は堀江貴文さんと落合陽一さん共著の『10年後の仕事図鑑』から、これからやってくる社会と仕事の変化について解説していきます。これから起きる変化を理解した上で、自分自身の方向性を考えてみてください。
未来を知る
なくなる仕事
これから「なくなる仕事・減る仕事」は、「コスト」という観点で、以下の二つに分類されると言います。
①不当に給料が高い仕事(例:経営者)
②低コストな仕事(例:事務職)
また、給料が安い仕事でも、複数人雇わなければならない場合、優秀なAIが一台あればいい、ということになるだろう。
【引用】10年後の仕事図鑑
では、具体的にどのような仕事がなくなっていってしまうのでしょうか。
①なくなる不当に給料が高い仕事
・管理職(クラウド型の会社管理ツールで代替可能)
・弁護士・裁判官・検察官
【引用】10年後の仕事図鑑
・会計士・税理士・社労士
(中略)
また、会計監査なども、AIで個人の特性を分析して魔が差す要因をマッピングすれば、その一般業務は代替可能だと思われる。
【引用】10年後の仕事図鑑
・スポーツの監督
(中略)
しかし、モチベーション喚起やコミュニケーションは別である。
【引用】10年後の仕事図鑑
②なくなる低コストな仕事
・秘書
・現場監督
(中略)
ただし、現場監督はAIに代替される。データをもとに効率的に働くプランを作るのは、人間よりもAIのほうが得意だ。AIの指示に従って人間が実働するのが最も理想的だといえる。
【引用】10年後の仕事図鑑
・事務職
【引用】10年後の仕事図鑑
・公務員
【引用】10年後の仕事図鑑
・銀行員
【引用】10年後の仕事図鑑
・翻訳
【引用】10年後の仕事図鑑
変わる仕事
AIに取って代わられる事でなくなることはなくとも、変わっていく仕事もあります。それらはどのように変化していくのか、見ていきましょう。
・営業職
【引用】10年後の仕事図鑑
・エンジニア
【引用】10年後の仕事図鑑
・介護職
【引用】10年後の仕事図鑑
・クリエイター
(中略)
「クリエイティブな仕事はAIに代替されない」というのは、幻想にすぎないのだ。ただし、統計、AIやプリンティング技術を使って、より新たな発想を生んでいくクリエイターは生まれるのではないだろうか。
【引用】10年後の仕事図鑑
今からできること
今後AIが生活に根付いていくことで多くの仕事が変化することはお分かりいただけたと思います。
現在はAIがコスト的に安価なものではないため、限定的に導入されています。しかし、AIの製造は今後一層安価になり、それに伴い一斉に普及していくでしょう。それはこの10年でのスマートフォンの普及のスピードを思い出していただければ分かりやすいと思います。
その変化を目の前に、私たちはどのように変化していくべきなのでしょうか。落合さんは2つのパターンがある、と解説しています。
未来を生き抜く2つのパターンを知る
①ブルーオーシャンの選択
【引用】10年後の仕事図鑑
つまり、統計データがまだ少ないようなことでは人間に勝算があるということです。機械には意志がないため、だれにも興味を持たれないようなニッチな領域を探求することで「AIに仕事を奪われる」といった漠然とした恐怖心からも開放されるのです。
だからこそ、趣味と仕事の境目のないような人が増えてきているとも言えます。それがどれだけニッチで誰も必要としないもののように感じても、何かに打ち込み、「専門性」が磨かれるとあなたの代わりはなかなかいません。「ゼネラリスト」の方がよっぽど代替可能な存在ということになります。
②責任と生存戦略をコンピュータに委譲する
【引用】10年後の仕事図鑑
これを個人レベルで考えてみると、予定管理が分かりやすいでしょう。就活中も感じることだと思いますが、面接やOB訪問の日程調整のやり取りを全て自分の手で行うと大きな工数となります。そこで予定管理システムを取り入れ、スケジューリングやリマインドを自動化できれば、ほかの事に時間を使えるようになります。
これら二つを生活の全てに適応させようとするのではなく、自分の生活に合わせて「まだら」に取り入れることが重要でしょう。
ポジションを取れ
【引用】10年後の仕事図鑑
なぜここまで落合さんや堀江さんは「早く行動しろ」と主張しているのでしょうか。それは機械の方が、速いスピードでポジションを取りに来るからです。私たちが専門性を磨き始める前に、その領域でのデータが溜まり、「機械ができること」になってしまうということです。
では、夕飯くらいは意志を持って決定することができるようになったとき、次にすべきことは何でしょうか。それは「問い」を立てることだと言います。
【引用】10年後の仕事図鑑
特定の領域で「自分なりの美学を成熟させる」ことで自分のポジションが取れるようになっていくのではないでしょうか。
まとめ
この10年で想像もつかないような変化が起きたように、次の10年でも今は考えられないような変化が起きるということは予測できます。そのなかでも仕事における変化は、私たちが最も敏感であるべきものです。世の中の流れを掴み、自分のキャリアプランに時代錯誤がないか、確かめてみてください。

恋愛コンテンツクリエイターとしてnote、Twitterを中心に毎日発信しています。
【「愛してると言えるようになるまで」|Twitter@あんず飴】
もっと多くの人が「なりたい自分」になる背中を押すために就活についての執筆もしています。
【就活生以外の皆さまに読んでほしい就活日記】
平成が終わる前に自著を出版することが目標。