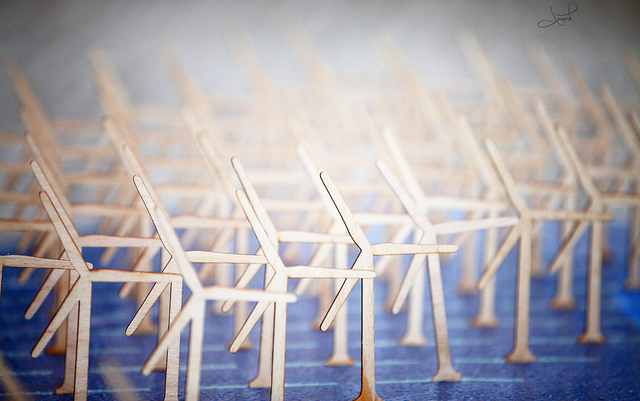"ワーク・ライフ・バランス"は必要?本当に必要なのは"ライフワーク・バランス"
12,687 views
最終更新日:2024年09月30日

パワハラ・ブラック企業などの言葉がニュースを賑わせている現代。
そのような傾向があってかワーク・ライフ・バランスがより重要視されるようになってきていると感じています。
みなさんの中にも「仕事とプライベートの両立ができる」という軸をもって就職活動をしている方も一定数いるのではないでしょうか。
しかし一方で"ワーク・ライフ・バランス"について正しく説明できる就活生も少ないと感じています。
本記事では"ワーク・ライフ・バランス"の説明とともに本当に必要なのか、ということについても述べていきたいと思います。
▶"ワーク・ライフ・バランス"とは
▶"ワーク・ライフ・バランス"は必要なのか
▶"ライフ・ワーク・バランス"を重視しない働き方とは
▶ライフワークなんて見つからなくて当然
▶最後に
"ワーク・ライフ・バランス"とは

みなさんがワーク・ライフ・バランスと言われてイメージするものは何でしょうか。
「短時間勤務」「フレックスタイム」「育児休暇」「テレワーク」などだと思います。これらは知っての通りワークライフバランスを実現するための制度です。
"ワーク・ライフ・バランス"という言葉自体の意味は「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」(平成19年 内閣府発表)によると、
引用:「仕事と生活の調和」推進サイト ワーク・ライフ・バランスの実現に向けて
となっています。
例えば「残業なしで9時〜17時まできっかり働く」ことも「9ヶ月死ぬほど働き、3ヶ月完全に休み」ことも同じく"ワーク・ライフ・バランス"です。
短時間で効率よく働くことが"ワーク・ライフ・バランス"なのではなく、自分の働き方を実践することが"ワーク・ライフ・バランス"という言葉が意味していることです。
つまり「『ワーク(=仕事)』と『ライフ(=余暇)』の比率を自らにあった配分にする」が"ワーク・ライフ・バランス"とされています。
"ワーク・ライフ・バランス"は必要なのか

引用:「ライフワークに出会えたら、努力は努力じゃなくなる」 尾原氏が語る、好きと得意のバランスの取り方
ワーク・ライフ・バランスが重視されている一方で、ワーク・ライフ・バランスは必要なのかという議論も存在しています。
「ワーク・ライフ・バランスはいらない」という意見は、「休暇なんていらない、働くことこそ人間の悦びだ」ということではなく、上記の引用のような「ワークとライフを区別する必要があるのか」という意見です。
背景として、大企業においても続々と副業が解禁されており今後パラレルキャリアが当たり前になっていくということが挙げられます。
それにより、
・副業が浸透し、やりたいことができやすい環境になる
・やりたいことができるため、ワークとライフの境目が曖昧になる
ということが実際に起こり始めています。
このような事柄から「ワークとライフを区別する必要はない、だからワーク・ライフ・バランスはいらない」という意見が出てきています。
"ライフ・ワーク・バランス"を重視しない働き方とは

上記のことがあり、ワークとライフを分けて考える"ワーク・ライフ・バランス"ではない新しい働き方が重要になってくると考えています。
今後は「ライスワークとライフワークの比率をどう配分するか」という"ライフワーク・バランス"が重要だと思っています。
この言葉にでてくる2つの用語について解説すると、
ライスワークは、「食べるためお金を稼ぐための仕事」
ライフワークは、「生きがいとしての仕事」
を意味しています。
”ライフワーク”が重要
引用:「ライフワークに出会えたら、努力は努力じゃなくなる」 尾原氏が語る、好きと得意のバランスの取り方
私は出張も多いため、私のことを「働きすぎだ」と言う人もいますが、辛いかと聞かれると全くそうは思わないんですよね。
「働いている」「働かされている」感覚がない。これが6%の人だと思います。極端な表現ではなく、趣味や部活に行くような感覚の人だと思いますね。
引用:これからの時代、活躍できる人材とは。|パーソルキャリア 佐藤裕|unistyleインタビュー
上記の引用のように"ライフワーク"は「やりたいことを仕事でする」ということです。
「やりたいことだから時間を忘れて没頭できる」「やりたいことだからどれだけでも時間をとうしてできる」というものが"ライフワーク"だと考えています。
上述の"ライフワーク・バランス"にライフがでてこなかったのは、ワークとライフを全く区別していないからです。
ライフワークは"仕事をする"のではなく”好きなことをする”という感覚で働いています。だからライフワーク≒ライフという公式が成り立ちます。
ワークとライフを区別しない代わりに、ワークをライスワークとライフワークという区別をしています。
全てのライフワークで稼げるわけではないですし、そもそもライフワークが見つかっているわけでもないと思います。だからライフワークではない、ライスワークが必要です。
もちろん「ライスワーク=ライフワーク」となることが理想ですが。
「ライスワークを本業に副業としてライフワークをする」「ライフワークで足りない稼ぎをライスワークで稼ぐ」といった自分にあったバランスを選択すること。これが”ライフワーク・バランス”です。
「会社に守られ、副業で攻める」について。 僕、大賛成です。これからはパラレルキャリアなんて普通になると思うし、ライスワークやライクワークを区別していかないと100年時代生き抜けないんじゃないかとも思ってます。 1社に居続けて会社依存性の高いスキルを磨いても未来先細りだろうなぁ。。
— むたか@unistyle編集部(@mutaka_unistyle) 2018年8月7日
ライフワークなんて見つからなくて当然

ライフワークが重要ということをお話してきましたが、結局のところほとんどの就活生がライフワークになりうる"やりたいこと"を見つけていないと感じています。
就職活動の半年〜1年間、やりたいことを自問自答することの繰り返しですが、それで答えが見つかるのはごく一部の就活生だと思います。
また社会人の方の多くもやりたいことが何なのか見つけていないとも感じます。
働いている社会人の方々でさえ見つけられていないのだから、働いていない就活生がやりたいこと・ライフワークを見つけることはとんでもなく難易度の高いことであるはずです。
何のために働くのかは考えなくていい。必死に働く中で見えてくる。
高島さんも20代のうちは、何のために働くのかは考える暇がないほど必死に考えたようです。必死に働くことを通して、現在彼は「人の喜ぶ顔を見るために働く」ということに気づかされたと言っています。彼は孫さんとはまったく別のアプローチで「何のために働くのか」という問いに対して答えを出し、結果を出しています。
引用:【就活を始める前に読んで欲しい】就職活動とは何か?なぜ働くのか?
こちらの高橋さんの言葉のように、実際に働いてみて見えてくるということもあると思います。
なので今は見えなくても、常に頭の片隅に置いて就職活動・社会人生活を送っていくことが"ライフワーク"につながる大切なことだと思っています。
最後に

本記事ではみなさんに向けて2つのメッセージをお伝えしました。
▶今後ワークとライフの境界が曖昧になり、生きがいとしての仕事"ライフワーク"が大切になる
▶就職活動中にライフワークが見つかっていることなんてほとんどない、だから常に頭の片隅ににおいて考え続けること
就職活動に正解はなく、ファーストキャリアの選択においても多数の考え方があります。
unistyleという一就活メディアの中にも、
「複数内定で迷った場合に何を基準に就職先を選ぶべきか」
「キャリアにおける「鶏口牛後」〜あえて難易度が低い企業を選ぶという選択〜」
「「やりたいことがない」学生は、とりあえずブランド企業に入社すべき」
など様々な考え方が提示されています。
これらの記事にも書いてある通り、自分の価値観・モノサシにそって納得感のある選択をしていくこと大切です。
自らの納得感のある選択を、そして自分の”ライフワーク”を見つけてほしいと思います。
unistyleがみなさまのキャリアの一助となれば幸いです。


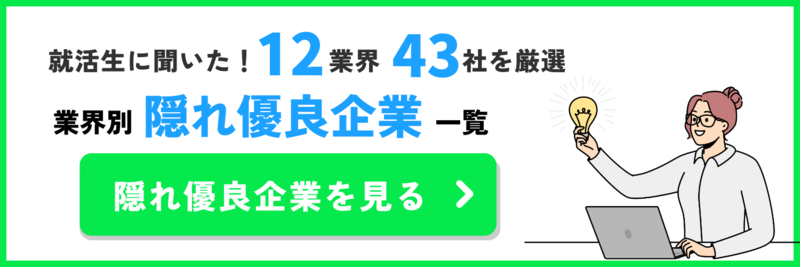





.png?1574321700)