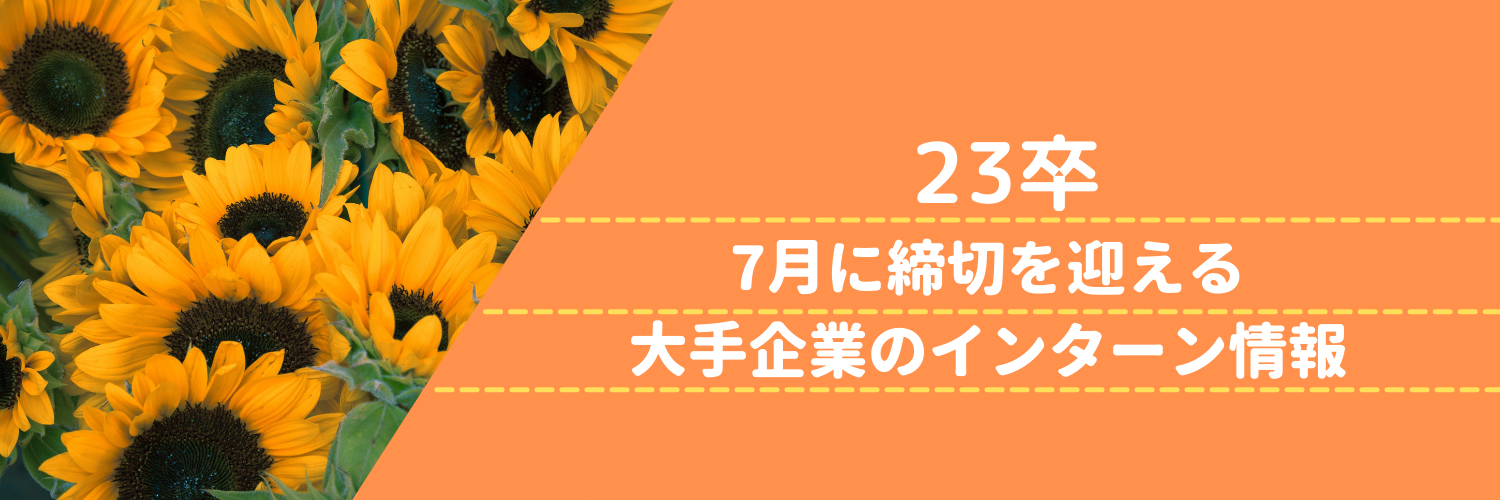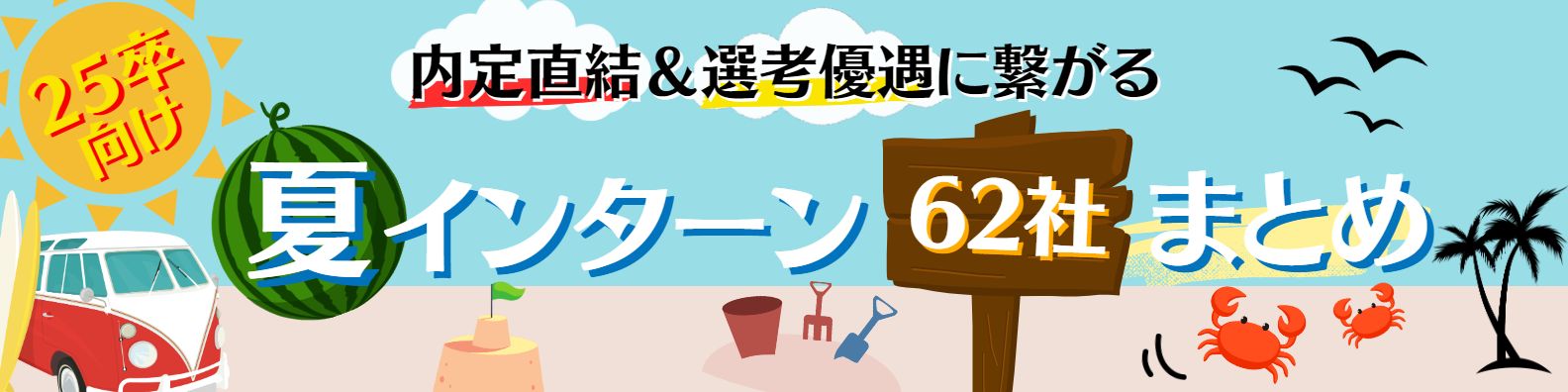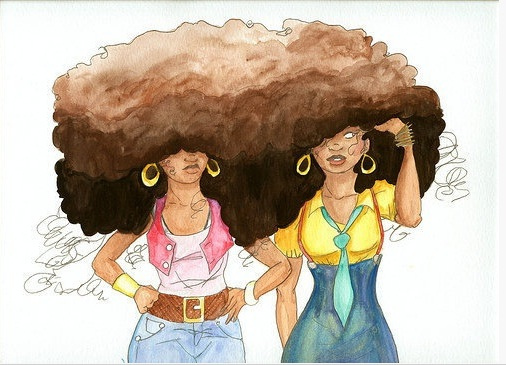70%が落ちることも!就活で学校推薦をもらった時に考えること
58,299 views
最終更新日:2023年11月01日

理系大学院16 卒、メーカーから内々定をもらった者です。
就職活動は一人一人異なるもの。同じ学部・学科の友人でさえ、全く同じ就活をしている人なんていないのです。だからこそ「こんな時どうしたらいいの?」とみなさんが思った時に、少しでも参考になれば幸いです。
就職活動は、就職サイトや企業のホームページからエントリーするもの、人材会社から紹介してもらうもの、スカウトなど様々なアプローチの仕方があるのはご存じの通りでしょう。さらに学校によっては学校推薦などの推薦制度もあります。私の学校も少ないとはいえ、一部それらのような推薦制度が存在していました。そして、運よく私は学校推薦に選ばれたので、推薦をもらった時の注意点などを紹介したいと思います。
推薦と言えども「落ちること」を念頭において就活をする
一番大事だと考えるのが、これです。リクルーター面接などを受け、代表として推薦されることが決まると、「推薦=内々定をもらえる」と考えがちです。
しかし、推薦と言えども100% 受かる訳ではありません。私が受けたものは学校推薦でしたが、学内選考で90% が落とされ、なんとか学校代表になれたと思ったら企業での選考では70% が落とされました。「推薦=受かる」ではないことを知っておくことはとても大切だと思います。
推薦の企業、一般応募の企業への時間配分
推薦と並行して一般応募の企業も応募する必要があります。(推薦によっては100% 内々定がもらえるというものもあるかもしれませんので、各自で確認して下さい。)
推薦をもらうと、その企業ばかり企業研究やOBOG 訪問をしがちです。もちろん、推薦の企業の方がより選考進度や内々定を出す時期が早いことが多いため、そこで決めたいという気持ちがあるのなら、その準備を全力で行うことは大切です。
しかし、それと同時に一般応募の企業にもエントリーシートを出すこと、そしてその企業に行きたいという気持ちを持って、手を抜くことなく本気で選考を受けに行くことが必要です。
推薦に落ちてしまった時の考え方
何度も書いていますが、推薦は落ちることもあります。何を隠そう、私もその一人です。
推薦は落ちるものと知ってはいたものの、実際落ちると息をするのも忘れてしまいそうなくらいの衝撃を受けます。そしてここで、上記の一般応募の企業も進めておくことが活きてきます。
教授に「絶対受かる」そう言われても、万が一という事があります。落ちてから準備をしては遅いのです。推薦に落ちても、他の会社を進めていれば、「まだまだ進んでいる会社が残っているし、他の会社の選考をがんばろう」と思い直すことが出来ます。
しかし、ここで推薦に頼りすぎていると、残りの手駒が少なく、ダメージは何倍にもなり、立ち直ることが難しいです。最後に自分を救えるのは自分しかいません。
ちなみに私は推薦の他にもたくさんエントリーしていたことが功を奏し、第一志望の業界、業種で内々定をいただく事が出来ました。推薦に落ちてしまった人も、これを読んで「まだまだいける」と希望を持ってもらえたら嬉しく思います。
また、推薦が控えている人は、準備していることで心の余裕が生まれ、自信を持って選考に臨んでもらえたらと思います。
最後に
推薦がある人もない人も、共通して大切なことは「今出来る事を少しでも多くすること」だと思います。「備えあれば憂いなし」です。頑張ったら頑張った分、心の余裕が生まれたり、後悔の少ない結果に結びついたり、何かの形で自分にかえってくるものです。
就活生のみなさんがそれぞれに合った企業と巡りあえる事を願っています。