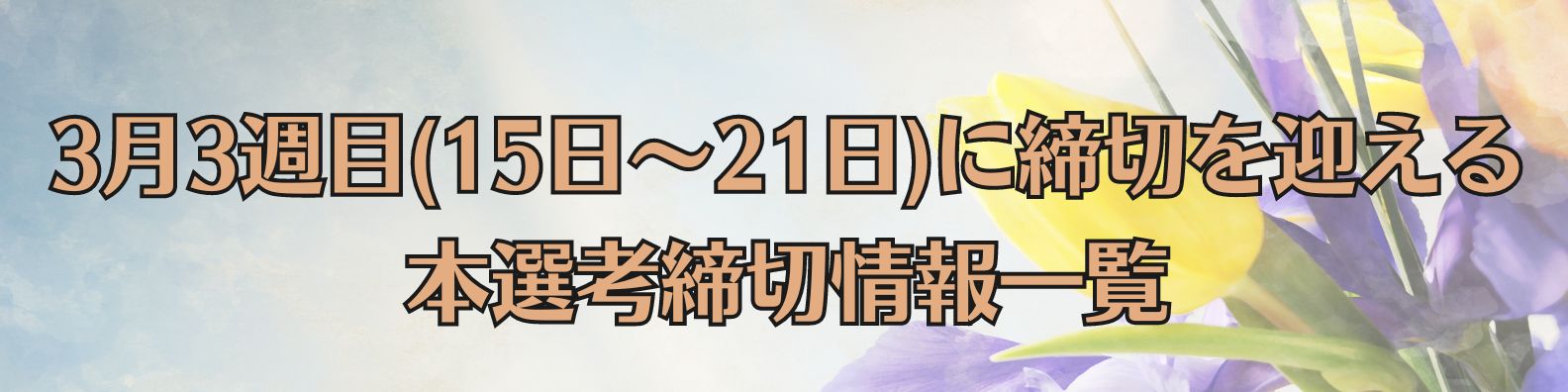何の実績もない一般就活生が持つべき心構え
37,435 views
最終更新日:2023年10月27日

16卒のマスコミ内定者です。
今回は就職活動体験記ということで、私が就職活動を通して感じたこと、伝えたいことをつらつらと書いていきたいと思っております。
まず、前提としてお伝えしておきたいことは、就職活動は個々人のスペックや経験によって取るべき戦略が全く異なってきますし、これといった「正解」はありません。一つ学年が上であるだけで偉そうに就活論を語ってくる方もままいますが、そういった方達の言葉を鵜呑みにせず、常に自分なりの価値観、指針を持って就職活動に臨むと良いと思います。(もちろん、この体験記を読む際もそうした意識を持ってください)。
自分が一般人であることを自覚しよう

最初にお伝えしておきたいことが、「自分は一般人であることを自覚した方がよい」ということです。
もちろん超人的なスペック(関東一部体育会、○○日本一、メディア運営者etc…)を持っている方も中にはいるはずですが、大多数の学生は普通にサークルして、アルバイトして、就職活動を迎えます。こうした学生たちは、おそらく社会人からすると「みんな一緒に見える」と思われます。
しかし逆に、学生たちはサークルやアルバイトでの小規模なコミュニティでそれなりの地位を築いていると、「自分って意外とすごい」と思ってしまいがちです。これは特に地元でちやほやされている高学歴の人に顕著だと思うのですが、冷静に考えてみてほしいのです。小規模なコミュニティなどそれこそ無数にあり、そこでちやほやされる学生もまた無数にいるのです。
例えば早稲田大学なら一学年に1万人程の学生がいます。ここに、早稲田ほど人数はいないとはいえ、東京大学、京都大学、一橋大学、慶応大学等の学生も加えて、脳内で全員整列させてみてください。
自分はその中の一人でしかないのです。なぜそれで根拠もなく「自分は大手優良企業に入れる」と思うのでしょうか。私自身そう考えていたクチではあるのですが、甘かったです。インターンの選考に参加した方ならわかると思いますが、普通に落ちまくります。
まず、自分はそこそこできるという驕りを捨てること。これが重要だと思います。
一般人はどう戦えばいいのか?

ここまで読むと、普通の学生はいったいどう就活していけばいいんだ、と思われるかもしれません。
その疑問に対する私なりの答えとしては、非常に単純ですが、「戦う土俵を変える」ということです。つまり、スペックで勝負しなければいいのです。
まず、スペックで差がつくのは学生時代がんばったことだと思います。ここはすごいことを書ければそれに越したことはありませんが、普通のことを書いてそれに対する自分なりの考え、価値観が書ければ充分です(unistyleのコラム等を見てそれに沿って書けば十分及第点のものが書けるはずです)。
大事なのは、「やってみたいこと(=新規事業など)」、「志望動機」などの部分です。これらの部分に関しては未来のことを書きますので、基本的にこれまでの経験はそこまで関係ありません(動機の部分は多少必要ですがどうにでもなります)。
これまでの経験が関係ないということは、スペック抜きで当人のビジネス的な素養が見られるということです。つまり、ここで頑張れば超人よりも評価される可能性があるというわけです。
まず、企業の採用基準というものを考えると、そこには企業への理解、理念への共感など様々なものが挙げられると思うのですが、一番大事なのって「企業に利益を生めるかどうか」ですよね。(慈善事業なら別ですが)
その「利益を生めるかどうか」を一番はかりやすいのが、「やってみたいこと」の部分だと私は思いますし、上場企業の社員の方もそうおっしゃっていました。それはなぜか。やってみたいことが考えられない=受動的な人間は仕事を生み出せないし、やってみたいことがたくさん考えられる=能動的な人間は仕事を生み出せるからです。
単純ですが、理由はこれだけです。色々な就活サイトで、主体性、チャレンジ精神が大事と言われていますが、これらの能力は仕事を生み出す力と言い換えてもいいですよね。
以上のことを踏まえると、一般的な学生は「やってみたいこと」の部分で他者と差をつけていくべきだと思います。
「やってみたいこと」の考え方

最後に、「やってみたいこと」の考え方について。
本人の創造性によるところももちろんありますが、アイデアを生む力というのは鍛えることが可能ですし、そういった本がたくさん出版されています。
私のおすすめは「コモディティ化市場のマーケティング理論」「センスは知識からはじまる」「発想の技術」の三つです。
私はこういった本でまずは理論をインプットしてから、いろいろな企業の過去ESなどでアウトプットの練習をしました。自分の頭で物事を考えられない人間は、今後の労働市場で淘汰されていくと言われています。考える力を就活で養っておきましょう。
長々と書いてきましたが、簡単にまとめると、「すごい実績がなくても、自分の頭で考えて、仕事を生み出せそうな人は評価される」ということです。
体験記というよりただのアドバイスになってしまいましたが、この記事がみなさんの就職活動にほんの少しでも役立てば幸いです。ありがとうございました。