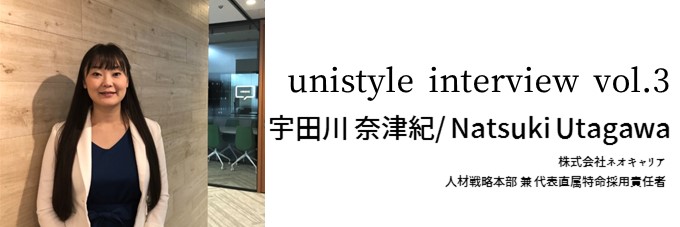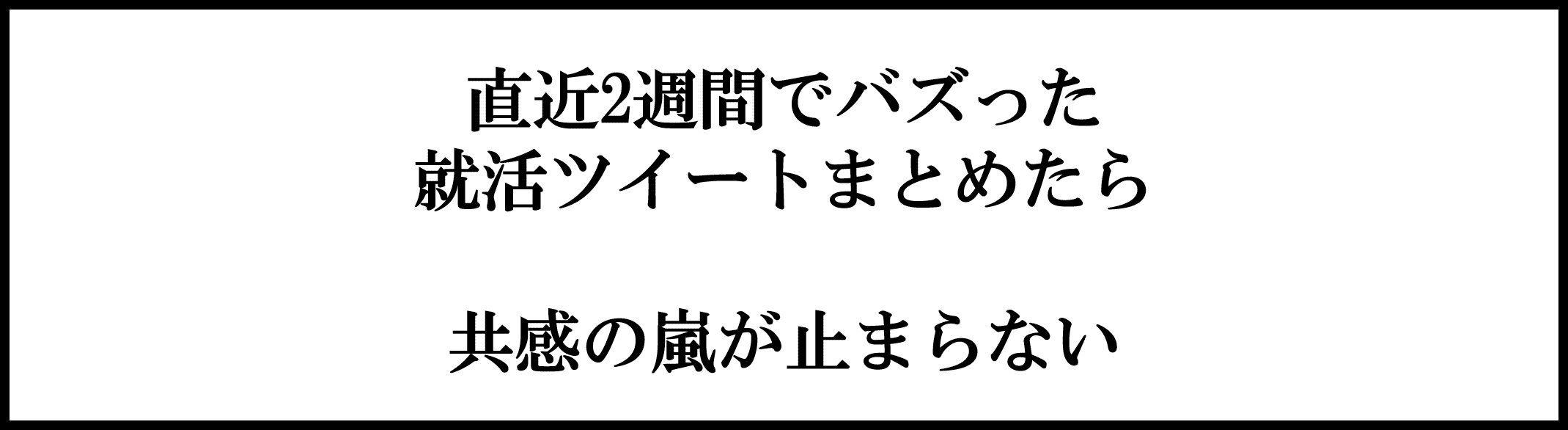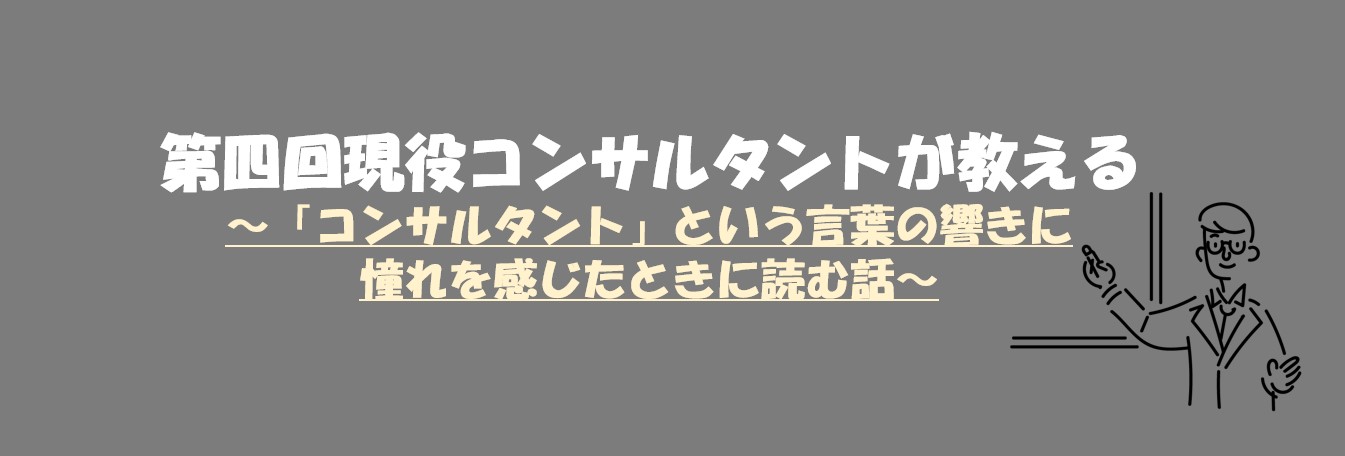目指すは「経営情報の大衆化」データ活用のトップランナーが視る、DXの未来とは。
4,812 views
最終更新日:2023年09月28日

「経営情報の大衆化」を目指し、日本経済に貢献していくー
昨今「DX」という言葉が頻繁に聞かれるようになったが、その中で1991年からDX・データ活用に携わり、今も数多くの大手企業のDX・データ活用を支援する企業が「株式会社ジール」(以下、ジール)である。
長きにわたりDX・データ活用に携わるジールが見つめる未来、実現したい社会、そして業界をけん引することのできる人材とはどんな人物なのか。
unistyle編集部は今回、ジールの取締役を務める沼田氏にインタビューを実施した。

沼田 善之(ヌマタ ヨシユキ)
株式会社ジール 取締役 COO。2001年に株式会社DHI(現・株式会社ジール)に入社。2013年に同社取締役に就任。新卒/中途の最終面接官を務め、1000名以上の面接を担当。
・IT業界において市場価値を高めたいと考えている就活生
・DXやデータ分析に関わる企業の選考を受けたい就活生
・若手から裁量をもって成長したいと考えている就活生
- 目次
- 増え続けるDX支援企業。取締役自ら語るジールの強みとは
└事業変革のためのDXという事業
└強みは「提案の幅の広さ」×「伴走」 - DXのリーディングカンパニーのトップが視る、DXの未来の姿
└「採用競合は同業他社ではなく、全ての企業。」その言葉の真意
└目指すは「経営情報の大衆化」 - 最前線で未来を見つめる「ジール」で働く魅力
└新入社員に求めるのはデータへの興味と素直さ、考えようする「オープン」な姿勢
└あらゆる企業のDX・データ分析を推進できる市場価値の高い人材になれる
└ジールで働くと価値提供ができる人間になれる
└若いうちから専門知識を駆使して裁量権を持って働くを実現できる秘訣 - 最終面接で「大学で研究していた内容」を聞く理由とは
└データへの興味関心と、相手にそれを分かりやすく伝えるという思い
└みんながガツガツ成長しなければいけないわけではない - 取材後記
増え続けるDX支援企業。取締役自ら語るジールの強みとは

事業変革のためのDXという事業
__早速ですが、ジールの事業内容をお伺いできますでしょうか?
企業のDX推進への支援がジールの事業でございます。
DXとは単なるデジタル化ではなく、デジタルから発生するデータ、このデータを活用する事で、既存の業務やビジネス、サービス、社会全体を変革することと我々は捉えております。
DXで一番重要であるデータ。このデータに基づいて意思決定や判断、予測、アクションすることをデータドリブンと言いますが、データドリブン経営を支えるデータ活用基盤の提供により、企業のDXを推進し社会全体の成長を目指しております。
DXの中で一番重要なのはデータをいかに活用していくかということです。
ジールでは、企業の社内外のビッグデータを活用しやすいように、データプラットフォームの構築支援を行っています。
例えば、ある総合商社様では、現行システムをクラウド化し、膨大なデータにも対応可能な優れたデータ分析基盤を導入したいという課題がありました。
そこでジールは、Oracle Cloudに関する高度な知識とインテグレーション力を用いて、数億行にわたる大規模なデータ基盤のスムーズなクラウド移行を実現し、コストを抑制しながらも圧倒的に優れた処理能力を有したデータ分析基盤を構築しました。
結果として、営業の現場からは「これまでレポート表示ボタンを押してから最大1~2時間程度かかっていた処理が数秒で返ってくるようになりました。全社的な視点で考えれば、こうした処理時間の短縮は大幅な生産性向上に貢献していると考えています」など、評価の声が寄せられました。
また、データ活用基盤の基盤とは、多種多様、大量のデータを活用可能となるデータプラットフォームを開発し提供するだけでなく、データ活用を社内で定着するためのコンサルティングやDX人材育成サービスの提供により、組織基盤の構築まで支援しております。
強みは「提案の幅の広さ」×「伴走」
__DX推進というところに参入してきている企業はたくさんあるかと思いますが、その中でジールの「他社には負けない」という強みは何でしょうか。
他社と比較した際の強みは、お客様がDXを推進するにあたってどんな課題を持ち、将来どんなことをやってみたいのかなどを、当社はシステム開発から運用の定着まで一貫してお客様と伴走できることです。
DX・データ活用というのは、ここ数年で膨大な量の製品が出てきています。その中で、日本製から海外製など多様なサービスをお客様に幅広くご提案できる会社は、日本企業ではジールしかないという自負があります。
幅広い商材を提案することで、お客様がDX・データ活用を始めるときに、DX・データ活用の「方法だけ」を支援するのではなく、お客様のDX・データ活用方法の選択肢を広げることができます。
DXのリーディングカンパニーのトップが視る、DXの未来の姿

「採用競合は同業他社ではなく、全ての企業。」その言葉の真意
__ジールはDX支援事業等を基盤として長きにわたり事業を展開されていらっしゃいますが、今後、DXがもつ価値や役割はどのようになっていくとお考えですか。
DX・データ活用の市場規模がさらに拡大していくことは、この場で私が言わなくても、誰もが認めるところです。
では、なぜ市場規模が広がっていくのかと考えると、やはり社会でDXは必要不可欠になるからです。
従来の企業におけるIT投資を振り返ると、いわゆるSIerに対して「システムを作ってください。すべてお願いします。」という受託開発型が大半でした。
しかし、最近ではDXが自分ごととなり、開発も含め自社でDXを進めていこうという流れが主流になっています。つまりDXの内製化です。そうなると従来の「ユーザー企業とIT企業」という関係性ではなく、お客様自身がIT企業のような側面も含んでいきます。そして、その流れはすでに始まっています。
そのため、今我々の採用上での競合他社は、一般企業になっています。その中で我々含めたIT企業の役割は大きく変わっていきます。
とはいえ、お客様が自社でDXの全てを内製化するのは、まだまだ難しいです。そこで、お客様が自社でDXの内製化からデータ活用の定着化まで、本当の意味でのDXが達成されるところまで伴走してくれるパートナーが求められており、実際にジールではDXを支援するサービスを多数提供しています。
支援サービスの一例として、国や自治体が公開しているオープンデータを使いやすく加工して配信・提供しているジールの「CO-ODE」という製品があります。
オープンデータ自体はお客様自身で入手する事は可能です。しかし、日々更新されるオープンデータを定期的にダウンロードし活用する事はユーザー部門では難しく、お客様のデータ分析担当者によるデータのダウンロード、加工、更新作業が必要であり手間もかかります。
それを我々の「CO-ODE」を利用することで、様々なオープンデータの収集・加工・更新の作業負荷が無くなるため、誰でも容易にデータを取得することができ、要因分析・原因分析・将来予測に利用することが可能です。「CO-ODE」で容易に取得したオープンデータを、お客様のデータと掛け合わせることで、データ分析の高度化を実現することができるのです。
ジールにはに単なる「DX・データ活用の支援」に留まらず、お客様のニーズに応え「DX・データ活用」をより高度に実現していくための支援をパートナーとして求められるようになっているのです。
目指すは「経営情報の大衆化」
__企業がDXを自社でできるようになるための手助けをしていくような会社になる、という未来なんですね。そうした大きな時代の変化がある中で、ジールが掲げるミッションはなんでしょうか。
ジールは、「経営情報の大衆化」をミッションとして掲げています。
ここ数年、企業を取り巻く経営環境は大きく変化し、企業価値や評価基準も変わっています。
企業価値の向上を目的とするガバナンス改革やDXの推進、さらには企業にサステナブルな成長を求めるESG投資の台頭です。企業に求められるのは、どのように社会的に持続性があり、かつ成長できるかを表明することです。
よって企業は今、これまで通りの財務情報だけではなくて、その企業活動を様々なデータを利用して開示しなければいけないですし、そこから意思決定・判断・未来予測をしなければならない状況に置かれています。それは経営者だけでなく、従業員も同じで、データを活用して意思決定や分析を求められる状況が増えています。
そのため、ジールのサービスを世の中に広めることができれば、あらゆる企業やその従業員がDX・データ活用をする文化を根付かせ、企業成長を促進させることができます。
これこそが日本社会全体の、いわゆる「経営情報の大衆化」に繋がるだろうと考えています。
最前線で未来を見つめる「ジール」で働く魅力

新入社員に求めるのはデータへの興味と素直さ、考えようとする「オープン」な姿勢
__これまで情報系を専門として学んできた学生にとって、DXを扱う企業がたくさんある中で、あえてジールを選ぶ面白さや魅力は何だと思われますか?
DX・データ活用に携わりながら、システム開発から定着化するためのコンサルティングまで、幅広く経験できるのが魅力です。
若いうちから幅広い経験値を積める環境は、ジールの一つの特徴です。
つまり、学生時代にデータサイエンス、プログラミングや統計学を学んだ学生であれば、学びを活かしてスピード感をもってスキルアップができ、いろんなことにチャレンジできる環境になります。
あらゆる企業のDX・データ分析を推進できる市場価値の高い人材になれる
__では、実際にジールで働くことで得られる価値は何だと思われますか。
ジールのお客様は、業界内でリーディングカンパニーと言われている企業がほとんどです。若いうちから様々な業界のリーディングカンパニーのDX・データ活用を経験できるのはジールで働く魅力です。
そのため、仮に転職をするとなった場合、「キャリアチェンジ」ではなく「キャリアアップ」を狙えます。
今までのITエンジニアのキャリアといえば、例えばプログラマーからSE、SEからPMになり、キャリアアップをするのが一般的でした。
しかし今後は、IT企業、例えばジールでDX推進やデータ活用という経験を積み、他の企業でDX推進の責任者としてやっていく、というキャリアも多くなってくると思います。
市場価値が上がることで、「キャリアチェンジ」ではなく「キャリアアップ」ができるのが、ジールで働く大きな価値だと思います。
ジールで働くと価値提供ができる人間になれる
また、ジールが働く上で大事にしている価値観というのはOPEN/VALUE/STRETCHの三つの軸になります。この中で、VALUE、つまり価値を決めるのは自分ではなく他者です。
その「価値」を上げるためには、他者の目線や、顧客の視点に立って考えるということが非常に重要です。
お客様と対峙するとき、単純にそのお客様の言われた通りするのでは価値の提供になりません。お客様に本当に必要なことは何なのか、それに対してしっかり考え、開発する上で様々なことを提案することが求められるため、顧客志向で考え、価値提供しようという姿勢が根付くのは、ジールで働くもう一つの魅力です。
また、「価値の提供」はお客様に対してだけではなく、仕事をする上でも先輩や後輩、メンバー同士でも相手目線に立っていろんなことを考えるということになります。相手にとっての価値は何なのか。それを突き詰めていくことが最終的には自分の価値が上がっていくことに繋がります。
知識を駆使して裁量権を持って働くを実現できる秘訣
__ジールの事業内容の特性上、専門知識や高度な経験をお客様から求められると思っています。一方で、ジールでは若手のうちから裁量権をもって仕事ができるという魅力があるとも思います。一般的な企業だと、割と相反するというか……知識や経験を得るために、ある程度の期間が必要なケースが多いと思うんですが、その中でもなぜそれらを両立できるのでしょうか。
仕組みというより、先ほど言ったVALUE、お客様にとって何が価値なのかを考えることが、それを両立できる秘訣だと思います。「言われたことをやる」という経験値と、「自分で考えて行動してやる」という経験値は、同じ1年でも全然密度の違う経験値です。
しかし、一番業界に詳しいのはお客様です。
その業種業界に介入して仕事をするとき、当事者意識をもって「お客様にしっかり聞く」ということや、「お客様側に立って考える」ことで、業界業種における経験値は大幅に短縮できます。
もちろん、経験値を補うための研修や、業界の方から様々な声を聞くことは会社として行っています。一方で、当事者意識であったり、経験値の差の短縮というのは、どこまで「顧客志向」を大切にできるかという点が大きいと思います。
最終面接で「大学で研究していた内容」を聞く理由とは

データへの興味関心と、相手にそれを分かりやすく伝えるという思い
__就活生に向けて伝えたいメッセージはありますか。
「入社までにどういうことをやっておけばいいですか?」という質問を就活生からよくもらいます。そこで私が常に言っているのは「研究論文の中のデータを、可視化してください」という話をしています。
論文に使用されているデータがただの羅列になっていると、読み手が非常に理解しづらくなります。「グラフ化などで工夫をし読み手に分かりやすく伝えることを取り組んでください」、と伝えています。
私は面接で、大学で研究していた内容を聞くことが多いです。
研究したことがインプットされていて、それを他者にアウトプットできる力があるのかを見極めるために聞いています。
当然、私にわからない研究をしている学生もいます。しかし、それを非常にわかりやすく説明できる学生がいる一方、「どうせ分からないだろう」という態度で説明する学生もいます。
同じ話の内容でも、相手に対してどのように説明すればいいのかということや、自分の言いたいことだけ話すのではなく、相手に自分を知ってもらう方法を考え、それを事前に準備して面接に挑んでほしいなと思っています。
__論文の書き方やその伝え方も、顧客志向に通ずるんですね。
みんながガツガツ成長しなければいけないわけではない
ジールは若いうちから幅広い経験値を積める環境で、スピード感をもってスキルアップができる、様々なことにチャレンジできる環境だと話しましたが、一方でそのスピード感を自分で調整できるというところは、ジールの特徴でもあります。
早く様々なことを習得して、チャレンジしていきたい、キャリアアップの道筋も早めていきたいという人もいれば、逆にじっくり取り組みたいという人もいると思います。
そういうのも認められ、自分のキャリアを着実に作れるというのは、ジールで働く上でのもう一つの魅力なのかなと思っています。みんながキャリア開発、ガツガツ働く、という雰囲気ではない。みんなそれぞれ好きなように自分のキャリアを考えて周りの先輩や上司と相談しながらやっていくことができます。
当然キャリア開発が早い人もいれば、そうじゃない人もいる。多様性を大切する文化もジールの特徴なのかもしれません。
取材後記
「経営情報の大衆化」をキーワードに、事業展開を進めているジール。
顧客視点を第一に考え、お客様への価値提供のみならず、働く社員自身の価値の向上も目指している会社だということが伝わったのではないでしょうか。
今回はDX・データ活用のトップで活躍し、ジールの取締役を務める沼田氏にお話を伺いました。
そんなジールは現在24卒向けのエントリー募集を開始しています。
本記事を通じて同社に興味を持った就活生は、下記の応募フォームから是非エントリーしてみてください。