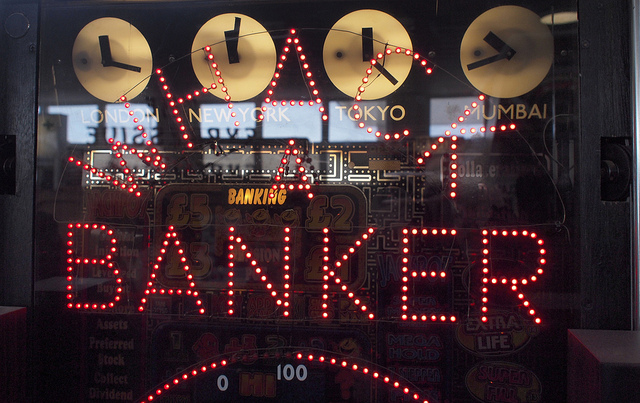学校では教えてくれない。IQよりもEQが高い人がGD最強説
17,771 views
最終更新日:2023年10月27日

EQという言葉を耳にしたことはありますか?
「IQの高い人がビジネスでも成功する」という通説にピーター・サロベイ博士、ジョン・メイヤー博士が疑問を持ち、心理学の立場から、「ビジネス社会における成功要因は何か」を探りました。調査の結果わかったのは、「ビジネスで成功した人は、ほぼ例外なく対人関係能力に優れている」というものでした。そこで生まれた概念が「EQ」です。
本記事では、「EQ」を活かせば企業にとって欲しい人材となれることを提示したいと思います。
ビジネスでは、IQよりもEQが重宝される

はじめに、「EQ」とは何でしょうか。
EQ(Emotional Quotient)とは日本語に訳すと、「心の知能指数」もしくは「感情指数」とされています。わかりやすく一言にまとめると、「自分および他者を理解し、受け止める能力」のことであり、多くの人がご存知と思われるIQ(intelligence quotient)に比する概念です。
「IQの高い人がビジネスでも成功する」という通説にピーター・サロベイ博士、ジョン・メイヤー博士が疑問を持ち、心理学の立場から、「ビジネス社会における成功要因は何か」を探りました。調査の結果わかったのは、「ビジネスで成功した人は、ほぼ例外なく対人関係能力に優れている」というものでした。そこで生まれた概念が「EQ」です。
ビジネスから生まれた概念であることからも、EQがビジネスに役立つことは間違いないですよね。世界トップ企業といわれる「フォーチュン500社」のうち、8割の企業が採用・教育等によって自社になんらかの形でEQを導入しています。つまり、就活においての面接やGDでも間違いなく有効活用ができます。
皆さんの周りにも「特別賢いってわけでもないのに、いつもクラスの中心にいて、尊敬されている」一目置かれている人っていますよね。そういう人がいわゆるIQではなくEQが高い人です。
さて、具体的にEQとはどんな能力で構成されているのでしょうか。「感情」がキーワードになりそうです。
EQを構成する4つの能力

EQは一般的に4つの能力から構成されています。
▶︎感情の利用:自分の感情をその状況で適切な状態、問題解決に役立つ状態へと持っていく能力。
▶︎感情の理解:自分や他者がなぜそのような感情を得たのか、またその感情はどのように変化していくのかを推察する能力
▶︎感情の調整:他者の感情に働きかけるために、自分の感情を適切に調整する能力
以上4つの能力は対人関係に置いて「識別」→「利用」→「理解」→「調整」の順で使われます。つまり、EQを発揮するためには、どれかが欠けてはいけないということがわかります。
次に、上記4つの能力の優れている人と劣っている人の特徴をまとめたものを提示します。
EQに対する優劣の指標
優)空気を読むのが上手い
劣)周囲に無頓着、浮きやすい、強引なところがある
【感情の利用】
優)他者との同調が上手い、ポジティブに考える、モチベーション管理が上手い
劣)コミュニケーションを避けがち、ネガティブに考える、モチベーション管理が下手
【感情の理解】
優)相手の感情の先読みができる、説得が上手い
劣)人をイライラさせやすい、自分が雰囲気を悪くしていると考えない
【感情の調整】
優)良好な人間関係が築ける、「人格者」としてみられやすい
劣)周囲とぶつかりやすい、周囲を無視した行動をとる
なんとなく、ご理解いただけたでしょうか。EQが高い人とは総じて人望が厚く、社会に出ても出世しそうですよね。いわゆるいつもクラスの中心にいる人気者のイメージに近いと思います。
さて、EQはどのように就活でも活用されるのでしょうか。グループディスカッションを例に考えてみましょう。
EQが高い人がグループディスカッションで評価される理由

企業が学生に求める「一緒に働きたいと思えるか」という抽象的なものに対する指標の1つに、「良い人間関係を築くための能力があるか否か」があります。
この、「良い人間関係を築くための能力」を企業が重視する理由は、他記事でも再三再四述べていますが、企業と名のつく組織で働く場合、一人で仕事をすることはまずありえないからです。
そのため、人と働いていく上で必要となる、メンバーの発言を理解する・自分の考えをきちんと伝える・円滑に議論を進めるためのEQの高い対人関係能力が必要不可欠です。
では、就活でどのようにEQスキルが現れるかということを「グループディスカッション」を例にしてみます。
グループディスカッション×EQ
この2つを根底に持ちつつ、グループディスカッションにおいては、以下の4つの項目で評価しています。
②議論のテーマや流れへの理解力
③自身の意見の主張力
④議論を統率するリーダーシップ
この4つの評価項目とEQを構成している能力と紐付けると、以下になります。
・人の意見を遮らずに聞けるか(感情の識別)
・自分と異なる意見でも尊重できるか(感情の理解)
・発言していない人に発言を促す、大きな声で話す等、周囲の状況に気を配ることができる(感情の利用)
理解力
・議論の流れに沿った発言ができるか(感情の識別)
・ディスカッションの最終的な目標を理解した上で議論を展開できるか(感情の調整)
・テーマに対する鋭い分析ができるか(感情の調整)
主張力
・根拠に基づき主張を展開できるか(感情の調整)
・完結にわかりやすい主張ができるか(感情の調整)
・自分ならではのユニークな主張ができるか(感情の調整)
統率力
・問題を的確に理解し、議論を適切に進行できるか(感情の調整)
・横道にそれた議論を軌道修正できるか(感情の調整)
・時間内に結論を出すべく進行できるか(感情の調整)
ここから、EQが高い人は明確にグループディスカッションにおいての評価が高くなることがわかります。相手の考えを汲み取った上で適切な対応ができるため、議論をスムーズに進めることができ、選考官からの評価が高くなるためです。
最後に

いかがでしょうか。あなたは自分自身のEQが高いとは思いますか?
ビジネスに必要な能力には、IQやスキル、業務知識や経験など、いろいろなものが考えられますが、優れた人材はこれらの能力に加えて、対人関係能力を持っています。将来どんな仕事をしようとも必ず人と働くことになり、対人関係能力は必要不可欠になります。
こうした「人間的魅力」を支えているのがEQです。そして、EQは後天的に身に着けることができる能力です。まずは、自分と他人の感情を知り、汲み取ることからやってみましょう。日頃から意識しておくと企業に属した後にも役に立つでしょう。