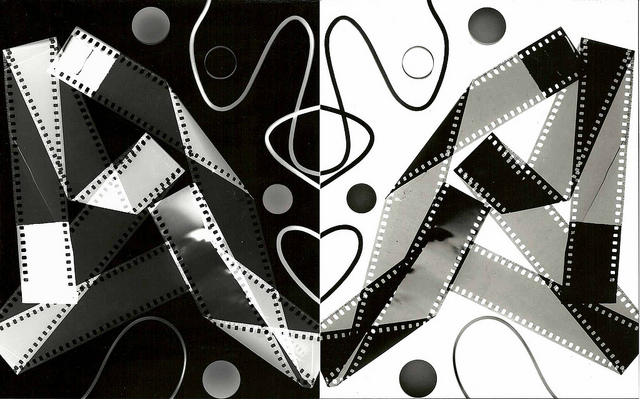「就活の進め方」大手メーカー内定者による質疑応答
36,512 views
最終更新日:2023年10月30日

先日、大手食品メーカーの内定者と就活生によるWeb質問会を開催いたしました。その際に多くの就職活動生の参考になる受け答えがありましたので、ここに記事として残したいと思います。食品メーカーを志望している方もそうでない方も参考になると思いますので、ぜひお読みください。
・回答者プロフィール
・多くの業界を受ける際の就活の軸や自己分析について
・食品メーカーの志望動機の作り方や業界研究について
・絶対に手を抜いてはいけない!ESやWebテストについて
・比較的基本的な質問が多い、大手食品メーカー面接の質問について
・自分のキャラクターを伝えるために意識した、面接でのテクニック
・大手食品メーカーの内定者の学歴や、人間性について
・最後に
回答者プロフィール
 【自己紹介】
【自己紹介】
大学:文系(私立)
学生時代に頑張っていたこと:大学の準体育会部活
内定先:大手食品メーカー2社、外資系消費財メーカー、不動産ベンチャー
一言:食品メーカーに絞らず多くの企業群を受けていました。総合商社、証券会社、エネルギー業界など。就職活動はやりきったと思っているので、経験を生かし色々な質問にできる限り答えていこうと思います。よろしくお願い致します。
多くの業界を受ける際の就活の軸や自己分析について

◆就活の軸は色々な企業を見ていく上で定める
どのような就活の軸をお持ちでしたか?軸に基づきどのような業界を受けていましたか?その中でもなぜ内定先の食品メーカーなのかといったことがあれば教えて下さい!!
6月からはもう企業はだいぶ絞れてきたので、自己分析を行って自分がその企業を志望する理由をもう一度考え直して志望動機を再検討していました。
最初の内定が出たのは4月の頭でした。外資系消費財メーカーです
◆キャリアパスを考えるためには採用HPで先輩社員のインタビューを読んだ
キャリアビジョンについて少し詳しく聞かせていただければ幸いです。今現在、自分のキャリアについて考える中で情報量の少なさや、やはり働いたことのないこともあり、具体性を持たせることが難しく、苦労しています。
また説明会でも社員の方にキャリアの王道的なのはあるのかと積極的に聞いていました。イメージしづらいものは関連する小説や映画などを調べて見てみるのも一案だと思います
◆自己分析はあくまで手段であり目的ではない!面接での反応を見て実践的に自己分析
自己分析は、どのくらいの期間を掛けて行いましたか?
自己分析は自己満ではなく面接官の視点に立って行わなければ意味がないです!
友達にはボイスレコーダーで録音し、反省を行っている人もいました。
◆就活解禁直後は志望度の高い企業から説明会に参加!
3月からはどういう手順で動けば要領良く進むと思われますか?
志望度の高くないものでもとりあえず一回説明会に参加すればエントリーシートのレベルを1つあげることができると思います。
◆選考シーズンは落ち込んでいる暇などない!落ちた原因は「企業に合わなかっただけ」と考えた
面接で落とされたときにどうやってモチベーションを上げ直したか教えてください!
それより選考シーズンは本当に怒涛の勢いで過ぎていくので、落ち込んでいる暇はないですよ!
◆軸は必ず自分の過去の経験から根拠だてて説明できるようにするべき
就職活動においての軸としていたものを教えてください
でした!軸は自分の経験からなぜその軸かを確実に説明できるようにしてくださいね。
食品メーカーの志望動機の作り方や業界研究について

◆志望動機は自分の経験を企業の業務内容にリンクさせて考えよ!
食品メーカーそれぞれの企業の違いについては意識していましたか?例えば明治と森永は併願している人が多いと思いますが、ライバル関係のある会社同士の違いについて徹底的に調べるといったことはしていましたか?
内定を受けた食品メーカーから他社と比較してウチはどうかといった質問はなかったです。
◆会社に入ってどのように活躍するのかをイメージしやすいような志望動機を意識した
食品メーカー、消費財メーカーそれぞれの志望理由ではその商材に関する経験などを盛り込んだのでしょうか?
どうしてもその商材が良い理由や経験があったほうが説得力は増すのでしょうか?
使い方としては
社会がこんな問題を抱えている、こんなニーズがあるといった問題意識がある。こんな想いから商品で変えたい!という流れから
↓
その商品開発の動機を自分の行動の動機にリンクさせて
↓
部活動でこんな問題があって、こういった思いで対処しました。これって貴社のあの商品と似ているなって思います!
的な回答をしていました。商品が好きだけだとお客様になってしまいがちなので、会社に入ってこう活躍できるというイメージを面接官に持ってもらうことを大切にしていました。
◆具体的な志望動機は家庭環境まで掘り下げ、自己PRは部活についてのみ
志望動機や自己PRはどのようなこと内容か教えてほしいです
↓
ものが増えて豊かさを感じていた
↓
私にとって身近なものが幸せを感じさせてくれる
↓
だから生活に近いものを扱う企業。その中でもそれを作る側に回り、自分が商品の親になりたい。
大学で新しいスポーツに挑戦し個人として全国で活躍、部長としてチームを導いた。
↓
この経験から自分は態度でチームを導き成功できる。
といった感じです。
◆メーカーは企業の商品を見ていくことで企業の色が分かる
数ある食品メーカーの中で、どのように受ける会社を決めましたか?
その色から直感的に選んでいきました。また大企業の方が将来的に多くのことに挑戦できるだろう考えから大企業メインで考えていきました。
絶対に手を抜いてはいけない!ESやWebテストについて

◆SPI対策はしっかりやるべき。時間制限があることも注意!
食品メーカーの筆記試験対策は主にSPIを勉強すれば大丈夫でしょうか?
SPIは実際に試験会場で受ける経験が大切だと思います。時間制限が本当にきついので。。。私は結局12回ほど受けなおしました。
◆ESを読む相手が社会人であることを意識するべき Unisyleのフレームワークを参照
大手食品メーカーに受かるにはESはどのようなポイントをおさえるべきでしょうか。
私も後輩のesを添削しますが、内容レベルはどっこいどっこいです。逆を言えば、学生が遠い記憶になっている社会人に対してもわかりやすい文章が書ければそれだけで評価は高いと思います。客観的な添削を多く受けてみてください。
◆ESは読みやすさを重視せよ!1つの設問に対して多くのエピソードを盛り込むな!
食品業界は人気の業界ですが、ESを書く際に気をつけていたことはありますか?
一つの設問に対して多くのエピソードを盛り込まない。Unistyleの志望動機フレームワークを意識して、伝えたいことを明確にする。
私の場合はエピソードから学んだことを特に明確にしていました。
◆ESで伝えるキャラと面接でのキャラは合致しているほうが良い
ご自身で、他の企業も含めどうして内定が得られたと考えますか?
具体的には主体的に動き、他者を巻き込んで一人では成し遂げられないことを行ってきた→会社でもその能力を存分にいかしますよ
をはっきり伝えられたことです。経歴がそこまですごくないので自分のキャラに逐一立ち返り説得力とわかりやすさを意識してました。
比較的基本的な質問が多い、大手食品メーカー面接の質問について

◆大手食品メーカーの面接での質問は基本的にオーソドックスなもの
面接ではどのような質問をされましたか
もう一社は〜に必要なことを3つあげよ→その理由は?という質問形式でした。
しかし両者とも面接が進むにつれオーソドックスなものが大半でした。
◆オーソドックスな質問の中で、幼少期の経験も聞かれた
二社、内定をもらったとの事ですが、最終面接で聞かれた質問を教えてください。宜しくお願い致します。
◆面接で変わった質問はされていない。理由をしっかり述べられることを意識
食品メーカーではなにか変わった質問をされたことはありますか?あればどんな質問があったのか教えてください。
変わった質問に対しても、ウケ狙いはせず、なぜこの回答をしたのかという理由をしっかり述べられるようにしていました。
自分のキャラクターを伝えるために意識した、面接でのテクニック

◆面接では自分の経験と会社の動向を照らし合わせ、話しやすい内容を選んだ
消費財ならば1人暮らしの男性の柔軟剤に潜在的ニーズがある。といったように、社会が抱えてる問題はメーカーの商材ごとに変えていたということでしょうか?
漠然とした問題について(高齢化など)、その会社はこの商品でこの方法でアプローチし、問題に対してこの立ち位置(主体的なのか補助的なのかなど)をとってるんだを理解し、僕の経験である部内の問題に対して、このようなアプローチを行った!と言う風にアプローチ方法や立場を企業ごとに考えていました。
◆面接では単なる暗記ではなく、自分が誇りに思うことを熱く伝えることが大切
「自分の活動に関して誇りを持っているところ」を評価していただいたとのことですが、私自身の学生時代の経験をアピールする際に同様に評価してもらうためにアドバイスがあれば教えて下さい!マイナースポーツをやられていたとのことですが、私自身もマイナーな取り組みをしているので参考にさせていただきたいです。
あとは内容だけではなく、発言するときの態度も単に記憶したものをなぞって言うのではなく、多少演技がかっても熱くいうことが大切ではないでしょうか!
◆面接では元気よく、はっきりと話す。自分のキャラが伝わるように意識した
また、面接の際に気をつけていたり、心がけていたことがあれば教えていただきたいです。
マイナースポーツをしていたのでウィキなどで門外漢の面接官にも伝わるようちょっとしたテンプレートを作っていました。あとは元気よく、はっきり、自分のキャラが伝わるように努めていました。
◆差別化をすることに意識しすぎる必要はない!話し方や態度から伝わるものである
ESや面接では、他の学生と何か差別化するために行ったことはありましたか?
これは人事の方に伺ったのですが、差別化は意識しなくてもその人の話し方や態度から見えてくるとおっしゃっていたので、少しでもキャラをしっかり確立させることが大切かとおもいます。
◆質問に回答するときは常に自分に立ち返ること
最終面接の質問内容や雰囲気を教えてください。
ポイントは繰り返しになりますが回答の際には常に自分に立ち返ることです。そうすれば発言に厚みが増します。
◆将来的なキャリアパスを具体的に話した。それによって自分を見直すこともできた
自分の志望動機やこれまでの経験を踏まえて、具体的にやりたい仕事などを面接では発言しましたか?
◆逆質問では社員の勤続年数を聞き、それに沿った質問をした
逆質問をする上でのポイントを教えてください。
大手食品メーカーの内定者の学歴や、人間性について

◆インターンシップが直接内定に関係するわけではないが、面接のクオリティをあげる上では非常に重要
インターンシップに参加しないと大手食品メーカーから内定が出ないのでしょうか?
インターンが直接内定に関係するかは、コネができるといった意味では関係しませんが、企業のことを深く知り面接での発言のクオリティを上げるといった意味ではとても有利だと思います。
◆内定者の学歴は旧帝:早慶:GMARCH:それ以外=3:5:2:0
文系、理系のそれぞれの内定者の学歴について、①旧帝大レベル、②早慶レベル、③GMARCHレベル、④それ以外で、それぞれの割合について教えて下さい。
理系は詳しくはわかりませんが、旧帝大と東工大でほぼ埋まっていた気がします。
◆大手食品メーカーに学閥はない。しかし、高学歴のほうが内定が出やすいのは間違いない
大手は学閥があるのでしょうか?
◆海外経験がなくても内定は取れる。しっかり自分の軸が面接官に分かるように伝えることが大事
食品メーカーでは海外展開の話が多い印象なのですが志望理由はそのことに触れましたか?
しかし私の場合は海外経験がなかったので、海外行きたい話は(他の留学経験者志願者に比して)説得力がないと思い控えていました。
あくまで自分の経験に基づいて回答し、自分のキャラクターが最終的にわかってもらうことが大切だと思います。部活動一色だったひとが海外大好きと言っても軸がぶれぶれですもんね。。。
◆内定者は自分の経験を熱く語れる人が多い
周りの内定者はどういった人が多いと感じますか?
最後に
 いかがでしたでしょうか。今回の質問会では大手食品や消費財メーカーだけについての内定戦略だけでなく、本人の具体的な就職活動の軸や業界研究の仕方まで知ることが出来ました。きっと多くの就職活動生の参考になる回答があったのではないかと思います。
いかがでしたでしょうか。今回の質問会では大手食品や消費財メーカーだけについての内定戦略だけでなく、本人の具体的な就職活動の軸や業界研究の仕方まで知ることが出来ました。きっと多くの就職活動生の参考になる回答があったのではないかと思います。
特に、準体育会系の部長としてどのように強みをアピールしたのか、そしてその強みをどのようにして志望動機につなげたかについては貴重な情報であったと感じます。ぜひ多くの就職活動生に今回の質問会で得た極意を生かして欲しいと思います。
photo by Martin Thomas


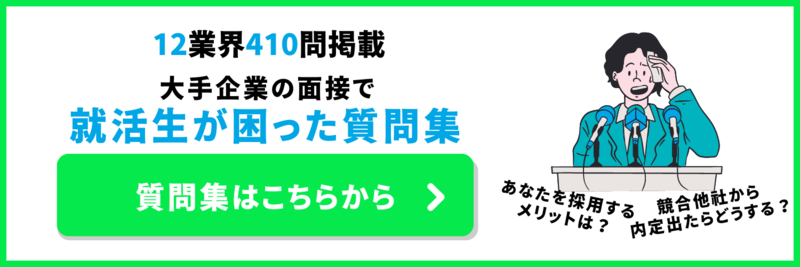



.jpg?1476160745)