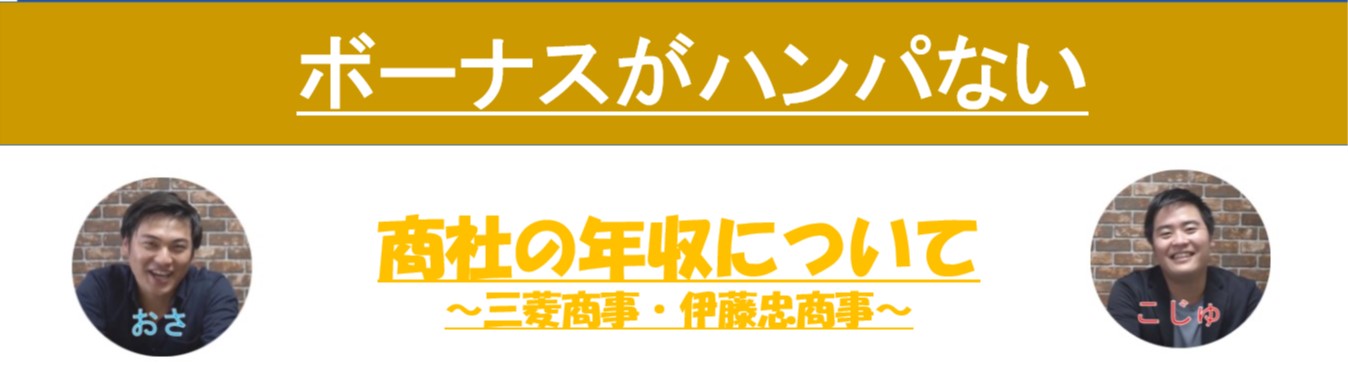無内定の長期留学経験者にありがちな5つの特徴
29,859 views
最終更新日:2023年10月27日

留学経験をうまくいかせず、無内定で悩んでいる人には、就職エージェントneoがオススメです。
アドバイザーから、他己分析してもらいながら自分にあった就職活動の進め方や企業の決め方を客観的にアドバイスがもらえるため、内定に一歩近づけます。
少しでも興味があるという方は、下記の画像をクリックしてサービスを利用してみてください。
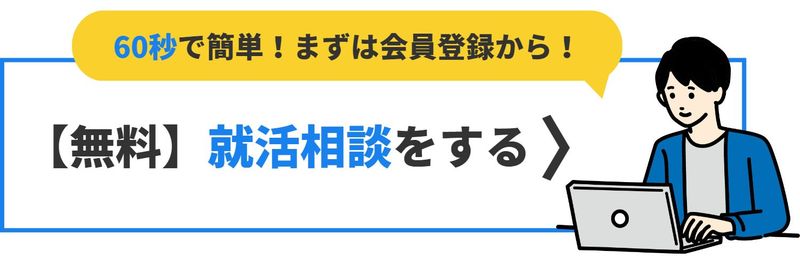
一般的に、就職市場において有利だといわれている留学経験者。
特に1年以上の長期留学経験では語学力のみならず、多様な価値観に対する理解力やコミュニケーション能力の向上も期待できます。こうしたさまざまな能力が企業側に評価された結果なのではないでしょうか。
しかし一方で、長期留学を経験した人の中にも「就職活動では苦労した」という話をちらほら耳にします。
主に「なかなか内定を得られず就活が長期化してしまっている」「内定を得たものの、自分が納得のいく企業ではない」などというケースです。
こうした状況を考えると、留学経験は必ずしも就職活動の武器になるとは限らないようです。
それでは、留学経験が就活にうまく活かせない人とは、一体どのような特徴を持っているのでしょうか。
筆者自身も留学・就職活動を経て、無内定の長期留学経験者にはある5つの共通項があるのではないかと考えています(自身の反省も含めて)。
本コラムでは、そうした「NG留学経験者」にありがちな5つの特徴を以下にご紹介します。
特に留学経験のある就活生のみなさんには、自身の就職活動と照らし合わせながら読んでいただければ良いのではないでしょうか。
無内定の長期留学経験者にありがちな5つの特徴
①語学力自慢だけ、中身のない就活生
特に1年以上の留学を経験した就活生で見られることがあります。
長期の海外経験から語学力に自信がつき、それをひけらかすことで就活を進めようとしてしまうタイプです。しかし、現実はそんなに甘くありません。
短期のものや語学研修が目的のものなど留学の形態は多様化していますが、2012年度の日本全体での海外留学者数は約20万3000人にも上るといわれています。(参考:JBPress )
そんな中、単純な「英語話せます自慢」で志望企業に内定をもらうことなど、ほぼ不可能だとは思いませんか?
言語はツールの一つに過ぎません。採用側は「英語が話せること」よりも「英語を使って何を話せるか」の方を評価しているのです。
②ことあるごとに海外では〜〜(自分の主張なし)
「海外だったらこうだったのに… だから日本はよくないんだ」などと、しきりに留学先の国の状況を引き合いに出す学生も見たことがあります。
しかし、こうした人に限って「自分自身の意見」を求められたときに言葉に詰まってしまうケースが多いように思いました。それでは、留学先で触れた価値観の単なる受け売りになってします。
グローバルスタンダードを知ることは重要なことですが、何でもかんでも自国の否定に終始してしまうのは非生産的ですし、何よりも企業で必要とされているのは多様な価値観に触れてより熟成された「その人自身の意見」ですよね。
③単に長く滞在しただけで、真剣に現地で取り組んでいない
ただ楽しそうだからという理由で留学し、現地で特別に目的意識もなく真剣に取り組まなかった人が陥るパターンです。
面接で留学経験があると言えば、たいてい「なぜ留学しようと思ったのですか?」「留学先で特に力を入れていたことは?」「留学先での専攻はどのようなものだったのですか?」といった質問が飛んでくることはほぼ間違いありません。
しかし、こうした質問が飛んできたときに急にうまく答えられなくなる留学経験者も実際にいるのです。一体何のため、何をしに留学へ行ったのでしょうか……。
④現地で何を学んだのか言語化できない
③とは異なり現地ではいろいろな経験をしていたとしても、それをうまく言語化できないケースです。
この原因は「自己分析不足」の一言に尽きます。もっと自身の留学経験を詳細に思い返し「何を考え、何を目標に、どんなことにチャレンジしてきたのか」を具体的に話せるようにしておきましょう。
これは留学経験に限りませんが、自己PRをする際に「がんばりました」に終始し、相手に自身の考えや努力をきちんと伝えられないのは非常にもったいないと思います。
⑤変に自信を持ち過ぎ
留学したことで良くも悪くも自信がつき、他の学生やはたまた人事部や面接官に対しても横柄な態度をとってしまっている学生を見たことがあります。
自信を持つこと自体はとても良いことですが、それと態度が大きくなることは別物です。
自信がある(=自分の考え・立場がしっかりとある)のなら、相手にそれを丁寧に伝えることができればベストです。
また、自身過剰が根拠のない余裕に繋がってしまい「大手企業しかエントリーしない」「面接対策をせずにぶっつけ本番」などといったリスクの高い行動をとっている就活生もいたように思いました。
以上が「無内定の長期留学経験者にありがちな5つの特徴」でした。
筆者の周りでも留学を経験していながら内定をもらえてない、もしくは納得できない企業からの内定しかない人がいることは事実です。
最後に
いかがでしたでしょうか。ここまでは、留学経験が就活の仇となってしまっているパターンを5つご紹介させていただきました。
しかし、そうはいっても言葉が伝わらない環境で試行錯誤、留学先で何らかの成果を上げようとした経験は就活においても評価される傾向にあります。
総合商社をはじめとする人気企業の内定者には実際に留学経験者が多くいます。それは語学力そのものではなく、言葉が通じないような人とも関係を構築して成果をあげることができたことを評価されたのではないしょうか。
(参考: 人気企業内定者に共通する5つの強み )
自身の就職活動を「NG就活」にしない対策法としては、上記でも述べているように「語学力」だけではなく「+α」の人間的魅力をアピールポイントとして磨いておくことが大切なのだと思います。
留学を経験した学生のみなさんは特にこの点を意識した上で就活を進めることができればよいのではないでしょうか。
photo by Martin Thomas