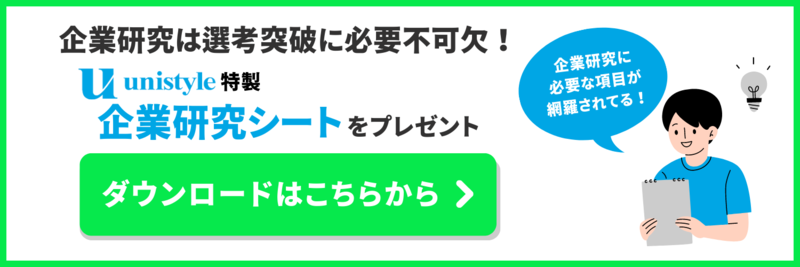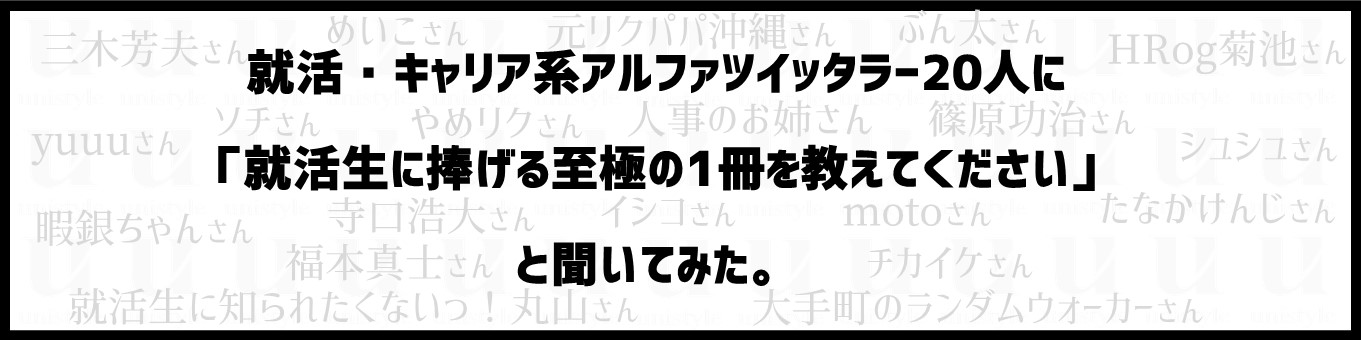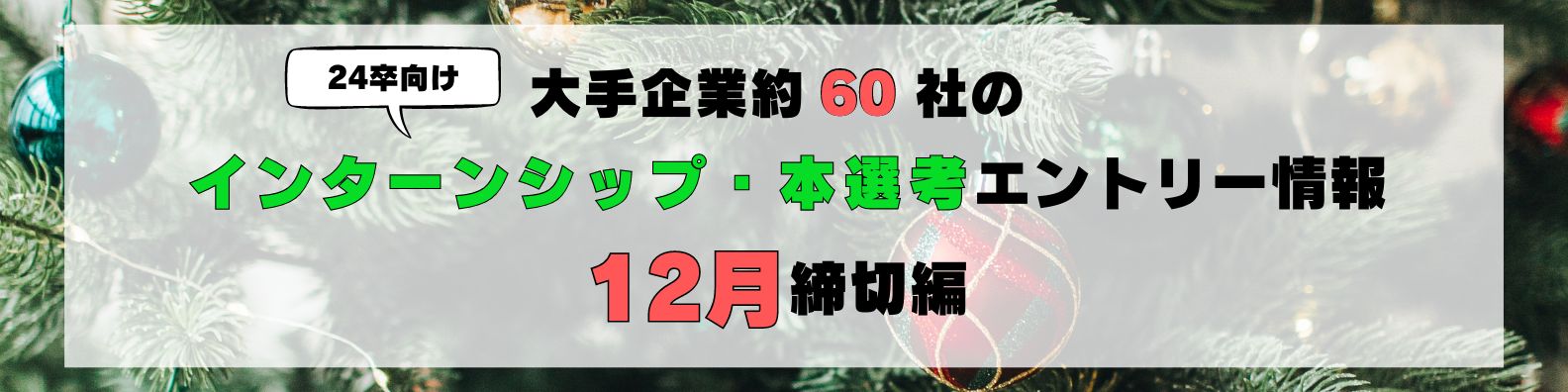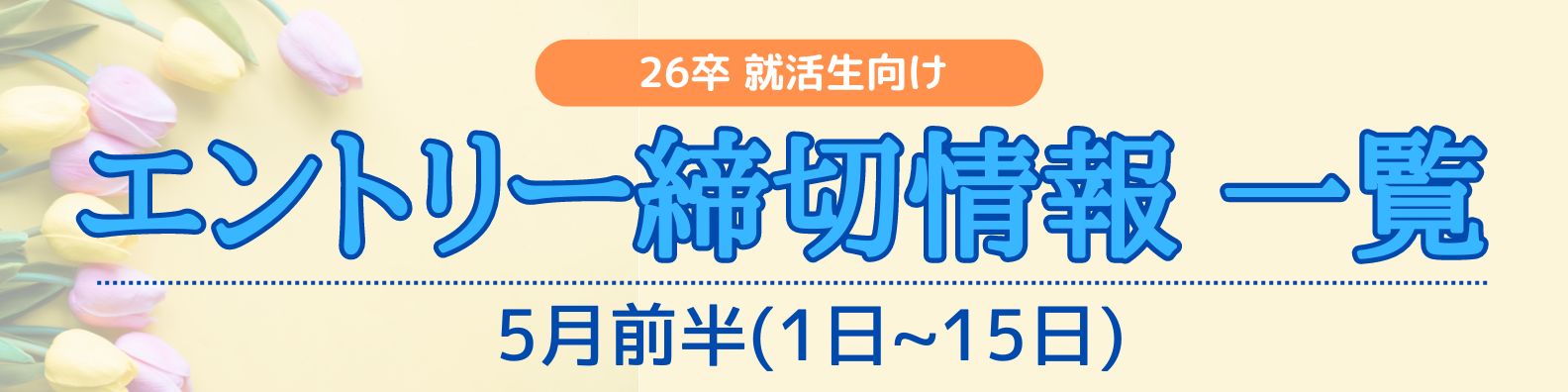【国連、UNICEF、IMF】新卒では入れない国際機関への就職とは
133,117 views
最終更新日:2024年10月21日

こんにちは。
現在国内のメーカーに勤務しているYです。
今回は私がこれまで出会った方々から伺ったお話、調べた事、そして多分の主観を織り交ぜて、国際公務員として働く道について考えてみたいと思います。
国際公務員って何?
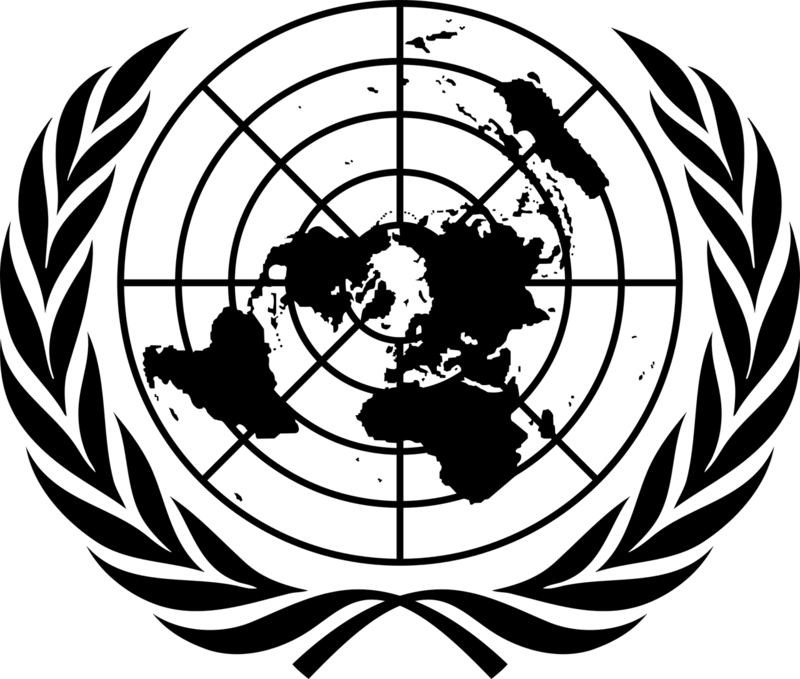
そもそも、国際公務員とは何でしょうか。言葉だけ聞くと、それは何か大きな事をする仕事なんだろうなぁ、なんてイメージを持ちがちです。
国際公務員とは、端的に言えばいわゆる国際機関で働く人たちの事を指します。公務員というくらいですから、そこにNGOなどは含めません。具体的に言えば、国際連合(UN)、より広くは国連システムの中に属しているいずれかの組織で働く者が国際公務員となります。
組織としては例えば、国連事務局、国連児童基金(UNICEF)、国連開発計画(UNDP)、世界保健機関(WHO)、国際通貨基金(IMF)等々があります。
上記の組織を眺めても、国際公務員と言っても実に多様な選択肢が有る事が分かります。この多様性が国際公務員の実態を分かり辛くさせている一因かもしれません。
しかし、その内実は其々の分野で高度な専門性を持った、プロフェッショナル集団と言えます。(国連の採用枠には、一般職と総合職の括りがあり、本稿で対象とするのは、専ら専門職です。)
そして大きな特徴として、終身雇用ではなく各ポストに2~3年の任期が設定されており、常に次のポストを探し続ける必要がある、という点があります。
国際公務員に必要な3条件

国際公務員≒国連職員を目指す上で満たすべき条件として下記の3つがあります。
1.修士号以上の学歴を有すること
2.応募するポストと関連する分野で2年以上の職務経験が有ること
3.英語またはフランス語で職務追行が可能で有ること
1,2については、国連職員は専門家集団である為、日本的な新卒という考えはなく、必要とされるのは常に専門家です。専門家としての要件として、学士ではなく修士、関連分野での2年以上の職務経験が求められています。
加えて、国連公用語の中でも頻繁に使われる英語もしくはフランス語で職務追行に問題ないレベルの語学力が必須です。(組織・ポストによっては、スペイン語等が必須とされる場合もあります。)
国際公務員へのキャリアパス

国連に勤務する為には、原則国連事務局、若しくは各組織から発表される空席情報に自ら手を挙げて、ポストを獲得する必要があります。その他にも下記の方法等があります。
・外務省が主催するJPO(Junior Professional Officer)として各機関に派遣後、国連職員として働きつつポストを探す
・国連事務局YPP(Young Professional Program)試験を受験する
・各組織が行う採用プログラム、ミッションへの応募
其々の選択肢で、求められる条件は違ってきますが、YPPを除く多くの方法では②で挙げた3条件が求められます。(YPPの場合、学士号でOKです。ただし、YPPは狭き門で、2012年度の実績として応募者41,023名、筆記試験対象者4,587名、面接対象者180名というデータが有ります。)
現在国連で働かれている日本人の4割はJPO経験者という事を考えると、JPOでの採用→公募ポストへの応募&採用という道が国連への道としては可能性が大きいようです。
ファーストキャリアをいかに選ぶべきか

では、国際機関で働く為のファーストキャリアとして、どこを選ぶべきなのでしょうか。
これは自身がどの様な分野でポストを見つけたいかに依ります。主な専門分野としては、次のものが挙げられます。
・開発、人権、人道、教育、保健、平和構築、モニタリング評価、環境、工学、理学、農学、薬学、建築、防災、人事、財務、会計、監査、総務、調達、広報、渉外、IT、統計、法務等
ご覧の様に、羅列しただけでも非常に多岐にわたる分野があります。この中から自分はどの様な専門をいくのかにより、ファーストキャリアも自ずと見えてくるのではないでしょうか。
ここでは更に現在国連で務められている方の具体的なキャリアパスを例示してみます(各情報は外務省及び国連フォーラムウェブサイトより)。
・Aさん
21歳:仏の大学に1年の交換留学→22歳:国内大学の商学部経営学科卒業→23歳:仏の大学にてMBA取得→24歳:会計事務所勤務→26歳:NGO活動参加後、インドネシアに半年滞在→27歳:民間企業2社勤務→29歳:米国公認会計士試験合格、JPO試験合格→30歳:WFPにJPOとして派遣(財務官)
・Bさん
国内大学卒業→外務省入省→米大学にてMA(政治学)取得→シンクタンク勤務→国内大学院博士課程→UNアフガン支援ミッション(分析官)
今、何をすべきか
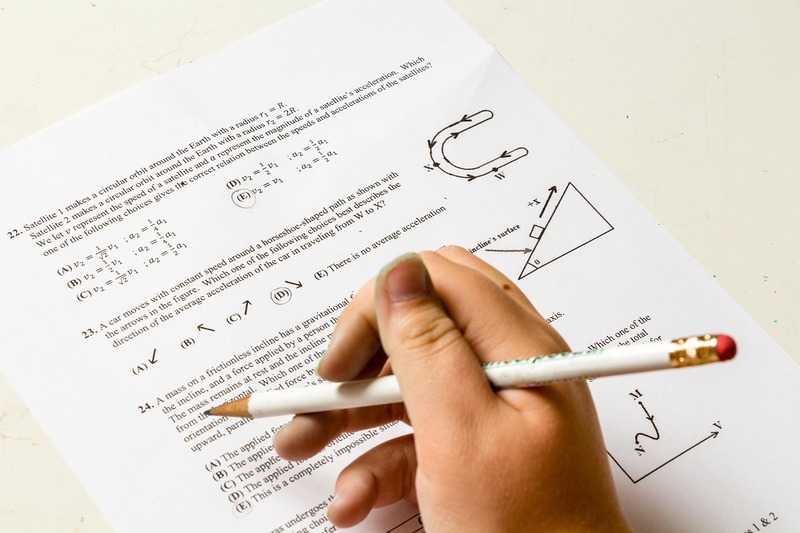
前の項で明らかな様に、国際公務員に成る為には決まった道はなく、唯一の正解は無い、と言えます。
ではそんな中で今何をすべきなのでしょうか。
第一に、語学力です。日本で教育を受けた場合、少なくとも英語は6年~10年間学んでいます。
ただ、職務追行可能なレベルの英語力が学校教育だけでは尽きません。よって留学等を通して、仕事をする上で問題の無い英語力を身に着ける必要が有ります。
参考までに、JPO合格者の方々はTOEFL-iBTにて平均で100点以上を獲得されているそうです。これに加え第二外国語としてフランス語などを学ぶ必要が有ります。
第二に、専門分野です。
自分が国連で何をしたいのか、そしてそれは国連でなければできないことなのか、どの様なキャリアパスを選ぶかを考えなければなりません。
例えば、建築の分野で働こうとする時に、MBAを持っていても大きな価値はありません。常に求められているポストで価値のある経験、学歴を提示し、自分が誰よりもその職に適することをアピールする必要があります。
第三に長い目でのキャリア、人生において国際機関で働くことをどう位置付けるかです。
これは先に述べた事とも関わりますが、国際公務員の任期は常に決まっており、その後のキャリアの保証は有りません。常に次のポストの事を考える必要があります。
また危険地域での職務となる時、家族を連れていけない場合が多々あります。他にも、ポストの状況によっては転勤が多いため、結婚生活の維持が難しい例も多く見られます。
以上の事を十分に考え、準備し、その上で尚国際機関で働くことを志す人に、国際公務員の道は開けるのでは無いかと思います。
最後に
国際公務員になるためにどのようなことが必要か理解できましたでしょうか。
新卒で入ることが出来ないため、目指している方はファーストキャリアを含めてしっかりとした対策が必要です。
自分の身だけでなく、家族を含めて考える必要がある大変困難な職業ですが、それに見合うだけのやりがいはあると考えられます。
国際公務員に少しでも興味がある方への参考になったら幸いです。
【参考資料】
・外務省国際機関人事センター『国際公務員への道 JPO派遣制度』外務省、2014年。
・国際機関人事センターニューヨーク支部『国連機関への就職 国際公務員就職ガイダンス資料 (2014 年版)』国際機関人事センター、2014年。
・国連フォーラム