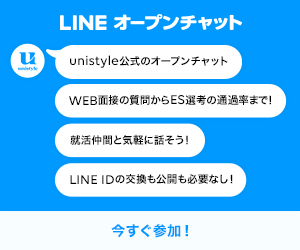グループディスカッションとは?対策、テーマ、進め方、練習方法などのコツを伝授
27,450 views
最終更新日:2024年03月13日

1.【まず始めにこれを読もう!】GDとは?基礎知識を解説
2.GDの対策方法・コツ
3.GD頻出テーマと業界別の過去に出題されたテーマ
4.GDのテーマごとの進め方
5.GDの役割別(司会・書記・タイムキーパー)の対策方法
6.一人でも複数人でも出来るGD練習方法(11選)
「グループディスカッション(GD)をやったことがないから正直よくわからない…」「どこを見て評価してるの?」こんな風に思っている就活生も少なくないと思います。
そんな就活生に向けて、グループディスカッション(GD)の基本的な情報から、企業の採用担当はどこを見てどのように評価しているかまでを詳しく解説していきます。
- 本記事の構成
- グループディスカッション(GD)とは
- グループディスカッション(GD)の目的
- グループディスカッション(GD)の評価基準
- グループディスカッション(GD)とグループワーク(GW)の違い
- 最後に
グループディスカッション(GD)とは
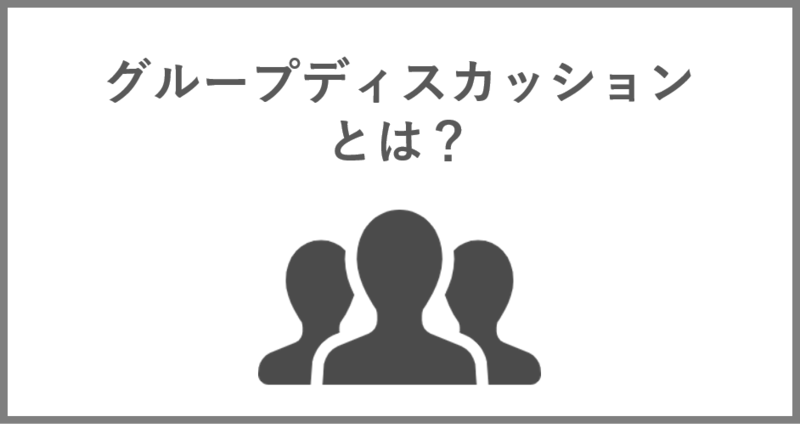 グループディスカッション(GD)とは、複数人のグループで与えられたテーマについて議論を行い、結論を導き出すという選考方法のことを指します。
グループディスカッション(GD)とは、複数人のグループで与えられたテーマについて議論を行い、結論を導き出すという選考方法のことを指します。
グループディスカッションのテーマは企業によって異なり、例えば社会や政治に関するものからビジネスの発想が求められるテーマまで様々です。
企業の選考官はその過程で就活生の行動や発言を見て評価をしています。
グループディスカッション(GD)を選考で行っている企業は多いですが、一体企業はどのような目的でグループディスカッション(GD)を選考フローに用いているのでしょうか。
以下で企業がグループディスカッション(GD)を行う目的について解説します。
グループディスカッション(GD)を行う企業の目的
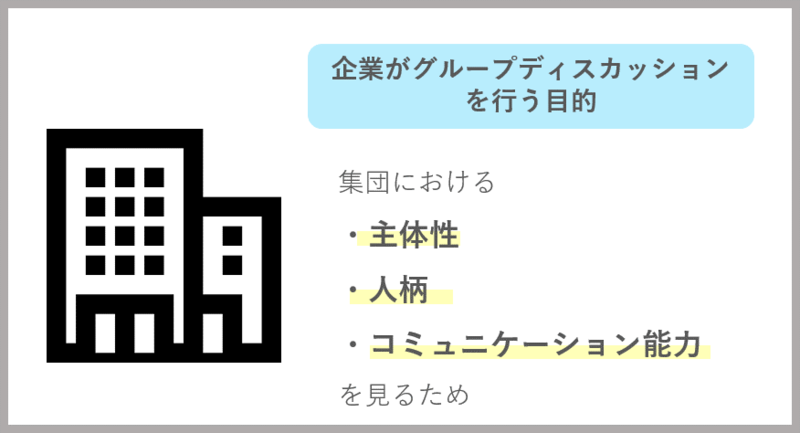 グループディスカッション(GD)は、一般的にESや面接だけでは評価しきれない部分を評価する目的で行われています。企業はグループディスカッション(GD)を通して学生を観察することで、集団における主体性やコミュニケーション能力、人柄などを理解することができます。
グループディスカッション(GD)は、一般的にESや面接だけでは評価しきれない部分を評価する目的で行われています。企業はグループディスカッション(GD)を通して学生を観察することで、集団における主体性やコミュニケーション能力、人柄などを理解することができます。
ESや面接の情報だけでは本当に採用すべき学生か否かの判断に自信が持てなくなっているという企業側の悩みから、選考フローにグループディスカッション(GD)を取り入れる企業が多くなっていると言えます。
グループディスカッション(GD)の評価基準
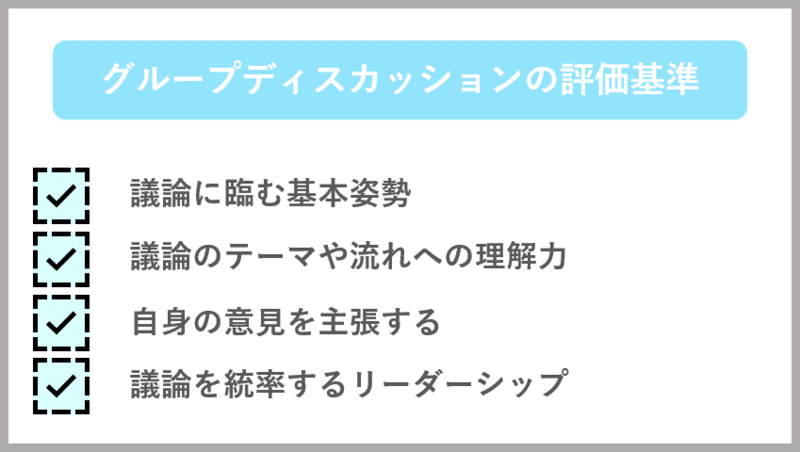
グループディスカッション(GD)の評価基準は4つに大別することができます。全ての企業がこの評価基準で見ているわけではありませんが、基本的にはこの4つを満たせば良い評価を得ることができると言えるので、以下の4つは意識するようにしてください。
①議論に臨む基本姿勢
②議論のテーマや流れへの理解力
③自身の意見を主張する
④議論を統率するリーダーシップ
以下でそれぞれについて詳しく解説していきます。
①議論に臨む基本姿勢
選考官がここで見ているポイントは「ビジネスパーソンとしての基本的マナーが備わっているか」です。
具体的には以下の2点をチェックしています。
- 集団での立ち回り方
- 基本的なマナー
それぞれについて解説します。
■集団の中での立ち回り方
集団の中で立ち回り方とは「他者への配慮ができるか」や「周囲の意見に耳を傾けることができるか」ということです。
具体的には、「グループ内で発言できていない人に発言を促すことができるか」「自分の意見だけを主張するのではなく、周囲の意見を聞き入れることができているか」などが挙げられます。
グループ内で発言していない人に発言を促すことができれば、選考官に「この人は自分のことだけでなく、周りを見ることができているな」というような良い印象を持ってもらうことができ、協調性があるという評価を得ることができると思います。
しかし逆に自分の意見だけを主張して周囲の意見を聞き入れることができない人は、協調性がないという悪い印象を与えてしまう可能性があります。
自分の意見を伝えることはもちろん大切なことですが、主張するだけでなくたとえ自分と異なる意見だったとしてもやみくもに否定せず、一旦聞き入れるように心がけましょう。
■基本的なマナー
基本的なマナーとは具体的に「ペン回しをしない」「話しているときは相手の目を見て話す」「肘をついて話さない」「貧乏ゆすりをしない」などが挙げられます。
選考という重要な場でこのような基本的なマナーを守れない人は、ビジネスの場でもこのような態度で臨んでしまうのではないか、常識がない人なのではないかというような悪い印象を与えてしまう可能性もあります。
そのためグループでの話し合いだからといって気を抜かず、基本的なマナーは絶対に守るようにしましょう。
②議論のテーマや流れへの理解力
選考官がここで見ているポイントは「議論が今どの段階にあって、何について話すべきかを適切に見極められるか」です。
具体的には以下をチェックしています。
- 論理的思考力があるか
選考官は就活生が"与えられたテーマに対し、議論すべき内容と進め方を的確に捉えることができているか"を見ています。
グループディスカッション(GD)は面接やESとは異なり、予測できない他人の意見を取り入れながらグループで1つの結論を出さなければなりません。社会人になるとそのような状況でも論理的思考をもって結論を導き出すことが多々求められます。
そのため論理的思考力が身についているかどうかは重要なポイントとなります。
このことから議論をする際は、出題されたテーマについて自分なりに整理・分析を行い、結論までの道筋をシンプルかつわかりやすく伝え、論理的思考力をアピールするようにしましょう。
その際は自分の意見が矛盾していないか、一貫性があるかどうかに注意してください。
論理的思考力をアピールする際に使用するフレームワークは以下の記事を参考にしてください。
③自身の意見を主張する
選考官がここで見ているポイントは「しっかりと自分の意見を他者に伝え、アウトプットに良い影響を与えられるか」です。
具体的には以下をチェックしています。
- 自分の意見を述べることができるか
ここで大切なポイントはただ意見を述べるのではなく、自分の意見をまとめ周囲にわかりやすく主張することです。ただ発言すれば良いという考えで発言してしまうと、まとまりがなく周囲の人にも何が言いたいか伝わらない可能性があります。
そのため、少し難しいかもしれませんが発言をする際は自分の意見をまとめてから発言するようにしましょう。
自分の意見を伝える際は以下のフレームワークで伝えるのが最もわかりやすいと言われています。

「私は〇〇(結論)だと思います。理由としては~~~。例えば(具体例)~~。なので〇〇だと思います。」というような流れで話すようにしてみてください。
また、"声が大きい/口数が多い人=主張力が強い人"と思われがちですが実際はそうではありません。
意見を論理立ててきっちり伝えることができれば、言葉数が少なくても十分に意見を通せると思います。
④議論を統率するリーダーシップ
選考官がここで見ているポイントは「自らのグループの意見を統率して牽引する動きができるか」です。
リーダーシップの有無を主に以下のポイントでチェックしています。
- 積極性
- 自信
- 分析力
- 責任感
- 方向性を示す力
- グループの全員を議論に巻き込む力
グループディスカッション(GD)におけるリーダーに適している人とは、グループ内の異なる意見をまとめて議論を深め、制限時間内で論理的な結論に導く能力がある人だと言えます。
「リーダー」と言われると真っ先に話し始める声の大きな人を想像したり、あるいはリーダーはグループ内で1人だけ必要と思われがちです。
しかし現代経営学の父という異名を持ち、今もなお多くの経営者の道標となっているピーター・ファーディナンド・ドラッカー(Peter Ferdinand Drucker)氏の言葉から、リーダーシップとは以下のように定義されています。
生まれ持った資質ではなく、地位や特権でもない、責任を持って遂行するべき仕事の一種
つまり"リーダー=議論を良い方向に導く人"という意味では、誰か1人の役割的なものではなく、グループの誰もがリーダーであるべきであり、グループ内に議論を統率できるリーダー的役割の人が多くいればいるほど良い議論になると言えます。
グループディスカッション(GD)とグループワーク(GW)の違い
 選考を行っていく上でグループディスカッション(GD)の他に、グループワーク(GW)という言葉を聞いたことはありませんか。
選考を行っていく上でグループディスカッション(GD)の他に、グループワーク(GW)という言葉を聞いたことはありませんか。
なんとなくこんな感じかなと想像できる人も多いと思いますが、グループディスカッション(GD)とグループワーク(GW)では具体的にどう違うのかと思っている就活生も中にはいると思います。
そんな就活生に向けて、上記2つの違いについて解説したいと思います。
まず初めに、グループディスカッション(GD)やグループワーク(GW)は、企業ごとに呼び方が異なるためこの2つについて明確に定義されていないことが多いです。そのため、以下では一般的なグループディスカッション(GD)、グループワーク(GW)の違いについて紹介していきます。
グループディスカッション(GD)
グループディスカッション(GD)とは先程も述べたように、複数人のグループで与えられたテーマについて議論を行い、結論を導き出すというものです。
グループワーク(GW)
グループワーク(GW)は複数人のグループで与えられたテーマに沿って話し合いを行い、実際に1つの成果(物)を作って発表を行うというものになります。具体的には、自分達で企画した内容の企画書やポスターなどが例として挙げられます。
このように聞くとグループディスカッション(GD)とそこまで違いがないように感じてしまう就活生もいると思いますが、グループでディスカッション(GD)とグループワーク(GW)の大きな違いは、"1つの成果物(物)を作るか否か"ということです。
一般教養やコミュニケーション力、発想力などを見ることができるグループディスカッション(GD)に比べ、グループワーク(GW)では模擬的な仕事場面を体験してもらうことによって就活生の普段の考え方や知識、技能を推し量ることができます。
https://unistyleinc.com/topics/26055
https://unistyleinc.com/topics/26715
最後に
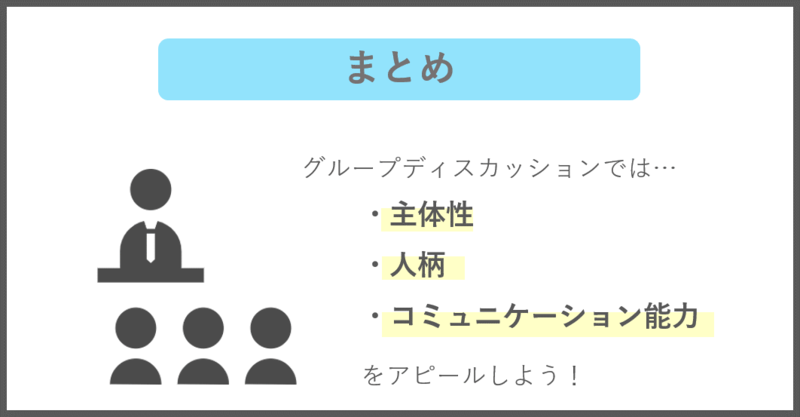 本記事ではグループディスカッション(GD)の目的、評価基準、グループディスカッション(GD)とグループワーク(GW)の違いについて紹介しました。
本記事ではグループディスカッション(GD)の目的、評価基準、グループディスカッション(GD)とグループワーク(GW)の違いについて紹介しました。
グループディスカッション(GD)の選考を突破するためには、目的や評価基準を理解しておく必要があります。
そのため、本記事を参考にしてグループディスカッション(GD)について理解を深めてもらえたら幸いです。
グループディスカッション(GD)の目的、評価などの基本を理解したら、次は対策やコツについて理解するようにしましょう。
以下の記事・動画からグループディスカッション(GD)の対策・コツのついて学ぶことができます。
1.【まず始めにこれを読もう!】GDとは?基礎知識を解説
2.GDの対策方法・コツ
3.GD頻出テーマと業界別の過去に出題されたテーマ
4.GDのテーマごとの進め方
5.GDの役割別(司会・書記・タイムキーパー)の対策方法
6.一人でも複数人でも出来るGD練習方法(11選)


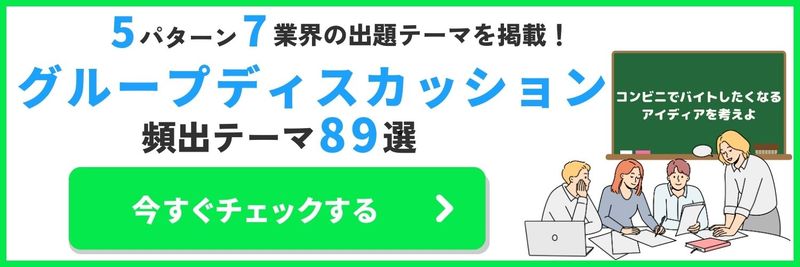



.png?1687158341)